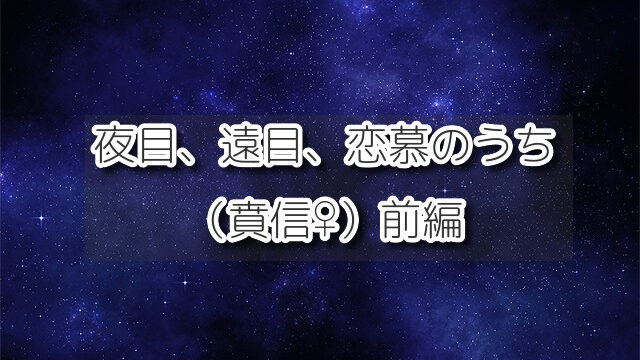- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 李牧×信/シリアス/馬陽の戦い/秦趙同盟/IF話/All rights reserved.
一部原作ネタバレあり・苦手な方は閲覧をお控え下さい。
優勢
馬陽の戦いにて、龐煖の登場により戦況は大きく覆った。
伝令からの報告によると、王騎は趙兵によって包囲されており、龐煖との一騎討ちが始まろうとしているのだという。
王騎の私怨と龐煖の武力については李牧も把握していた。もとより王騎の死を目的とした戦である。
ここで討ち取ることは叶わずとも、龐煖は確実に致命傷となる傷を刻むだろう。
龐煖の方も無傷で済むとは思っていないが、王騎が彼に私怨を抱いているように、彼にも負けられぬ理由がある。
これは長丁場になりそうだと、李牧が馬上で引き続き伝令を待っていると、すぐに新たな伝令が届いた。
決着がついたにしては早過ぎる。戦況の報告だろう。
「伝令!どうやら飛信軍が戦場から離脱を図る模様!」
馬から降りた兵が李牧たちの前で膝をつき、供手礼をして報告を告げる。
「飛信軍…」
聞き覚えのある言葉に、李牧は思わず呟いた。
王騎の養子が将を務めている軍だ。信という名であり、常に仮面で顔を隠して戦場に出ているため、女とも男とも言われている。
(なぜこの機に離脱を…)
あとは王騎の死という目的を果たすのみであったが、戦況としては趙軍の勝利に傾いていた。
王騎と同様に、厚い忠義を持っている将だと聞いていたこともあり、秦軍を見捨てたとは考えにくい。
「飛信軍の数は?」
「およそ一万かと」
一万の兵力では今の戦況は覆すことは不可能だ。戦の経験が乏しい者が考えても分かることである。
此度の総大将である王騎が信に戦場を離脱するよう命じたのならば、王騎はこの戦況を覆せないことを理解しているということになる。
一騎討ちに手出しをしないと分かっていたが、親子の情が動いたのだろうか。
養子とはいえ自分の子なのだから、情を掛けたとしてもなんらおかしいことではないし、むしろ父親として我が子を想う何よりの証言だろう。
李牧はまだ信の姿を目の当たりにしたことはないが、飛信軍の武功は既に中華全土に轟いている。
このまま放っておけば、王騎軍に引けを劣らぬ力を蓄え、確実に趙の強敵となるだろう。
「後軍が飛信軍を追撃中です」
離脱を許さずに追撃しているという伝令の報告に、李牧は思考を巡らせるために一度目を伏せた。
既に王騎軍は包囲されている。飛信軍の追撃に兵を割いたところで、龐煖と王騎の一騎討ちには何の影響も出ないはずだ。
追撃をしている後軍によって信を討ち取ることが出来ればと思うのだが、恐らく一筋縄ではいかないだろう。
養子とはいえ、王騎のもとで厳しく育てられた経験が実を結び、若い年齢ながら将軍の座に就いたことが信の強さを示している。
この戦で王騎が死ぬことになれば、飛信軍と王騎軍の残党は確実に趙への憎しみを糧に今以上の強さを得ることになる。
それは趙国を滅ぼす刃となると李牧も分かっていた。
「…いえ、無理に追撃をしなくて良いでしょう。離脱を許して構いません」
飛信軍の戦場離脱を許す言葉に、周りの兵たちが驚いていた。
今後の戦でも、李牧には揺るぎない勝算があった。どれだけの強さを得ることになったとしても、それを抑え込む数多くの軍略が李牧の頭脳に詰め込まれている。
伝令が再び馬を走らせたのを見送りながら、李牧は小さく息を吐いた。
もしも王騎に命じられて戦場を離脱しているのならば、飛信軍の信は今、他の誰でもない父の死を受け入れざるを得ないことと迫り来る敗北に、身も裂かれるような痛みを抱えていることだろう。
守るべき者が違うだけで、多くの命と領土を奪い合わなくてはならない。それが戦というものだ。
「?」
趙軍本陣で引き続き伝令を待っていると、僅かな地鳴りを感じ取り、李牧は弾かれたように顔を上げた。乗っている馬も何か気配を察知したのか、しきり辺りを見渡している。
動物は人間よりも嗅覚や聴覚に優れているものであり、まるで何か危険を訴えているようだった。
他の兵たちの馬も同様に嘶きを上げ、どこか落ち着かない様子を見せ始める。
(これは…)
多くの兵たちがこの場で待機しているというのに、この地鳴りは一体なんなのだろうか。
戦場に立っている時に感じる地鳴りには覚えがあった。それは大軍の移動によるものである。
伝令が一騎討ちの勝敗を告げに走って来ているとしても、たかだか馬一頭でこのような地鳴りは起こらないだろう。
「全軍!周囲を警戒せよ!」
側近のカイネも少し遅れて何かを察したようで、辺りの兵たちに大声で指示を出す。
李牧の頭には、先ほどの飛信軍が戦場離脱した報告があった。まさか一万の兵でこの本陣に迫って来るとはとても思えない。
前線に出ていた軍が戻って来たのかとも考えたが、一騎討ちが始まった伝令を受けたのはつい先ほどのことだ。まだ決着はついていないうちに撤退するとは考えにくい。
(だとすれば、一体…?)
地鳴りの正体を引き続き警戒していると、李牧は全身を何かが射抜くような、恐ろしい感覚が走った。
「!」
戦場で幾度も感じて来たその感覚の正体。それが殺意だとはっきりと思い出した時、李牧は東の崖を見上げていた。
大勢の兵の姿が見えて、李牧はすぐに敵襲だと声を上げかけたのだが、「趙」の旗が掲げられていることに気付き、言葉を飲み込んだ。
他の兵たちも崖の上にいる趙軍の姿を見つけ、戸惑ったように顔を見合わせている。
ここからの距離ではどの将が率いている軍か見分けられない。
しかし、前線から撤退して来たにせよ、なぜあの東の崖を辿って来たのかと李牧は考えた。
あの東の崖は森を抜けて来ないと辿り着かないはずだ。
なぜ我が軍が優位である今の戦況下で、まるで人目を忍ぶように森を通って来たのか。
(まさか…!)
李牧ははっとして目を見開く。
しかし、その時にはすでに東の崖から趙兵たちが迫って来るところだった。
崖を降りる勢いを崩さず、この本陣へ向かって来る趙兵たちに、何事かと本陣待機の兵たちが戸惑っていた。
先頭で馬を走らせている趙の鎧を身に纏った将が、仮面を被っていることに李牧はいち早く気付いた。
「飛信軍か!」
戦場を離脱したはずの飛信軍の本陣奇襲が始まった事実に、李牧は冷や汗を浮かべた。
奇襲
「敵襲!あの者たちは趙軍ではない!迎撃せよ!」
怒気と焦りが籠もった李牧の指示に、辺りの兵たちは動揺のあまり動けずにいた。
指示を出した李牧自身の動揺が伝染していくのが見て取れる。
なぜならば、こちらへ迫っている兵たちは趙の旗を掲げ、趙軍と同じ鎧を身に纏っているのだ。
戦場に転がっている屍から鎧と旗を奪い取ったのだろうか。奇襲だけでなく、趙兵に扮してやって来るとはさすがの李牧も予想外だった。
「ぎゃああッ」
後ろの方で兵の悲鳴が聞こえ、一斉に場がざわめく。何事かと李牧が顔を向けると、趙兵同士で斬り合いが始まっていた。
「お、お前、何をしてる!?」
「違う!俺じゃない!」
いきなり仲間を背後から斬りつけた兵に、周りの兵たちが混乱している。
迫り来る飛信軍の焦燥に追い打ちを掛けるように、その混乱は趙兵の中でたちまち広まっていった。
この混乱に乗じて、すでに趙兵に扮した敵が侵入して来ていたのだと気づき、李牧は奥歯を噛み締めた。
「落ち着け!飛信軍の迎撃に備えよ!」
混乱に陥っている趙兵たちにカイネが怒号を飛ばすが、敵がどこに紛れているのか分からない以上、兵たちの混乱は解けそうになかった。
(まずい!)
こちらの混乱に乗じて、飛信軍がすぐそこまで迫って来ている。
迫っている兵の数はおよそ一万。兵力差で言うならば、この本陣で待機している五万の兵で十分に対抗できるはずだった。対抗ではなく圧勝と言っても良かっただろう。
しかし、李牧が危機感を抱いているのは兵力差ではなく、この状況だ。
すでに趙兵たちが疑心暗鬼に陥っている状況で、さらに飛信軍が趙兵に扮して襲撃をおこなおうとしている。敵味方の区別がつかず、わずかな時間で士気は大幅に減滅していた。
いくら数で勝っているとはいえ、この士気と戦況では十分な抵抗すらできない。
(このままでは…)
一刻も早く迫り来る飛信軍を止めなければ、ますます味方同士で混乱が広がり、被害は拡大していく一方だろう。
李牧の予想は命中し、布陣も整えずに真っ直ぐに突っ込んで来ただけの飛信軍の一万の兵と趙の五万の兵が入り乱れることとなった。
何が起きているのか事前に把握していたはずの李牧でさえ、敵味方の見分けがつかないでいる。
(後軍の追撃は?壊滅させられたのか?)
戦場を離脱する飛信軍を追撃していた後軍の姿が見えない。
追撃は不要だと伝令を頼んだが、それはつい先ほどのことで、伝令と後軍の合流はまだ出来ていないはずだ。
一万もの飛信軍兵が鎧を奪うとすれば、戦場に転がっている屍だけで足りなかったのだろうか。もしかしたら、追撃をしていた後軍の鎧を奪ったとも考えられる。
堂々と敵兵の鎧に着替える姿を見られぬよう、あの森の中に誘い込んだとも考えられるが、どちらにせよ、この有り様では飛信軍が後軍を壊滅したことは間違いなさそうだ。
「李牧様!」
思考を巡らせていたところを、カイネの声で意識を引き戻された。
同じ鎧を着た趙兵たちが混乱している中、仮面で顔を隠した一人の兵が迷うことなく李牧のもとへと馬を走らせて向かって来ていた。
カイネがすぐに李牧を庇うように前に出て、二本の剣を構える。
(この者が、飛信軍の信…!)
仮面で顔を覆っているが、鎧で覆われた体つきは確実に男だ。
性別が明らかになっていないのは、その圧倒的な強さを前に、正体を見抜いた者たちが全員生きて帰れなかった証拠である。
養子とはいえ、王騎の息子だ。天下の大将軍とまで称される彼の下で育てられた将を討ち取るのは至難の業である。
「カイネ、他の兵たちの救援を。このままでは混乱が広がる一方です」
李牧は腰元に携えていた剣を抜き、冷静に指示を出した。
この本陣を落とされるのが先か、それとも龐煖が王騎に致命傷を負わせて撤退させるのが先か。
「龐煖と王騎の一騎討ちを終えるまで、ひとまずここは耐えねばなりません」
「…わかりました。ご武運を!」
持久戦に持ち込む気なのだと主の考えを察したカイネは、混乱している兵たちの救援へと馬を走らせていく。
その姿を横目で見送り、李牧はいよいよ目前まで迫って来た信と対峙する。
「…飛信軍がこのような奇策を使うとは、初めて知りましたよ」
本陣に奇襲をかけて趙軍を混乱に陥れたことに、李牧は素直に称賛の言葉を贈った。しかし、ここで大人しく首を渡す訳にはいかない。
仮面で顔を覆われているせいで、信の表情は見えないが、はっきりとした敵意が感じられる。
しかし彼から向けられるそれは、先ほど感じた全身を射抜くような、あの凄まじい殺意ではなかった。
飛信軍が崖から降りて来る時に感じたあのはっきりとした殺気は、兵たちを先導する信から向けられていたものだと李牧は疑わなかった。
(なんだ?何か、違和感が…)
自分にあの殺意を向けていたのが本当にこの男なのだろうかと怪しんだ瞬間、全身を射抜くようなあのおぞましい感覚が李牧を包み込んだ。
「ぐッ!」
背後を振り向くよりも先に、李牧は馬から飛び降りていた。
地面に着地した途端、それまで自分が居た場所に剣が横一文字に振るわれたのが見え、間一髪のところで避けられたことを悟る。
馬から飛び降りたのは無意識だったとはいえ、一瞬でも遅れていたら李牧の首は繋がっていなかっただろう。
頭上から舌打ちが聞こえた。
「避けやがったか」
李牧を背後から斬りつけようと剣を振るった兵が、馬上で呟いた。趙の鎧を身に纏っているが、飛信軍の兵だろう。
信将軍に従う副官だろうか。気配を察知するのが遅れたとはいえ、かなりの腕であることが分かる。
「…!」
副官だと思われる兵が、秦の紋章が刻まれた剣を握っていることに気付き、李牧の表情が険しくなる。
仕えている国の紋章が刻まれている剣といえば、戦の褒美として授かるほど価値の高いものだ。今この場にやって来た一万もいる兵の中で、なぜこの者だけがその剣を握っているのだろう。
副官としての実績が認められた証拠なのかもしれないが、それほどの実力がある者が副官で留まっているはずがない。
「お前が裏で手を引いていた軍師だよな?李牧って言ったか?」
馬上から、その兵が剣の切先を李牧に突きつける。その兵の声には聞き覚えがあった。
「…なぜ伝令役など危険な真似を?気づかれれば、命はなかったはずですよ」
その兵は、李牧に飛信軍の戦場離脱を伝えた伝令役だった。まさかすでにこの本陣に侵入されていたとは思わなかった。
剣を下ろしたその兵は、肩を竦めるようにして笑った。
「ああ。気づかれなかったから、お陰で無事だったぜ?」
こちらを挑発するように笑ったその兵が女だと気づいたのもその時で、李牧は表情に出さずに動揺する。
恐らく、迫り来る飛信軍の迎撃から気を逸らすために、趙兵を斬り捨て、この本陣を混乱に陥れたのも彼女だろう。伝令役を演じておきながら、ずっとこの機を傍で見計らっていたに違いない。
(これは奇襲以上に予想外でした)
李牧は唇をきつく引き結ぶ。こちらが優勢だったことに対する油断を突かれたのだと認めざるを得なかった。
「あんまりもたもたしてっと父さんに叱られるから、とっとと終わらせるぞ」
女兵が顎で何かを合図すると、李牧の背後に立っていた信将軍が仮面を投げ捨て、すぐに馬を走らせていった。
無言の指示に従ったことから、立場は彼女の方が上であることは明らかである。この女兵は副官ではなかったのだ。
秦の紋章が刻まれた剣を彼女が所持していることが、彼女が副官でない理由だと気づき、李牧の心臓がますます早鐘を打つ。
「…あなたが、信将軍だったのですね」
「そうだ。死ぬ前に気づけて良かったな?」
初対面にしてはこれ以上ない険悪な雰囲気で、お互いに名乗り合うつもりはなかった。
先ほどの背後からの一撃を回避出来なければ、信の正体を知ることもないまま息絶えていたに違いない。
まさか将軍自らが、敵兵に扮して本陣に潜入するという大胆な奇策。そして見事それを成し遂げたことに、信は相当、頭が切れる女であることが分かった。
「………」
殺気は向けられていたが、今すぐに襲い掛かる様子は見られない。素顔と正体を知られ、今さら仮面で顔を隠すこともしないようだ。
李牧は手綱を手繰り寄せ、再び馬に跨る。馬上で睨み合いながら、静かに口を開いた。
「王騎に命じられて来たのですか?ここにいる私を討てと」
「いや?」
意外にも信は首を横に振ったので、李牧は瞠目した。
「別の軍師がいるっていうのは、目星をつけてたみたいだけどな?ちょうど手持ち無沙汰だったんで、俺が代わりに確認しに来てやったんだよ」
王騎と龐煖の一騎討ちを邪魔しない代わりに、思いつきでやって来たのだと彼女は言った。随分と余裕な態度だ。
こちらは突然の奇襲と、女だったという正体に大いに驚かされたというのに、そんな笑顔を見せつけられると、こちらまでつられて笑ってしまう。
奇襲 その二
「………」
信に意識を向けつつ、辺りの様子を伺った。
同じ鎧を着ている者同士が戦っており、仲間討ちのような戦況になっている。
趙軍の兵たちも迎撃しなくてはという意志があるのだが、果たして目の前にいるのは本当に自分たちの仲間ではないのかと躊躇いがあるようで、飛信軍の兵たちに次々と倒されていく。
五万もいる趙兵たちが、たった一万の兵たちに次々と打ち倒されていった。飛信軍のその強さは今まさに李牧の目の前で証明されていた。
もしも飛信軍が秦兵の鎧のままだったのならば、数で圧倒しているこちらが優位のままだっただろう。
しかし、このような奇策を用いて本陣を襲撃するとは、ましてや普段は前線で活躍している飛信軍が敵兵に扮するとは、さすがの李牧も予想出来なかったのである。
「王騎将軍が龐煖を討つのが先か、俺がお前を討つのが先か、どっちだろうな」
剣を握り直しながら、信がからかうように笑った。
趙軍の優勢に傾いていた戦況を、諸刃の剣で逆転させようというのか。
いや、彼女の言葉を聞く限り、負けるつもりはないのだと言っているのだろう。
「…残念ながら、そうやすやすと討たれる訳にはいきません。私を討ち取るのは至難の業ですよ」
「本陣への潜入は余裕だったけどな?」
それは伝令に扮していたからこそだろう。小生意気なことを言うと李牧は苦笑を深めた。
しかし、もう李牧は動揺することはない。
受けた奇襲と、信が女であったことを知り、既に激しく動揺していたのだ。これ以上の動揺があるとすれば、龐煖が王騎に討たれることくらいだろう。
しかし、それは絶対にあり得ないことだと、李牧は確信していた。
「…余裕そうだな?」
「ええ、無駄口を叩けるくらいには余裕かもしれません」
穏やかな声色で返すと、信が僅かに目を細めた。どうやら癪に障ったらしい。頭が切れる割には、簡単に感情を表に出す女だ。
こちらはすでに冷静さを取り戻している。本来の目的を忘れてはならないと李牧は自分に言い聞かせた。
この戦の目的は王騎の死であって、自分の首を差し出すことではなかった。目的を成すためには、この奇襲に耐えねばならない。
戦が始まる前に念入りに描いた軍略通りに進んでいるのならば、もう少しでその目的は果たせる。
自然と李牧の唇には笑みが浮かんでいた。それがますます気に食わないのか信の顔に怒気が浮かんでいく。
先ほどの挑発を返すように、李牧が口を開いた。
「…あえて言うならば、これは余裕でも無駄口でもなく…時間稼ぎというやつでしょうか」
「なに?」
信がその言葉の意味を理解するよりも早く、伝令役の兵が馬を走らせて来た。
「伝令ーッ!龐煖様が、秦の王騎を討ち取ったとのこと!」
大混乱の中、その伝令の声は李牧と信の耳にはっきりと届いた。弾かれたように信が伝令役の方を見る。
「父さんッ…!?」
それまで浮かべていた怒気が消え去り、信じられないといった驚愕の表情にすり替わっている。
彼女の顔を見て、李牧の胸に何か言葉に言い表せぬ感覚が走った。
気づけば李牧は馬上から腕を伸ばし、彼女の手を掴んでいた。驚愕の表情が濃くなり、何をするんだと視線を向けられる。
李牧は近くで信の顔をまじまじと見つめ、二度とその顔を忘れまいと網膜に焼き付けた。
「放せッ!」
信が反対の手に握っている剣を振り上げたのを見て、李牧はすぐに手を放す。
咄嗟に身を引いたが、鋭い切っ先が、李牧の手の平を傷つけた。きっと信は腕を切り落とすつもりで剣を振るったに違いない。
「絶対に殺してやる…!」
刃のように冷たい瞳を向けられて、李牧は目を細める。先ほどまで余裕ぶっていた彼女が素の表情を出したのだと思うと、胸に喜悦が走った。
感情を表に出しやすい女だとは思ったが、冷静な判断は出来るようで、信は李牧に斬り掛かることはしなかった。
「全軍撤退だッ!急いで戻るぞッ!」
手綱を引いて馬の横腹を蹴りつけ、信は馬を走らせていった。彼女の指示に従い、趙兵に扮していた飛信軍が撤退を開始する。
隙だらけの背中を李牧に見せていたが、李牧はその背中を斬りつけるような真似はしなかった。
「…また会いましょう、信」
遠ざかっていく彼女の姿を見つめながら、李牧は血を流している手の平の痛みを、疼きのようにも感じていた。
宴
秦趙同盟が結ばれた後に開かれた宴の席で、李牧は大いにもてなしを受けていた。
振る舞われた酒と食事を口に運ぶが、どうにも味を感じない。
六大将軍であった王騎を討つ軍略を企てた軍師として、一部の者たちからは殺意交じりの視線を向けられているせいだろう。無意識のうちに身体が警戒していた。
しかし、同盟を成した後では誰も李牧の首を取ることは叶わない。
主の仇と取ろうと意固地になる兵もいるだろうが、とりあえず人目のある宴の場では安全は保証されそうだ。
顔にはいつものように笑みを繕っていたが、このように少しも楽しめない宴の席は初めてだった。
元々賑やかな席を得意としない李牧であったが、二国を結ぶ同盟の宴ともなれば宰相である自分が参加しない訳にもいかない。
悼襄王の寵愛を受ける春平君と趙からの使者である自分たちの首を守る代わりに、韓皋の城を失うことになった。
築城中であったものの、防衛に優れた城を失うことは痛手ではあったが、命には代えられない。
向かいの席に座る呂不韋といえば、この不穏な空気を他人事のように振る舞っている。妓女たちを両脇に侍らせて酒を煽っている彼の姿に苦笑を浮かべつつ、李牧はさり気なく宴の席を見渡した。
(あれは…)
奥の席に秦王の姿を見つけた。呂不韋との交渉の場では玉座に腰掛けたまま口を出さなかった嬴政という名の秦王は、意志の強い目をしている青年だった。
従者たちと何かを話している。
この距離からでは何を話しているのかは聞き取れないが、どうやら宴の席からそろそろ退こうとしているようだ。
「…?」
秦王の傍らに、赤色の着物を着た女性が座っており、仲睦まじく話をしている。正室だろうか。
まさかこのような宴の場に王女が参加するとは思わず、李牧は興味本位でその女性の姿を目で追っていた。
「おや?宰相殿、気になるお相手でも見つけましたかな?」
酒で酔っているのだろう、ほんのりと顔を赤くさせている呂不韋が李牧の視線に気づいたようだった。
「ああ、いえ…」
李牧の視線を追い掛けた呂不韋が、嬴政と共にいる赤い着物の女性に気付き、納得するように大きく頷いていた。
「これは宰相殿もお目が高い」
まるで良い品物に目をつけたとでも言うような口ぶりで、呂不韋が顎髭を撫でつけた。
「まさか王女までもがこの宴に来て下さるとは、大いに歓迎をしてくださるようで何よりです」
李牧がそう言うと、呂不韋は顔の半分が口になってしまうほど大口を開けて笑い出した。
おかしなことを言っただろうかと李牧が小首を傾げていると、ようやく笑いが落ち着いたらしい呂不韋が息を吐く。
「あの者は王女などではない」
「え?」
「元下僕ながら今や将軍の座に就いている、今は着飾ってマシな見目をしているものの、普段は色気の欠片もない女ですぞ」
元下僕から将軍にまで上り詰めた女といえば、秦国には一人しかいない。
「…彼女が、信将軍ですか?」
馬陽の戦いで、網膜に焼き付けた彼女の姿を思い返し、李牧の心臓が早鐘を打ち始めた。右の手の平がじんと疼く。
あの時、彼女によってつけられた傷はもう癒えているものの、痕を残している。それはまるで李牧が信への興味が尽きていない証のようにも思えた。
「ええ、そうです」
李牧が信の名を口に出すとは思わなかったのだろう、呂不韋は少し驚いたように目を丸めてから頷く。
あの時に見た顔は忘れないと心に決めたはずだったのだが、今は鎧ではなく、美しい身なりを整えているせいで、彼女が信だとすぐに気づけなかった。
呂不韋が嬴政と楽しそうに話を続けている彼女に視線を向けてから、静かに李牧を見据え、今度は薄く笑んだ。
何か含みのある笑いに、李牧の胸に嫌なものが広がる。
その顔は先ほどの交渉の場で見せた、呂不韋の元商人としての顔だと気づいた。
もう韓皋の城も渡すと決めたのだから、これ以上は何も渡すことは出来ないと釘を刺そうとしたのだが、呂不韋が言葉に出したのは予想もしていなかった言葉だった。
「あの者は養父のこともあって、随分と宰相殿のことを恨んでおるようだが…此度の秦趙同盟をより強固にするために、趙に嫁がせてはいかがかな?宰相殿がお相手ならば、誰も文句は言うまいて」
仮にも敵地であるこの場所で、信を嫁にもらってくれと言われると思わず、李牧は瞠目した。隣でカイネが何を言っているんだと目を剥いて呂不韋を睨み付けている。
「御冗談を」
軽くあしらい、李牧は酒を口に運ぶ。
秦趙同盟を結ぶ際の、呂不韋の交渉術を身を持って知った李牧は、彼の進度に合わせれば、全てを持っていかれるのだと学習していた。
しかし、呂不韋の厄介なところは、提示した条件を確実に呑ませるために、相手を自分の進度に巻き込もうとするところだ。
自分が優位に立ち、最大の利益を得るために、彼は使えるものはなんだって使う強欲さに満ちていた。
命を奪われるのは免れたとはいえ、今回の交渉の場は、もともと呂不韋が用意したものである。
春平君を人質に取ることで悼襄王と宰相を動かせると読んだ呂不韋が、軍師としての才能を開花しなくて良かったと李牧は人知れず安堵する。
「冗談なものか。あの娘が宰相殿のお眼鏡にかなったとあらば、この機を逃すのは勿体ない」
それはつまり、長い目で見た時に、呂不韋に利をもたらすということだろう。
元下僕という立場である信が、王家という名家に入ることが出来たのは、養父である王騎がいたからこそである。
しかし、王騎がいない今、信には後ろ盾がないはずだ。
名家というものは、やたらと血筋を重視する存在であると李牧も分かっていた。
王家の者たちからしてみれば、信の存在は煙たがられているに違いない。それが秦国に欠かせない強大な将軍であったとしてもだ。
元下僕の立場で由緒ある名家の養子となった話が大いに広まったのも、前例がない異例中の異例の出来事だからである。
信が将としての才を開花させたからこそ、誰も口を出せずにいるのだろう。
ゆえに、彼女を王家から追放できるのならば、理由は何だって良いのかもしれない。仇同然の男に嫁ぐことになったとしてもだ。
王家との繋がりがない呂不韋が、李牧に信との婚姻を提案して来たということは、味方であろうと使えるものは何だって利用しようと考えている証拠である。
後ろ盾もない彼女が王家から守られることはないだろうし、将軍とはいえ、信は丞相の命令に逆らえる立場ではない。
つまり、呂不韋が命じれば、あとは李牧の承諾次第で、彼女は趙に嫁ぐしかなくなるのだ。
「………」
李牧は口元に笑みを繕うばかりで、答えるようとはしなかった。
あえて何も答えずにいるというのに、それを承諾の返事と勘違いしたのか呂不韋が、満面の笑みを浮かべて立ち上がる。
「何も難しいことはない。ここはお任せあれ」
「え?」
まさか本当に婚姻の話を進めるつもりなのかと、李牧の瞳に動揺の色が浮かぶ。
引き留めるよりも先に、呂不韋が席から離れていってしまったので、残された李牧は呆気に取られていた。
信のところに向かったのかと、秦王がいた方に目を向けたが、嬴政と信の姿はもうそこにはなかった。
「全く、無礼な…!」
隣でずっと呂不韋と李牧の話を聞いていたカイネが顔を真っ赤にして目をつり上げていた。
彼女が自分の代わりに怒りを露わにしてくれることで、李牧は何だか救われた気持ちになる。
「お酒が入って気分が良くなっているのでしょう。そう気にすることはありません」
もしも信との婚姻の話を進められたとしても、自分さえ断れば丸く済むと李牧は考えていた。
自分に嫁がせれば、秦の強大な戦力である信を戦から遠ざけることが出来る。
今後、秦と戦をすることがあれば優位に事を運ぶことが出来る利点があるのは李牧も十分に分かっていた。
しかし、それは姑息で卑怯な方法だ。
手に入れるのならば、呂不韋の手を借りるのではなく、自らの手で掴み取りたいと李牧は考えた。
右の手の平が引きつるような、疼くような痛みを覚え、李牧は視線を向ける。
この傷跡を見る度に、李牧はあの日の光景を、まるで昨日のことのように思い出せた。
殺意の眼差し、怒気を含んだ声、悔しそうな表情。あの瞬間、間違いなく彼女の全ては自分だけに向けられていると感じた。
その事実に、李牧は陶酔感のようなものを覚えていた。それが恋心だと知るのは、もっと先の未来である。
宴の夜
その後、李牧は侍女によって客間へと通された。
宮廷の一室とはいえ、幾つもの間を通ったところにその部屋は用意されているらしい。他の家臣たちとは違う待遇に、油断は出来ないと思った。
別部屋に案内された家臣たちの耳に、自分の声が届かない部屋に案内されるということは、夜間の奇襲の可能性を示しているからだ。
武器の所持は許されていたが、複数で押し掛けられれば、いくら李牧とはいえ無傷で生還することは出来ないだろう。
「こちらのお部屋をお使いください」
侍女が深々と頭を下げ、今来た道を戻っていく。
彼女の姿が見えなくなってから、李牧は持っていた剣を鞘から抜いた。扉を開けた途端に、待ち構えている伏兵たちによって襲われる可能性を考えてのことだった。
宴の席で酒に毒でも盛られていたのなら、安易にこの命は奪われていたに違いない。
呂不韋はとことん信用出来ない男だ。此度の交渉でそれがよく分かった。
宴の席で油断させておいて、気を抜けたところを討ち取るように指示を出しているかもしれない。
自分はともかく、カイネたちは無事だろうかと心配になる。
この部屋の向こうにいる兵たちを一掃し、首謀者と企みを吐かせなくてはと、意を決した李牧は躊躇うことなく扉を開けた。
剣を構えて室内を見渡したが、中に自分を待ち構えている兵たちはいなかった。
代わりに、天蓋つきの寝台の上で一人の女が寝そべっており、李牧の存在に気付くと気怠そうに身を起こした。
「やっと来たのか。寝るとこだった」
その女が信だと気づいた李牧は、予想外の展開にしばらく言葉を失っていた。
剣を構えている李牧の姿を見ても、彼女は動揺する素振りを見せない。李牧がこの部屋を訪れることを分かっていたからだろう。
「…なぜ、あなたがここに?」
剣の切先を信に向けたまま尋ねた。
周囲への警戒も怠らなかった。何故なら彼女に意識を向けているうちに、背中を斬られてしまうかもしれないからだ。
馬陽の戦いでは彼女が背中を斬りつける役ではあったが、今度は飛信軍の副官や兵がその役目を担っているかもしれない。
李牧があからさまに警戒している姿を見て、信は肩を竦めるようにして笑った。
「安心しろ。伏兵もいないし、武器も持ってねえよ」
寝台に腰掛けたまま両手を上げたが、李牧は信用しなかった。
美しい装飾が施された帯の中や、赤い着物の袖の中に短剣の一本くらいは隠してそうだ。
李牧が怪しんでいることに気付いたのか、信は気怠げに立ち上がる。
迷うことなく彼女は自ら帯を外し、表着を脱いで床に落とす。裳の紐も解くと、彼女の身体の線に沿って布が落ちていった。
赤い着物が信の足下に落ち、まるで床に赤い血溜まりが出来たように見えた。
恥じらいも躊躇いもなく、一糸纏わぬ姿になった信が静かに李牧を見据える。
「何の真似ですか」
自ら武器の類を持っていないことを証明した行動に、李牧は何の目的があるのか分からず、眉根を寄せた。
「呂不韋の野郎に、お前と寝ろって言われた」
「は?」
まさかここで呂不韋の名前を聞くことになるとは思わず、李牧は瞠目する。
先ほどの宴の席で、信との婚姻についての話を進めておくと言っていたが、まさか彼女にその話を通したのだろうか。
だとすれば、李牧は信の行動がますます理解出来なかった。
敵軍の軍師、ましてや養父の仇に等しい男に嫁ぐなど、彼女が絶対に受け入れることはないと思っていた。
易々と身を差し出すような行動に、寝首を掻きに来たのかという結論に辿り着く。
武器がないことを自ら証明していたが、隠そうと思えば着物の中だけではなく、寝具や家具の隙間にだって隠せるだろう。
あくまで自分を油断させる策なのだと考え、李牧は警戒を解かずに信を見据えていた。
傷だらけではあるが、若さを主張する艶のある肌と、無駄な肉などない引き締まった身体、しかし女性にしかない胸の膨らみは申し分がない大きさだ。
男ならば、この体を前にして生唾を飲み込むだろう。しかし、今の李牧は違った。
決して信に女としての魅力を感じない訳でも、李牧が一人の男として、彼女の身体を好きにしてしまいたいという欲求を感じない訳でもない。
信の意志ではなく、これが呂不韋の命令だということが気がかりだった。
彼女の誘いに応じることは、彼の策略通りに事が進み、自分の命を差し出すのと同等の行為である。
「………」
李牧が一向に手を出そうとしないので、信は床に落ちていた表着だけを身体に羽織った。
それから彼女は李牧の脇をすり抜ける。部屋を出ていくのかと思ったが、彼女は内側から扉に閂を嵌め込んで、外部からの侵入を防ぐために鍵を掛けている。これで密室が出来上がった。
自分と信以外の誰かがいる気配は感じられない。この密室で自分を殺そうとする者がいるのなら、それは間違いなく信だけである。
どこに武器を隠しているのか、どのような手法で自分を殺そうとしているのかと李牧が考えていると、信は再び寝台に戻って腰を下ろしていた。
「…奇襲はされない。けど、外に聞き役がいる」
扉越しに李牧の死を確認する者がいるというのか。彼女の言い草から、聞き役というのは、恐らく呂不韋が差し向けた者だろうと考えた。
呂不韋の命令にせよ、信が自分を殺そうとしているに違いないと眉根を寄せると、彼女は腕を組んで溜息を吐いた。
念のため、李牧は彼女の問い掛けた。
「私を殺すつもりは?」
「同盟が続く限り、ない」
即答した信に、李牧はようやく剣を鞘にしまった。
「それどころか…お前と寝ないと、俺のとこの軍師と副官たちの首が飛ぶ」
渋々と言った様子で話し始める彼女の瞳に憤怒の色が浮かんでいたのを、李牧は見逃さなかった。
「…すべて、呂不韋からの命令なのですね」
「ああ」
苛立ちに声を低くしている信の顔に、暗い影が差していた。
ここに来たのは信の意志ではなく、呂不韋の命令だったのだ。人質まで取られたことから、信も従わざるを得なかったのだろう。
「お前があいつと何を話したのかは知らねえけど、あいつは俺を政から遠ざけようとしてんだよ」
「政…秦王のことですか」
そうだ、と信が頷く。
宴で仲睦まじい姿を見せていたことから、きっと秦王と信は親しい関係なのだろう。
交渉の場で感じた呂不韋の強欲さから、彼が丞相という座だけに収まっているとは思えなかった。
まさかあの男の強欲さは秦王の座にまで向けられているのだろうか。
飛信軍の軍師と副官を人質にとるくらいなのだから、秦王と親しい信を趙へ嫁がせようとするのは、呂不韋が秦王の座を狙っていることと関係しているのかもしれない。
夜伽
「…お互い、あの男にしてやられたというわけですね」
「そうなるな。同情するぜ」
まさかこんなところで信との共通点を見出すとは思わなかった。
李牧は鞘にしまった剣を机に置くと、寝台へと向かう。隣に腰を下ろすと、信はちらりと視線を送って来たが、それ以上は何も言わなかった。
人質に取られている軍師と副官の命を助け出すためには、李牧に抱かれるしかない。かと言って、強引に行為を迫ることもしなかった。
きっと彼女の中では、王騎の仇である男に抱かれなくてはいけないという葛藤があるはずだ。
「どうしますか?」
李牧はあえて信に問い掛けた。
呂不韋の企みに乗ってやるのは正直気が引けるし、飛信軍の軍師と副官の命など、李牧が心配する立場はない。
冷静に物事を見返すと、天秤に掛けられているのは信の仲間の命だけであって、こちらの損失は何もないのだ。
呂不韋が自分と信の存在を邪魔に思っているのは間違いないだろう。しかし、ここで夜襲をかけないということは、韓皋の城を明け渡すと決めた以上、少なくとも自分の命は保証されるはずだ。
李牧は静かに口を開いた。
「人質の件は同情します。しかし、相手が敵国の宰相である以上、あなたにも断る権利があるはずだ」
「………」
下唇をきゅっと噛み締めたのを見る限り、信は未だ選択を決め兼ねているように思える。
大切な仲間たちの命が掛かっているとはいえ、相手が悪かった。養父の仇である男に抱かれるなど、この上ない屈辱のはずだ。
この女を抱くかどうかなど、李牧にとってはどちらでも良かった。
女に不便をしている訳でもないし、自分に損失のない以上、気分で選択をしても構わない。
どうしてもと信に懇願されるのならば抱いても良いと思えたのだが、無理強いを迫るほど余裕のない男だと思われるのも、その様子を呂不韋に報告されるのも癪だった。
「…はあー…」
やがて、信が長い溜息を吐いた。
ようやく決断したのだろうかと彼女の顔を見ると、目が合った。
「…俺が殺すのを躊躇うくらい、善がらせてみせろよ」
その瞳の色に浮かんでいるのが諦めだと分かり、李牧は唇に苦笑を滲ませる。
隣に座っている信の身体を押し倒すと、寝台が軋む音が響いた。
「ええ、善処しますよ」
李牧の言葉に、信がゆっくりと目を伏せた。
中編はこちら