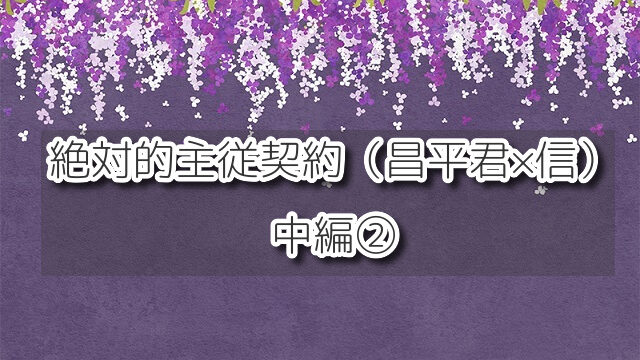- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 桓騎×信/王翦×信/毒耐性/シリアス/IF話/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は毒酒で乾杯をの番外編です。
訪問
屋敷に到着すると、すぐに家臣の者たちが出迎えてくれた。
通された客間で、既に王翦が酒を飲み始めている。桓騎の後ろにいる信の姿を見ても、彼が表情を変えることはなかった。
さすがに重厚な兜は脱いでいるが、目元だけは黒い仮面で覆われていた。彼の素顔を知っている者は、果たしてこの中華にいるのだろうか。信はふとそんなことを考えてしまう。
桓騎に以前尋ねたことがあったが、彼も王翦の素顔は見たことがないのだという。
二人が席に着くと、
「…王騎の娘も来たか」
静かに酒を口に運びながら、王翦が独り言のように呟いた。その言葉に信は緊張し、体を縮こませる。
「本当は二人で話すつもりだったんだろ?悪いな」
桓騎によって無理やり連れて来られたようなものだというのに、信はそれを告げず、謙虚に謝罪した。
隣の席に座っている信を横目で見つめながら、桓騎はこれが王一族の中での彼女の立場なのかと考える。王騎という後ろ盾を失ったことで、当主である王翦に頭を下げなくてはならなくなったのだろう。
「桓騎に連れて来られたのだろう」
謝罪を聞いても、王翦は大して気にしていない様子だった。それどころか、こちらが何も言っていないというのに、信がここに来ることになった過程まで見抜いたらしい。
得意げに笑った桓騎が隣にいる信の肩に腕を回す。
「宝は隠しておくより、持ち歩いた方が守りやすいからな」
「お、おいっ?」
首回りを隠している襟巻きを奪われないように、信が慌てて桓騎の腕を押さえ込む。
ちょうどその時に侍女たちが部屋に入って来て、客人である桓騎と信へ料理と酒を運びにやって来た。
丁寧な手付きで杯に酒を注いでくれたが、桓騎はあとは手酌でやるので酒瓶は置いていくよう指示をする。
王翦のような名家の主ともなれば、手酌をする機会などないのだろうが、信と桓騎は違う。しかし、桓騎の指示に王翦は何も言わなかった。
恐らく王翦も桓騎と酒を飲み交わす時は、従者の出入りを断っているのだろう。侍女たちは素直に従っていた。
「…あいつら…」
何か気になるのか、桓騎が侍女たちの後ろ姿を見つめている。
「どうした?」
彼の視線を追い掛けるが、すでに侍女たちは部屋を出て行った後だった。
「いや、何でもない」
話を逸らすように、桓騎は酒が注がれた杯を手繰り寄せた。
乾杯はしなかったが、向かいの席に座っている王翦に杯を掲げると、桓騎はすぐに酒を口にした。
王翦は盃を掲げることはしないが、視線を向けながら静かに酒を飲んでいる。
蒙驁の副官として付き合いの長い二人には、これくらいの距離感がちょうど良いのだろう。
大いに談笑をしながら賑やかな宴をする飛信軍と違い、何だか大人の貫録というものを感じられた。
信も二人に続いて、注がれた酒を口に運んだ。
毒酒の罠
(うッ…!)
一口飲んだ途端、信の顔が大きく強張った。
口に含み、喉を通るまでに強い痺れを感じたのである。そして、独特な生臭さが鼻腔を抜けて、思わず泣きそうなほど顔を歪めてしまった。
もてなされた立場ということもあって、無礼をする訳にもいかず、信は咄嗟に俯いて前髪で表情を隠す。
桓騎と王翦にちらりと視線を向けたが、二人は話をするのに夢中のようで、信の変化には気付いていないようだった。
(これ、鰭酒か…?)
口に含んだ瞬間に強い痺れと、独特な生臭さを感じたことから、毒魚の鰭を使ったのは明らかである。
(まさか毒酒でもてなされるとはな…)
自分の杯に注がれたのが鰭酒なら、桓騎が飲んでいるのも同じものだろう。
さすがに王翦は自分たちと違って、毒の耐性がないので普通の酒を飲んでいるに違いなかった。
そこまで考えて、そういえば王翦に過去に一度でも毒の話をしたことがあっただろうかと考える。
「信?」
隣に座っている恋人が暗い表情を浮かべていると、いち早く気づいた桓騎が振り返る。
「どうした。もう酔ったか」
「あ、いや…」
慌てて首を振った。
もしかしたら、桓騎が自分たちの特殊な体質なことを告げたのかもしれない。
王翦がせっかくこの酒を用意してくれたのだから、その気遣いを無下にする訳にはいかないと信は再び鰭酒に口づける。
やはり独特な生臭さが鼻につき、信は顔を引き攣らせた。
「…王翦将軍。この酒はどこから取り寄せたんだ?」
口元に笑みを繕いながら信が尋ねた。
毒酒を作れる者は限られている。毒酒を作ることを生業としている者はとても少ないのだ。
桓騎が贔屓にしている鴆者は酒蔵で、普通の酒の製造も行っていると聞いた。普段は鴆者であることは隠しているらしい。
確かに暗殺道具を作る者が勤めていると広まれば、売り上げにも大いに悪い影響が出るだろう。
「北方の酒蔵からだ」
王翦の返答に、桓騎が納得したように頷いた。
「寒い地方なら強いワケだ。そういや、北の酒は初めて飲むな」
肩を竦めるようにして桓騎が笑う。彼の言葉を聞き、信は目を見開いた。
(初めて…?それじゃあ、桓騎の酒は…鰭酒じゃないのか?)
酒を注いでくれたのは侍女たちだったが、将軍同士の話があると言って、今この部屋にいるのは信と桓騎と王翦の三人だけである。
それぞれの食膳には酒瓶が添えられている。全員が同じ酒瓶だったので、同じ種類の酒だと思っていたのだが、どうして自分にだけ鰭酒が与えられたのだろう。
「桓騎…」
一度、王翦が部屋から出たのを見計らって、信は机の下から遠慮がちに彼の着物を引っ張った。
「ん?」
何か言いたげに視線を送って来る恋人を、桓騎が不思議そうに見やる。
信が毒に耐性を持っていることを知っているのは飛信軍の一部の兵たちと、彼女の側近に当たる者たちだけだ。一方の桓騎も公言はしておらず、桓騎軍の側近たちだけらしい。
以前、後宮で嬴政の正室である向の食事に毒が盛られたことがあり、彼女の護衛につくよう指示された時は、嬴政や彼の一部の側近たちに特殊な体質を知られてしまった。
後宮の騒動はそれなりに大きく広まっていたようだし、もしかしたら、どこからか情報が洩れて王翦が聞きつけたのだろうか。それならば鰭酒を事前に用意していたことも納得がいく。
だが、桓騎も同じ体質であることは知られていないのだろうか。自分にだけ鰭酒が注がれたことに、信は違和感を覚えた。
「王翦将軍って…毒のことを知ってるのか?」
小声で問い掛けると、桓騎は首を横に振ったので、信は思わず言葉を詰まらせた。
「………」
王翦が毒耐性のことを知らないのに、なぜ自分に鰭酒が振る舞われたのだろう。
そして、桓騎も自分たちの毒耐性の話題を出されたことに、何か勘付いたようだった。
「あっ」
信が制止するよりも先に、桓騎が鰭酒の入っている杯を手に取る。ちょうどその時、一度席を離れた王翦が部屋に戻って来た。
「…ほう?」
杯を顔に近づけただけで、桓騎は独特な匂いからこれが鰭酒だと気づいたようだった。
何者かが意図的に信を毒を盛ったのだという事実に、桓騎の額に青筋が浮かび上がったのが見えた。
「面白ェことするやつがいたもんだな」
いきなり低い声でそう囁いた桓騎に、王翦が何事かと見つめている。
(やめろって!)
冷や汗を浮かべながら信が桓騎の着物をぐいと引っ張る。
桓騎はともかく、自分は王家の中で後ろ盾のない弱い立場だ。養父である王騎の死によって、後ろ盾がなくなったのが一番の理由である。
今さら王家を追い出されることには何も未練もないが、当主である王翦のもとで騒ぎを起こしたとなれば、亡き養父の顔に泥を塗ったのも同然の行為だ。それだけは絶対に避けたかった。
「…何事だ」
桓騎の目の色が変わったことに気づいた王翦が静かに問い掛けた。毒を盛られたことを桓騎が告げるよりも前に信はあたふたと話し始める。
「いや、な、何でもねぇんだ!美味い酒だな!」
咄嗟に桓騎の手から杯を奪い取り、信はまだ残っている鰭酒を一気に飲み込んだ。苦手な生臭さが鼻腔を突き抜け、鳥肌が立った。目頭に思わず涙が滲んだが、何とか笑顔を繕う。
「誰かがこいつの杯に毒を盛った」
こちらの気持ちなど少しも考えず、桓騎があっさりと白状したので、信は目を剥いた。
毒酒の罠 その二
王翦が目を大きく開いたことから、彼も珍しく動揺していることが分かる。
「毒だと?」
「ああ、間違いない。魚の毒だ」
平然と答える桓騎に、信が諦めたように溜息を吐く。王翦と目が合い、信は狼狽えたように視線を彷徨わせた。
「…そなた、毒が効かぬのか」
頷きながら、さすがだと敬服した。
毒酒を飲んだというと、大抵の人間は驚くか、すぐに医師の手配をしようと慌てる者の二択である。
しかし、王翦は毒酒を飲んで平然としていられる信を見て、すぐに毒の耐性があることを察したらしい。
「お前が知らなかったってことは、もてなしで振る舞ったワケじゃねえのは確実だな」
信が毒への耐性を持っていることを知った上で鰭酒を振る舞ったというならば分かるが、そのような珍しい耐性を持っていることを王翦は知らなかった。
つまり、意図的に信の杯に毒酒を盛り、彼女を毒殺しようとした者がいるということである。
それが王翦ではないのは明らかだ。彼は姑息な手段を使って相手を死に至らしめるようなことはしない。それは信も桓騎も断言出来た。
信に毒を盛った犯人はこの屋敷に仕えている者だろう。きっと杯に鰭酒を盛った犯人は、信が毒耐性を持っていることを知らなかったに違いない。
もしも毒酒を注ぐ杯を間違えれば、主を殺すことになる危険すらあったというのに、それだけの危険を冒してでも信を殺そうとした意志が伺える。
「…誰が盛った?」
桓騎の声が普段よりも低くなり、信が狼狽えた。
部屋には桓騎と信と王翦の三人しかいないのだが、酒に毒を盛れる人物は限られている。
酒を注いでくれた侍女か、酒を用意した者か、もしくは彼らの目を盗んで盛った者の誰かだろう。
そして唯一分かっていることといえば、毒殺を企てるほど信を憎んでいる者だろう。
「桓騎、やめろ…」
特殊な体質でなければ、今頃のたうち回りながら息絶えたかもしれないのに、彼女の表情からは事を大きくしたくないという意志が伺える。
まるで自分さえ我慢していれば丸く収まるのだという態度に、桓騎は不機嫌に舌打った。
「お前が本家に来たくないって言ってのは、このことだったのか?」
「おいッ…!」
王翦の前で堂々と問われ、信が桓騎の着物をぐいと引っ張った。
「………」
三人の間に沈黙が横たわる。
まるで顔色を伺うように、冷や汗を浮かべながら信が王翦に視線を向けた。
こんな風に、相手の機嫌を伺う素振りを見せる彼女を見るのは初めてだった。それほど王家の中で、信の立場は弱いものなのだろう。王騎がまだ生きていた頃は違ったのかもしれない。
「お前は何にビビってんだよ」
からかうように信の肩を小突くと、信がきっと目尻をつり上げた。まるで黙れと言わんばかりの態度だ。
王翦を苦手だと言う話は聞いたことがないが、確かに戦と自分の野望以外何を考えているか分からない男であることは桓騎も同意していた。
息子の王賁ほど、王翦は名家という立場にこだわりはないようだが、信にとっては敬うべき立場だ。
秦王には普段から無礼な態度で接しているくせにと心の中で毒づきながら、縮こまる信を見て、桓騎は苦笑を浮かべた。
「………」
王翦は相変わらず表情を変えないでままでいる。
恋人である桓騎以上に何を考えているのか分からない男で、信は緊張のあまり、固唾を飲み込んだ。
「なぜ王騎の娘が狙われた」
王翦の言葉に、桓騎の片眉が持ち上がる。
「はあ?どっからどう考えても、こいつを殺そうとしてのことだろ」
本来、毒酒は暗殺道具として使われるものだ。
信と桓騎は毒が効かぬ特殊な体質を持つ者であり、毒酒を嗜好品として愛飲しているが、もしも毒の耐性がなければ、信は絶命していただろう。
信の王家の中での立場の弱さはこれで証明されたが、王翦はどうして信が狙われたのかを理解出来ずにいるらしい。
毒を仕込んだのが王翦でないとしても、桓騎は彼の態度が無性に腹立たしくなった。
王一族の本家当主にあたる王翦さえ、家臣たちを説き伏せていたら、王騎という後ろ盾を失った信の立場を気に掛けてくれていたのならという想いが溢れて止まなくなる。
しかし、王翦は桓騎の気持ちなど露知らず、鋭い眼差しを向けて来た。
「…貴様はともかく、王騎の娘が屋敷に来ることを、家臣たちは誰一人として知らなかったはずだ」
その言葉を聞いた信がはっとした表情になる。
桓騎から今日の誘いを受けたのは昨夜のことで、本来、王翦の屋敷に訪れるのは彼だけだった。
信も同行することを事前に連絡していないし、信が桓騎と共に屋敷に訪れることを知らなかったのは王翦だけでなく、彼の家臣たちもだ。
鰭酒を作る過程は複雑ではないのだが、浸けておく時間が必要であり、最低でも一晩は要する。取り寄せるとなればまた違った過程と日数が発生する。
前もって彼女が屋敷に来ることを知っていたのならまだしも、その情報もないのに彼女が鰭酒を盛られた理由は何なのだろうか。
誰かが意図して毒酒を盛ったのは事実だが、本当に信を殺すつもりだったのだろうかと王翦は疑問を抱いた。
もしも信が今日の酒の席に来なかったとしたら、毒酒は注がれていたのだろうか。それとも、毒酒を飲ませる相手は最初から信ではなかったのかもしれない。
王翦の推測を聞き、信が目を丸めている。
「…じゃあ、本当に鰭酒を飲まそうとした相手って…」
「俺か?」
桓騎がにやりと笑った。
毒酒の罠 その三
頬杖をついた桓騎に、王翦は普段通り冷たい眼差しを向けている。
「王騎の娘のおかげで、命拾いしたようだな」
まるで挑発とも取れる王翦の言葉に、桓騎が苦笑を深めた。桓騎自身も信と同じく毒への耐性があるのだが、彼が王翦にそれを告げることはなかった。
毒耐性があることを王翦に打ち明けないことには何か理由があるのだろうと考え、信は二人の間に口を挟まなかった。
「…毒酒を盛る直前になって殺す標的を変えたか、それとも間違えたか。どっちにしろバカの犯行だな」
毒殺されかけたのは自分だというのに、桓騎は少しも動揺する素振りはない。
こんなことで動揺するような男ではないのだと信も分かっていたのだが、あまりにも重々しい空気に包まれて、つい黙り込んでしまう。
(やっぱり、来るんじゃなかった…)
俯いて着物をきゅっと握り締めた信は、重い空気の中でひたすら後悔していた。
桓騎を殺そうとした者がいるのなら、それは確かに許せないが、どちらにせよ王翦に迷惑をかける形になってしまった。
亡き養父への罪悪感に苛まれ、俯いたまま顔を上げられなくなってしまう。
隣で暗い表情を浮かべている恋人に気付いた桓騎が、王翦の死角となる机の下でそっと手を握ってくれた。
思わず桓騎の方を見ると、彼は表情を微塵も変えていなかった。
しかし、心配するなと言ってくれているような優しい目をしていて、信の胸がきゅっと締め付けられる。
「ただ酒を飲み交わすだけじゃつまらねェ。犯人探しに付き合えよ」
大胆に足を組み直した桓騎が、背もたれに身体を預けながらそう言った。王翦は静かに杯を置き、じっと桓騎の目を見据えている。
「良いだろう」
「…えッ!?」
まさか王翦が承諾するとは思わず、信は立ち上がっていた。
「味方に毒を盛る者など信用出来ぬ。最初から排除しておくに限る」
仮面越しに真っ直ぐな視線を向けられて、信は思わず口籠る。
「ましてや、私の副官になる将に毒を盛る者など、弁明の余地はない」
「え?…それって、俺か?」
そうだ、と王翦が頷いた。
過去に断ったはずなのに、なぜ王翦の副官になることを前提としているだろうと信は思ったが、隣にいる桓騎からつまらなさそうな視線を向けられているのは分かった。
「ど、どうやって犯人を捜すんだよ?」
王翦と桓騎からの視線に耐え切れず、信は話題を切り替えた。
秦軍の知将として名高い二人が揃っているのだから、無策で犯人を捜し出すことはしないだろう。
桓騎は台の上に両足をどんと乗せ、挑発するように王翦を見やった。
「鰭酒は鴆酒と違って、そう難しいモンじゃないからな。作ろうと思えば誰でも出来るだろ」
毒酒の準備が誰にでも出来るものならば、入手経路から犯人を追うのは困難かもしれない。
恐らく桓騎もそれを分かっていて、王翦に犯人を見つけ出す方法があるのか問うているのだ。まるで王翦の頭脳を試すかのような態度である。
「………」
顎に手をやりながら王翦が口を噤んだ。犯人を捜し出す方法を考えているのだろう。
隣で桓騎がにやりと笑んだので、信は嫌な予感を覚える。
「…連帯責任なら、全員殺すのが一番手っ取り早いだろ」
「おいッ!」
あまりにも物騒な策に、信は思わず桓騎の肩を叩いてしまう。
自分が敵とみなした相手にはとことん容赦がない桓騎の性格は知っているが、さすがにそんな提案を許す訳にはいかなかった。
確実にこちらを殺すつもりで毒を盛ったのだとしても、ここは戦場ではないのだ。
憤怒で顔を真っ赤にしている信に、桓騎は肩を竦めるようにして笑った。
今の発言を冗談だと撤回することはなく、桓騎は鰭酒の入っている酒瓶を見やる。王翦もじっと机の上に並べられている酒瓶を見つめていた。
見たところ、三つの酒瓶は全て同じだった。中に鰭酒が入っていることを見分ける目印がないことに気づいたのは、王翦と桓騎のどちらが早かったのだろう。
「…王翦将軍?」
ゆっくりと王翦が立ち上がったので、何をするのだろうと信は小首を傾げた。彼は三つの酒瓶を台の中央に集め、まだ中身が存分に残っていることを確認していた。
部屋を出た王翦が、酒と料理の料理の用意をしてくれた厨房の者たち、部屋を出入りした侍女たちを呼び出した。そして人数分の杯を持ってくるように指示を出している。
主から突然呼び出されたことに、従者たちは戸惑いを隠せないでいるようだった。合わせて十人の従者が部屋に集まり、机の上に従者たちの杯が用意された。
何をするのだろうと信が黙って見ていると、王翦は従者たちに背を向けながら、持って来させた杯に酒瓶の酒を注ぎ始める。
(あ…)
しかし、王翦は鰭酒が入っている酒瓶にだけは手をつけていない。鰭酒の入っていない二つの酒瓶を使って、杯に酒を注いでいる。
しかし、主の後ろ姿しか見えない従者たちには、三つの酒瓶から酒を注いでいるように見えるだろう。
「…桓騎将軍からのもてなしだ。飲むが良い」
全ての杯に酒を注ぎ終えた王翦は高らかにそう言った。
まさか自分に酒をもてなしてくれるとはと従者たちが驚いている。しかし、王翦も桓騎も従者たちの中に、不審な動きをしている者がいないか目を光らせているのが分かった。
(…もしかして…)
これが彼の策なのだと信は気づいた。
どうやら杯を持って来るよう命じていた時点で、桓騎は既に気づいていたようだが、彼は決して王翦の策に口を挟む真似はしなかった。
王翦の策
いきなり酒を振る舞われたことに、従者たちはあからさまに躊躇っている。
それは毒酒を盛ったことを気づかれたのではないかという動揺ではなく、客人がいる手前、立場の低い自分たちに酒を振る舞う主の行動を理解し兼ねてのことだった。
しかし、これこそが王翦の策なのだろう。
鰭酒を用意した者がこの場にいるのなら、渡された杯に鰭酒が混じっているのではないかと警戒するはずだ。そのためにわざわざ背を向けて酒を注いで見せたのだ。
「遠慮は無用だ。飲むが良い」
主に酒を勧められ、もちろん断る従者はいなかった。王翦に声を掛けらた従者たちは各々、静かに杯に口をつけていく。
「………」
信は注意深く従者たちの行動を見つめていた。
もしも、酒を口にしない者がいるとすれば、それは酒瓶の一つが鰭酒であることを知っている犯人だけ。
口に含めば即死するほど強力な毒だと知っていれば、主の命令であったとしても安易に口づけることは出来ないはずだ。
(もしかして、あいつか?)
庖宰 の男が一向に酒を飲もうとしないことに気が付いた。杯を持つ手が震えており、顔も青ざめている。
桓騎も気づいたようで、横目でその男に鋭い眼差しを向けていた。
「ッ…?」
信が立ち上がろうとした瞬間、机の下で桓騎に手を押さえられる。桓騎は信と目を合わせず、口を噤んだまま、その手を放そうとしなかった。今はまだ動くなと言いたいのだろう。
「…飲めぬのか」
庖宰の男に問い掛けた王翦は腕を組み、冷たい眼差しを向けていた。
普段から仮面の下の表情を変えない男だが、今はその瞳にはっきりと敵意が浮かんでいるのが分かる。
重々しい空気が室内を満たしていく。他の従者たちも主の威圧感に怯えていた。
王翦からあんな目つきで睨まれたら、自分でさえも足が竦んでしまうだろうと信は思った。
しかし、桓騎は何を思っているのか、台から足を下ろすと、つまらなさそうに頬杖をついていた。
もしもこの場を仕切るのが王翦ではなく、桓騎だったのなら、あの男に惨たらしい罰を与えていたに違いない。
信の前ではそのような発言は控えるようになったのだが、それでも桓騎軍の素行の悪さは未だ健在している。
信の策
「…答えよ。なぜその酒を飲まぬ」
単刀直入に王翦が男に問うた。
庖宰 の男は、今にも失神してしまいそうなほど顔から血の気を引かせている。
「飲まぬのではなく、飲めぬのか」
「………」
室内に広がる重々しい空気と沈黙に、信はまるで自分が責められているような錯覚を覚えた。
このまま男が答えても、答えなくても王翦は彼を罰するつもりだろう。
「っ…」
あの男が桓騎を殺そうという明白な目的を持って毒酒を盛ったのなら、許す訳にはいかない。
どのような私情があるのかは分からないが、秦軍に欠かせない知将の一人である桓騎を毒殺しようとした罪は重い。
毒殺は叶わなかったとはいえ、重罪として扱われ、処罰は免れないだろう。
それに、毒酒を盛る相手を間違えていたとすれば、王翦が死んでいたかもしれないのだ。
奇跡的に信と桓騎が毒への耐性を持っていたことが幸いし、犠牲は出なかったものの、毒酒を盛ったことを認めれば、男は間違いなく斬首となるだろう。
(でも…)
信はきゅっと唇を噛み締めた。胸が締め付けられるように痛む。
まるで「余計なことはするな」と言わんばかりに、桓騎が信に鋭い眼差しを向け、机の下で掴んでいる手に力を込めて来た。
しかし、信はその手を振り解いて立ち上がると、王翦から男を庇うように間に立った。
「…何の真似だ」
王翦の低い声に、信は思わず息を飲む。仮面越しに睨まれると、それだけで膝が笑い出してしまいそうになった。
彼の息子であり、友人の王賁がこの威圧感を受け継がなかったことを幸いに思いつつ、己に喝を入れ、信は庖宰の男を振り返る。
「酒が苦手なんだよな?美味そうだから俺にくれよ」
有無を言わさず、信は男の手に握られたままの杯を奪い、一気に飲み干した。庖宰の男が何か言いたげに口を大きく開いたが、言葉にはならなかった。
「…うん、美味い」
本当は自分に注がれるはずだった酒が喉に染み渡り、信は長い息を吐いた。
「飲まねえなら俺が全部飲んじまうぞ!」
王翦と桓騎から呆れた視線を向けられているのは分かったが、信はあえて自然に振る舞った。
机の上に置いてあった鰭酒の酒瓶を手に取り、信は迷うことなく口づける。
「~~~ッ!」
苦手な生臭さが鼻腔を突き抜けて、思わず身震いしたが、嚥下するのはやめない。針を刺すかのように、毒酒の独特な痺れが喉を伝う。
「ぷはっ」
あっと言う間に酒瓶を空にした信は手の甲を口を拭い、空笑いをしながら涙目で王翦を見た。
「あー、悪い悪い。全部飲んじまった!いや~、本当に美味い酒だな~!」
すっかり空になった酒瓶と杯を勢いよく台に置き、信はこれで証拠は無くなったと言わんばかりに王翦に挑発的な視線を向ける。
わざとらしい演技をする信に、桓騎があからさまに溜息を吐いたのが見えた。
「…下がって良い」
王翦は何の感情も読み取れないいつもの瞳で、従者たちを下がらせる。
毒酒を盛ったと思われる庖宰の男もそそくさと逃げていった。
弁明
客間から従者たちが出ていき、三人だけになると、緊張が解けたかのように信はずるずるとその場に座り込んでしまった。
「なぜ証拠を消すような真似をした」
腕を組んだ王翦が冷たい眼差しで信を見下ろしている。
あのまま毒を盛ったとされる庖宰 の男を処罰すれば済む話だったのに、彼を庇うような行動をした信の真意が分からないのだろう。
そのまま視線を合わせていると、王翦の威圧感に呑まれて何も言えなくなってしまいそうだったので、信は俯いて視線を逸らした。
「そういう、つもりは…ただ、俺は、鰭酒を飲みたかった、だけ…で…」
視線を逸らしていても、身が竦んでしまいそうなほど伝わって来る王翦からの威圧感に、語尾が掠れてしまう。
「…あの様子じゃ、自分から暇を取りに来るだろ。それか、今から逃げ出す準備してるだろうな」
それまでだんまりを決め込んでいた桓騎が、助け舟を出すような言葉を掛けた。
いつものように、目を抉り出して手足を切り落とせとでも言うのかと思っていた信は、桓騎がまさかそのような発言をするとはと驚いた。
「…かもしれぬ」
信が鰭酒を飲み干してしまったことで、王翦はあの男を処罰する気を失せたのか、何も言わずに椅子へ腰掛けた。
先ほどと似たような重々しい空気が室内に広まり、信は唇を噛み締める。
「あ、の…」
掠れた声で王翦に声を掛けるが、返事どころか、視線さえも向けてくれなかった。
恋人に毒を盛ったあの男を庇ったことに、信は微塵も後悔していない。
一歩間違えれば主を殺してしまう危険もあった上で、毒殺を目論むくらいなのだから、余程の事情があったに違いないと思ったのだ。同時にそれは自分の甘さであることも自覚していた。
「王翦、将軍…」
だが、王一族の中で、後ろ盾もない弱い立場の自分が勝手をしたことを謝罪しようと、信が頭を下げようとした時だった。
「私の副官になれ、王騎の娘」
まさかそのような言葉をかけられるとは思わず、信がぽかんと口を開ける。王翦は仮面越しにじっと信のことを見据えている。
自分を副官にすることをまだ諦めてなかったのかと、眉間に困惑の色を浮かべた。
「俺は…」
何度誘いを受けても答えは同じだ。
王翦が野心家でなく、秦国と嬴政に忠義を尽くしてくれたのならば、副官になっても良いとは思っていたが、その気持ちは今でも変わりない。
しかし、王翦の方も野心家であることは変わっていない。お互いの気持ちは平行線のままだ。
何度誘われても答えは同じだと、信は誘いを断ろうとした。
「う”…」
突然心臓が何かに掴まれたかのように、胸が重く痛み、信は呻き声を上げる。
息が乱れていき、今度は燃えるように胸が熱くなっていく。
(ま、まずい…!)
似たような症状を過去にも体験していた信は、毒の副作用が始まったのだとすぐに勘付いた。
急に蹲って苦しげに喘ぐ信を見て、王翦が何事かと見つめている。
そして、背後では桓騎が不敵な笑みを浮かべていたのだが、信がそれに気付くことはなかった。