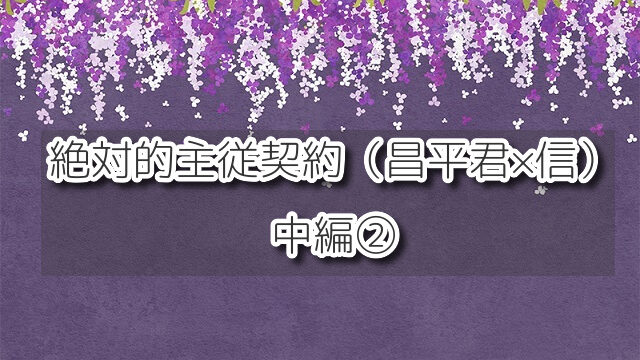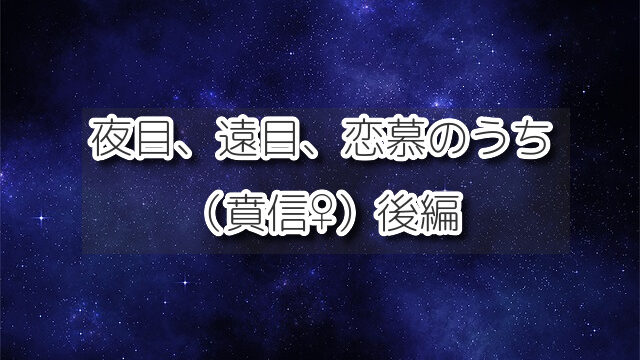- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 昌平君×信/ヤンデレ/無理やり/メリーバッドエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
眠りの狭間
※本編で割愛したシーンです。
薬と香が効いて来たのだろう、ようやく眠った信は唇を戦慄かせており、何か言葉を紡いでいた。
寝言なのは分かっていたが、もしかしたら先ほど縫合をした左足の痛みを訴えているのかもしれない。昌平君は着物の袖で鼻と口元を抑えながら、彼女の口元に耳を寄せた。
「――、―――」
朦朧としている意識で信が唇を戦慄かせている。僅かに空気を震わせたその言葉を聞き、昌平君は目を見開いた。
李牧。それは趙の宰相の名だった。
此度の敗因は、彼の軍略によるものである。どうして彼の名前を信が口にしたのか。
考えられるのは、李牧が信にとっては父親の仇同然の男であることが関係している。飛信軍が兵の大半を失うという膨大な被害も李牧の軍略によるものだった。
亡くなった兵たちのことを想うあまり、信は医師団の忠告も聞かず、傷だらけの体に鞭打って鍛錬をこなしていた。李牧に対する恨みが募っている証拠でもある。
そうだと分かりながら、昌平君の心中は穏やかではなかった。
好意を寄せている女性が自分以外の男の名前を、それも意識がない中で敵の宰相の名前を口にするというのは、どうにも許せないものである。
「…信」
呼び掛けるが、信は完全に寝息を立てており、薬と香によって意識の糸を手放していることが分かった。
医師団が処方した薬と香はかなり強い薬効を持つものだ。恐らく数日は目覚めないだろう。
「ん…」
昌平君は眠っている信の頬を手で包むと、導かれるように唇を重ねていた。
先ほども薬を飲ませるという目的で唇を重ねたが、少しも抵抗がないと、まるで想いが通じ合っている恋人同士のようだと錯覚してしまう。
唇を押し開き、舌を差し込み、彼女の赤い舌に絡ませた。
「ん…」
ざらざらとした舌の表面や、唾液で滑った唇の柔らかい感触が堪らなくて、夢中で舌を絡め合う。
信は静かに寝息を立てるばかりで、自ら舌を絡ませて来ることはなかったが、それで良かった。
「…信」
口づけを終えてから、耳元で名前を囁くが、信が起きる気配はなかった。
「はあ、…は、…」
薬を飲んだ訳ではないのだが、部屋で焚いている特殊な香には、体の緊張を解く作用がある。
その香を吸い続けている昌平君も、今では脱力感とも陶酔感ともいえる、不思議な感覚に身を委ねていた。
「……、……」
眠り続けている信の頬に手を添える。
瞼を閉じていても、今彼女の目の前にいるのは自分だけで、今この瞬間だけは確かに彼女は自分だけのものだった。
信の寝顔を見つめながら、優越感と独占欲が昌平君の胸に広がっていく。
薬と香のせいだと分かっていても、穏やかな寝顔を見ていると、まるで自分のことを受け入れてくれているのだと錯覚してしまう。
「ッ…」
昌平君は着物の袖で鼻と口元を覆った。
今さら香を嗅がずにいたところで手遅れかもしれないが、これ以上、傍にいれば信をどうにかしてしまいそうだった。口づけ以上のことを求めてしまうに違いない。
「!」
部屋の扉が叩かれ、昌平君は驚いて振り返った。
「信、医師団から聞いたぞ。また足の傷が開いたそうだな」
扉を開けて入って来たのは嬴政だった。苛立った口調をしている。
信の親友である彼が自ら見舞いに来たのかと内心驚きつつ、昌平君はすぐにその場に膝をつく。
香を嗅がないように鼻と口元を布で覆っている嬴政が、なぜここに昌平君がいるのかと目を丸めていた。
「…ああ、医師団に頼まれたんだったな」
思い出したように嬴政が頷く。
どうやら嬴政は医師団から先ほどの経緯について報告を受けていたらしい。昌平君に薬を飲ませて香を焚くよう頼んだことも聞いていたのだろう。
「全く…医師団や昌平君の苦労も知らずに…」
寝台で寝息を立てている信を見下ろし、嬴政は呆れたように溜息を吐いた。
しかし、その眼差しには慈しみの色が宿っており、嬴政は優しい手付きで彼女の髪を撫でている。
「――――」
その姿を見て、昌平君は思わず焦燥感に駆られた。
まるで心臓を鷲掴みにされたような感覚になり、昌平君は思わず歯を食い縛る。
「…大王様。後で、ご報告したいことが」
誰にも聞かせたくない話であることを告げると、嬴政の眉間に皺が寄った。
偽り
嬴政が信の見舞いを終えた後、玉座の間に移り、昌平君は嬴政と二人きりとなった。
事前に人払いをしていたこともあり、玉座の間には重い沈黙が広がっている。
「報告を聞こう」
昌平君は嬴政の前で跪いたまま、口を開いた。
報告を進めていくにつれ、嬴政の顔から血の気が引いていくのが分かる。
それは当然だろう。親友である信が趙の密通者である可能性が高いなど、信じられるはずがない。
「…確かなのか?」
「可能性ですが、その説が考えられます」
「………」
信が趙の宰相である李牧と密通している証拠は何もないのだと知り、嬴政は複雑な表情を浮かべる。
此度の飛信軍が壊滅状態に追いやられたことは、嬴政も知っていた。
しかし、仲間想いである信が、まさか自分の軍を壊滅に追い込むことに、結果として秦軍が敗北するように、趙に手を貸したとは信じたくなかったのだろう。
彼女を信じたいという気持ちで嬴政が、口を開きかけたが、昌平君はそれを遮るように言葉を続けた。
「飛信軍は、事前に五十人もの兵で山中の調査を行い、そこに伏兵は居なかったと報告を出していました。しかし、実際には伏兵が待機していた」
「………」
「山中の調査には、信将軍自ら名乗り出たと報告を聞いています。…伏兵を見逃した可能性があるやもしれませぬ」
嬴政はあからさまに目を泳がせ、何かを探っているようだった。
信がそのようなことをするはずがないと言い返したいのだろうが、反論材料に欠けているのだろう。
恐らくは李牧が山中で見つからぬ場所を事前に指示し、兵を潜ませていたに違いない。
しかし、親友の裏切りの可能性を示唆された嬴政は、そこまで冷静に思考が働いていないようだった。
「…大王様」
静かに昌平君が声を掛ける。嬴政は苦しそうに眉根を寄せながら、昌平君を見据えた。
「此度の件、今は内密に願います。彼女の傷が癒えてから、真実を明らかにするべきかと」
深々と頭を下げながら昌平君がそう言うと、嬴政は沈黙の後に頷いた。
「もしも密通の疑いが事実ならば、この咸陽に、彼女と接触を図ろうとする趙の使者が現れるやもしれません。信の身柄を、療養という目的で預かっても?」
「…ああ、頼む」
許可を得たことで、昌平君はもう一度頭を下げた。
その口元が怪しい笑みを浮かべていることに気づく者は、誰もいなかった。
李牧×信のバッドエンドはこちら
偽り その二
信の身柄を屋敷に移したが、彼女は未だ目を覚まさない。その方が昌平君としても都合が良かった。
家臣たちに事情を説明し、見張り役を立てることとなった。
もし見張りの目がない時に部屋から脱走をしても分かるよう、部屋の扉にも鈴を取り付けた。
薬と香の効能によって、そう安易に目を覚ますことはないだろうが、念には念を入れておかなくてはならない。
あとはもう少し外堀を埋めなくてはいけない。嬴政からの許可は得たが、他にも密通の疑いを伝えるべき人物といえば、まずは河了貂だろう。
飛信軍の軍師であり、自分を師と慕う彼女が密通の疑いを知れば動揺するに違いない。
もちろん信は密通などしていない。だが、密通だと疑われる行為をしたのは事実だ。
山中の伏兵調査に乗り出したのは信自身だったというのを、昌平君は河了貂から報告を受けていた。
それからもう一つ。秦趙同盟が結ばれた後、趙の一行をもてなすための宴が開かれた。
宴の席を抜け出し、趙の宰相と何かを話していた姿を、昌平君はこの目で見ていた。
あの場に出くわしたのはただの偶然だったのだが、見方によっては信の密通を疑わざるを得ない光景である。
物陰から二人の会話に耳を澄ませていたが、密通など感じさせるものは一つもなかった。
しかし、人目を忍ぶように趙の宰相と二人で会っていたという、その事実を利用さえすれば、それで良かったのだ。
秦国に欠かせない強大な戦力である信の立場が崩れていく図が、昌平君の中に浮かんでいった。
「…………」
寝台の上で信は未だ寝息を立てていた。
身の回りの世話を任せている侍女の話だと、朦朧としながらも、信が目を覚ますことが幾度かあったそうだ。
その時に水や食事を摂らせながら、調合した薬を飲ませ、また眠らせている。その甲斐あってか、左脚の傷はすっかり塞がりかけていた。
「…信」
眠っている彼女に呼びかけるが、目を覚ます気配はない。
頬に触れても前髪を指で梳いてやっても身じろぎ一つしないことから、未だ深い眠りに落ちていることが分かった。
「………」
身を屈め、昌平君は彼女に口づける。眠っている彼女に口づけるのはこれが初めてではなかった。
角度を変えて何度も唇を重ねる。柔らかい感触に夢中になった。
「ん…」
薄く開いている口に舌を差し込み、歯列や歯茎をなぞり、赤い舌を絡ませる。
決して信の方から口づけに応えてくれることはなかったが、幸福感で胸がいっぱいになっていた。
彼女に触れている今この瞬間だけは、この女は自分のものであるという実感が湧いた。
目を覚ます気配のない信の体を組み敷くと、二人分の重みで寝台がぎしりと軋む。
眠っている彼女に口づけながら、昌平君の手が彼女の帯を解いた。襟合わせを広げると、信の傷だらけの肌が現れた。
屋敷に連れて来てから、幾度も見て来た身体だというのに、何度見ても欲情してしまう。昌平君は生唾を飲み込んだ。
身を屈め、貪るように彼女の肌に吸い付く。
着物で隠れていた彼女の肌には、幾つもの赤い痕が残っている。新しいものから消え掛けているものまであり、それは全て昌平君がつけたものだった。
彼女の艶のある肌に顔を埋め、また新しい痕を刻み、優越感に胸を浸らせる。
「信…」
まるで恋人同士のように、敷布の上で指を交差させ、名前を囁く。
当然ながら信が返事をすることはなかったが、いずれは同じ想いであると応えてくれるはずだと昌平君は信じて止まなかった。
控えめだが手の平に収まるほど形の良い胸を揉みしだく。隆起の先端は、素肌に溶け込んでしまいそうなほど薄い桃色で、まだ芽を立てていなかった。
指で摘まんでやり、優しく愛撫を続けていくと、硬く芽を立てていく。
「は、…」
僅かに吐息が聞こえ、昌平君が上目遣いで信を見上げる。
まだその目は閉じられたままだったが、胸への刺激に反応を示したのは確かだ。
硬く立ち始めた芽を舌で転がし、唇で優しく食む。僅かに身体が震えたのが分かった。
眠っていても刺激を感じているのなら、目を覚ました時にはどのような反応を見せてくれるのだろうか。
…その答えを知る日はそう遠くないだろう。
甘く歯を立てながら、昌平君は彼女の足の間に手を伸ばした。
秘め事
当然ながら、そこは濡れていなかった。眠っているのだから、反応が鈍いのも当然だろう。
体を起こした昌平君は彼女の膝を立て、足の間に身体を割り込ませた。
自分の指を咥えて十分に唾液を纏わせると、その指で二枚の花弁の合わせ目をなぞる。
唾液の潤いが移ったのを確認してから、二枚の花びらを指で押し広げた。艶めかしい紅色の淫華が現れ、思わず生唾を飲み込んでしまう。
蜜を流し始めれば、この紅色がますます美しく輝くことを昌平君は知っていた。
淫華に顔を寄せると、入り口の部分を狭める襞が見える。
処女膜がまだ健在していることが、信がまだ男の味を知らない何よりの証拠だった。
迷うことなく昌平君はそこに舌を伸ばす。
破瓜の痛みは男が想像出来ないほどの苦痛を伴うという。薬と香で眠らされている信も、破瓜の痛みを感じれば目を覚ますだろうか。
もしも破瓜の痛みで信が目を覚まし、自分と身を繋げているのだと分かれば、彼女は一体どのような表情を見せてくれるのだろう。
そんなことを考えながら、昌平君は未だ破られていない処女膜に舌を伸ばし、淫華に唾液を注ぎ込んだ。
唇と舌を使って花芯も可愛がっていると、中の肉壁が、唾液ではないもので潤い始めたのを察した。
繊細な淫華を傷つけないよう、ゆっくりと人差しを差し込んでいく。
指を出し抜きする度に卑猥な水音が立ち始め、眠っているはずの信が軽く息を切らしているのが見えた。
「はっ…ぁ、ぅ、うぅん…」
意識は眠りに落ちていても、体は刺激に反応しているのだ。
そのことに気を良くしながら、昌平君は中に入れた指を鉤状に曲げて肉壁を擦り上げる。
「ッあ、ぁ…」
ある一点を指が擦った時、眠っているはずの信の身体が仰け反った。
「信?」
名前を呼ぶが、信の意識は未だ眠りに落ちたままである。
蜜を垂れ流している淫華に指をもう一本突き挿れ、再び抜き差しを始めた。
もっとして欲しいと訴えるかのように、肉壁が打ち震えているのを感じ、昌平君の口角は自然とつり上がっていった。
まだ一度も触れてもいないのに、眠っている信の体を弄っているだけで男根が上向いている。
「はっ…」
乱暴に着物を脱ぎ、昌平君は余裕のない手付きで男根を扱く。
根元の辺りを手で扱きながら、反対の手で花弁を押し開き、先端を淫華の入り口に擦り付けた。
信が眠っている間に、こうして自慰に浸るのは初めてではない。眠り続けている彼女の口唇を使ったこともある。
破瓜を破っていないものの、信の体を汚しているという自覚は十分にあった。
もとより、信を手に入れるために密通の疑いをかけ、この屋敷に連れて来たのだ。
本当ならば見つめ合いながら、手を繋ぎ合って、性器だけじゃなく心も繋げたい。
しかし、それが叶わないことを昌平君は分かっていた。信が秦将であり続ける限り、彼女の瞳には戦しか映らない。
「信…っ」
息を荒げながら、昌平君は切なげに眉根を寄せて男根を扱いていた。
「っ、あ…!」
全身に痺れが走り、頭の中が真っ白になる。
尿道から精液が勢いづいて吐き出され、艶めかしい紅色をした淫華と内腿を白く汚した。
息を整えながら、白濁が淫華の中に流れ込んでいくのを見つめる。
(将をやめさせるのなら、私の妻にして、孕ませてしまえば良い)
ふと、思考を過ぎったその考えは、恐ろしいほど呆気なく昌平君の中に染み渡っていった。
秘め事 その二
今までは信の体を使って虚しく自慰に浸っていたが、今となってはこの行為にも十分に意味を見出せた。
信から戦を奪うには、将をやめさせれば良いのだ。密通の疑いを利用して、将としての信頼を喪失させて、居場所を失くせば良い。
趙への密通だけでなく、李牧との姦通した事実を広めれば、信は秦将の立場どころか、その首を失うことになるだろう。
しかし、嬴政が親友である彼女を断罪できるとは思わない。恐らくは秦将の立場から降ろす慈悲に留めるはずだ。
信を将の座から降ろすその計画は、聡明な昌平君の中では、手足を切り落とすよりも簡単なことだった。
「信…」
昌平君は体を起こし、未だ寝息を立てている彼女に再び口づけた。
何度も唇を重ねていると、それだけでまた男根が上向いて来る。先ほど吐精したばかりなのに、体が目の前の女を求めて欲情しているのだ。
醜いまでに浅ましい欲望だと思う。
それだけ自分は信のことを欲していて、自分の欲望を叶えるために、彼女の将としての人生を壊そうとしている。
すまないと心の中で謝罪をしながらも、昌平君はやめるつもりはなかった。
もう自分の意志一つでは安易に止められぬほど、信を手に入れる欲望は広く深まっていたのだ。
「……、……」
信の両膝を広げ、淫華に再び男根の先端を宛がう。
今までのように性器を擦り付け合うのではなく、いよいよ挿入を試みた。
「っ…」
蜜と白濁が混ざり合って、淫華の入口がぬるぬると滑った。
しっかりと入り口に先端を押し当て、ゆっくりと腰を進めていくと、入り口を狭めている処女膜が、まるで男根の侵入を拒むように押し返して来る。
「くっ」
昌平君は信の体を抱き締めながら、力強く腰を前に押し出した。
ぶつん、と処女膜が裂けた感触がした途端、押し返される感覚がなくなり、一気に奥まで男根が突き刺さる。
「あ”ッ…」
掠れた声がして、弾かれたように顔を上げると、信が喉を突き出して口を開けていた。しかし、まだその瞼は閉ざされたままである。
無駄な肉など少しもついていない引き締まった太腿が僅かに震えている。眠っている意識でも、破瓜の痛みを感じているのだろうか。
自分の男根を根元まで咥え込み、血の涙を流している淫華を見下ろし、ようやく信と一つになったのだと実感した。
男根を包み込んでいる肉壁の感触に、快楽が押し寄せて来る。今までは性器を擦り合うだけだったが、彼女の中は想像以上に温かくて気持ちが良かった。
「…あ、…は、ぁ…」
信が唇を戦慄かせている。
眠っているはずの彼女の瞼から涙が伝ったのを見て、昌平君は身を屈め、その涙を舌で掬い上げた。
「ん、…ぅん、…っ」
唇を重ねながら、昌平君はゆっくりと腰を引いていく。開通したばかりの道はまだ狭く、男根を締め付けたまま放そうとしない。
信に意識はないはずなのに、まるで男根を強請られているかのようだった。
「ッ…!」
浅く抜いた男根をもう一度深く叩き込むと、信の体が力なく仰け反った。
敷布の上に力なく落ちている信の手に指を絡ませ、口づけを続けながら、昌平君は堪らず腰を律動させていた。
破瓜の血と蜜と精液が合わさって、卑猥な水音を立てている。
「は、はあっ、ぁっ、ぁ…」
体を揺すられながら、信の唇からも吐息が洩れていた。
眠りながらも自分を感じてくれているのだと思うと、昌平君の胸は火が灯ったかのように熱くなる。
寝台が激しく軋む音が行為の激しさを物語っていた。
「ぐっ、…ぅ…!」
絶え間なく息を弾ませ、時々歯をきつく食い縛って、くぐもった声を洩らす。
信が男を咥えるのが初めてなら、無理はさせるべきではない。頭では分かっているのだが、欲望が先走るあまり、加減が出来なかった。
口づけの合間に、愛していると囁き、昌平君は絶頂に駆け上るために、激しく腰を揺すった。
「ッ…!」
やがて、全身を戦慄にも似た激しい痺れが再び貫いた。
目の前が真っ白に染まる。体の奥底で生成された熱が爆発を起こしたようだった。
「はあッ…、はあ、はっ…」
下腹部を震わせながら、信の細腰を掴んで引き寄せ、最奥で吐精する。
子宮の入口に男根の先端を押し付けたまま、吐精を終えた後も、しばらく動かずにいた。
このまま子種を植え付けて、孕ませてしまえば、信はどのみち将の座を降りることになる。
少しずつ冷静になって来た思考で、昌平君はやはり彼女を手に入れるために、信の全てを奪おうと決意するのだった。
「…何も、心配することはない」
静かに囁き、昌平君は信の額に口づけを落とす。
まだ何も知らずにいる彼女は、目を覚ましたら、どんな表情を浮かべるのだろうか。
後日編
※本編の後日編です。
腕の中で眠っている妻が僅かに身じろいだので、起きたのだろうかと昌平君も瞼を持ち上げた。
窓から白い日差しが差し込んでいることから、まだ陽が昇り始めたばかりだと気づく。
彼女の色素の抜けてしまった髪がきらきらと輝いていた。美しい宝石のような髪を指で梳いていると、信の瞼がゆっくりと持ち上がる。
「…昌、平君…?」
寝ぼけ眼でこちらを見上げる信に、つい口元が緩んでしまう。
「眠っていろ」
肩まで寝具をしっかりと掛けてやり、その体を抱き締め直すと、信の身体があからさまに強張っていた。
いつもなら、甘えるように胸に凭れ掛かって来て、すぐに寝息を立て始めるのに今日は違う。
「信?」
悪い夢でも見たのだろうかと顔を覗き込むと、彼女の顔から血の気が引いていた。
「な、なに…して…」
驚愕のあまり、体を強張らせているのだと気づいた。
冷たい指先で昌平君の胸を押し退け、信が勢いよく寝台から起き上がる。
見知らぬ部屋にいると気づいた信が戸惑った表情で昌平君を見つめている。なぜ自分はここにいるのだと答えを知りたがっているのだろう。
「…あまり無茶をするな。体に障る」
「やめろっ」
ゆっくりと身を起こし、信の手首を掴むと、その手を振り払われた。
宙を切って行き場を失った手に虚しさを覚えながら、しかし同時に懐かしさを覚える。
「なんなんだよっ…」
怒りと不安が混ざり合った表情で、信は寝台から立ち上がろうと床に足をつけた。
「身重の身体でどこへ行く」
腕を掴みながらそう言うと、身重という言葉に反応したのか、信の身体が硬直する。
ゆっくりとこちらを振り返った信の顔は笑えるほど白くなっていて、見開かれた瞳がゆっくりと下に向けられる。
掴まれた手を振り払うこともせず、彼女は呆然と薄口を開けていた。
「え…、な、なんで…?」
なだらかに突起した臨月を示す腹に、自分の腹に赤子が眠っていることが信じられないようだった。
「お、俺…いつ、こんな…」
動揺のあまり、身体の震えは止まらず、立っているのも辛いようだった。その身体を支えながら寝台へと連れ戻すと、信は俯いたまま顔を上げないでいた。
視線の先にある膨らんだ腹を見て、言葉を失っているのだと気づき、昌平君はおもむろに彼女の腹を撫でてやる。最近になって、胎動がより目立つようになっていた。
「私とお前の子だ」
「は…?」
聞き返した声は、情けないほど震えていた。
腹を撫でている昌平君の優しい手付きにすら怯えているのか、信の身体が泣きそうなほど顔を歪めている。
どうやら、あの香の効力が解けたようだ。
使用を続けることで、記憶を失うという恐ろしい副作用があるのだと医師から聞いていたが、時々記憶が元に戻るらしい。
昌平君の妻になったことや、子を孕んでいることを忘れ、将だった頃の彼女の意識が戻って来る時があるのだ。
将だった頃の全てを忘れ、自分の妻の役目を全うしていた信ももちろん愛おしいが、昌平君が惚れたのは将だった頃の彼女だ。
もちろん記憶が抜け落ちていたとしても、信であることには変わりない。
どちらも愛おしい存在であり、昌平君にはかけがえのない存在である。
「い、いやだ…なんで、こんな…」
青ざめて涙を流し始める信は、昌平君の子を孕んでいる事実を受け入れられないでいるらしい。妻になったことも覚えていないのだから当然だろう。
浅い呼吸を繰り返している信を慰めるように、昌平君は優しい手付きで頭を撫でてやる。
またあの香を焚けば、自分に従順な妻が戻って来るのは分かっていたが、昌平君はそうしなかった。
「…お前の将としての役目は終わった」
何を言っているのか理解出来ないといった顔で、信が涙目で昌平君を見つめている。
「お前が生きる場所は、ここだけだ」
昌平君はその涙を舌で舐め取ると、何度目になるか分からない愛の言葉を囁いて、信の体をゆっくりと寝台に押し倒したのだった。
終
昌平君×信のハッピーエンド話はこちら
信が昌平君の護衛役を務める話はこちら