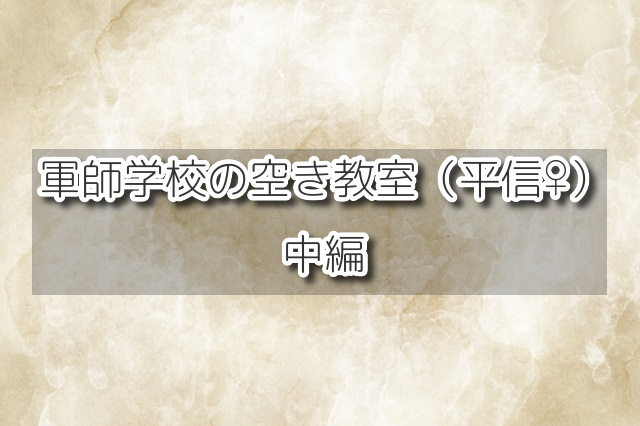- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 昌平君×信/ツンデレ/ギャグ寄り/IF話/軍師学校/ハッピーエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
進展と妨害
軍略の基礎中の基礎を、信は三か月かけて、どうにか頭に詰め込んだ。
基礎を覚えたら次のことを教えると昌平君は伝言をしていたが、特に彼が指導をすることはなく、信はひたすら河了貂と蒙毅を相手に軍略囲碁を打っていた。
覚えたばかりの陣形を実際に動かすと、どのような時に利点と欠点があるのか理解出来るようになる。
もしかしたら昌平君はそれを見越して、軍略囲碁を打たせているのかもしれないと信は思った。
軍略囲碁はあらゆる地形、戦い方を想定して行うため、同じ条件で勝負をすることはほとんどない。それだけ軍略の形には数が多く、戦い方もその倍は存在している。
河了貂も蒙毅もこの軍略学校で軍師としての才能を開花させており、信は二人を相手に何敗もしていた。
しかし、数を重ねていけばいくほど、あらゆる動きの想定が出来るようになっていき、勝利に至ることはなくとも、敵本陣に攻め込む一歩手前まで駒を進められるようになっていた。
(…あ、ここに道がある)
軍略囲碁をこなしていくうちに不思議なことが起きた。それは軍略囲碁をしている最中に、道筋が見えるようになったことだ。
蒙毅と河了貂には見えていないようだが、まるで光が浮かび上がるかのように、一つの道が見えるのだ。
浮かび上がった光の道の先には敵大将のいる敵本陣があって、導かれるようにそこに駒を進めると、蒙毅と河了貂は驚いたように、その道の妨害をしようと別の駒を進める。
敵の駒が動くと、そちらの対処もしなくてはならないので、光の道が消えてしまう。しかし、そうしているうちにまた別の道が浮かび上がり、信はまたそこに駒を進めていく。
初めのうちは余裕の表情を浮かべて信に圧勝していた蒙毅と河了貂だが、日を追うごとに苦戦を強いられるようになっていた。
二人を相手に幾度も勝負を重ね、軍略囲碁を打った数はとうに三桁を越えようとしていた。
優等生である河了貂と蒙毅が苦戦を強いられている姿を見て、周りの生徒たちも信の軍略囲碁を注目するようになり、勝負の度に生徒たちが囲碁台を取り囲むようになっていた。
「あー、くそーっ、また負けた…!」
河了貂が駒を進め、信の本陣を奪ったことで軍略囲碁は終了。此度も河了貂の勝利だった。
追い詰めはするものの、あと一歩というところで敵本陣への道を妨害されてしまう。
光の道筋が消えてしまうと、敵の駒を対処することに集中するのだが、次の道筋が浮かび上がる前にこちらの本陣を落とされてしまうのがいつもの敗因だった。
「いや、あのまま進められてたら俺は負けてたよ」
勝負を終えた河了貂は安堵したように、長い息を吐き出す。
「うん。今回も危なかったね」
口元に手を当てながら、蒙毅は険しい表情を浮かべている。信が動かした駒の動きをじっと見詰め、何かを考えているようだった。
過程がどうであれ、負けは負けだと信は椅子の背もたれに身体を預ける。
「ああー…考え過ぎて、頭いてえ…」
気づけば夕方になっていて、朝から軍略囲碁を打ち続けていた体は疲労を抱えていた。頭がずきずきと痛む。凝り固まった肩を回しながら、信は溜息を吐く。
頬杖をつきながら、信は疲労感に身を委ねていた。鍛錬ではなく、頭を使ってへとへとになるのは軍師学校に来てから毎日のことだった。
王騎からは相変わらず音沙汰はない。きっと今頃は厳しい鍛錬を終えて、花の浮かべた風呂に浸かっているのだろうなと信は考えた。
…一体いつになったら屋敷に帰れるのだろうと、信は目を伏せながら考えた。ずっと剣を振るわず、机上での学びを続ける日々で、すっかり筋力が落ちてしまった。
戦の気配はまだないようだが、軍師学校ではひたすら軍略について学ぶ場であるため、そういった情報が入って来るのは遅い。
将軍昇格への道が遠ざからぬよう、次の戦までには強化合宿を終えたいのだが、昌平君から合宿の終了条件に関しては未だ告げられていない。
しかし、河了貂と蒙毅を軍略囲碁で倒せるくらいにならないと許しを得られないような気がしていた。
王騎が言っていたように、五年や十年かかったらどうしようと信は不安と焦りを覚えた。
「…うおッ!?」
目を開くと、昌平君の横顔が目の前にあって、驚いた信は椅子から飛び上がった。
いつもなら河了貂と蒙毅に任せっきりである昌平君が、今は真剣な眼差しで囲碁台を眺めている。
河了貂の勝利で終わったことは見れば明らかなのだが、その過程についてを確かめているようだった。
「…なぜ、ここの軍を迂回させなかった?」
昌平君が軍に見立てた駒の一つを指さす。
「あ?」
今回設定した地形は特に山や川などの障害物のない平坦なものだった。
伏兵を隠せるような場所もなく、中央で激戦が行われる。それはこの地形を設定されてから信も河了貂も、もちろん他の生徒たちも分かっていた。
中央に集められた軍が陣形や兵法を用いて戦いを行う中で、信は軍を幾つかに分け、中央に集まっている敵軍を無視して前進を図ったのだ。
だが、兵力を分散させれば簡単に討ち取られてしまう。陣形を組んだ敵兵力の前なら尚更だ。しかし、信は陣形を作って対応することをせず、軍が壊滅する危険を犯してまで前進を続けたのだ。
無謀だとは思うが、がむしゃらに敵本陣を狙っているようには思えず、昌平君は彼女にその意図を尋ねた。
これには蒙毅も河了貂だけでなく、他の生徒も驚いていた。
なぜなら昌平君が一人の生徒に対して、そのような問いかけをするのは初めてのことだったからである。
わざわざ本人に尋ねなくとも、残っている結果を見れば、どちらがどのような動きをしたのか簡単に予想するほど、総司令官という役割を担う彼は聡明だからだ。
しかし、そんな彼が信に真意を問い掛けた。昌平君でさえ、信がこのように軍を動かした意図を計りかねているということである。
もちろんそんなことを知らない信は、囲碁台を眺めながら「んーと…」と間延びした声を上げ、考えていたことを思い出そうとする。
「全部の軍から百ずつ兵を分散させたから、合わせて五百をここで合流させて…」
信は激戦地を指さした。
五百の兵に見立てた駒を手に取り、信は敵本陣へ繋がる一本の道へと運ぶ。それは河了貂と軍略囲碁の最中に見えた光の道筋だ。
「ここの道を通れば、敵本陣に行けると思ったんだ」
大胆にも敵と味方が入り組んでいる場所の真横をすり抜けて、信は敵本陣を目指そうと睨んでいたのだ。
河了貂と蒙毅は、信が駒をその道に進ませた時に驚いていた。信が駒を進ませた場所が道になっていることに、二人は気づけなかったのだ。
二人も他の生徒たちも、真横を通ろうとは考えもしなかった。敵本陣へ向かうならば、敵味方が入り組んでいるその場を大きく迂回するはずと考えていたのだ。
結局は五百の兵を向かわせている最中に、分散してしまった味方兵力を押し抜いた複数の敵軍によって、味方本陣を先に取られてしまったことが此度の敗因である。
「…そうか」
昌平君はそれだけ言うと、背を向けて行ってしまった。
(なんだったんだ?)
軍師学校に来てからというものの、彼からは何も教えられていないなと思いながら、信は両腕を頭の後ろに組む。
進展と妨害 その二
使用した駒を片付けようとしない信に、河了貂は腕を組んで彼女を睨み付けた。
「おい、信ッ!片づけは負けた方がやる約束だろ!」
「んな怒るなよ。今やるとこだったって」
やれやれと椅子から立ち上がり。信は囲碁台の上に並べてある駒を手に取っていく。
「じゃあ、俺から宿題だ。軍略基礎の木簡の第一巻を読み直すこと!平坦な戦での兵法や陣形が載ってるから、もっかい読んでおけ」
久しぶりに木簡の話題が出て来て、信はどきりとした。
「あー…えーと、だな…」
あからさまに表情を曇らせて目を泳がせる信に、河了貂は円らな目をさらに真ん丸にさせる。信が嘘を吐けない性格なのは、昔から付き合いがあるからこそ分かっていた。
軍略学校からの付き合いである蒙毅でさえも、信のあからさまな動揺に疑問を感じているようだった。
「どうしたんだよ?なんかあったのか?」
「いや、その…部屋に、ある…んだけどよ…」
「?」
河了貂と蒙毅が二人して目を丸める。部屋に置いてある木簡がどうかしたのだろうか。
まさか失くしたとは思えない。あんな質素な部屋ならば、木簡を失くすような要因など何一つないだろう。
だとすれば一体何があったのか、二人の聡明な頭脳を持っていたとしても、想像が出来なかった。
教室にも同じことが記されている木簡はあるのだが、今は他の生徒が目を通しているようだったので、河了貂は仕方がないと溜息を吐く。
「じゃあ、俺が信の部屋から持って来てやるよ」
「えッ!?いや、部屋戻ったらちゃんと読むから大丈夫だッ」
「なんか怪しい!そこで蒙毅と待ってろ!」
信の制止も聞かず、河了貂が宿舎へ向かおうとする。彼女を止めようと信は腕を伸ばしたが、河了貂はその手をすり抜けてさっさと行ってしまった。
あからさまに動揺している信を横目で見て、蒙毅はどうしたのだろうと小首を傾げていた。
「―――信ッ!!」
しばらくして信の部屋から木簡を持って来た河了貂は憤怒の表情を浮かべていた。
彼女が持って来たのは一つだけではなく、両手に抱え切れるだけの木簡だ。
第一巻を読み直すように信に言っていたはずなのに、どうしてそんなに持って来たのだろう。
だが、信は理由が分かっているようで顔を強張らせて、泣き笑いのような表情を浮かべている。
「どうしたんだよ、これッ!」
「テンッ、声がでけえよ!」
あたふたと信が河了貂の口を塞ごうとするのだが、河了貂の怒りは止まらない。教室中に彼女のよく通る高い声が教室に響き渡ったことで、生徒たちから好奇の視線が向けられていた。
昌平君だけは相変わらず手元にある木簡に目を通していて興味を示していないようだが、河了貂の声は彼の耳にも届いているだろう。
「一体誰にやられたんだよッ!こんなの、自分でやるはずないだろ!」
顔を真っ赤にして声を荒げながら、河了貂が信の部屋から持って来た木簡を広げる。軍略の基礎について記されているはずの木簡には、全ての文字を覆うように墨が塗られていた。
不注意で墨を零したような染みではなく、わざと文字が読めなくなるような塗り方をされていた。
「これは…」
蒙毅が瞠目する。
他の木簡を広げると「出ていけ」「帰れ」「下僕出身」「奴隷の分際で」などと言った文字が乱雑に記されており、記されている文字などとても読めそうにない。
どれも墨は乾き切っており、随分と前からそのような状態になっていたことは蒙毅も河了貂も簡単に予想がついた。
木簡について信が狼狽えたのは、きっとこのことを知っていたからだろう。
「お、落ち着けって…」
目をつり上げて自分のことのように憤怒している河了貂を宥めようと、信が声を掛ける。しかし、河了貂の怒り少しも収まらない。
彼女はぐるりと教室を見渡して、初日に信へちょっかいを出して来た黄芳のもとへと大股で近づいた。
「黄芳ッ!お前がやったのか!」
河了貂に怒鳴られて、黄芳はあからさまに顔を引き攣らせた。教室に張り詰めた空気が広がる。
「い、いきなり何だッ!そんな言いがかりをつけて…!俺がやったっていう証拠でもあるのかッ!」
「いつも信にちょっかい出してたのお前だろッ!お前以外に誰がやったって言うんだよッ」
ちょっかいという範囲で収まるかどうかは話が別だが、黄芳が一番の容疑者だというのは誰もが予想していた。
軍師学校に入門してから、信が軍略基礎を頭に詰め込み終えるまで、黄芳は頻繁に口を出しに来た。
初日に投げつけたような軽い嫌味ばかりで、信は大して気にしていなかったのだが、河了貂と蒙毅はその度に彼に言い返してくれたのである。
しかし黄芳はしつこく、軍略のことを何も分かっていない信にやたらとちょっかいをかけ続けた。
ここでは素性を明かさないという王騎との約束を守るために、信が「自分は下僕出身で運よく入門できただけだ」と黄芳に告げてからは、彼の言動は激化したように見える。
下僕出身だと言えば素性も隠せるし、相手にされなくなるだろうと思っていたことが、裏目に出てしまったようだ。
どこかの貴族の出なのだろうか、取り巻きの連中も何人かいるし、もしかしたら木簡のことも彼らに命令してやらせたのかもしれない。
今までのことを考えると、黄芳しかありえないというのが河了貂の見解だった。
「信に謝れよ!」
「な、なんで俺が!俺がやったっていう証拠もないくせにッ!」
このままではどちらかが手を出して暴力沙汰になると思い、信は蒙毅と共に河了貂のもとへと急いだ。
二人の間に割って入り、信は河了貂の丸い肩を掴む。
「テン、やめろ。お前ももうガキじゃねえんだから」
「なんで信も黙ってたんだよッ!」
墨だらけの木簡を指さして河了貂が信に迫る。
「それは…」
言えば今のような騒動になると分かっていたし、大事にしたくなかったのもあるのだが、何より、このような幼稚な真似をする者の相手にするのが面倒臭かったというのが一番の本音である。
下僕出身なのは事実だし、当時に受けた待遇に比べたら黄芳の行いなど大したことではないと思っていた。
そんなことを、頭に血が昇っている彼女に本音を打ち明ければ確実に殴られてしまうと思い、信は口を噤んだ。
「―――今日はこれで終いだ。皆、帰りなさい」
教室に漂っている張り詰めた空気を打ち破ったのは、立ち上がった昌平君の一言だった。
黄芳は逃げるように教室を飛び出していき、他の生徒たちも嫌な空気から逃れるように足早に教室を出て行った。
教室に残ったのは昌平君と信、それから河了貂と蒙毅の四人である。
「さ、さーて、俺も戻ろーっと」
何事もなかったかのように信も教室を出ようとするのだが、残念ながらそんな上手く逃げられる訳がなかった。
「信!話はまだ終わってないぞッ!なんで黙ってたんだよッ!」
河了貂に背中から腕を掴まれて、信は肩を竦めるようにして笑った。
「んなこと言ったってよ…今さらどうしようないだろ、これ」
真っ黒に塗り潰された木簡に視線を向けて信がそう言うと、河了貂が悔しそうに奥歯を噛み締めた。
木簡がこのようになっていると気づいた時、信も河了貂と同じくらい驚いた。しかし、驚愕の後にやって来たのは、怒りではなく諦めだった。
自分が騒いだところで犯人が名乗り出るとは限らない。河了貂は黄芳の仕業だと信じているようだが、彼を罰したところで木簡が元に戻る訳でもない。
恐らくそれは昌平君も思っていることだろう。何も言わずに信の姿を見つめているが、その瞳からは怒りも感じないし、咎めようとする様子は微塵もなかった。
軍師学校の夜
授業が終わり、生徒たちが宿舎に戻ると、軍師学校はもぬけの殻になる。
宮廷のあちこちには常に見張り役の衛兵たちが出入りしているため、昌平君は一人になりたい時や、集中して何かを考えたい時は、夜の軍師学校に来る習慣があった。
今日中に目を通しておこうと考えていた木簡を片手に、反対の手には明かりを持ち、昌平君は廊下を歩く。
誰も居ないのだから使う教室はどこでも良かったのだが、突き当りにある空き教室を使うことが多かった。空き教室の窓から月がよく見えるからだ。
月見をするのではなく、月明かりが差し込むので、文字が読みやすいという味気ない理由である。今宵は満月で、月の光がより多く差し込んでいた。
「…?」
突き当りの空き教室から明かりが洩れているのが見えて、昌平君は僅かに身構えた。
生徒たちは既に宿舎に帰っている時間だし、この時刻なら既に寝入っているはずだ。自分以外にここを利用する者がいたのかと驚いたのが正直なところだ。
心当たりがあるとすれば、同じ呂氏四柱の一人である蔡沢くらいである。しかし、彼は外交に出ているため、今は不在にしているはずだ。
野盗という可能性もあるが、ここは学校で金目の物などは置いていないし、そう言った目的なら宮中に行くはずだ。宮廷内にあるこの学校も易々と忍び込めるような建物ではない。
生徒が軍略が記された木簡を読み耽っているのかとも考えたが、わざわざ空き教室を利用せずとも、宿舎の部屋で読めばいいはずだ。
昌平君が明かりが灯っている空き教室を覗き込むと、そこにいたのは信だった。
椅子を使わず、窓枠に腰を下ろして月を眺めている…だけなら良かったのだが、傍らに酒瓶と杯があるのを見て、昌平君は思わず眉根を寄せた。
「ここは学校だぞ」
「授業が終われば学校じゃなくて、もぬけの殻だろ」
昌平君に声を掛けられても信は驚きもしないどころか、振り向かずにそう答えた。足音と気配で自分だと気づいていたのだろう。
空になっていた杯に酒を注ぎ、信は豪快に飲み干す。女にしては良い飲みっぷりだった。
「どこから持ち込んだ」
近くにあった椅子に腰を下ろし、持って来た木簡を広げながら昌平君が尋ねる。
「麃公将軍からの差し入れだ。お前も飲むか?」
ようやく振り返った信の顔は紅潮していた。ここで飲み始めてからどれくらい時間が経ったのかは分からないが、既に酔っているようだった。
軍師学校に信がいることを麃公は一体どこから知ったのだろうか。もしかしたら宮廷で遭遇したのかもしれない。
強化合宿と称しているが、授業以外の時間は拘束していない。王騎との約束があるため、屋敷に戻らず、宮廷で暇を潰していたのかもしれないと昌平君は考えた。
麃公も咸陽宮を出入りすることがある将軍だ。大酒飲みで知られている彼は、王騎とも交流があり、彼の養子である信のことも気にかけているようだ。
持って来た木簡にざっと目を通してから、昌平君は彼女の近くに椅子を寄せた。酒の誘いに乗ったのだ。
「ああ、悪いな。杯は一つしかねえんだ」
信が手に持っていた杯を掲げながら言う。構わずに昌平君は彼女の手から杯を奪い、酒を注いだ。
口に含んだ途端、ぬるいせいか、酸味と苦味がはっきりと舌に広がる。しかし、雑味が含まれていない分、後味はすっきりとしていた。芳醇な香りもまた良い。飲み込むと、胃に火が灯ったかのような感覚を覚える。
思わず長い息を吐いた昌平君を横目で見た信は、楽しそうに目を細めていた。
強い酒だというのは、大酒飲みである麃公からの差し入れだと聞いた時から察していたが、酒に弱い者が飲んだら卒倒してしまうだろう。
酒瓶の中身はまだ半分も減っていなかったが、こんなにも強い酒を一人で飲み干そうとしていたのだから、彼女は随分と酒に耐性があるらしい。
月見酒と特別授業
一つの杯で酒を飲み交わしていると、信がどこか寂しそうな表情で月を見つめていた。
酒瓶の中身が大分減って来た頃、昌平君の頬にも赤く染まっており、酔いが回り始めたことを自覚する。
「…なぜあの者たちに言い返さず、黙っている」
気づけば昌平君は信にそう尋ねていた。尋ねる気など微塵もなかったのに、口を衝いて言葉が出てしまったのだ。きっと酔いのせいだろう。
彼女が軍師学校に来た初日から、黄芳や彼の取り巻きの生徒たちから、軍師の才がないことを馬鹿にされていることを、昌平君は知っていた。
彼女が何も言い返さない分、代わりに蒙毅と河了貂が彼らを軍略囲碁で打ち負かしているのも、視界の隅でいつも見ていた。だが、信が黄芳に言い返したり、怒っている姿は一度も見たことがなかった。
「下僕出身なのは事実だろ」
「…庇うのか?」
昌平君が聞き返すと、信が不思議そうに首を傾げた。
「は?何も間違ったことを言ってねえあいつらから、何を庇うって言うんだよ」
まさかそんな答えが返って来るとは思わず、昌平君は表情を変えずに驚いた。
感情的になりやすいことは信の弱点だと思っていたのだが、黄芳や取り巻きたちに掛けられる言葉に、信は微塵も興味を抱いていないらしい。
気にしないようにしているのか、それとも本当に鈍いのかは分からないが、河了貂が怒るのも頷けた。
「下僕出身の俺が気に入らないんだろ。そんなのは王賁から言われ慣れてる」
王一族の中心である宗家には、信の幼馴染である王賁がいる。玉鳳隊の隊長である彼は、下僕出身である信が王家の一族に加わることが気に食わないのだという。
しかし、信は剣に覚えがあり、初陣から武功を挙げ続け、あっという間に五千人将にまで上り詰めた。王騎と摎が見抜いた力を発揮したのだ。
王賁から下僕出身のことをあれこれ言われなくなったのは最近だというから、恐らく彼も信の実力を認めようとしているらしい。
空になった杯を昌平君の手から奪い取りながら、信は酒を注いだ。青白い月明りを浴びた彼女の横顔が何だか儚げに映って見えた。
「…平等って、何なんだろうなあ」
信の口からその言葉が出て来るのは初めてのことだったが、彼女が疑問に思うのも当然だろうと昌平君は思った。
注いだ酒を一気に喉に流し込むと、信がにやりと歯を見せて笑った。
「下僕にも、当たりとはずれがあるんだぜ。知ってるか?」
「………」
何を言わんとしているのか、昌平君には手に取るように分かった。
この戦乱の世では親を失って、下僕として売り捌かれる子どもは珍しくない。信のように才能を見初められて、下僕の立場を脱する者はほんの一握りしかいないのだ。
信と時機を同じくして奴隷商人に売られた者たちは、今も下僕としての生活を続けている者が大半に違いない。
自分は当たりであると信にも自覚があるらしい。もちろんそんなことは本人だけでなく、誰に聞いても答えられる質問だ。
「そんじゃあ、下僕の当たりはずれには、どんな種類があるかを知ってるか?」
一歩踏み込んだ質問が投げかけられる。信のように名家に引き取られるのが当たりなら、他にはどのような道があるのか。
安易に想像はつくのだが、下僕の出だからこそ知っている話もあるのだろうと、昌平君は彼女の言葉に耳を傾けていた。
何も答えない彼が話を聞く態度でいるのを見て、信が得意気に笑う。
「特別に今日は俺が先生になって授業してやるよ。机上じゃ絶対に知らない知識ばかりだ。良い勉強になるぜ?」
立ち上がった彼女は、酔いのせいでふらふらとした足取りだったが、まるで教鞭を執るように空き教室の中心に立った。
「下僕ってのは、運が良けりゃあ、奉公先で金持ちの旦那に飼われることもある。女だろうが男だろうが関係ない。物好きはたくさんいるからな。慰み者になって死んでく奴もいる」
「………」
酒で顔を赤く染めながら、誇示するように信は饒舌を振るう。
「姓がなくたって、力があればそれだけで価値がある。下僕の中でも、男ってだけで優遇されるんだよ」
男の下僕ならば農耕や荷役などの重労働をさせるために、その労働力を買われることも、徴兵されて軍事力にもなると言いたいのだろう。
酔いが回っているせいで、立っているのが辛くなったのか、信は昌平君の向かいにある椅子に腰を下ろした。
「…織布や家事とか、そりゃあ女にも色んな仕事はあるけどよ。女はそれなりに顔が良けりゃあ、娼館や後宮に売られたり、どこかの男の妾になることもある。妓女として才能があるんなら、出世だってできるんだ」
女の下僕は、男とは大いに生き方が異なるのだと信は言った。
「女としての価値が買われるんなら、飢えも寒さも凌げる。…それじゃあ、ここで先生に質問だ」
信が口元に笑みを繕った。口元とは正反対で、その瞳は少しも笑っていない。
「見てくれも悪けりゃ、愛想も物覚えも悪い。何の取り柄も価値もねえ女はどうなると思う?」
「……」
昌平君はすぐには答えなかった。口を噤んでいる彼を見て、信が不思議そうに小首を傾げる。
「そんなに難しいかよ?前に王賁や蒙恬にも聞いたけど、あいつらも答えられなかったんだよな。簡単だろ」
つまらないという表情で信が椅子の背もたれに身体を預けた。
「それは違う」
昌平君が低い声で否定すると、信は彼に視線だけを向ける。
「二人が答えなかったのは、お前を気遣ったからだろう」
その言葉に、信の口の端が引き攣った。一瞬、彼女の目から殺意にも憤怒にも似た、底知れぬ感情が浮かび上がったのを昌平君は見逃さなかった。
「…それじゃあ、お優しい名家の嫡男様たちのように、お前も俺に気を遣って答えないってことか?」
挑発的な瞳を向けられ、昌平君は静かに口を開いた。
「…世を儚み自ら死を選んだか、悪戯にその命を奪われたか、どちらかだろうな」
どうやら正解だったらしく、信があははと笑いながら拍手を送った。
「見たことあるか?これから戦に出るどこぞの嫡男様に、逃げ惑ってるところを弓矢の的にされたり、武器の切れ味を確かめるのに使われることもあるんだぜ?埋葬もされないまま、野ざらしで捨てられて、カラスや獣の餌になったやつだっている」
次々と信の口から告げられていく残酷な事実に、昌平君は口の中に苦いものが広がっていく。
奉公先でいじめに耐え切れず自ら命を絶つ者や、飢えや寒さに耐え切れ得ず亡くなっていく者がいるのだろうと想像していた。
しかし、信の口から聞かされたのは、あまりにも粗末な扱われ方だった。
同じ命だというのに、生まれが違うだけで、こんなにも生き方が異なる。だからこそ信は平等について疑問を感じていたのだろう。
信は将軍の才を王騎と摎によって見抜かれたことで、そのような死を回避出来た。だが、もしも二人が信を見つけてくれなかったのなら、その辺に転がっている小石と何ら変わりない価値のまま、玩具のように弄ばれて殺されていたかもしれない。
「…生まれた時から恵まれている者たちが憎いか?」
どうしても問わずにはいられなかった。普段から言葉にしないだけで、信は内側に下僕の命を粗末に扱う者たちに怒りを秘めているのかもしれないと思ったからだ。
しかし、昌平君が問うと、信はすぐに首を横に振った。
「別に、そんなの考えたことねえよ。…腹が減った時に飯が食えて、屋根がある場所で眠れる。それで良いじゃねえか」
頬杖をついて、信はゆっくりと瞼を下ろす。酔いが回って眠くなって来たのだろうか。
「そんなことが当たり前だと思ってる坊ちゃんたちは、それ以上に何が欲しいんだろうな。俺には分かんねえよ」
微睡みながら、信が呟く。
完全に瞼を下ろし切ってしまった信がこのまま寝てしまうのではないかと思い、昌平君が声を掛けた。
「寝るなら部屋で寝ろ。風邪を引く」
「寝てねえよ。もうちょっとだけ…酒飲み終わったら、戻る」
すぐに動き出さないところを見れば、本当に寝入ってしまうのではないかと疑わしくなる。酒の中身は二人で飲んだおかげで大方減っているが、まだあと数杯分は残っていた。
あんな話をした後で、機嫌良く過ごせるはずがない。表面的には笑顔を浮かべていたが、心の中で、信はどう思っているのだろうか。
「っくしゅん!」
静寂を打ち消すように、信が盛大にくしゃみをかました。
わざとらしく溜息を吐いた昌平君は紫紺の羽織を脱ぐと、その羽織を信の体に掛けてやる。
「酒が回って暑くなった。お前が預かっておけ」
「え?」
「馳走になったな」
肩に掛けられた羽織に信が戸惑っている間に、昌平君は酒瓶と杯を持って空き教室を出て行った。学校に酒瓶があったとなれば騒ぎになるのは目に見えている。不始末にならないように持って行ったのだろう。
まだ中身が残っていたのにお預けを食らったような気分になり、信は口を尖らせる。
「………」
一人教室に残された信は複雑な気持ちを抱いていた。
いくら麃公が差し入れてくれた強い酒を飲んでいたとはいえ、陽が沈み、夜風が吹いている今は誰であっても「暑い」とは思わないだろう。
風邪を引かないよう配慮したことを言わず、恩着せがましくないやり方で自分に羽織を着せていった昌平君に、信は妙な苛立ちを覚えた。
「何なんだよ…」
大人の余裕を見せつけられた気分だ。
いつかその余裕ぶった態度を揺すってやりたいと思いながら、信は窓の向こうに浮かんでいる月を眺めていた。
事件勃発
翌朝の軍師学校に、信の姿がなかった。
屋敷にいる時は他の兵たちと同様に早朝から夜遅くまで厳しい鍛錬をこなしていた信だったが、ここでの生活に慣れてからは、朝は随分とゆっくりと起きるようになったらしい。
眠っているところを副官である騰に首根っこを掴まれて、無理やり部屋から連れ出されることもないと笑っていた。
だから河了貂も、信が教室に来るのが遅いことに何も疑問を抱かなかった。
しかし、その日は違った。生徒全員が学校に集合して、蒙毅と河了貂がいつものように軍略囲碁を打ったり、勉学に勤しんでいたのだが、いつまでも信は現れない。
軍略囲碁が四回戦を終えた頃、もう時刻は昼になろうとしていた。
信はまだ教室に姿を現さない。さすがに遅すぎると河了貂は信を宿舎へ迎えにいった。
しばらくすると血相を変えた河了貂が教室に飛び込んで来て、円らな瞳を限界まで広げて蒙毅の腕を掴んだ。
「も、蒙毅ッ!来てくれ!」
「どうしたんだい?」
普段から冷静である蒙毅も、妹弟子の動揺に何かあったのだろうかと考える。
しかし、状況を説明するよりも見てもらった方が早いと言わんばかりに河了貂は蒙毅の腕を掴んで教室を飛び出して行った。
階段を駆け上がり、一番奥にある信の部屋に向かっていると、既に異変が起きていた。
「これは…」
信の部屋の前に、巨大な本棚が置かれていたのである。
「こんなもの、一体いつ…」
蒙毅の疑問に河了貂は首を横に振る。
「俺が朝、部屋を出た時にはこんなのなかった!」
「うん。僕も部屋を出た時に、こんなのを見た記憶はないよ」
蒙毅と河了貂は信よりも早い時刻に隣接している軍師学校へと着いていた。
昨夜こんな本棚は廊下にも置かれていなかったし、二人が部屋を出た時にだってこんな物が置かれていた記憶はない。
それに扉の前に置いてある本棚を見る限り、まるで信を部屋から出さないように、扉を塞いだとしか思えない。
一体どこからこんな大きな本棚が運ばれたのだろうか。誰がやったのか考えてみるが、一人での犯行はまず不可能だろう。そして当然ながら、室内にいる信の自作自演の線はなしである。
二階にこんな本棚が置いてあるのは見たことがない。どこかから持って来るにせよ、ここまで本棚を運ぶということは、あの階段を上って来なければならない。
複数犯しか有り得ないと分かると、河了貂と蒙毅は顔を見合わせた。黄芳とその取り巻きに違いないと二人は同じことを考える。
しかし、今は信のことが気がかりだ。
「信!おい!信ってばッ!」
本棚と扉越しに、中にいるであろう彼女に呼びかける。しかし、返事は一向に返って来なかった。
木簡を墨で汚された時も黙っていたのだから、今回の犯行に関しても、信は怒らずに大人しくしているのかもしれない。
しかし、河了貂は妙な不安を覚えた。さすがにこんな時間なのだから、信も起きているに違いないのに、どうして返事がないのだろう。
「河了貂。とりあえず、この本棚をどうにかしよう!」
「あ、ああ!」
蒙毅と共に本棚を扉の前から押しのけようとするのだが、少しも動かない。
かなりの重量があるのは目視しただけでも分かっていたが、まさかこれを抱えて階段に上がって運んで来たなんて。軍師よりも戦場で敵を薙ぎ払う方が向いているのではないだろうかと二人は考えた。
「んん~ッ!ダメだ!びくともしない!」
二人で力を込めても、本棚は少しも動かない。他の生徒たちの力を借りるべきかと考えた時だった。
「あー、いたいた。探したよ」
「兄上!」
蒙毅の兄である蒙恬がひらひらと手を振りながら、廊下を歩いて来たのだ。蒙恬の後ろを不機嫌そうな顔で王賁が歩いている。
王賁が不機嫌なのは、蒙恬に引っ張られて来たからに違いない。王賁の父である王翦は蒙驁の副官である。呂不韋側についている蒙家との接点があるため、軍師学校への出入りは蒙恬同様に警戒されない立場であった。
軍師学校を首席で卒業をしている蒙恬は、弟の蒙毅の顔を見るのを理由に時々ふらりとやって来る。
本当は軍師学校に可愛い女子生徒が入門していないか確認しているのだと知っているのは弟の蒙毅くらいだ。
「どうして兄上がここに…」
「信が来てるんでしょ?こっちに用があったら、顔出していこうと思ってさ」
素性を隠して軍師学校に強化合宿をしていることをどこから聞きつけたのか、蒙恬の情報網は早い。しかし、悪意は微塵もなく、純粋に友人を労いに来たのだろう。
「それが…」
蒙毅が言葉を濁らせて、顔色まで曇らせたので、蒙恬と王賁は何かを察したようだった。
部屋の前にある本棚を指さし、河了貂が目尻をつり上げる。
「黄芳の奴ら…信を部屋から出られないようにしやがったんだ!」
「は?」
蒙恬と王賁が瞠目する。こんな姑息なことをするのは黄芳に違いないと、憤怒した河了貂が言葉を続ける。
「俺と蒙毅が、信より先に軍師学校に行くのを知ってて、その隙にやったに違いない!絶対にあいつらの仕業に決まってる!」
「…ちょっと待ってよ。その言い方、もしかして他にも前例があるってこと?」
急に険しい目つきになった蒙恬が聞き返す。
強化合宿と称して信が軍師学校に来てから、蒙恬と王賁が来るのは初めてのことだったが、河了貂の言葉を聞いた二人は、彼女が穏やかな学校生活を送れていないのだとすぐに気づいた。
蒙毅は信が軍師学校に来てから、黄芳に言われた言葉や嫌がらせについてを二人に全て打ち明けた。
話を聞いていくうちに、蒙恬と王賁の顔がどんどん険しくなっていく。
「下僕出身だとしても、王家だと名乗れば、そのようなことはされなかったはずだろう。養子とはいえ、王騎将軍の娘だぞ」
腕を組んだ王賁が低い声で二人に聞き返した。ここに来てようやく口を開いたということは、王賁も憤りを感じているに違いない。
苦虫を嚙み潰したような顔で、河了貂が首を横に振る。
「…王騎将軍が、自分たちは大王側の人間だから学校では素性を隠せって言ってたらしくて…信は、ずっと何も言わなかったんだ…何されても、へらへらしてて…」
「あのバカ女…」
呆れたように王賁が肩を竦めている。信のことだからそうではないかと予想はしていたが、蒙恬は納得出来ないと声を荒げる。
「ちょっと、信だって女の子なんだよッ?そんなことされて、傷つかない訳ないだろ!」
顔を真っ赤にして自分のことのように怒る兄を蒙毅が宥める。弟の説得を受け、冷静さを取り戻した蒙恬がぎらりと目を光らせた。
「…よし、決めた。そいつら全員、卒業したら宦官にしちゃおう。男じゃなくなれば多少は反省するんじゃない?」
「兄上、落ち着いてください」
男の象徴である大事な物を捥いでしまえという蒙恬に、弟の蒙毅が静かに首を横に振った。
「女性にこのような振る舞いを行う低俗な者を宦官にするのは反対です。改心させるためにはもっと痛い想いをさせなくては」
笑顔で恐ろしいことを言い放つ兄弟子に、河了貂が青ざめていた。
「と、とにかく、まずはこれを退かそうぜ!」
話題を変えようと河了貂が本棚を指さした。四人がかりならばきっと本棚も動かせるだろう。
全員で本棚を動かそうとした時、廊下の向こうから昌平君がやって来た。
「…何をしている」
「先生!」
教室に信を含めた三人の姿がなかったことを気にかけていたのだろう。
なぜか宿舎に蒙恬と王賁がいることに昌平君は表情を変えないでいるが、何か異変があったことを察したようだった。
もう昼になるとはいえ、いつまでも信が学校に来ないことから、河了貂と蒙毅が迎えにいったことは分かっていた。
昨夜のこともあり、寝坊をしているのか、体調が優れないのか確認するために、昌平君も腰を上げたという訳である。
「………」
蒙毅から一通りの事情を聴いた後、部屋の前を塞いでいる大きな本棚を見て、昌平君の切れ長の瞳が鋭くなる。信が軍師学校に来ない理由は、寝坊でも体調不良でもないことは明らかだった。
黄芳のことは、信自身が気にしていないようだったので、こちらも口を出すことはしなかったが、このようなことが続くのならばそろそろ熱い灸を据えなくてはならないかと昌平君は考えた。
「信ッ!」
部屋の前から重い本棚を動かし、河了貂が扉を開けた。
「んんー、なんだよ…うるせえなぁ…」
返事がないことを怪しんでいたが、扉を開けた先で、信は寝台に横たわっていた。
まだ眠いと言わんばかりに、頭まで布団を被ったのを見て、信以外の全員が顔を強張らせたのだった。
惰眠
「信、なに寝てんだよッ!?」
こちらの心配や苦労など知らず、ぐっすりと寝入っていたらしい信に、河了貂が怒鳴りつける。
布団越しに信の体を揺すり、河了貂は行き場を失った怒りをぶつけている。
河了貂に続いて、信のもとに駆け寄った蒙恬が苦笑を浮かべる。すん、と鼻を鳴らして、蒙恬が苦笑を浮かべる。
「…信、お酒臭いよ。まさか酒飲んだのか?さすがに俺だって軍師学校にいる時は我慢してたのに」
「へへ…この前、麃公の将軍から差し入れてもらったんだ」
布団から顔を覗かせ、何の悪気もなく笑顔を浮かべて答えた信に、王賁がずかずかと大股で近づき、拳を振り上げる。ごつんと鈍い音を立てて、王賁の拳が信の額に振り落とされた。
「いでえぇッ!?王賁てめえ、何しやがるッ!」
一切加減のないげんこつに、信が涙目で王賁を睨み付ける。
「これだから己の立場も弁えぬバカはッ…」
本気で苛立っている王賁に、信は聞き飽きたと言わんばかりに肩を竦める。
自分が下僕出身だと打ち明けてから、黄芳たちからも似たような言葉を掛けられていたのだが、王賁に言われた言葉の数に比べると、ほんの一つまみにしかならない。それが信に強い耐性をつけていたのだろう。
「あー、もう昼か。飯食って、いや、その前に宮廷でもらい湯して来るかなあー」
ようやく寝台から体を起こした信が呑気にそんなことを言うものだから、全員は溜息を吐いた。
まだ眠たい目を擦りながら、信が思い出したように昌平君を見る。
「あ、先生。これってズル休みじゃねーよな?そんな重い本棚が塞いでたんだから、俺にはどうしようも出来なかったし」
どこか得意気に笑いながら尋ねる信に、昌平君は僅かに眉根を顰める。
部屋の前に本棚で塞がれていたのは不可抗力だ。軍師学校に来れなかったのは、信が原因ではない。
「…そうだな」
昌平君が頷くと、信は満足そうに笑った。
「これ、ありがとな」
身に纏っていた紫紺の羽織りを脱ぐと、信は畳むこともせず昌平君の胸に押し付けた。
昨夜彼女に貸した羽織りだった。ずっと着ていたということは、部屋に戻ってからすぐに寝てしまったのだろう。本当に今の今まで眠り続けていたらしい。
「先に宮廷でもらい湯して来るわ。じゃあな」
ひらひらと手を振りながら、信が部屋を出ていく。
「………」
彼女がいなくなってから、その場にいる全員から視線が向けられたのを感じ、昌平君はわざとらしく咳払いをした。
にやりと嫌な笑みを浮かべた蒙恬が、先ほど信から返された昌平君の羽織に視線を向けている。
「先生、信と晩酌したんですか?二人きりで?」
その言葉を聞いた王賁が瞠目していたが、昌平君は何事もなかったかのように羽織に袖を通して全員に背を向ける。
どうして信が彼の羽織を着ていたのか、全員が気になっているようだが、余計なことは何も言うまいと昌平君は口を閉ざしていた。
愕然としている三人と違い、なぜか蒙恬だけはにやにやとした笑みを浮かべていた。
空き教室で酒を飲み交わしていたことを、とても話す気にはなれなかった。口は災いの元なのである。
再会と再戦
もらい湯を済ませ、遅い昼食を終えてから、信はようやく学校へと向かった。
まだ二日酔いが続いていたが、昼までぐっすりと休めたこともあって、気分はすっきりしている。
また河了貂から説教を食らいそうだなと考えながら教室に向かっていると、廊下の向こうから昌平君がこちらへ歩いているのが見えた。
「信」
すれ違いざまに呼び止められて、信は振り返る。
「お前に客人が来ている。ついて来なさい」
「俺に?」
そうだ、と昌平君が頷く。客人が誰なのかを告げずに歩き出したので、信は彼の背中を追い掛けた。
軍師学校を出てからしばらく長い廊下を歩き、宮中の一室に辿り着いた。客人というのは誰だろうと小首を傾げながら、信は昌平君と共に部屋に入る。
見覚えのあり過ぎる大柄な男が、椅子に腰掛けたままこちらを振り返った。
艶のある分厚い唇を意味ありげにつり上げた男に、信がぎょっと目を見開く。
「父さ…王騎将軍ッ!?」
「ンフフフ。元気そうですねェ?」
大らかに笑う養父は相変わらずのようだ。久しぶりの再会ということもあって、信の口元が自然と緩んでしまう。しかし、どうして彼がここにいるのか分からない。
「なんでここに?」
咸陽宮に何かしら用があって、立ち寄ったついでに自分の様子を見に来たのだろうか。それとも、昌平君から強化合宿の進行具合について聞きに来たのかもしれないし、両方かもしれなかった。
「…さて、軍略を学んだ成果を見せてもらいましょうか」
得意気に王騎が微笑んだので、戸惑ったように信は視線を泳がせた。
「んなこと言っても…騰が俺の剣、持っていっちまっただろ」
屋敷を追い出されたあの日、軍師学校に武器は不要だからと剣は没収されていた。真剣な表情でそんなことを言う娘に、王騎がココココと独特に笑う。
「何を言っているんです?軍師学校で勝負といえば、これでしょう?」
養父の視線を追い掛けると、軍師学校にも置かれている囲碁台がある。
まさか軍略囲碁で勝負しろというのか。信の心臓がどきりと跳ね上がった。
「座りなさい」
「………」
信はぎこちない表情のまま、囲碁台を挟んで向かいの席に腰を下ろした。
「それでは、今回の勝負は平坦な地にしましょう」
特に障害物も挟まず、隠れることも出来ない平坦な地を戦場と見立てることとした。
軍に見立てた駒を用意していく王騎を、信は緊張した面持ちで見つめている。昌平君は二人の間にある囲碁台をじっと見つめていた。二人の勝負を見守るつもりなのだろう。部屋から出る気配を見せない。
自分と信にそれぞれ駒を分けた王騎は、真剣な眼差しで口を開いた。
「もしも私に勝てれば、屋敷に帰る許可をあげましょう」
養父の言葉に信が弾かれたように顔を上げた。顔に喜色が浮かんでいたが、すぐに消え去ってしまう。
「…負けたら?」
聞き返した信の声が僅かに震えている。負けた時の罰はきっとひどいものだと、彼女は既に予想しているようだった。
「そうですねェ」
口元に手をやり、王騎が考える素振りを見せる。
「即座に五千人将の座を解き、あなたの地位を伍長に戻します。強化合宿も年単位で延長としましょう」
「ッ…」
これには信だけでなく、さすがに昌平君も驚いた。そのような話は初耳だった。
いくら大将軍である王騎とはいえ、信の五千人将の座を解く権限は持っていない。本来、その権限を持つ立場の総司令官が傍にいる状況を、王騎は味方につけたのだ。
「………」
王騎と昌平君が、事前にそのように話をつけていたと信は見事に勘違いし、固唾を飲んでいる。
青ざめている娘を見据え、王騎が挑発するように笑い掛ける。
「怖いのなら、勝負をしないという手もありますよ?その場合、将が不在ということで飛信隊は解散となりますが」
あまりにも容赦ない王騎の言葉に、勝負を見守る立場の昌平君までもが固唾を飲んだ。
王騎に勝利をしなければ飛信隊は解散。勝負から逃げても同様だ。
選択肢を与えるようにみせかけて、一つの道しか与えない王騎の厳しさに、信は嫌な汗を滲ませながら呼吸を繰り返していた。
将軍を目指す以上は、敵を前にして逃亡も敗北も許されない。きっと幼い頃から信はそう教えられていたのだろう。
「…やるしかねえだろ」
信は自分に言い聞かせるように、返事をすると、椅子に座り直した。