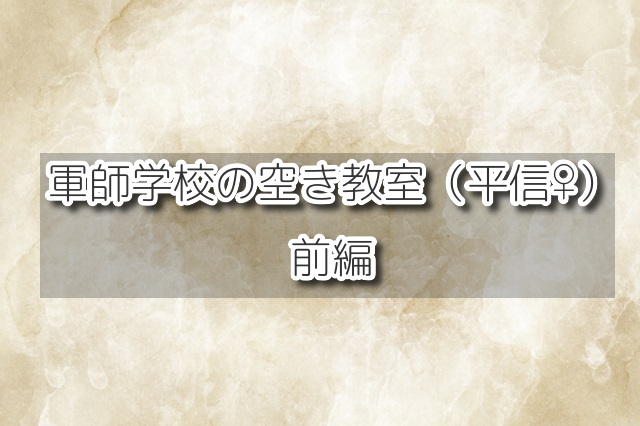- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 昌平君×信/ツンデレ/ギャグ寄り/IF話/軍師学校/ハッピーエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
養父からの命令
戦を終えて屋敷に帰還した信は、誰が見ても分かるほど落ち込んでいた。此度の戦は秦軍の勝利で終えたのだが、少しも勝利を喜んでいない。
今頃、秦の首府である咸陽では大いに祝宴を挙げているだろうに、信はまるでこれから葬儀にでも参列するのかと思うほど暗い雰囲気を携えていた。
いや、実際に葬儀は執り行った。作法に基づいたものではないが、戦地で大勢の兵たちの死を悼んだのだ。
大勢の屍の前で打ちひしがれている信に肥を掛けたのは、養父である王騎だった。
恐らく此度の戦も参戦せずに遠くから眺めていたのだろう、「帰ったら話があります」と呼び出されたのである。
咸陽宮で行われた論功行賞の後、勝利を祝う宴には参加せず、信はすぐに馬を走らせて屋敷へと帰還した。
馬で帰路を走っている最中も、信の気持ちは少しも晴れない。呼び出された時から説教を受けることになるのは分かっていた。
包帯だらけの身体を引き摺って、信は王騎の部屋へと向かった。
戦の後、王騎に呼び出された時は必ずと言って良いほど、説教を受けるのだ。
少しくらい娘が無事に生還したことを喜んだり、戦での活躍を労ってもらいたいものだが、王騎は厳しいのだ。かといって、自分を棚に上げることはしない。
兵たちと共に命がけの鍛錬を行い、常に自分の力に磨きをかけている父だからこそ慕う者も多く、天下の大将軍と称えられているに違いない。
だから信はお説教を受けることは憂鬱ではあるが、それほど苦ではなかった。
咎められたことを次の戦で活かせれば、素直に褒めてくれるし、これまでの経験で得た知識を授けてくれる。王騎は甘言と脅しの使い分けが上手いのだ。
しかし、今回のお説教は長引きそうだというのは信も察しがついていた。
何故なら信が率いる飛信隊は、此度の戦で兵の大半を失ったのである。壊滅状態と言っていい。将としての責を厳しく追及されるだろう。
此度の戦で戦果を挙げれば、将軍昇格になることは信も嬴政から聞いていたのだが、この被害を受けて見直すことになったらしい。
父に一歩近づけたと思ったのに、仕切り直しになってしまった。
次回の戦で大いに武功を挙げれば、将軍昇格を再び検討してもらえるらしいが、此度のような軽率な行動を行えば、仕切り直しどころか、将軍昇格は白紙になってしまうかもしれない。
きっと王騎もそのことを自分に厳しく伝えるつもりなのだろう。信はあらかじめ覚悟をしていた。
「入る…入り、ます」
普段のように敬語を使わず声を掛けそうになったが、信は寸でのところで言葉遣いを直した。下手すれば入室の時点から叱られてしまう。
秦王の前に出るため礼儀作法を習っていたこともあったのだが、少しも身についていないのは、王騎も摎も信の物覚えの悪さに諦めてしまったからだろう。苦手なものは何をしても苦手なのだから仕方ない。
扉を開けると、王騎が呆れた表情を浮かべて信を見た。
「ンフゥ。来ましたね、戦況も見えないお馬鹿さん」
さっそく王騎から此度の戦の失態を比喩したような声を掛けられる。副官である騰も一緒だった。返す言葉もないと信が苦笑を浮かべると、部屋にいたのは王騎と騰だけでなかった。
紫色の着物を身に纏った男が振り返る。彼こそ秦軍の総司令官を務める右丞相の昌平君である。
「え?なんで昌平君が…?」
戦後の事務処理で一番忙しくしていそうな男が一体なぜこの屋敷にいるのだろう。
疑問を抱くのと同時に、王騎の呼び出しと昌平君の存在に繋がりがあるような気がして、信は嫌な予感を覚えた。
しかし、王騎はすぐに昌平君がここにいる理由を打ち明けることはせず、信をじっと見つめる。
「ッ…」
戦場でないというのに、毛穴にびりびりと食い込むような嫌な感覚に、信が後退りをしそうになった。しかし、腹に力を込めて王騎と真っ直ぐに見つめ合う。
気迫だけで人を圧倒させることが出来るのは、天下の大将軍と称えられるほどの実力を兼ね備えている父だからこそ出来る技だろう。
しばらく無言で見つめ合い、重い沈黙が部屋を包み込む。先に口を開いたのは、王騎の方だった。
「信、あなたを勘当します」
「え…」
勘当という言葉が親子の縁を切るものだと知っている信は頭の中が真っ白になった。
「というのは冗談です。驚きました?ココココ」
「………」
冗談だと笑われても、信の全身から浮かんだ嫌な汗は少しも引いてくれなかった。愕然としたままでいる娘に、王騎は肩を竦めるようにして笑う。
王騎が人をからかうのが大好きなのは分かっていたが、信には少しも笑えない冗談だった。
「さて、本題ですが…此度の飛信隊の動きは、とても残念でした」
「………」
信は唇をきゅっと噛み締める。やはり予想していた通りの説教が始まるようだ。
「まるで発情期の獣が、ようやく雌を見つけて、なりふり構わず襲おうとしているような…あんなにも単純かつお馬鹿さんな隊は初めて見ましたよ」
信にはよく分からない比喩だったが、王騎はやたらよく分からないものに比喩するのが好きだ。
要約すると、布陣を構えた敵陣に突っ込んでいったのは無謀だったのだと言いたいのだろう。
王騎と昌平君の二人の間には軍略囲碁台が置かれている。時々、この部屋で王騎が副官の騰や録嗚未たちと軍略囲碁をするのは知っていた。
信は剣の扱いや兵たちの鍛錬の指揮を得意でも、軍略に関してはからきしだったので、一度も父と軍略囲碁を打ったことはない。
下僕出身ということもあり、文字の読み書きなど出来ない自分には剣しかないと思っていた。
養子となってからは、鍛錬の合間に字の読み書きの練習をさせられて何とか習得したのだが、ずっと勉学とは無縁だったせいか、机に向き合う時間は今も好きに慣れない。
恐らく信が来るまでに二人で打っていたのであろう軍略囲碁も、一体どちらが勝利したのか、どんな勝負だったのか、今並んでいる駒を見ても信には少しも分からなかった。
「私も反省すべきところでした。多くの戦を見て学ばせたつもりでしたが、ここまでお馬鹿さんだったとは思いませんでしたよ。今までの武功は全て運が良かっただけでしょうねェ」
「なっ…!」
今までの戦で命を落としそうになったことだって一度や二度じゃない。
何度も死地を乗り超え、多くの兵たちの犠牲の上で得た勝利を、「運が良かった」という一言で片づけられるのはとても腹立たしかった。
何か言い返そうと信が口を開いたが、王騎がその言葉を遮った。
「軍略について学んで来なさい。強化合宿というやつです」
「…へっ?」
怒りを飛び越して、信が呆けた顔になった。
強化合宿
「軍略の…強化合宿…?」
言葉を繰り返すと、王騎がゆっくりと頷いた。
「期限は特に定めていません。判断は総司令官に委ねます」
「な、なんで…」
狼狽える信を見つめながら、王騎は艶のある分厚い唇を歪めて笑う。
「愚問ですねェ。あなたに軍略を学ばせようという父の優しい想いですよ?」
どう考えても命令にしか聞こえない。こんな風に王騎が自らを父と名乗って何かを話す時ほど、恐ろしい目に遭った。
幼い頃に「残党を最低十人は殺してその証を持ち帰って来なさい」と言われ、崖から突き落とされたことを思い出し、信はぶるぶると全身を震わせる。
いつも王騎はこうやって無理難題を押し付けて来る。そして達成出来ないと絶対に屋敷に入れてくれないのだ。
戦で死地を乗り超えて来たが、幼少期の鍛錬に比べればマシかもしれないと思えるほど、信には過酷な思い出として頭に刻まれている。
そして今回も自分には拒否権はないのだろう。信は顔を引き攣らせることしか出来なかった。
「合宿って…ど、どれくらいかかるんだよ…」
声を震わせながら信が二人に問うと、自分の髭を指で丁寧に整えながら、王騎は口の端をつり上げた。
「さあ?総司令官のお許しが出なければ、五年でも十年でもいるかもしれませんよォ?もちろん、その間は戦に出ることは許しません」
「―――」
信の顔からみるみる血の気が引いていく。ただでさえ今回の件で将軍昇格への道が取り消しになろうとしているのに、戦で武功を挙げなければ、将軍昇格がどんどん遠ざかってしまう。
「そ、んなぁ…」
軽い眩暈を覚えて、信はその場にしゃがみ込んでしまった。
…勘当は冗談だと言っていたが、もしかしたら王騎は本当は自分を屋敷から追い出す名目で強化合宿の話を考えたのだろうか。
愕然としている信に、王騎がくすくすと笑い、昌平君と騰は先ほどからずっと表情を変えていない。
「が、合宿って…どこで…」
泣きそうな声で尋ねると、王騎が目を細める。
「もちろん軍略学校ですよ。そのために総司令官においでいただいたのですから」
昌平君は軍の総司令官であり、右丞相を務める男だが、もう一つの顔があった。それは軍師学校の指導者である。
昌平君の軍師学校といえば、秦の軍師育成機関の中でも国内最高峰とも言われている。全国に多くの入門希望者がいるが、百人に一人が通ることの出来る超難関だという。
信の友人である河了貂もその軍師学校に通っており、日々勉学に勤しんでいる。
軍師の才がある者を集め、育成している場所で、大将軍を目指している信には無縁の場所だと思っていた。
強化合宿という一時的なものではあるが、六大将軍・王騎の力による、いわゆる裏口入門というやつである。
河了貂に会えるのは嬉しいが、軍師でもない自分が軍師学校に通わなくてはならないということに、信はいたたまれない気持ちになった。
どうやら娘の考えを読んだ王騎が呆れたように肩を竦める。
「軍略を練るのは軍師だけではありません。将も頭を使った戦をしなくてはなりませんからねェ」
「………」
「いかに強さがあっても、それを使いこなす頭が無ければ、意味はありませんよ。飛信隊の強さをどうしたら活かせるか、軍師学校で学んでらっしゃい。その間、飛信隊は私が預かります」
信が返事をせずに狼狽えた視線を向けたので、王騎は溜息を吐いた。
「騰」
「はッ」
騰が信の背中に携えていた剣を奪い取る。何をするんだと信が剣を取り返そうとするのだが、騰は信の襟を掴んでその体を猫のように軽々と持ち上げた。
「騰ッ!放せッ!せめて剣は返してくれよッ!」
「軍師学校に剣は不要だと、殿と総司令官殿が」
どれだけ手を伸ばしても剣を返してくれる気配はなかった。王騎軍の副官である騰にとって、王騎の命令は絶対なのである。
ぎゃーぎゃーと喚く信が騰と共に部屋を出ていった後、王騎は困ったように笑みを深めていた。
「…ああ言ってしまいましたが、長くても半年と言ったところでしょうか。次の戦の気配があれば、飛信隊にも出番をあげたいですからねェ」
信が居なくなってからようやく本音を打ち明けた王騎に、昌平君は表情を変えぬまま瞬きを繰り返す。
「素直にそう言えば良かったのではないのか。養子とはいえ、娘だろう」
幼い頃から信に厳しい鍛錬を強いていたのは噂で聞いていたが、今のやり取りを見る限り、本当に容赦ない鍛錬を強いて来たのだと分かる。
王騎軍が日々こなしている厳しい鍛錬については知っていたが、まさか娘にまでそのような鍛錬を強いていたとは思わなかった。
しかし、今の王騎の言葉を聞く限り、彼もがむしゃらに信を躾けている訳ではなさそうだ。単純に愛情表現が不器用なのだろうか。
昌平君には未だ妻子はいないのだが、他の同僚たちの家庭を見ていると、父という存在は娘に甘いものだという認識があった。天下の大将軍といえど、その認識はこの中華では共通らしい。
「甘やかす役割は、母親が担っていましたからねェ。ココココ」
右手の甲を左頬に押し当てながら、王騎が大らかに笑った。母親というのは、今は亡き六大将軍の一人である摎のことだ。
彼女が趙の龐煖に討たれてから、信もがむしゃらに強さを求めて武功を挙げるようになっていた。その焦りが、今回の飛信隊壊滅に繋がったのかもしれない。
「では、娘のことを頼みましたよ。あなたが動かしやすい駒になるよう、しっかりと学ばせてやってください」
あえて駒という言葉を使ったのは、決して嫌味ではない。軍師にとって将や兵は駒であるのは事実だし、戦に出ない分、大勢の命を背負っている役割がある。
此度の戦で兵の大半を死なせてしまった信にもその役割を学ばせて欲しいという王騎の気持ちの表れだった。
「字の読み書きは一通り出来るはずですが、机上で何かを学ぶ経験が乏しいので、上手くやってください」
要するに信はかなりの飽き性なのだと告げられ、昌平君は返答に困った。
王騎からの頼みである以上、何も成果を出さずに彼女を帰す訳にはいかない。半年という期限を設けられたが、その間に一体どれだけの軍略を詰め込めるだろうか。
信の幼少期の鍛錬についてはこちら(李牧×信)
出発
「開門ッ!開門しろーッ!」
追い出されるように、身体を放り投げられ、信はすぐに立ち上がった。
門が閉じられてしまう前に全速力で駆け出すが、寸でのところで門が閉められてしまう。こうなれば何をしても開かないことは信も分かっていた。
「くっそー!騰の馬鹿野郎ッ!」
怒鳴りつけるが、もう騰は門の向こうにもいないだろう。
今日の浴槽に浮かべる花は何だろうと思っているような顔で、信を放り投げていたし、本当に薄情な男だ。
信は門に背中を預けてその場にずるずると座り込んでしまった。
(…軍略を学んだって…)
自分が五千人将にまで昇格したのは、飛信隊の強さだと自負していた。
過去の戦では楽華隊の蒙恬や、玉鳳隊の王賁にも無謀だと言われたことは何度もあったが、それでも飛信隊の強さがあれば敵の布陣を崩すことだって容易に可能だった。
信頼している兵たちの力があるからこそ、ここまでやって来れたし、きっと将軍になってからもそうなるだろう。信はそう疑わなかった。
だが、今回の飛信隊の被害の原因は他の誰でもない自分だと王騎に指摘をされてしまい、自分には将として才能がないのかと信は落胆してしまう。
軍略を学んだところで、自分は戦に活かせるのだろうか。それよりも鍛錬を積んで兵たちの強化に充てた方が良いのではないだろうか。色んな考えが脳裏を過ぎる。
「…ん?」
馬の嘶きが聞こえて、信は顔を上げた。屋敷の前に馬車が一台停まる。
来客だろうかと信が立ち上がった途端、背後で門が開く音がした。反射的に信は開いた門に全速力で飛び込んでいた。
「どこへ行く」
「ぐえッ」
先ほど騰にされたように、目にも止まらぬ速さで昌平君に襟元を掴まれて、信は喉を詰まらせた。彼が屋敷から出て来たということは、王騎と話を終えたようだ。
襟首を掴まれたまま、信はじたばたと手足を動かした。
「放せよッ!門が閉まっちまう!」
「そろそろ戻らねば日が暮れる」
「勝手に決めつけたくせに見送りもしねえッ!父さんに文句言いに行ってやる!」
信がぎゃーぎゃーと騒いでいる間に、再び門が閉められてしまった。
なおも暴れる娘の首根っこを掴んだまま、昌平君は無言で馬車へと引き摺っていった。
有無を言わさず、まるで荷物のように馬車に身体を押し込まれ、昌平君も乗り込むと、すぐに騎手が馬を走らせた。
「………」
がたごとと揺れる馬車の中で、信は拗ねた子どものように膝を抱えて、窓から遠ざかっていく屋敷を眺めている。
むくれ顔なのは、王騎に強化合宿を勝手に決められたことと、剣すら持たせてもらえなかったことや、見送りもされなかったことなど様々な要因だろう。
戦場に立つと彼女は別人のように顔つきが変わるという。軍師として後方に立ち、戦場に赴くことがない昌平君は、子どものような表情しか知らなかった。
態度を見る限り、どうやらもう逃げ出すつもりはないらしい。戻ったところで屋敷に入れないことは信も分かっているのだろう。
「………」
昌平君は先ほど王騎から渡された書簡に目を通しながら、果たして信はいつ屋敷に帰せるだろうかと考えた。
此度の飛信軍の動きだけではなく、今までの戦での兵の動かし方を見る限り、彼女は兵の強さを過信する傾向にあるようだ。
確かに飛信隊の騎馬兵や歩兵たちの強さは、王騎軍にも引けを取らぬものがある。
だが、いかに兵力があっても使い方によっては簡単に弾かれてしまう。今回の飛信隊の壊滅は良い例だ。
彼女が五千人将にまで上り詰めた実力を疑う訳ではないが、将軍に昇格するとなれば、兵力も増員する。
それだけ多くの命を預かるのだから、今以上に将としての責任も重くなる。王騎はその自覚を促そうとしたのかもしれない。
今後の戦で今回と同じように無茶な戦い方をして、兵が壊滅する被害がないとは限らない。
敵軍がどのような策を使って来るかは分からないが、軍略を学ぶことで、対応策を立てることだって出来るはずだ。
信が将軍の座に就いたのなら、今後の秦軍の兵力は強大なものになる。恐らく王騎もそれを見込んで、軍略を学ばせようとしたのだろう。
話によると、王気は幼い頃から信を連れて数多くの戦を見せていたらしいが、将軍同士の戦いに夢中になるばかりで軍略に関してはちっとも興味を示さなかったそうだ。
将軍たちが何を考え、あのような動きをしているのかについても助言をしていたようだが、信はそれを聞き流していたという。
天下の大将軍である王騎から助言を聞ける機会など、将を目指す者たちからすれば喉から手が出るほど貴重なことだというのに勿体ないことをする。
「別に軍略なんて学ばなくても、飛信隊なら…」
小さく信が呟いたので、昌平君は視線を動かして彼女を見た。声色から察するに、信は軍略ん冠して微塵も興味がないことが分かる。だが、興味がないからというのは軍略を学ばない理由にはならない。
これから信は今以上の兵の命を預かることになるのだから、そのような考えは捨て去るべきだ。此度の失敗を次の戦に活かさねば亡くなった兵たちのためにもならない。
「…そのような感情論は捨てろ。戦ではその過信が命取りになる」
昌平君の言葉に、体のどこかが痛んだかのように、信がきゅっと眉を寄せた。
「………」
抱えた膝に顔を埋めた信がそれきり何も話さなくなったので、昌平君も何も言わなかった。
軍師学校がある宮廷に到着するまで、馬車の中は重い沈黙で満たされていた。
宿舎
宮廷に到着した時には、既に陽が沈みかけていた。
馬車から降りた後も、信の表情は暗いままである。ここまで来たのなら軍略を学ぶしかないと諦めたという様子でもない。
憂いの表情を浮かべているのは、亡くなった兵たちのことを考えているからなのだろうか。
「信、来なさい」
構わず昌平君は彼女に声を掛け、軍師学校へと向かった。宮廷にある軍師学校には、生徒たちが寝泊まりできる宿舎も備えられている。二階には空き部屋があったはずだ。
「………」
地面を睨み付けるように前屈みになって、信は昌平君の後ろを歩いていた。
しばらく長い廊下を歩き続け、突き当りに軍師学校へと続く新たな廊下があった。軍師学校と宿舎は隣接している構造となっている。
一階の全てと、二階の階段手前の部屋は男子生徒が使っており、二階の奥の方は女子生徒が使用している。軍師学校に通う女子生徒は、今は信の他に一人しかいないので、奥の方はほとんどが空き部屋になっていた。
一番奥の空き部屋に入り、昌平君は手に持っていた木簡を信に押し付けるように渡した。
「これは?」
「王騎からだ」
まさか養父の名前が出るとは思わなかったのだろう、信は驚いたように目を丸める。
受け取った書簡の内容に目を通すと、信の表情はみるみるうちに強張っていった。
「…はあ…」
最後の一文まで目を通した彼女は書簡を乱暴に折り畳み、大袈裟な溜息を吐く。
書簡は昌平君に宛てたものであったが、信にも見せるよう伝えられていた。
―――内容を要約すると、軍師学校では己の素性を隠すこと、昌平君の指示に従うこと、無断で帰って来ても屋敷には入れないことが記されていた。
素性を隠すよう指示したのは、昌平君が呂氏四柱の一人であることを気遣ってのことだろう。昌平君が仕切っているこの軍師学校は、呂氏陣営の一つだと言っても過言ではない。
しかし、王騎軍と飛信隊は大王側に身を置いている。敵対関係にある将を軍師学校に入門させるとなると、あらぬ疑いを掛けられてしまうに違いない。
それは信と王騎だけでなく、王騎の頼みを受け入れた昌平君もである。
昌平君が軍師学校で軍略を教えることは、呂氏陣営や政治とは一切関係のない公務とはいえ、どこで誰が聞いているか分からない。恐らく王騎はそれを警戒しているのだろう。
長くとも半年だと期限を設けたのは、信を次の戦に出すためだと言っていたが、いつまでも敵地に娘を置いておきたくないという親心なのかもしれない。
「どうせ父さんのことだから、そうだろうと思ったぜ…」
屋敷で話していたことと内容は大して変わりないのだが、書簡にして残すほど王騎が本気なのだと分かった信は、ここに来てようやく腹を括るしかないといった表情を浮かべていた。
唇を噛み締めた信が何か言いたげに昌平君を見上げたが、それは言葉にはならなかった。
「河了貂もいる。分からないことがあれば彼女に聞きなさい」
二人が成蟜から政権を取り戻す時からの付き合いだと知っている昌平君がそう言うと、信は小さく頷いた。
旧友との再会
昌平君が宿舎を出て行った後、信は与えられた部屋に入って重い溜息を吐いた。
まるで修道院を思わせるかのような簡素な部屋で、机と椅子と寝台くらいしかなかった。
軍師学校に通う生徒は、色々と必要なものを持ち込んでいるのかもしれないが、追い出されるように連れて来られた信は何も持って来ていない。あるのは先ほど昌平君から渡された書簡くらいだ。
剣も没収されてしまったのは、軍略に集中しろという王騎の伝言なのかもしれない。
「………」
寝台の上に横たわり、信は天井を見上げた。
一体いつになったら屋敷に戻れるのだろうか。昌平君の許しが出るまでとのことだが、軍略について今から改めて学ぶなんて、どれだけ時間がかかるのだろう。
幼い頃、両親に幾度も戦に連れ出されたのは、自分の目で見て軍略を学べということだったのかもしれない。
将軍同士の白熱した戦いにばかり目を奪われていた幼い自分を、今になって悔いた。しかし、今さら悔いたところでもう遅い。
天井を見上げながらひたすら溜息ばかり吐いていると、扉が開かれる音が聞こえて、信は反射的に起き上がった。
扉の隙間からこちらを覗いている少女を見て、信は、あっと声を上げた。
「テン!?」
「聞いたことのある声がすると思ったら、やっぱり信だったか!」
河了貂という名の少女が駆け寄って来て、満面の笑みを浮かべる。
信にとっては妹のような存在である河了貂は嬴政が弟である成蟜から政権を取り戻す時に出会った。最後に会った時よりも、彼女の姿は随分と大人びて見えた。
「その年で五千人将になんてすごいぞ!五千人将から昇格したら、次は将軍なんだろ!?」
「あ、ああ…」
久しぶりの再会を喜んだのも束の間、信はみるみるうちに暗い表情になる。河了貂もその表情の変化に何かを察したようだった。
「信…軍師学校に来たってことは…」
信が五千人将として活躍している話を知っているのなら、此度の飛信隊のことも知っているはずだ。河了貂は言葉を探すように目を泳がせている。
軍師学校に集うのは、軍略を学ぶ生徒たちだ。信が五千人将だからと言って例外はない。
「…今回の戦と、また同じことを繰り返したら、飛信隊が解散になるかもしれねえ。そうなったら、将軍昇格どころじゃねえ…」
「ええッ!?」
河了貂が驚いて大声を上げた。
寝台の上で縮こまりながら、信は戦から帰還して先ほどまでの経緯を河了貂に包み隠さず伝えた。
もしもここで河了貂に会わなかったら、愚痴の一つも零せず、溜息ばかり吐いていたに違いない。
信から一通り話を聞いた河了貂は、掛ける言葉を選ぶように「あー…」と顔を強張らせていた。
「…でも、やるしかないだろ」
顔を上げて信が苦笑を浮かべながらそう言ったので、河了貂は大きく頷いた。
「あ、ここじゃあ、素性を隠すよう言われてんだ。やりにくいだろうけど頼むぜ」
長く軍師学校にいる河了貂はなるほどと頷いた。
詳細を告げなくても、呂不四柱の昌平君と、大王側につく王騎の立場を考えてすぐに納得してくれたようだ。
ここに来るまでは色んな思いがあって複雑な気分を抱いていた信だったが、旧友との再会に気分はすっかり良くなった。我ながら単純だなと思うほどに。
「…?」
扉の向こうからまた別の気配を察知し、信は顔を上げる。
「誰だ?」
声を掛けると、扉の向こうにいる人物がゆっくりと部屋に入って来た。
「蒙毅!」
河了貂の顔に明るいものが差し込む。知り合いだろうか。
くっきりとした目鼻立ちの端正な顔立ちにはどこか見覚えがあった。蒙毅という名の少年は部屋に入るなり、信に向かって供手礼をした。
「兄上…蒙恬がお世話になっております。僕は弟の蒙毅と申します。信五千人将」
「えッ」
予想もしていない言葉を立て続けに言われ、信の声が裏返った。
そういえば友人である蒙恬には弟がいて、軍師学校にいるのだと過去に聞いていた気がする。見覚えのある顔立ちをしていたのは、彼が蒙恬の弟だからだったのか。
こちらはまだ何も名乗っていないというのに、正体を見抜いたことに、信は青ざめた。
「お、お前っ…」
「先ほど先生から話を伺いました。ご安心下さい」
どうやら蒙毅自身が信の正体に気付いたのではなく、昌平君から話を聞かされていたらしい。
つまり、この軍師学校で信の正体を知っているのは昌平君、河了貂、蒙毅の三人だけということになる。
信が複雑な表情を浮かべていると、河了貂がちょんと体を肘で突いて来た。
「蒙毅は俺の兄弟子みたいなもんだ。心配しなくて良い」
安心させるように河了貂が微笑んだので、信は頷くことしか出来なかった。
信が蒙恬と河了貂と友人であることから、芋づる式に蒙毅に正体が気づかれてしまう前に昌平君が打ち明けたのだろう。
彼の父である蒙武も呂不四柱の一人だ。父親が呂不四柱の一人ならば、息子の蒙恬や蒙毅だって呂不韋側の人間ということになる。
大王側についている信に、あらぬ疑いを掛けられる前に手を打ったに違いない。本当に頭の切れる男だ。
しかし、裏口入門にここまで付き合ってくれるのはどうしてなのだろうか。
六大将軍の一人である王騎の存在がそれほど偉大なものなのは分かっているが、そうだとしても同じ国内の敵対勢力に準ずる自分を、ここまで優遇してくれるのには、何か別の理由があるような気がした。
「それでは、まずは基礎中の基礎から始めましょう」
「は?」
いきなり話題を切り出され、信は小首を傾げた。
蒙毅が廊下を出たかと思うと、両手に大量の木簡を抱えて部屋に戻って来る。かと思えばまた廊下に出て大量の木簡を部屋に運ぶ。それを五回ほど繰り返した頃には、机に木簡の山が出来ていた。
「は?え?な、なんだ、これ?」
「なにって、軍略の基礎が記されている木簡です。まずはこれを頭に詰め込んでください」
大量の木簡を運び終え、まるでいい汗をかいたと言わんばかりに蒙毅が手の甲で額の汗を拭った。
河了貂は木簡の一つを手に取って目を細めている。
「わあ、懐かしいなあ。これ、俺も最初は覚えるの苦労したよ」
「ふふ。でも河了貂は来たばかりだったのに、あっと言う間に覚えたじゃないか」
二人が思い出話に花を咲かせている中で、信も木簡の一つを手に取って、目を通した。
文字ばかりのそれが軍略の基礎について記されているのは分かったが、一つの木簡を解読する頃には信は謎の頭痛に襲われていた。
「え…これ、全部か…?俺、さっき来たばっかりなんだぞ…?」
「まずはこれを覚えたら次のことを教えると、先生からの言伝です」
口元に笑みを浮かべた蒙毅が頷いたので、信の手から木簡が滑り落ちる。
前言撤回だ。昌平君は頭の切れる男ではなく、ただの鬼である。
軍師学校
夜通し、軍略の基礎について記された木簡を読み、信はいよいよ力尽きた。
容赦なく朝がやって来て、目の下に濃い隈を刻んだ信は、河了貂に引っ張られながら宿舎で朝食を済ませ、軍師学校へと向かった。
軍師学校と宿舎は隣接している構造になっているので、すぐに教室に辿り着く。百人に一人しか入れないという難関の軍師学校の教室には、既に生徒たちで賑わっていた。
様々な地形や戦い方を想定した軍略囲碁を打っている者が大半である。教室を見渡しても、昌平君の姿は見えなかった。この時間は呂不四柱としての政務をしているらしい。
恐らく昌平君は自分が不在の間のことも考えて、信の正体を知る河了貂と蒙毅という協力者を作ったのだ。同時に勉学を怠っていないか監視させる役割も担わせたのだろう。
(こんな生活がいつまで続くんだよ…)
既に信は屋敷に帰りたかったのだが、許されるはずがない。
教室の中には蒙毅の姿もあったが、別の生徒と軍略囲碁を打っていた。こんな朝から頭を使わなくてはならないなんて本当に憂鬱になる。何も考えずに剣を振るう鍛錬の時間が恋しくて仕方がなかった。
この教室にいる生徒の年齢はまばらであり、信や河了貂と近い年齢の者もいれば、立派な髭を生やしている者もいる。軍師学校にいる女子生徒は信と河了貂だけのようだ。
とはいえ、信の口調や化粧っ気のない外見から見れば男だと間違えられても仕方がないが…。
その点、河了貂は最後に会った時よりも随分と大人びて、女性らしくなったように思える。この差は何なのだろう。
「…さてと、まず、信は昨日の続きだな」
河了貂に引っ張られながら教室の奥へと移動する。
見慣れない姿に好奇の視線を浴びるが、新しい生徒だろうと大して気にも留められなかった。
生徒たちはみんな軍略を学ぶことに忙しく、新しい仲間が入って来ても大して気にならないのだろう。
河了貂の話だと、せっかく難関の軍師学校に入っても思うように実力がつかず、泣く泣く辞めていく生徒も少なくないのだそうだ。
全国から応募が来ると言っていた割には宿舎に幾つも空き部屋があるのはそのせいなのかもしれない。生徒の入れ替わりが激しいのだろう。
教室の奥には、昨夜、部屋に運ばれたと同じ内容が記されている木簡が積み重なっていた。
椅子に腰を下ろし、渋々木簡を手に取った信が思い出したように顔を上げる。
「テンは俺に付き合ってて良いのかよ?」
眉根を寄せて、信が河了貂に尋ねた。
自分に軍略の基礎を教える役割を担っているのなら、その間、河了貂は自分に付きっきりになってしまう。
しかし、河了貂は肩を竦めるようにして笑った。
「ここにいる奴らで、俺の相手が務まるのは蒙毅くらいだからな」
「えッ!?」
信が目を見開く。数年離れていた間、河了貂も立派な軍師の卵になっていたのだ。
これだけ数多くの生徒がいるというのに、蒙毅と二人で教室の頂点に立っているのだという。
成長したのは体だけではなかったのだと分かり、信は驚愕する。
「そっ、それなら別に俺が軍略学ばなくなたって、テンが飛信隊の軍師に―――」
「さっさと昨日の続きやるぞ!」
慌てて河了貂の両手が信の口に蓋をする。
もがもがと手の下で口を動かしている信を、河了貂が睨み付けた。可愛らしい顔でも凄まれれば、鬼人のような恐ろしさになる。
(素性を隠すんだろッ)
小声でそう言われ、そうだったと思い出した信は小さく頷いた。
「おはよう、河了貂。それに、信殿」
軍略囲碁を終えたらしい蒙毅がやって来る。
悔しそうな顔をして項垂れている対戦相手の反応を見る限り、どうやら蒙毅の圧勝だったらしい。
「……?」
自分に向けられている視線の数が多くなって来たことに気付く。
先ほどまでは見慣れない顔だと、生徒たちから好奇な視線を幾つか感じていたが、すぐに興味を失ったように軍略を学ぶことに没頭していた。
だが、今は確実に視線の数が増えている。ただの新人だったなら、ここまで興味を示されなかっただろう。
恐らくは、優等生である河了貂と蒙毅の二人から親切にされているということで、自分もただならぬ軍師の才能を持っている新人なのではないかと勘違いされているらしい。
「………」
いたたまれなくなり、信は木簡で顔を隠した。
「信?寝るなよ」
「寝てねえよッ」
河了貂の小言に信が声を荒げて、彼女の額を指で弾いた。
「いでっ!相変わらずの馬鹿力だなッ!」
仰け反った河了貂が額を擦りながら信を睨み返す。こんなやりとりをするのも久しぶりだなと思いながら、信は頬杖をついた。
彼女とは成蟜から政権を取り戻す時からの付き合いで、最後に会ったのも随分と前だったのだが、性格が変わってなくて良かったと心の中で安堵してしまう。
もしも昌平君のもとで軍略を学んだ影響で、彼のような鬼になっていたら泣いていたかもしれないと信は思った。
一方、可愛い妹弟子である河了貂の額を指で弾いた信に、蒙毅はただならぬ雰囲気を携えていた。それが殺気に近いものだと察し、信は反射的に身構えてしまう。
「…な、なんだよ、蒙毅」
「信殿。ここは軍師学校です。頭を使った勝負をしましょう。その方が覚えるのも早いかもしれません」
積み重なっている木簡の一つを手に取った蒙毅が、うっすらと口元に笑みを浮かべた。
その姿は、信の友人であり、蒙毅の兄である蒙恬が怒った時とそっくりな威圧感で、信は思わず冷や汗を浮かべたのだった。
もしかしたら蒙兄弟から時々感じる恐ろしい威圧感は、師である昌平君の影響なのかもしれない。
軍師学校 その二
陣形や兵法、城の攻略策や防衛策…軍略の基礎と一言で言っても、覚えることは膨大である。
昨夜読み進めた部分の復習だと蒙毅に幾度も質問をされたが、信は一つも答えられなかった。
大量の知識を詰め込まれ、そして忘れぬようにと質問を繰り返されて、いい加減に眩暈を起こしそうになる。
信は元々下僕出身の身で、王騎と摎に引き取られるまで字の読み書きも出来なかった。机上で何かを学んだという経験はその時くらいで、その後はすぐに鍛錬や戦場に連れ出されていた。
初陣を終えてから、あっと言う間に五千人将にまで上り詰めた信の強さは、幼い頃から天下の大将軍である王騎と摎に鍛えられた経験よるものだった。軍略がどうとかは知る由もない。
昨夜渡された木簡に載っている陣形や兵法は確かに戦場で見かけたものではあったが、それがどういった効力を持つものなのかを考えたことはなかった。
厳しい鍛錬をこなす飛信隊ならば、完璧なまでに整えられた陣形であっても容易に崩すことが出来たからだ。
しかし、此度の戦ではそうはいかなかった。王騎が言った通り、今までは運が良かっただけなのかもしれないと信はここに来てようやく思い知るのだった。
「はあ…分からねえ…」
「こればかりは繰り返し覚えるしかありません」
「うう…」
自分の物覚えの悪さに嫌気がさす。
もしも自分が下僕出身ではなくて、本当に王家に生まれていたのなら、王賁や蒙恬のように軍略というものを意識しながら戦をこなしていたのだろうか。
もしそうだとしたら、今頃は五千人将ではなくて、父と並んで大将軍として戦に出ていたかもしれない。
「…そんな簡単なことも分かんないなんて、なんで入門出来たんだ?」
机に突っ伏して頭痛を堪えていると、蒙毅でも河了貂でもない男の声が降って来た。
ただでさえ頭痛がするのだから余計な刺激をしないでもらいたいと思いながら、信が顔を上げると、河了貂と蒙毅が目をつり上げているのが見えた。
まるで全身の毛穴に針を刺されているかのような嫌な感覚に、思わず信は顔を強張らせる。
二人が睨み付けている先には、信と同い年くらいの男子生徒が立っていて、彼は腕を組んでこちらを小馬鹿にするような顔をしていた。
ふんぞり返っているその姿が、嬴政の腹違いの弟である成蟜のように見えて、信は思わず苦笑してしまう。ああいう性格の男というのは政権絡みでなくても、どこにでもいるらしい。
「それくらいの基礎知識はこの軍師学校に入門する前に覚えているのが常識だろ。なんだってそんなやつがここにいるんだか」
あからさまに敵意を向けられている。しかし、信は頬杖をつきながら聞き流していた。
父から素性を隠すように言われていたし、正体が気づかれれば混乱どころじゃすまない。
嬴政側の自分たちが何かしようと忍び込んでいたのだとあらぬ疑いをかけるかもしれないし、そうなれば天下の大将軍と称えられている養父の顔に泥を塗ることになる。
「…黄芳、学び方は人それぞれ違います。そのような言い方は改めた方が良い」
黄芳という名の少年に、諭すように蒙毅が言った。穏やかな口調を努めているが、目つきは怒りに染まっている。河了貂も同じだった。
しかし、黄芳は蒙毅の言葉も気に食わないのか、ふんっと鼻を鳴らす。
自分を庇うように怒ってくれる二人に信は感謝しながらも、「気にすんなよ」と小声で声を掛ける。
大事にするべきではないと二人も分かってはいるのだろうが、怒りが抑えられないのだろう。
蒙毅の言葉を聞いても態度を改めようとしないところを見ると、どうやら黄芳は優等生である彼のことも気に食わないのだろう。
もしかしたら自分ではなくて、蒙毅と河了貂に言いがかりをつけたいのだろうか。
しかし、下僕時代に受けて来た待遇に比べたら、鞭を突き付けて脅すようなこともしない分、黄芳の言葉など可愛いものだと信は思った。
「そんな基礎も分からないなんて、此度の飛信隊の五千人将みたいな失敗をするぞッ」
まさか黄芳の口から飛信隊の名前と自分の存在が出ると思わず、信は硬直した。蒙毅と河了貂も目を見張る。
「何の策も講じずに突っ込んで壊滅だなんて、馬鹿の一つ覚えじゃないか!あんなのがよく五千人将になったもんだ!」
気づかれたのだろうかと冷や汗をかいたが、どうやら違うらしい。
恐らく黄芳は信の正体に気付かず、知識がないことをバカにするためだけに飛信隊壊滅の話を突き付けたのだろう。此度の戦での飛信隊の動きはまさか軍師学校にも伝わっていたのか。
「基礎も知らないなんて、お前も飛信隊と同じことになるぞ!」
指をさされて、罵倒された信はこめかみに青筋を浮かべた。
その失敗を活かすために軍師学校に放り込まれたという事情を黄芳が知るはずもないのだが、信は拳を震わせた。
ここで手を出す訳にはいかない。問題を起こせば王騎の顔に泥を塗ることになると自分に言い聞かせ、信は黄芳の言葉に耐えていた。
しかし、怒りに打ち震えているのは信だけではなかった。
「…さっきから黙って聞いてりゃ、黄芳ッ!好き勝手に言い過ぎだろ!」
先に堪忍袋の尾が切れたのは河了貂の方だった。
まさか河了貂が怒鳴るとは思わなかったのだろう、黄芳が驚いたように顔を強張らせる。
「飛信隊は俺たちと違って、実際に戦場で命を懸けて戦ってんだぞ!一生懸命戦ってくれた兵たちによくもそんなことが言えるなッ!」
河了貂のよく通る声は教室中に響き、波を打ったかのような静寂をもたらした。
「…テン」
いたたまれなくなり、信は河了貂の着物を引った。怒りに染まっていた河了貂の真っ赤な顔がはっと我に返る。
素性を隠さねばならない自分が言い返せないのを分かった上で怒ってくれた河了貂と、黄芳を諭すように声を掛けてくれた蒙毅に、信は純粋に感謝した。
しかし、ここで素直に礼を言うと正体に気付かれてしまうかもしれないので、信は穏やかな笑みを二人に向ける。
「ふ、ふんッ!これだから女は嫌なんだ!」
どうやら河了貂の威圧に負けたらしい、黄芳は最後まで憎まれ口を叩きつつ去っていく。
静寂だった教室が元の賑やかさを取り戻したので、信はにやっと歯を見せて河了貂と蒙毅を見た。
「ありがとな、二人とも」
周りに聞こえないように、信は二人に感謝の言葉を伝えた。二人も黄芳がいなくなったからか、穏やかな笑みを返してくれる。
「!」
再び木簡に目を通そうとした時、視界の隅に昌平君の姿を見つけた信は心臓を跳ね上がらせる。
一体いつから居たのだろう。河了貂と共にこの教室に来た時には彼はいなかったはずだ。
座って木簡に目を通している姿を見る限り、もしかしたら先ほどの黄芳とのやり取りを聞かれていたのかもしれない。
信が焦燥感を抱いているのは黄芳とのやり取りではなく、自分がまだ基礎を覚えていないことを咎められるのではないかという不安によるものだった。
真面目にやっているつもりだが、全然基礎の一つも覚えていないと知られれば、有無を言わさず強化合宿を延長させられることになるかもしれない。それだけは嫌だった。
(やべッ!)
うっかり目が合ってしまい、信は木簡で顔を隠し、存在感を消そうと縮こまる。
あからさまに挙動不審となった彼女に、蒙毅と河了貂は小首を傾げていた。
恐る恐る木簡を盾にしながら昌平君の方を覗き見てみたが、彼は既に手元の木簡に視線を向けていた。
安堵しながら、信は蒙毅と河了貂から再び軍略の基礎についてを教わるのだった。