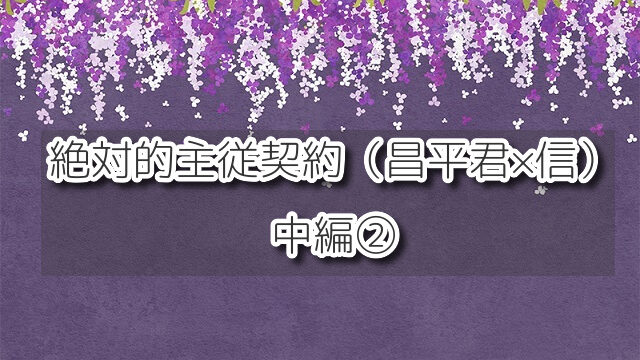- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 桓騎×信/李牧×信/年齢操作あり/年下攻め/執着攻め/秦趙同盟/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
Contents
身代わり
まるで痛みを堪えるような信の表情を見て、桓騎の中にあった嫉妬の感情がより大きく膨らんでいった。
あの男がまだ信の心を巣食っているのは明らかだ。しかし、一方では信に対して怒りの矛先が向けられている。
彼女が李牧と関係を持っていたことを知らなかったのは、きっと自分だけではない。
秦将である立場にあるにも関わらず、趙の宰相と姦通していたとなれば、過去のものだとしても重罪として扱われる可能性がある。信もそれを理解していたからこそ、今まで誰にも告げなかったのだろう。
ただ、どうして自分にさえ打ち明けてくれなかったのかという、行き場のない怒りが桓騎の嫉妬の炎をより燃え盛らせた。
彼女が李牧との関係を素直に打ち明けてくれたところで、何が変わる訳でもないし、信の心から李牧が消え去ることはないことも分かっている。
それなのに、彼女のことなら全て把握しておきたいという気持ちが絶えることはない。
幼い頃から信のことを想っていた桓騎は、自分だけが信の特別な存在になりたい願っていた。
彼女の秘密を共有すれば、信にとって自分は特別な存在になれたのかもしれない。
たとえそれが、李牧とは違う意味での特別だとしても、桓騎は彼女の心に自分という存在を刻みたかったのだ。
それほどまでに、桓騎は信のことを愛していた。
「信…」
未だ傷が癒えていない彼女の右手を掴んで、桓騎はその手の平に口づける。今彼女と唇を重ねれば、間違いなく舌を噛み千切られると思ったからだ。
いつも剣や槍を握っている彼女の手の皮はマメだらけで肥厚している。爪を立てて血が流れたということは、相当な力を入れていたのだろう。
回廊で李牧に会った時、養父を討たれた憎しみ以外にも、色んな感情が蘇ったに違いない。
「か、桓騎…」
震える声で名前を呼ばれて、桓騎は手の平に唇を押し付けながら、信を見た。
発熱しているせいか顔が赤い。それが恥じらいによるものであれば、どれだけ救われたことだろう。
「…俺は、あいつの代わりだったんだな?」
「―――」
静かに問い掛けると、信が目を見開いて、言葉を喉に詰まらせる。
それが信に対しても、自分に対しても、残酷な問いであることは十分に自覚していた。
否定されなかったことから、それが答えだと確信した桓騎は、口の中に苦いものが広がっていくのをまるで他人事のように感じていた。
次いで、胸が引き裂かれるように痛み、いつものように小言を返す余裕もなくなってしまう。
顔から表情を消した桓騎を見上げて、信が力なく首を横に振った。
「…違う」
すぐにでも消えてしまいそうな、弱々しい声。それは紛れもなく桓騎の問いを否定する言葉ではあったものの、桓騎の胸に響くことはなかった。
「桓騎、俺は…」
「もういい」
弁明の言葉を遮ると、信が怯えた表情を浮かべる。
桓騎は幼い頃から聡明な頭脳を持っていた。相手に見抜けぬ奇策を用いることで次々と敵軍を一掃して来たし、相手の思考を見抜くことを得意とし、何より物事の理解が早かった。
だから、信と李牧の関係を確信してから、自分が信にとってどういう存在であったのかも、すぐに理解してしまったのだ。
ある意味では、それは桓騎の望む特別だった。だが、李牧以上の特別になることはない。
「お前が俺を戦に出したくなかったのも、あいつの代わりだったからなんだろ」
「ちが…」
小癪にもまだ弁明をしようとするその口を塞ぐために、桓騎は唇を押し当てた。薄く開いた口の中に舌を差し込んで、彼女の舌を捉える。
「んんッ…!」
自分の口の中に信の舌を導くと、容赦なく噛みついた。
血が滲むほど強く噛んでやり、このまま黙らせるために舌を噛み切ってやろうかと考える。
鉄錆の苦い味が口の中に広がると、今まで夢見ていた信との甘い口づけとは、程遠い現実だったことを自覚した。
血の味の口づけを交わしながら、彼女の手を頭上で一纏めに押さえ込む。
「ふう、ッ、んん…!」
くぐもった声を上げた信が、まるで許しを請うように、涙で潤んだ瞳を向けて来た。
もしも初めから、李牧の身代わりとして自分を拾ったのだと教えてくれたのなら、自分は喜んでその役目を全うしただろう。
たとえ身代わりだとしても、きっと今以上に愛してもらえたに違いない。
しかし、身代わりであることは一切告げず、桓騎の自我を崩さぬように扱って来たのは他でもない信だ。憎らしいほど、彼女は他人を欺く才に恵まれなかった。
身代わりであることを確かめたのは、他でもない桓騎自身だ。もしも李牧と信の関係に気づかなければ、一生この事実を知らないままでいられたかもしれない。
信が自分の中に李牧の姿を見ていたとしても、それを知ることなく、偽りの愛情で満足して死ぬという道もあっただろう。今となっては全て手遅れだが。
それでも、自分が李牧の身代わりだったと分かってもなお、桓騎の信を愛する気持ちが揺らぐことはなかった。
自分こそが救いようのないバカだと、桓騎は引き攣った笑みを浮かべる。
彼女にとって自分が李牧の身代わりなのだとしたら、その役目を全うするべきだ。それは信のためではない。信に愛されるためであって、他でもない自分のためである。
「李牧にされたこと、俺が全部やってやるよ。俺はあいつの身代わりだからな」
「…!」
その言葉が、信の胸に重く圧し掛かったのは、彼女の表情を見ればわかった。
ざまあみろと歯を剥き出して笑ってやれたのならと思うのだが、切なさで胸が満ちているせいか、上手く笑みを繕えない。
「桓騎ッ、やめろ…!」
再び律動が始まったことに、信が焦燥の表情を浮かべる。
身代わりになることを選んだというのに、一切喜ぶ様子のない信に、桓騎はやるせなさを覚える。
しかし、その気持ちとは裏腹に、腰は軽快に動いた。
「やああッ」
喜悦に染まった声が上がった。それは紛れもなく、女の声だった。
最奥を突き上げた時に、こつりと何かが亀頭に触れる。それが女にしかない尊い臓器だと分かると、桓騎は夢中でそこを突いた。
「ぁあっ、や、めッ、ぁああ」
上体を覆い被さるようにして、まだ逃げようと抵抗を続ける信の体を強く抱き押さえる。
黒髪を振り乱して体を痙攣させるところを見れば、急所を突いているのだと分かった。
濡れた瞳と視線が絡み合う。耐え難い苦悶に眉根を寄せながら泣いている表情が愛おしくて、もっと壊してやりたいという想いに駆られた。
初めから李牧の身代わりであることを潔く受け入れていたのなら、信は抵抗することなく、その身を委ねてくれたのだろうか。今となってはもう分からない。
「ぁぐッ…!」
両手首を押さえていた手で、男根を咥え込んでいる腹を圧迫してやると、外側と内側から圧迫される刺激によって、信の体が大きく仰け反った。
「ぐる、しぃ…」
許しを乞うように、信が涙で濡れた瞳で見上げて来る。
絶対に許さない。自分が味わった苦しみを、信も同じ分だけ味わえば良いと思った。それが自分が李牧の身代わりとなる条件だ。
もっと苦しめと心の中で呟きながら、桓騎は力強く彼女の体を抱き込む。
すでに彼女の最奥まで貫いているはずなのに、さらに奥へと進みたくて腰を突き出した。
「はッ…はあッ、ぁあっ、ああぅ」
苦悶を浮かべていた信の顔が徐々に蕩けていく変化を、桓騎は見逃さなかった。
腹の底から込み上げて来る快楽に、桓騎も絶頂へ上り詰めることしか考えられなくなっていく。
激しい律動を繰り返していると、信が縋るものを探して桓騎の背中に腕を回して来た。情事中の彼女の癖なのだろうか。
今だけは、自分を求めてくれている。
その事実さえあれば、桓騎はこのまま死んでも良かった。もちろん信も道連れにして。
身代わり その二
「ぁ、ま、待て、ほんとに、も、やめろ…!」
荒い呼吸の合間に、信が上擦った声で言葉を紡いだ。
背中に回していた手で、覆い被さっている桓騎の体を押し返そうと肩を掴んだものの、その手にはほとんど力が入っていなかった。
「抜けっ、もう抜けってば!」
犯されている体は今も喜悦の反応を見せているが、彼女の中にある強固な意志は決してそれを許さないようだ。信らしいと桓騎は笑った。
「放せって…!」
自分の体を力強く抱き締めて放さない桓騎の腕に、信が何度も同じことを訴える。それが無意味なことだと何故気づけないのだろう。
信はどんな負け戦でも最後まで諦めない不屈の精神を持つ女だが、状況と相手が悪かった。
どうにかして深い結合を解こうと腰を捩る姿に、さらに嗜虐心が煽られる。
ずっと恋い焦がれて止まなかった女を、この腕に抱いているのだ。途中でやめられるはずがない。
「李牧には、自分から足開いてたんだろ」
信の瞳に怯えが走った。
自ら男根を手で愛撫して、口淫まで行った信を見れば嫌でも分かる。あれは男を喜ばせる術であり、李牧に行っていたのだろう。
それを彼女に教えたのが李牧なのか、他の男なのかは分からない。もしかしたら誰に教わった訳でもなく、信が男を誘う才を芽吹かせただけなのかもしれないが、もうそんなことはどうでも良かった。
「いや、いやだッ」
さらに力強く信の体を抱き込むと、桓騎は容赦なく腰を突き出した。
子供のように泣きじゃくりながら信が腕の中で力なく暴れ出すが、結合が解ける気配はなく、桓騎の体を押し退けられないと分かると、小癪にもまだ抵抗を続けるつもりなのか、腕や背中に爪を立てて来た。
「や、ッ…桓騎、頼むから、話を…」
「今さら話すことなんて何もねえだろ」
弁解も哀訴も聞きたくないと、桓騎は彼女の口を己の唇で塞いだ。
「んんッ…!」
くぐもった声を上げた信が、まだ何か言おうとしているのだと分かると、桓騎は口内に舌を差し込んで今度こそ言葉を奪った。
もう何も聞きたくないと、桓騎は彼女の赤い舌に容赦なく歯を立てる。
「ん、ふ…」
再び口の中に血の味が広がって、自分たちに相応しい口づけの味だと桓騎は嘲笑を浮かべた。
血の味で嗜虐心がさらに煽られると、桓騎はいよいよ彼女の中に子種を植え付けるために腰を打ち付ける。
張り詰めた男根が、何度も淫華の奥にある子宮の入り口を何度も穿った。
桓騎が今行っているのは、紛うことなき凌辱だった。
「んっ…!んんッ、ん…ぅ」
信の悲鳴の中にも、僅かに被虐の喜悦の色が浮かんでいることを桓騎は感じ取っていた。
想いが通じ合わないとしても、彼女が自分を男として受け入れている。
それは桓騎が幼い頃から望んでいたことで、まさかこんな凌辱の中で夢が叶うとは思っていなかった。
「はあッ…はあ…」
息が苦しくなって口を離すと、信が大口を開けて呼吸をしていた。涙を流し続けるその顔は、憎らしいほど淫蕩が増していた。
「あっ、あぁっ、やだ、やめろっ、はなせ、だめだって、頼むから」
射精に向けた昂進に、信が哀願を振り絞る。
疲労のせいで抵抗もままならないのだろう。声を上げるのが精一杯といった様子だった。
言葉とは裏腹に、男根を咥え込んでいる信の淫華が、子種を求めてきゅうきゅうと締め付けて来る。
「中で出すからな」
腹の底から駆け上がる吐精の衝迫に、堪らず呟くと、信が青ざめたのが分かった。
李牧の身代わりとして、信が彼にされたことを全てやるつもりだったが、こればかりは嫌がらせだった。
彼女に今も子がいないことから、腹に子種を植え付けられたことはないのだろう。それは桓騎にとってとても都合が良かった。
どれだけ李牧のことを想っていたとしても、信が身籠るのは他でもない自分の子である。
嫌でも自分という存在を意識して生きなくてはならない。これは自分の好意を利用した信の贖罪だ。一生をかけて償えと桓騎は心の中で吐き捨てた。
「やだ!やめろッ、やだあぁッ」
悲鳴を上げながら、必死に逃げようとする信の細腰をしっかりと両手で捉える。一番奥深くまで性器を密着させた状態で、尚も先に進もうと腰を揺すり続けた。
「あッ…やぁああーッ」
信の体が弓なりに反り返ると、子種を全て吸い尽くすかのように、男根を痛いくらいに締め上げた。
「ッ…!」
眩暈がするほど凄まじい快楽が全身を貫いたのと同時に、桓騎の下腹部が痙攣を起こした。痙攣に合わせて、精液が何度かに分けて吐き出されていく。
快楽の波に意識が飛ばぬよう、縋りつくものを探して、彼女の身体を腕の中に閉じ込める。
吐精が終わるまで、桓騎は彼女の身体を強く抱き締めたまま動かずにいた。
「…ぁ、あ…う、嘘…」
子宮に子種を植え付けられる、女にしか分からない感覚に、信の顔が絶望に染まっていく。
絶頂の余韻と、家族のように想っていた男から犯された事実に、瞳から止めどなく涙を流している。
きっと李牧には、その表情を見せたことはなかったに違いない。
そう思うと、李牧の身代わりだと知ってから切なさでいっぱいだった桓騎の胸は、不思議と優越感で慰められた。
夜明け
一度目の絶頂を迎えた頃はまだ真夜中だったが、今では灰青色の夜明けの光が室内に入り込んで来ていた。
もう何度絶頂を迎えたのか、信も桓騎も覚えていない。繰り返し抽挿する男根も淫華も擦れて赤くなり、どちらの性器も焼けつくような痛みがあるだけでなく、敏感になっていた。
信の中に植え付けた子種も、桓騎が腰を揺する度に逆流して、二人が繋がっている僅かな隙間から零れている。
後背位や騎乗位など様々な体位で繋がっては、何度も信の中で吐精して、信も甲高い声を上げて絶頂を迎えた。
いつまでも繋がったままでいたいと思うし、しかし、体を繋げていれば、腰を動かさずにはいられない。
「も、無理ッ…だって、ぇッ…!」
止めどなく涙を流しながら、信が力なく桓騎の体を押し退けようとする。
覆い被さるように彼女に抱き締めながら、桓騎はうるさい口を黙らせようと、唇で蓋をした。
「んんッ、んッ…!」
信が嫌がって首を振る。舌を差し込んだが、もう噛みつく気力すら残っていないらしい。
ずっと水分も摂らず、性の獣に成り果ててしまったかのように交わりあっているせいで、濃い唾液を絡め合った。
もうやめてくれと信が許しを請う度に、より一層苦しめてやりたくなる。
自分が味わった苦しみを信に思い知らせれば、少しは気が晴れると思ったが、余計に虚しさが駆り立てられるばかりだった。
「あ…ぅ…」
激しい凌辱によって、ついに気を失ったのか、信がぐったりと動かなくなる。閉ざされた瞼が鈍く動いていたが、目を覚ますことはなかった。
「っ…」
ゆっくりと腰を引くと、中で吐き出した精液が逆流して溢れ出て来た。
尻や内腿を伝っていく精液を指で抄うと、桓騎は迷うことなく、潤んで充血している中へと押し込んだ。
確実に子種を実らせようと、指を使って自分の精液を中に塗り付ける。何度も男根を突き上げてやった子宮口には念入りに擦り付けた。
どれだけ自分を拒絶をしたとしても、内側から芽吹いた種は、その身に根を張っていくのだ。容易には取り除けないほどに。
自分の子を身籠った信は、一体どんな顔を見せてくれるのだろう。我が子ですら、李牧の身代わりとして扱うのだろうか。
「クソ…!」
きっと信は、李牧の代わりになるのなら、自分じゃなくても良かったに違いない。今まで信へ向けていた純粋な好意を、利用という形で踏み躙られた。
彼女が腹の内に黒いものを抱えていることに気付けなかったのは自分の失態だが、どこまでも自分を苦しめる残酷な女だと思った。
意識を失ってからも涙を流し続けている信の寝顔を見下ろして、やるせなさが込み上げて来た。
李牧の身代わりとして自分を利用していた信のことが憎いはずなのに、それを上回る愛情が、桓騎の心を惑わせる。
憎しみに靄が掛かってしまうのは、これだけ残酷な仕打ちをされても、信を愛しているからだ。
「…信…」
彼女の身体を強く抱き締め、桓騎は彼女の首筋に顔を埋める。
幼い頃はこうやって甘えれば、穏やかに笑んだ信が抱き締め返してくれて、眠りに就くまでずっと背中を擦ってくれた。
あの頃から、信は自分を李牧の身代わりとして見ていたのだろうか。李牧の身代わりにするために雨の中で倒れていた自分を保護したのだろうか。
目頭がじんと沁みるように熱くなり、桓騎は強く目を閉じた。
朝陽が昇り、二人きりの時間は強制的に終止符を打たれた。
信の看病を命じられた女官が部屋を訪れたことで、信を抱き締めながら眠っていた桓騎は部屋から追い出されたのである。
その後、桓騎が信の部屋に侵入したことがきっかけになったのか、療養のために宛がわれたあの一室には見張りの兵がつくようになった。
熱が出ていた身体に無理を強いたことが原因で、どうやら信の体調が悪化してしまったらしい。医師が慌ただしく部屋を出入りしている姿を幾度か見かけた。
ろくに水分も摂らずに激しい情事を続けていたのだから当然だ。冷静になった頭で、桓騎は今さらながらに後悔と罪悪感を抱いた。
合意の上だったのかと問われれば、素直に首を縦に振ることは出来ない。
しかし、熱と疲労で朦朧としながらも、信は桓騎と共に寝台に横たわっていたのを目撃した女官を説得してくれたようで、桓騎に処分が下されることはなかった。
合意もない上に、熱を出して弱っている彼女の寝込みを襲ったとなれば、秦王嬴政からすぐにでも斬首を命じられたかもしれない。嬴政がそれほど親友の存在を大切に想っていることは桓騎も昔から知っていた。
此度の件が嬴政の耳に入るのを信が事前に阻止したのか、その後も特にお咎めはなかった。
自分のことが嫌になったのなら、さっさと嬴政に事実を告げて斬首にすれば良いのに、どうして信はそうしなかったのだろう。
女として男に犯された事実を他の者に告げたくなかったのか、それとも将として、桓騎という軍力を失いたくなかったのか。もしくはまた別の理由があるのかもしれない。
真意を確かめたかったが、ただでさえ秦王がいる宮廷内には見張りの兵が多いので、窓からの侵入は困難だろう。
見張りの兵を上手く唆して無理に押し通っても良かったが、そんなことをしたら、さすがに信も怒り狂うことになるだろう。次は嬴政に報告して斬首の運びに持っていくかもしれない。
(上手くいかねえな…)
こうなれば、ほとぼりが冷めるまでは時間と距離を置くしかない。
熱が出ていた体に無理強いをしたことを謝罪するつもりはあったが、彼女と身を繋げたことに関しては少しも後悔していないし、自分を李牧の身代わりとして利用していたことを許すつもりはなかった。
敵対心
三日ほど経ってから、桓騎は再び宮廷へと訪れた。
回廊を進んで信が療養している部屋に向かっていると、扉の前で兵が見張りを行っている。
まだ信があの部屋で療養していることが分かると、桓騎の中で複雑な想いが浮かんだ。
軽快したという報せは聞いていなかったし、むしろあの夜のことがきっかけになって今もまだ寝込んでいるのではないかと心配だった。
彼女の顔を一目見られればそれで良かった。きっと信にしてみれば、自分とは二度と会いたくないと思っているかもしれない。
もしかしたら、自分の顔を見たら即座に斬りかかって来るかもしれない。
彼女に殺されるなら、信がその人生を全うする最期の瞬間まで、自分を忘れさせぬよう、呪いの言葉を吐いて死んでやろうと思った。
(さて、どうするか…)
柱の陰に身を潜めて、扉の前にいる見張りの兵をどのようにして追い払うか考えていると、部屋から何者かが出て来た。
見張りの兵が礼儀正しく一礼したその人物に、桓騎は思わず目を見開く。
(は…?)
なぜか信の部屋から、趙の宰相である李牧が出て来たのである。桓騎は思わず睨みつけるようにして目を吊り上げた。
(なんであいつが…)
趙の一行は未だこの宮廷に留まっている。秦趙同盟を結んだ暁に、丞相の呂不韋から咸陽の観光を勧められて、予定以上の滞在になっているという話は噂で聞いていた。
宮廷にいることは不思議ではないのだが、なぜ信が療養している部屋からあの男が出て来たのだろう。
「…!」
柱の陰に身を潜めていたのだが、李牧の存在に驚いて身を乗り出していたことで、向こうもこちらの気配に気付いたらしい。
目が合ってしまい、桓騎は咄嗟に顔ごと視線を逸らした。その場から立ち去ることも出来たのに、なぜか桓騎の足は杭に打たれたかのように動かない。
護衛も連れず、李牧は一人で信に会いに来たようだった。彼が信と会っていたことは安易に予想出来たが、一体何を話していたのだろう。
優雅な足取りでこちらに近づいて来る。
先日のように、そこにいない者として素通りされるのかとばかり思っていたが、今日は違った。
「あなたが桓騎ですね」
桓騎のすぐ前までやって来た李牧が、まるで天気の話題でも出すかのように、明るい声色で問い掛けた。
先日、信に声を掛けて来た時にも感じたが、彼は一見ただの優男に見えて、中には触れてはいけない何かを抱えている。
それはきっと、鋭い刃の切先のような、安易に触れようとした者の手をたちまち傷をつけてる棘のようなものに違いない。
「………」
返事の代わりに睨みを送ってやると、まるで挑発するかのように、李牧が人の良さそうな笑みを深めた。
「信の体調が悪いと聞いたので、見舞いに来たのですよ」
こちらは何も聞いていないというのに、李牧は信に会った目的を話し始めた。
信に熱があることを指摘したのは確かに李牧だ。宴の夜から体調が悪化したことを何処からか聞いたのだろう。
秦王の勅令もあって侍女が看病に就いていたくらいなのだから、噂が広まっていたのかもしれない。
李牧がその場を去ろうとしないことから、まだ何か用があるのかと桓騎は眉根を潜めた。
僅かに身を屈めて、桓騎の耳元に口を寄せて来た李牧が、
「せっかく恋い焦がれて止まなかった彼女を抱いたというのに、随分と辛そうな顔をしていますね?」
「ッ…」
声を潜めてそう言ったので、桓騎は弾かれたように顔を上げる。まるでその反応を予想していたかのように、李牧が目を細めた。
初めに思ったのは、信が李牧にあの夜のことを告げたのかという疑問だった。
動揺のあまり、聞き返すことも出来ずに桓騎が李牧をじっと見据えていると、彼は信が療養している部屋の方に視線を向けた。
「信が求めていたのは、貴方ではなかったということですね」
その反応を見れば分かりますと、勝ち誇ったような笑みを向けられて、目の奥が燃えるように熱くなる。
桓騎の怒りを煽るかのように、李牧は静かに言葉を紡いだ。
「…彼女に破瓜の痛みを、男を喜ばせる術を教えたのは私ですよ。そして、今でも彼女は私のことを求めている」
顎が砕けるのではないかと思うほど、桓騎は無意識のうちに歯を食い縛っていた。
もしも今、剣を手にしていたのなら、間違いなく目の前の男の首を斬り落としていただろう。両手が拳を作っていなかったら、その首を締め上げていたに違いない。
怒りに打ち震えたまま沈黙する桓騎に、今度はまるで同情するかのような、慈しむ視線を向けて来た。
「信にとって、あなたは、私の代わりでしかない」
その残酷な事実は、信と李牧の関係を知ったことで桓騎自らが掴み取った結論でもある。まさか、よりにもよって李牧から聞かされることになるとは思わなかった。
怒りが胸に渦を巻いており、ぐらりと眩暈がした。
しっかりと両足で立っているはずなのに、視界だけが揺れていて、吐き気が込み上げて来る。
「………」
回廊から空を見上げ、まるで墨絵のような雲が空を閉ざし始めていくのを李牧は黙って見つめていた。
やがて、雨が地を打ち始める。
今朝までは晴れていたというのに、陰鬱な天気になったことに、桓騎は空が自分の代わりに泣いてくれているのかと思った。
「…そういえば、私が彼女のもとを去ったあの日も、雨が降っていました」
独り言のようにそう囁くと、李牧は桓騎から興味を失ったかのように歩き始めた。
その場に残された桓騎は雨の音を聞きながら、泣いている空を見上げる。堰を切ったかのように、雨はどんどん強まっていった。
「………」
そういえば、自分が信と出会った日もこんな雨だったと、桓騎はぼんやりと考えた。
雨の日
信が自分を見つけて保護してくれたあの日、彼女は簦 を二本持っていた。
一つは自分たちが濡れないように差していたが、もう一つは足下に転がっていた。
あの場に居たのは信と自分だけで、あの簦の持ち主は誰だったのか、桓騎はずっと答えを知らずにいた。
―――…そういえば、私が彼女のもとを去ったあの日も、雨が降っていました。
先ほどの李牧の言葉を照らし合わせ、桓騎はいよいよ立っていられずに、その場に座り込んでしまう。
簦を差して雨を凌いでいたはずの信の頬が何故か濡れていたことも、全てが繋がった。
桓騎が信と出会ったあの日、李牧が信のもとを去っていたとしたら?
優しい性格の彼女のことだから、雨で濡れないよう、李牧に簦を届けようとしたのだろうか。それとも李牧を引き止めるために追い掛けていたのだろうか。
「…く、くくっ…」
柱に背中を預けながら、桓騎は引き攣った笑みを浮かべていた。
回廊には丈夫な屋根があり、雨は降り注いでいないはずなのに、幾つもの雫が頬を伝っていく。
「くく、はは…ははッ…は…」
乾いた笑いが止まらない。頬を伝う雫もいつまでも止まらなかった。
信にとって、自分が李牧の身代わりであることを、心のどこかでは拒絶していたのだ。
しかし、あの雨の日に李牧が信のもとを去り、それがきっかけとなって自分が保護されたのだとしたら、その残酷な事実を認めるしかない。
秦軍の知将と名高い桓騎が回廊に座り込んで泣き笑いをしている奇妙な光景に、通りすがりの女官や兵たちが好奇の目を向けている。しかし、誰も声を掛けようとしない。
(結局、何も変わらねえ)
地位や名誉を手に入れたところで、結局は自分の力で立たないといけないのだ。
信と出会うよりも、その残酷な事実をずっと前から知っていたはずなのに、心の中ではいつも縋るものを探していた。
信は素性も分からぬ自分を怪しむことなく、一人の人間として扱ってくれて、この身が汚れていようとも、構わずに抱き締めてくれた。
そんな彼女だったから、身も心も、命すらも差し出せたのに。
いっそ李牧の身代わりとして彼女の傍で生き続けると開き直れたらと思ったが、信は凌辱を強いた自分を見限ったに違いない。しかし、秦王に告げ口をしなかったのは、彼女なりの慈悲なのだろう。
(信…)
もう二度と彼女から口を利いてもらえず、目も合わせてもらえないのなら、このまま生きていても意味などない気がした。桓騎にとって、信の存在だけが生きる理由だった。
潔く、秦王に信を凌辱したことを告げて、斬首にしてもらった方が手っ取り早く楽になれるかもしれない。
俯いたままの桓騎が静かに鼻を啜っていると、
「…桓騎、お前…泣いてんのか?」
上から聞き覚えのある声が降って来て、真っ赤に泣き腫らした瞳で桓騎は声の主を見上げる。
相変わらずこちらの気持ちも考えず、無神経に顔を覗き込んで来る女の顔を見て、桓騎は無性に苛立った。
同時に、それを上回る愛おしさが込み上げた。