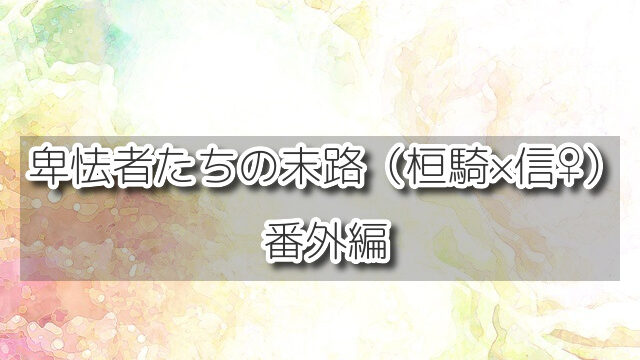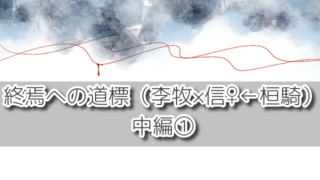- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 桓騎×信/李牧×信/年齢操作あり/年下攻め/執着攻め/秦趙同盟/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
療養
桓騎に犯されたことで、ただでさえ弱っていた体に無理が祟ったのか、さらに高い熱が出た。
侍女が部屋に訪れたのは朝方のことで、夜明けまで信のことを犯し続けていた桓騎も疲れ切り、彼女を抱き締めて寝入っていた。
隠しようのない情事の痕跡が体や室内に多く残っていることから、二人が何をしていたのかは言葉にせずとも分かったのだろう。
桓騎はすぐに部屋から追い出されたが、信は朦朧とする意識の中で、侍女にこのことは誰にも告げないように懇願した。
合意のない行為であったことが嬴政の耳に入れば、間違いなく彼は桓騎に処罰を与える。
熱が出ている自分の看病に当たるよう侍女に命じたのも嬴政だ。信の体調が悪いというのに、桓騎が寝込みを襲ったと誤解されるに違いない。
それに、桓騎のことだから、凌辱の罪を問われても弁明することなく、喜んで斬首を受けるような気がしてならなかった。
そこまで桓騎のことを心配してしまうのは、長年共に過ごして来た情なのかもしれない。
苦い薬湯の味も分からないほど熱が出たのは初めてのことだった。しかし、朦朧とする意識の中で考えていたのは、やはり桓騎のことだった。
三日も経つと熱は引いて、普段通りに体を動かせるようになっていた。
まだ少しだけ喉の痛みと咳が続いていたが、すぐに快調するだろうから、もう薬湯は飲まなくても良いと医師から言われていた。
看病をしてくれていた女官も役目を終えたのだが、桓騎とのことは内密にしておくことを誓ってくれた。
ずっと横になっていたので、体力の衰えを取り戻さなくてはと信はすぐ鍛錬に励もうとした。しかし、完治するまでは武器を持つことを親友である嬴政は決して許さなかった。
見張りの兵がついたのは外部からの侵入を防ぐためではなく、信の逃亡阻止と、行動を監視をするためだったのだろう。
脱走を阻止するためにわざわざ兵を手配した親友の相変わらずな心配性に、信は肩を竦めた。
桓騎とのことは知られずにいるようだが、一晩で体調が悪化した報告は聞いていたのか、無理をさせまいとしているのだろう。
もしかして見張りの兵をつけたのは、自分が無理をしたことが原因で体調が悪化したのだと思っているのだろうか。桓騎とのことを知られずに済むのなら誤解されたままにしておこうと考えた。
完治するまで部屋で大人しくしてれば、速やかに釈放されるに違いない。
「………」
腹を擦り、信は目を伏せた。
桓騎はこの身に子を宿らせるために、凌辱を強いたのだろうか。
―――…俺は、あいつの代わりだったんだな?
あの時、すぐに違うと否定していたのなら、桓騎は自分の言葉を信じてくれたのだろうか。
まさか李牧とこんな形で再会するとは思わなかったし、昔から自分のことなら何でも把握したがる桓騎が、李牧のことを気にならないはずがなかった。
趙の宰相である李牧と過去に関係を持っていたことは、秦将の立場であることから、後ろめたさを感じていた。
この国と嬴政に忠誠を誓っている立場でありながら、趙の宰相と過去に関係があったことを知られれば、あらぬ噂を流されて謀反の疑いを掛けられる要因にもなり得る。
当時の李牧は何者でもなかった。だからこそ、彼が自分のもとを去ってから、敵国に仕え、宰相の立場に上り詰めるだなんて想像もしていなかった。
同盟が成立したとはいえ、秦国の敵として李牧が自分の前に現れたことに、何を話すべきか分からなくなってしまった。
自分の養父だと知りながら、馬陽で王騎を討ち取ったのは、自分との決別を意味していたのだろう。
あの日に自分のもとを去っただけでなく、今度は自分から大切なものを奪っていくのかと信は絶望した。
李牧の存在が秦国とっての脅威となることを信は頭では理解していたのだが、共に過ごしていたあの日々がそれを認めたくないと拒絶している。
「はあ…」
気になるのは李牧のことだけではない。
寝台に横たわりながら、次に桓騎に会った時、何を伝えるべきなのかを考えていた。
もしかしたら桓騎は自分に嫌悪して、二度と顔も見たくないと思っているかもしれない。この腹に子種を植え付けたのは、きっと凌辱の延長に過ぎないのだろう。
―――ば、バカッ、抜けよ!何してんだッ!
目を覚ました時、なぜか桓騎と身を繋げていて、心臓が止まるかと思うほど驚愕した。
昔から足音と気配を忍ばせて、布団に潜り込んで来ることは多々あったが、まさか幼い頃から面倒を見て来た彼に抱かれることになるとは夢にも思わなかった。
―――今さら言われても抜けねえだろ。お前が早く欲しいって言ったくせによ。
桓騎の言葉を思い出すと、まるで自分が桓騎を誘ったような状況だったらしいが、信は少しも覚えていない。熱のせいだろうか。
「はあー…」
考えることが山積みで、しかしどれもが自分で結論を導き出すことの出来ない悩みで、信は頭痛を催した。
もともと考え込むのは性に合わない。かといって、直接話を聞き出すような度胸も、今の信にはなかった。
来客
扉が叩かれたので、信は反射的に起き上がった。
見張りの兵が扉を叩く時は食事の時か、来客のどちらかだ。
数刻前に食事は終えていたし、となれば消去法で誰かが面会に来たのだろう。療養している自分に、囚人と同等の扱いを指示をした嬴政かもしれない。
「信将軍。趙の宰相がお見えになりました」
「えっ!?」
扉越しに聞かれされた来客に、信は驚いて声を上げた。
(しまった…)
呼び掛けに反応せず、眠っていたことにしていれば良かったと後悔する。慌てて口を塞いだが、もう遅かった。
「お通しします」
「あ、お、おいッ!?勝手に…」
扉越しに信の声を聞いた兵が、こちらの承諾も得ずに扉を開けた。
面会を断るか問われなかったのは、同盟が成立したばかりの今、秦趙の間で波風を立てるのを防ぐためだろう。
「………」
部屋に入って来た李牧の姿を見て、寝台に腰掛けたまま、信は思わず眉根を寄せた。
どうして自分が宮廷に療養していることを知っているのだろう。
「あ…」
頭を下げた兵が早急に部屋を出ていく。
李牧と二人きりにならないよう、室内で待っているよう兵に命じておくべきだったと、信はまたもや後悔した。
「………」
信に睨みつけられた李牧は少しも臆することなく彼女の前までやって来ると、僅かに身を屈めて手を伸ばして来た。
あの回廊で会った時のように、信の頬に優しく触れると、穏やかな笑みを浮かべる。
「…熱は下がったようですね」
その手を振り払うことは簡単に出来たはずなのに、信はそれをしなかった。
まだ心のどこかに、李牧の温もりに触れていたいと、彼と共にいたいと望んでいる自分がいるのだ。
それを未練がましいと思いながらも、信は上目遣いで李牧を見上げる。
「…なんで」
「先日、医師が慌てた様子で部屋に入っていくのを見かけたので、心配していました」
どうして会いに来たのかと問おうとした信の言葉を、李牧は遮った。
宮廷のこの部屋で療養をしていることを、彼は何処かから知り得たのだろう。
自分の看病に当たってくれていた侍女から、まだ趙の一行が帰還していないことは聞いていたが、まさか李牧自らここにやって来るとは思わなかった。
彼は自分のことをずっと気に掛けて、何処からか見ていたのかもしれない。
それが趙の宰相として敵将を警戒してのことなのか、それとも本当に自分を心配してのことなのか、信には分からなかった。
「突然すみません。もう明日には発たないといけないので」
少し寝ぐせが残っている黒髪を撫でられて、信は咄嗟に俯いた。
隣に腰を下ろした李牧が穏やかな眼差しを向けていたことには気付いていたが、信は決して目を合わせようとしない。
少しでも目を合わせれば、何故だと問い詰めてしまいそうだった。
「…驚きましたか?趙の宰相として現れたこと」
信の考えを察したのか、李牧が苦笑しながら問い掛けた。
「………」
その問いを肯定し、怒鳴ったところで李牧の立場は変わらない。膝の上で静かに拳を作った途端、李牧の手がそれを押さえつけた。
「また傷を作るつもりですか」
「っ…」
先日まで包帯が巻かれていた右手を開かせる。
もう傷はほとんど塞がっていたが、まだ痕が残っているそこに、あの時と同じように唇を落とされた。
「あ…」
唇の柔らかい感触に、信の背筋が甘く痺れた。
目を合わせるまいと俯いていたのに、反射的に顔を上げてしまい、李牧の双眸と視線が絡み合う。
すぐに顔ごと視線を逸らそうとしたのだが、顎を捉えられて、視線を逸らすのを阻まれた。
何を言う訳でもなく、李牧は信のことを見つめている。
「ッ、やめろ…!」
まるで蜘蛛の糸のように粘っこく視線を絡められ、耐え切れなくなった信は両腕を突っ撥ねて李牧の体を突き飛ばした。
全身の血液が顔に集まったのではないかと思うほど顔が赤くなっていることを自覚していたが、からかわれたくなかったので、態度だけは冷静を装う。
「ハッ、立ち振る舞いや言葉遣いのせいで、別人みたいになっちまったな。久しぶりに会ったのに、誰か分からなかったぜ」
皮肉っぽく言ってみるものの、李牧は眉一つ寄せることをしない。
この男に挑発の類は無意味だと知っているものの、わざとらしく信は溜息を吐いた。
「…見舞いじゃなくて、別の用があって来たんだろ。さっさと言えよ」
意外そうに李牧が目を丸めた。
「見舞いという理由で会いに来てはいけませんでしたか?」
趙の宰相ともあろう立場の男が護衛もつけず、家臣たちも連れずにわざわざ一人で会いに来たのだ。誰にも聞かれたくない用件があるのだろう。
「御託はいいから、さっさと言えよ」
睨みつけながら催促すると、穏やかに笑んでいた李牧の顔から表情が消える。
「信、俺と共に趙へ来い」
一人称も口調も、目つきも雰囲気も別人のように変わり、信は目を見開いた。
今目の前にいるのは、趙の宰相ではなく、信がよく知っている李牧そのものだった。
選択
「……、……」
動揺のあまり、声を喉に詰まらせてしまう。心臓が激しく脈を打ち始めた。
趙の宰相と軍師になってからは、趙王だけでなく、多くの高官や将達と関わる機会が増えたのだろう。兵や民からの支持にも影響するため、親しみやすい雰囲気を繕ったのだと思っていた。
もしかしたら、過去の自分を全て壊して、今の人格を作り上げたのかもしれないとも考えていたのが、そうではなかった。
信が愛していた李牧は今でも存在している。いや、何も変わっていなかった。
自分のもとを去った後、趙の宰相という立場にまで上り詰めたのは、何か考えがあってのことなのだと、信はすぐに理解した。
だが、秦将である自分が趙に行くということは、つまり、この国を裏切るということだ。
「俺…は…」
俯いてしまいそうになるのを、顎を掴まれて再び阻まれた。
「秦国はいずれ滅びる。そうなる前に、趙に来るんだ」
秦国が滅ぶ未来を断言したことに、信は思わず寝台から立ち上がった。炎のような激しい怒りが腹の内を突き上げる。
「まさか、お前…馬陽で父さんを討ったのも…」
怒りで声が震え、全身を戦慄かせた。
睨みつけても、李牧は少しも臆することなく平然と答える。
「王騎の死は始まりに過ぎない」
全身の血が逆流するようなおぞましい感覚に、怒りで燃えていた信は水を被せられたように押し黙った。
「秦国を滅ぼすのは他でもない、この俺だ」
追い打ちを掛けるように告げられた言葉に、視界がぐるぐると回りだし、自分が立っているのか座り込んでしまったのかさえ分からなくなる。
「馬陽では、王騎の死が目的だった。初めから全て俺の策通りに進んでいたというのに、そのことに気づいた者は、秦国には誰一人として居なかっただろう」
座ったままでいる李牧の手が伸びて来て、信の手首をそっと掴んだ。
その手は以前と変わらず温かいはずなのに、触れられた場所から凍り付いていくような錯覚を覚える。
「もし、あの戦にお前がいなければ、秦軍の全てを壊滅させる手筈も整えていた」
予想もしていなかった事実を知らされて、信は束の間、呼吸することを忘れていた。
李牧が持つ戦の才は、嫌というほど知っている。戦況を手の平で弄ぶような発言が、決して冗談ではないことも信は理解していた。
だからこそ、背筋が凍り付くほど恐ろしくて堪らない。
李牧が本気でこの国を滅ぼす手立てを練っていて、もしかしたら馬陽で王騎を討ち取った後から今も、彼の策通りに進んでいるのではないかと不安に駆られた。
此度の同盟も彼の策だとしたら。そう考えるだけで肺が凍り付いてしまいそうだった。
「は…はぁッ、ぁッ…はあ、ッ」
胸が締め付けられるように苦しくなって喘ぐように呼吸を再開すると、まるで慈しむかのように、李牧は優しく笑んだ。
寝台に座り込んでしまった信の頬を両手で包み、無理やり目線を合わせると、李牧がゆっくりと口を開く。
「俺は本気だぞ」
「っ…」
李牧の双眸に、凍り付いた自分の顔が映り込んでいた。
共に過ごしていた日々では、時々冗談を言って自分を笑わせてくれたこともあったし、彼の聡明な思考にはいつも何かを学ぶことが多かった。
しかし、今の李牧は一切嘘を吐いていない。双眸に宿る強い意志を見て、すぐに分かった。
脅迫とも取れるその言葉を聞き、李牧が本気で秦国を滅ぼす意志を固めたのだと悟る。
「信、俺と趙に来るんだ」
無理だ。この国を裏切ることは出来ない。
この国には自分の大切な仲間たちが生きている。たくさんの思い出が詰まっている。それを斬り捨てるような真似なんて出来ない。
これからも自分が秦将であり続けることは、最後まで秦国に忠誠を誓っていた養父に対しての誓いだとも思っていた。
もしも相手が李牧でなかったのなら、刃の切先を向けて罵倒していたに違いない。同盟さえ成立していなければ、その首を掻き切って王騎の墓前に供えていただろう。
「………」
唇を噛み締めて、信は力なく首を横に振った。秦国を裏切ることは出来ないという精一杯の意志表示だった。
「…信」
信が誘いを拒絶することを李牧は知っていたようで、その表情が崩れることは少しもなかった。
「あ…」
李牧の両腕が信の背中に回される。
青い着物に顔を埋める形になると、抱き締められる温もりと懐かしさを感じて、目頭に熱いものが込み上げた。
「ッ…」
無意識のうちに、李牧の背中に腕を回しそうになった自分の手を制し、信は李牧の体を突き放そうとした。
しかしそれよりも早く、李牧の腕が信の体を抱き押さえる。
「お前の将としての誇りも、王騎の意志も、俺が全て受け継ぐ。だから、お前はもう戦に出るな」
「……、……」
その言葉の意味を問い質すことは出来ず、信は唇を戦慄かせることしか出来ない。
腕の中から李牧を見上げると、信がよく知っている李牧の顔がそこにあった。
「趙で俺に嫁ぎ、子を育めばいい。母国を裏切ったと後ろ指をさすような連中など、俺が全て黙らせてやる」
「っ…」
返事を聞くつもりはないのか、李牧は信の体を抱き締めたまま放そうとしない。
それはまるでお前に拒否権はないと言われているようだった。
記憶にある李牧はこんなにも強引なことはしなかったのに、彼が自分のもとを去ってから、一体何があったのだろう。外見は李牧であるはずなのに、中味だけが別人になってしまったかのようだった。
いや、もしかしたらこれが李牧の本性なのかもしれない。自分が知らなかっただけで、ずっと李牧は自分を騙していたのだ。
その真実に、信の胸は引き裂かれるように痛んだ。
選択 その二
「…一つ、答えろ」
李牧の着物を弱々しく掴んだ。
「趙に行く前から…俺と、出会った時から、ずっと…俺を、利用してたのか?」
彼の胸に顔を埋めたまま、信は問い掛けた。
この着物の下の肌にはたくさんの傷が刻まれていることも、自分がつけた傷痕があることも、信は鮮明に覚えている。背中に残した掻き傷は、もう消え去っているだろう。
李牧と肌を重ねる度に、彼の肌に刻まれたたくさんの傷痕を指でなぞるのが好きだった。
あの森で倒れていた李牧を助けてから、療養という名目で共に生活し、彼が自分のもとを去るまで、それなりの月日があった。
今でも鮮明に覚えているあの日々は、信にとってはかけがえのないものだというのに、その情さえも李牧は利用していたのだろうか。
答えを知りたいと思う自分がいる一方で、聞きたくないと叫んでいる自分がいるのも事実だった。
「信」
名前を呼ばれても、信は顔を上げられずにいた。
心の何処かでは、李牧が出会った時からずっと自分を利用していたのだと諦めに似た答えを導き出してしまっている。
「信」
もう一度名前を呼ばれ、顎に指を掛けられて顔を持ち上げられると、信は怯えた瞳で李牧を見上げた。
「知っているだろう?俺が卑怯者だと」
「ッ…!」
問いに対する答えになっていないが、やはり自分は利用されていたのだと悟り、信の胸は引き裂かれるように痛んだ。
(桓騎も、同じだったのか…?)
あの時の桓騎も、きっと同じ痛みを感じていたに違いない。
李牧の身代わりとして利用していたつもりは微塵もないのだが、このまま誤解が解けなければ、桓騎はいつまでもこの胸の痛みに耐えなくてはならないのだ。
李牧の手が信の薄い腹を撫でたので、何をするのだと信は瞠目した。
「お前は趙に来て、桓騎の子を産めばいい」
先日の夜、桓騎に犯された時のことが脳裏に蘇り、信はひゅっ、と息を飲む。
「…な、んで…それを…」
掠れた言葉を紡いで問い掛けると、李牧は刃のような凍てついた瞳を向けて来た。
「俺以外の男の子種で実った命だとしても、お前の子であることには変わりない」
青ざめながら、信はその言葉を他人事のように聞いていた。
「…なんで、桓騎だって…」
上擦った声で、どうして桓騎の名前を出したのか問うと、李牧が目を細める。幾度も自分を狂わせたあの妖艶な笑みだった。
網膜に焼き付いているその笑顔に背筋が甘く痺れ出し、信ははっとして拳を強く握って意識を取り戻した。
「あの夜、せっかく見舞いに行ったのに、先に来客がいただろう」
瞬きをすることも忘れて、信は李牧を見つめていた。
あの夜、李牧は見ていたのだ。自分以外の男に犯されている信の姿を。
それを知った上で、李牧は今も信を手放したくないと言っているのだ。
心臓を鷲掴みにされたかのように、信は喘ぐように苦しげな呼吸を繰り返していた。
こんなにも胸が痛むのは、李牧にあの場を見られていたことに対する羞恥心ではない。
李牧が王騎の次に、桓騎を標的にするのではないかという耐え難い不安だった。
「……、……」
この腹に桓騎の子種が実っているかは分からないが、信は自分の腹を守るように両手を当て、怯えた目で李牧を見上げる。
どうやらその反応が気に障ったのか、ここに来て李牧が初めて眉根を寄せた。
「何を迷うことがある。お前はあの男を俺の身代わりとして利用していたんだろう?」
「違うッ!」
李牧の言葉を遮るように、信は叫んだ。否定したのは、ほとんど無意識だった。
どうしてあの時、桓騎にも同じようにすぐ否定してあげられなかったのだろうという後悔が信の胸を締め上げた。
急に大声を出したせいか、こめかみがずきずきと熱く脈動し、顔が赤く上気していく。
「俺は、桓騎を…お前の身代わりだと思ったことなんて、一度もない」
声を振り絞ると、李牧は黙って信の言葉に耳を傾けていた。
「お前が…俺のもとを去っていったあの日に、桓騎と出会った」
あの雨の日のことは、いつでも瞼の裏に浮かび上がる。
悲しそうに微笑む李牧から理由も伝えられず、一方的に別れを告げられて、信は引き留めることも追い掛けることも出来ず、ただ立ち尽くしていた。
彼が濡れないようにと、持っていった簦 も使うことはなかったし、いっそ雨に打たれて、ひどい風邪を引いてそのまま死んでしまえたらなんて安易なことまで考えていた。
「…でも」
桓騎を保護したのは、その帰り道だった。
「あの雨の日じゃなくても、倒れていたのが桓騎じゃなかったとしても、俺は…きっと同じことをしていたし、お前の面影と重ねるなんて、絶対にしない」
もし、桓騎と出会ったのがあの日でなかったとしても、倒れていたのが桓騎でなかったとしても、信は目の前で倒れている人がいたのなら、保護していたに違いなかった。
目の前の人々を救うことは、自分の信念であったし、そこに李牧の存在は関係ない。
李牧と男女の関係を築いていたのは確かな事実だが、だからと言って桓騎を李牧の代わりとして見ていたことは一度もなかった。
ただ、彼を戦に出したくなかったのは、本当だ。自分に懐いてくれている桓騎が戦で殺されると思うと、胸が痛む。
しかし、それは桓騎でなくても同じだ。誰かが死ぬのは、自分の前から居なくなるのは悲しいもので、それでも哀悼に優先順位はつけられない。
人の命というものは、平等なのだから。
選択 その三
「…っ」
頬に熱いものが伝い、信は自分が涙を流していることに気が付いた。
泣き顔を見られまいとして、咄嗟に俯いて前髪で顔を隠す。
「信…」
静かに鼻を啜っている信の体を抱き寄せると、李牧はその耳元に唇を寄せた。
「きっと、今以上に辛い想いをさせることになる。これからも秦将として戦場に立ち続けるなら尚更だ」
「………」
奥歯を噛み締めて、信は無意識のうちに拳を作った。爪が手の平に食い込む前に、李牧がそっとその手を包み込む。
「もう無意味な傷を作るな」
李牧の胸に顔を埋めたまま、信は唇を噛み締めた。
しかし、彼について行くとは決して答えない。言葉にせずとも、李牧は信の意志をすでに察しているようだった。
それでも共に来るよう説得を続けるのは、彼女を失いたくないからだ。
信の背中に回している両腕に、自然と力が籠もる。だが、信は両腕を伸ばして彼の体を押し退けた。
今も涙を流し続ける信の黒曜の瞳に、李牧が生唾を飲み込む。
その濡れた瞳に浮かんでいる強い意志が、自分との決別を確立したものだと察し、李牧の胸は針で突かれたように痛んだ。
「…俺は…お前とは、行けない」
信が発した言葉は、情けないほどに震えており、とても聞けたものではなかった。しかし、瞳と同じで揺るがない強い意志が宿っている。
それは将として、一人の女として、信という存在そのものが選んだ道だった。信は最後の瞬間まで、滅亡の運命にも抗うつもりなのだ。
「信、考え直せ。まだ間に合う」
力強く両肩を掴んで、説得を試みる。しかし、何度訊いても信の答えは変わらなかった。
彼女の頑固な性格も、忠義の厚さも、李牧は理解していた。だからこそ、ここで引く訳にはいかなかった。
愛する女が死ぬ姿なんて見たくない。
趙国の宰相に上り詰めたのも、滅びの運命にある国から信を救うためだったのに、彼女を秦から連れ出せないのなら何の意味もない。
もちろん彼女を趙へ連れていく手段など幾らでもある。だが、それでは意味がない。
彼女の意志でこの国を見限らせなければ、趙へ連れて行ったとしても、すぐに秦へと逃げ帰るだろう。そうなれば、今以上に秦国を守ると固執してしまう。
李牧が予想外だったのは、彼女の中で、自分の存在と秦国に対する忠義が逆転していたことだった。
共に過ごしていた時のように、愛する自分に従順であった彼女はもう何処にもいない。
しかし、李牧は今でも信が秦国よりも自分を優先してくれるはずだと自負していた。未だ彼女の心の中に自分という存在が根付いていることと、理由はもう一つあった。
それは信が保護し、今では知将としてその名を広めている桓騎の存在だ。
信は彼を自分の身代わりとして育て、傍に置くことで、自分がいなくなった後の寂しさを埋めているのだと思っていた。
だからこそ、再び彼女と再会したのならば、あの時のように、素直に自分の言うことを聞いてくれると、李牧は疑わなかったのだ。
だが、それは自惚れに過ぎなかったのだと、ここに来てようやく理解した。
彼女はもう、自分の背中を追い掛けるのをやめて、自分が決めた道を歩み出しているのだ。誰かに命じられた訳ではなく、自分自身の意志で。
もう何を言っても信の決意が揺るがないと分かった李牧は、諦めたように力なく笑った。
「…そうだな。お前はそういう女だった」
頬を伝う涙を拭ってやり、李牧が呟いた。
「ご、め…」
幼い子供のように泣きじゃくる彼女が、趙には行けないことを謝罪をしようとしたので、李牧はその言葉を唇で塞いだ。
「ん、…ぅ、っん…」
抵抗する素振りはなく、むしろ受け入れるようにして、目を閉じたまま李牧の口づけに応えている。これが最後の口付けになるのだと、信は悟ったようだった。
お互いの体を強く抱き締め合い、何度も唇を交えてから、李牧はまだ頬を伝う涙に舌を這わせる。塩辛い味がして、喉の奥がきゅっと締め付けられるように痛んだ。
「お前が謝罪することは何もない。謝るのは俺の方だ」
「…っ、……」
しゃっくりを上げながら、信が李牧を見つめている。
少しも泣き止む気配のない信に、幼い頃から相変わらず泣き虫な女だと思いながら、李牧は穏やかな瞳を向けた。
どれだけその双眸を涙で濡らしていても、その奥にある意志は決して揺るがない。その意志の強さに惹かれたことを、李牧は思い出した。
同時に、彼女を泣き止ませるのは、もう自分の役目ではないのだと思い知らされる。
信が自分に背を向けて歩み出しているのならば、自分も前に進まなくてはならない。
深く息を吸ってから、李牧は意を決したように信を見つめた。
「俺たちが次に会う時は戦場で、俺は趙の宰相、そしてお前は秦の将だ」
まさかまた彼女に決別の言葉を告げることになるとは思わなかった。
信は涙を流しているものの、引き止めるような言葉は言わない。しばらく沈黙した後、彼女の手が、ずっと掴んでいた李牧の着物をようやく放した。
自分と離れる覚悟が出来たのだと察し、それを合図に、李牧は躊躇うことなく立ち上がる。
「李牧…」
弱々しい声に名前を呼ばれて、李牧は振り返った。
何を言う訳でもなく、信は眉根を寄せて祈るような表情で李牧のことを見つめている。
本当は行かないでほしいと、自分を引き止めようとするのを必死に堪えているのが分かり、同時に愛おしさが込み上げた。
彼女から別れの言葉を聞かずとも、その顔さえ見られれば、それで十分だった。
「俺は卑怯者だが、嘘は言わない。今でもお前のことを愛しているし、これからもそのつもりだ」
その言葉を聞いた信が両手で顔を覆い、声を上げて再び泣き始めた。
瞼の裏に、いつも自分の胸に顔を埋めて、声を上げて泣いていた彼女の姿が浮かんだ。しかし、もうその肩を抱いてやることも、慰める言葉を掛けることは出来ない。
信の泣き声を聞きながら、李牧は振り返ることなく、部屋を出ていく。
部屋を出てからも、李牧は、一度も後ろを振り返らなかった。