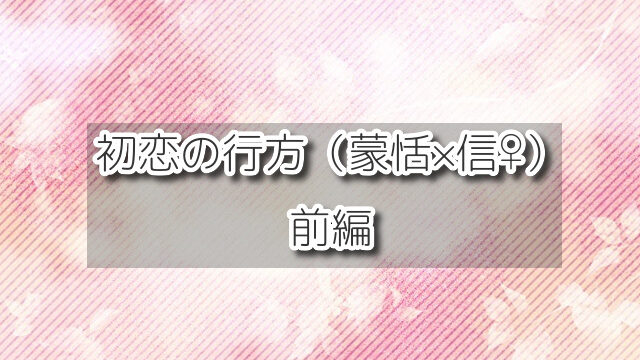- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 蒙恬×信/王賁×信/ヤンデレ/執着攻め/バッドエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
歪な関係
蒙恬と関係を持ってから、信は今まで以上に口数が少なくなっていた。
仲間たちの前では何ともないと気丈に振る舞って見せていたが、いつも目元を腫らしている彼女を不審に思わない仲間はいなかった。
何かあったのかと尋ねても彼女は何でもないと無理に笑うばかりで、決して答えようとしない。
蒙恬に自分たちの関係を口止めされたことはなかったし、脅された訳でもなかった。それは王賁も同じである。
他者に告げたところで、この状況に終わりはないことを信は分かっていた。二人もそれを知っていたからこそ、口止めなど不要なことをしなかったのだろう。
きっと蒙恬も王賁も、信が誰にも打ち明けないことを察していたに違いない。
信は蒙恬の言うことを何でも聞く、そして蒙恬は桓騎に同士討ちの件を黙らせておくという取引は今でも続いていた。
特に蒙恬には、飛信隊という人質があり、改めて言葉にすることはないが、その沈黙の脅迫は着実に信の心を蝕んでいた。
仲間たちの命を守るためには自分が耐えるしかない。
自分が桓騎軍の兵と娼婦を斬り捨てたことが糸口となったことであり、これは他の誰でもない自分の責任である。
同士討ちの件を、蒙恬を通して桓騎に黙らせておくのは、決して保身のためではなかった。もしも自分の首だけで済む話ならば、信は潔く命を差し出しただろう。
しかし、五千人将の地位に就いている信の同士討ちの罪は重い。
もしもこの事実が明るみに出て軍法会議に掛けられれば、間違いなく連帯責任として全員が処刑されてしまうだろう。それだけは何としても避けたかった。
信が決して声を上げず、歯を食い縛って蒙恬との取引を続けるのは、仲間たちのことを思ってのことだった。
終わりのない取引に、信の精神は着実に蝕まれていく。
(これは、罰なんだろうな)
背後から蒙恬に身体を揺さぶられながら、信は考えていた。
彼の男根が突き上げている、その先に眠っていたはずの尊い命。抱き上げることはおろか、顔も見ることも叶わなかった小さな命を想い、信は涙を流した。
「っ、ぅ…ふ、…」
情けない嗚咽を零しそうになった口に手で蓋をする。昔からずっと、声を上げて泣くことが苦手だった。
まだ王騎と出会う前、下僕である自分が泣くことで、自分を買い取った男からうるさいと怒鳴られ、鞭で叩かれた苦痛の記憶が刻まれているからだ。
容赦なく肌を打つ鞭の痛みに、自分には帰る場所などないのだと思い知らされた。
親の顔も知らない自分の生き場所はここしかないのだと、そのやり場のない虚しさを紛らわすために、ひたすら木剣を振るっていた。
手の平のマメが潰れ、血で真っ赤に染まっても、痛みというものを一切感じなかったのだ。
その後、剣の腕を見込まれ、信を養子として引き取りたいと王騎が申し出た時、男は人が変わったように自分を差し出した。
今までさんざん自分を甚振っていたはずの男の豹変ぶりを見て、信は悟った。
自分にも、力と名声があれば、もう酷い目に遭うことはないのだと。
「っ、ぅ、んんッ…!」
行為から気を逸らすのは許さないとばかりに、項に噛みつかれ、信の身体がびくりと震えた。
肉を穿つ打擲音と蒙恬の荒い吐息を聞き、まるで終わりなき地獄にいるようだと錯覚する。敷布を力強く掴みながら、信はなんとか意識を繋ぎ止めていた。
「…王賁がつけた痕、すっかり消えちゃったね」
たった今つけたばかりの噛み痕に舌を這わせた後、蒙恬が囁いた。
自分で見ることは叶わなかったのだが、蒙恬の屋敷で療養をしていた頃、信の体には王賁につけられた情事の痕があったのだという。
情事の際、体に痕をつけられたことは、これまでも何度かあった。
もちろん愛の言葉を囁かれるなんてことは一度もなかったが、王賁と身を交えた証が確かにこの身に刻まれたような気がして、信はいつもその痣を眺めては溜息を吐いていた。
がむらしゃらに快楽に身を委ね、女として生まれた喜びを得られていたのなら、少しは苦痛も紛れたのかもしれない。
何も考えずに快楽を追い求めれば、もっと楽になれただろう。
しかし、それを許さないのは、他ならぬ信の理性だった。仲間たちの命が天秤に掛けられている限り、永遠に楽にはなれないだろう。
「はあッ…あ…イく…ッ」
「ッ…!」
耳元に蒙恬の熱い吐息を掛けられ、信は身を強張らせた。
それまで腹の内側を抉っていた男根が引き抜かれ、内腿に白い子種が迸る。
中に射精されなくて良かったと胸を撫で下ろすのは、これで何度目だろうか。
「……、……」
絶頂の余韻に息を整えている蒙恬が後ろから体を抱き締めて来たので、信はようやく終わったのかと長い息を吐いた。
「んぅ」
顔を覗き込まれたかと思うと、そっと唇を重ねられ、信は戸惑った。
王賁と身を繋げた時もそうだが、妻でも恋人でもない女と口づけをするのは、体に痕をつけるのと同じで、行為の延長なのだろうか。
「ふ、ぅ…」
ぬるりとした舌が入り込んできて、信は蒙恬に教えられたように舌を絡ませた。
唇と舌を交えながら蒙恬が笑った気配を感じ、機嫌を損ねていないことに安堵する。
名家の嫡男だというのに、蒙恬も王賁もなぜ自分にこのような行為を強いるのか、信には理由が分からなかった。
彼らの立場を考えれば、喜んで足を開く女はごまんといるだろうに、どうして自分でなければならないのだろう。
貴族の娘を相手にするのと自分を相手にするのとでは随分と事情が違う。
きっと何にも気遣わず、好きに扱える都合の良い道具として見ているのだろう。
早く飽きて見放してくれれば良いのにと思う。
だが、もしもそうなれば、同士討ちの件を黙ってくれている蒙恬が次に何の欲求をして来るのかが分からず、信はそれが恐ろしかった。
歪な関係 その二
「もう帰るんだ?」
着物の袖に腕を通している信に、寝台に横たわったままでいる蒙恬がつまらなさそうに声を掛けた。
帯を締めながら、信は振り返ることなく頷く。
あの日から頻繁に呼び出されては体を交えるようになっており、先ほどまで蒙恬の男根が埋まっていた其処に、疼くような、擦れるような言葉にし難い痛みが続いていた。帰路で馬に跨るのが憂鬱だった。
ゆっくりと起き上がった蒙恬が、口元に手を当てて何かを考えている。
「じゃあ、次はさ」
「…王家の集まりがある」
次に会う日取りを告げようとした蒙恬の言葉を、信は低い声で遮った。
今日まで呼び出しを断ることがなかった信が初めて断ったので、蒙恬は驚いたように目を丸めていた。
ふうん、と返事はするものの、それ以上は何も言われない。蒙恬も嫡男として、そういった集まりの重要さは理解しているのだろう。
私用であったのなら蒙恬の呼び出しを優先していたのだが、王家の集まりとなれば、自分の都合ではどうにもならない。
少しでも蒙恬と離れられる時間があることに、信は表情に出さず安堵していた。
「王賁に会うんだ?」
蒙恬の口からその名を聞くのは珍しいことではなかった。
気が合うようには見えないが、名家の嫡男同士の付き合いがあるのだろう、蒙恬は昔から王賁のことを知っていた。信が王騎の養子として王一族の一員となり、王賁が出会うよりも前から二人は面識があったのだろう。
養父である王騎は、王一族の中では分家の人間にあたる。天下の大将軍として中華全土に名を轟かせていた養父ではあるが、本家当主の座とは離れていた。
そのせいか、信が蒙恬と初めて出会ったのは、お互いに三百人将の地位に立っていた頃だった。
軍師学校を首席で卒業しただけでなく、戦での功績は噂で聞いており、初めて会った時、まさかこんな優男が蒙武将軍の息子なのかと大層驚いたものだ。
(…あの頃は、今よりマシだったな)
父の背中をひたすら追い求めていたあの頃は、今のように雁字搦めな状況ではなく、いくらでも羽ばたけた。
まだ王騎が生きていた頃、王賁から嫌味は言われるものの、少なくとも今よりはまともな扱いを受けていた。三人で戦での功績を競い合っていたあの日々も、今となっては懐かしい思い出だ。
信が女であることを王賁は出会った時から知っていたし、初陣から性別を偽るようになっていたことにも彼は何も言わなかった。
そもそも興味がなかったのだろうが、その無言の気遣いが当時の信には嬉しかった。
「信」
束の間、昔の王賁に思いを馳せていると、蒙恬から名前を呼ばれ、信は弾かれたように顔を上げる。
振り返ると、蒙恬がじっとこちらを見つめていた。暗く淀んだ瞳と目が合うと、信はそれだけで動けなくなってしまう。
何を言われるのかと固唾を飲んでいると、蒙恬がゆっくりと口角をつり上げた。
「…信はさ、俺のものになったんだよね?」
その問いには、一体どんな意味が込められていたのだろう。
考えるよりも先に、信は頷いて、蒙恬の言葉を肯定していた。彼の機嫌を損ねないために。
安堵したように、蒙恬は優しく笑んだ。
「うん、分かってるならいいよ。気をつけて帰ってね」
「………」
穏やかな声色を掛けられ、信は無意識のうちに安堵の息を吐いていた。今日も仲間たちの命を守ることが出来たようだ。
再会
王一族の集まりというのは、いわば論功行賞のようなものである。
褒美こそ出ないが、名家と称される自分たち一族に、相応しい貢献出来ているかを評価されるのだ。
本家の屋敷で行われるこの集まりは昔から続いており、養父である王騎はよく名を呼ばれてその功労を称えられていた。
分家の出であるものの、誰よりも中華に名を轟かせていた養父が誇らしくもあったし、その広い背中はいつまでも信の目に焼き付いている。
信も飛信隊の将としての活躍を称えられることはあったものの、下賤の出である彼女の功労を称えるのは形ばかりで、一族の者たちから冷たい視線を向けられていることには昔から勘付いていた。
養子として引き取られることが決まった時も、王一族の間では随分な騒ぎになったらしい。しかし、王騎の多大なる功績が認められていたからこそ、下賤の出である信は、異例として彼の養子となることが認められた。
名家の一員に下賤の出である彼女が加わることを快く思っていない者は未だ多くいる。
だからこそ、養父である王騎が馬陽で討たれた時、信はそれを理由に王一族を追放されるのだとばかり思っていた。
しかし、王騎の遺言が記されている木簡が屋敷で見つかったことで、追放は免れた。王騎はいつか自分が戦場で命を失い、自分と言う後ろ盾がなくなった娘のことをずっと案じていたのである。
王騎が亡くなったことで、すぐに追放されるはずだった信が、今でも王一族にいられるのはその遺言による効力のおかげだ。
しかし、隠蔽されている同士討ちの件が広まれば、すぐに信は王一族から追放となるだろう。
最期まで自分を案じてくれていた養父には申し訳ないが、彼が龐煖に討たれた時、いっそ王一族から追放された方が良かったかもしれないと思うことがあった。
そうなれば、幼馴染であり、良き好敵手でもあった王賁との上下関係を意識することもなかっただろう。
王騎が生きていた頃は、下賤の出であることに対して嫌味は多かったものの、今よりも人として接してくれていた。
あの時の優しい王賁を、信はいつまでも心待ちにしている。
この苦痛さえ耐え凌げば、いつかはあの時の優しい王賁に戻ってくれると、疑うことなく信じていた。
夕刻に祝宴が始まった。王一族の者たちがこうして一つの場に集まることは滅多になく、それを理由に毎度宴が開かれるのだ。
信の席も相変わらず端の方に用意されていたが、とても宴に出る気にはなれなかった。
ここ最近は蒙恬から呼び出される度に身体を暴かれているので、その顔には濃い疲労の色が滲んでいた。
(集まりには顔を出したんだら、もう十分だろ)
何も言わずに、愛馬を預けている厩舎へ向かおうと踵を返す。
宴に出ないで帰ることに断りを入れずとも、誰も信のことを気にしていないようだった。
王騎が生きていた頃は、王賁と酒を飲み交わして互いの功績を讃え合い、朝までどちらが先に天下の大将軍の座につくか酒を飲み交わしながら語り合っていたのだが、もうそんなことはなくなってしまった。
先に将軍の座に就いたのは王賁と蒙恬であって、信は今でも五千人将の座に就いたままである。大きく開いてしまったこの差は、もう永遠に埋められぬような気がしてならなかった。
「………」
廊下では、一族の者たちをもてなすために従者たちが慌ただしく動き回っている。
突然の来客があった話をしており、その対応に追われ、ますます忙しさが増しているようだった。
宴の間から聞こえる談笑に後ろ髪を引かれることもなく、信は屋敷を出ようと入り口を目指していた。
「っ…?」
不意に後ろから腕を掴まれ、驚いて振り返る。王賁だった。
蒙恬に逆らえない関係が始まってから、そういえば王賁とは一度も会っていなかった。
最後に会ったのは、楚の防衛戦に成功した帰路だ。桓騎軍の兵と娼婦を斬り捨てる前、呼び出された天幕で彼と身を繋げていたことは、朧げではあるが覚えていた。
「お…」
名前を呼ぼうとして、信は慌てて口を噤む。
以前ならば気さくに名を呼んでいたが、今ではもう許されない。
用があって引き留めたのだろうが、声を掛けることはおろか、目を合わせたら生意気だと頬を打たれるのではないかと怯えてしまい、信は俯いたまま顔を上げられずにいた。
青ざめたまま動かない信に、王賁は一向に表情を変えることはないが、いつものように向けられる鋭い眼差しは、どこか怒っているようにも感じる。
王家の嫡男であり、此度も名前を呼ばれて功績を讃えられていたというのに、宴に出なくても良いのだろうか。
捕まれた腕を放される気配がなく、信は戸惑ったように狼狽えた。
「あっ…」
何も言わずに王賁に腕を引っ張られたので、信は大人しく彼の後ろをついていく。自らの意志でその腕を振り解くことは出来なかった。
廊下を進むにつれて、この先に王賁の私室があるのだと思い出し、心臓が激しく脈打ち始める。
もう嫌だと心が悲鳴を上げるものの、それを言葉にすることは許されない。
「うっ…」
部屋に入るなり、信は寝台にその身を投げ出される。上質な寝具で統一されている高価な寝台がぎしりと軋んだ。
驚いて起き上がろうとするが、それよりも早く王賁が信の身体を組み敷いた。
「なにして…」
顔色を見れば、王賁が酒に酔っていないことは明らかだった。宴の間では一族が集まっているというのに、何を考えているのだと驚いた。
「お、王賁、さまっ…!」
帯を解こうと伸ばされた手を掴み、信が教え込まれた呼び方で制止を求める。
王騎が討たれてから、王賁は信にこれまで通りの態度を許さなくなった。
以前は名前を呼び捨てていたのに、立場を弁えなければ容赦なく頬を打たれるようになって、信は王賁より下の立場であることをその身にとことん教え込まれたのである。
腕を跳ね除けられ、呆気なく帯を解かれる。
強引に襟合わせを開かれると、先日の情事で蒙恬につけられた赤い痣の残る肌が露わになった。
それが自分がつけたものではないとすぐに気づいた王賁が右手を振り上げる。信は両手で顔を守るよりも先に、反射的に目を瞑っていた。
「うッ…!」
乾いた音が鼓膜を揺すり、左頬に激しい痛みが走る。
「ち、ちが、う…」
まだ何も問われていないというのに、信は否定する。熱を帯びて、痺れるような痛みがする左頬に手をやりながら、信は何度も違うと首を横に振った。
自分が望んだことではないのだと、王賁には分かって欲しかった。
しかし、仲間たちのためにも、同士討ちの件を告げることも、蒙恬が関わっていることを告げることも許されない。
真実を隠し通さねばならないという気持ちと、王賁にだけは誤解されたくないという想いが鬩ぎ合う。
「違う、ちが、う…」
彼の子を身籠ったと分かった時も、これで何かが変わるかもしれないと、また以前のように自分と接してくれるかもしれないと信じていた。
生まれる前の尊い命は戦の侵襲と負担が原因で失われてしまったのだが、それでも信が今でも王賁のことを信じているのは、彼と共に過ごしたあの日々の思い出が、鮮明に心に刻まれているからであった。
初めて体を暴かれた時の破瓜の痛みも、道具として利用される悲しみも、全ていつか救われると信じていた。
自分さえ耐え凌げば、いつかまたあの時のように優しい王賁に戻ってくれると思っていたのだ。
「い、だッ…!」
首筋に歯を立てられ、血管を食い千切られるかもしれないという恐怖に身を震わせる。
いつかはまたあの温かい日々が戻って来ると信じていた彼女を嘲笑うかのように、痛みによって意識が現実へと引き戻された。
恐怖症
体を震わせるばかりで抵抗しなくなった信のさらしを強引に外しながら、王賁が不機嫌に眉間を寄せた。
「誰の許可を得て、その身を許した」
低い声で問われると、それだけで信の体は強張ってしまう。
「あ、あの、俺…」
王賁以外の男にこの身を差し出したことは既に気づかれている。
それが蒙恬だと素直に打ち明けることで、同士討ちの罪に気付かれないだろうか、今の王賁に同士討ちの件を知られて、上に報告されるのではないかと不安がよぎった。
取引通りに蒙恬は桓騎を口止めしてくれているが、横槍を入れるように、王賁が同士討ちの件を上に報告したのならば、間違いなく軍法会議が行われるだろう。
「ぁうッ」
狼狽えていると、今後は右の頬に痛みが走った。容赦なく頬を打たれ、痺れるような痛みの余韻に涙が滲む。
「答えろ」
鋭い瞳に見下ろされ、信は息を詰まらせた。
「……っ…」
唇を戦慄かせ、自分を抱いた男の名を口に出し掛けた寸前、信の瞼の裏に仲間たちの姿が浮かぶ。
(だめだ)
自分の保身のためじゃない。大切な仲間たちの命を守るために、信は沈黙を貫いた。
いつものように奥歯を強く噛み締め、溢れ出そうになる涙と声を堪える。せめてもの意志表示に、瞼を下ろし、強く拳を握り締めた。
「貴様…」
王賁の視線がますます鋭くなる。
歯を食い縛りながら、次なる痛みに堪えていたが、着物を脱がされていく感触があった。
「あっ…!?」
あっと言う間に下袴を奪われ、剥き出しになった下肢がひやりとした空気に触れる。
驚いて閉じていた目を見開くと、今まで見たことのない王賁の表情がそこにあった。
憤怒だけではなく、まるで親とはぐれた迷子のような不安の色と、耐え難い痛みを堪えているような、複雑な色が混ざり合った表情。
その表情を見て、王賁が何を自分に思ったのか、信には何も分からなかった。
「ん、っ…!」
いきなり唇を重ねられ、信は瞠目する。
体を重ねている最中に口づけられることは何度かあったが、まだ挿れてもいないのに口づけられたのは初めてのことだった。
「ふ…ぅ、ッん」
唇を交えながら、王賁の手が信の内腿をするりと撫で上げる。
足の間に辿り着き、まだ乾いたままである淫華に触れられたかと思うと、花弁の合わせ目を指がなぞられ、信は思わず体を跳ねさせた。
「は、ぁ…」
破瓜を捧げた男に愛撫されているのだと思うと、それだけで熱い吐息が零れた。
いけないと頭では分かっているのだが、繊細な箇所を擦られる甘い刺激につい膝を擦り合わせてしまう。
「っ…あう、ぅ…」
王賁の唇が首筋を伝った感触に、信は小さな声を上げた。
淫華から卑猥な水音が立つ。僅かな刺激だけだというのに、蜜が滲み始めて来たことに、信は浅ましい自分の体に嫌悪感を抱いた。
「あ、ッ…はぁ…」
滑りを利用して、中に指が入り込んで来る。
初めて王賁の男根を咥え込んだ時は、あまりの激痛に泣き喚いていたというのに、今では男の味を覚えてしまった。
女として生まれた喜びを知った浅ましい体が、快楽に全てを委ね、何もかも忘れてしまえと甘い言葉を囁いて来る。
何の感情かもわからない涙で視界がぼやけてしまう。このまま何も分からなくなってしまえたらと、どれだけ願ったことだろう。
「…、……」
体の力を抜いて、信はゆっくりと目を閉じた。
いつも通り、王賁の機嫌を損ねないように声を堪えれば良い。蒙恬はやたらと声を上げさせたがるのだが、王賁は違う。泣き声がうるさいと、何度も頬を打たれたことを信は覚えていた。
「…っ…ふ、ぅ…」
瞼を閉じたことによって広がった暗闇の世界で、王賁の吐息だけが聞こえていた。
膝裏を大きく持ち上げられ、指が差し込まれていた場所に、熱くて硬い男根の先端が押し当てられる。
「んんんうッ」
狭い其処を押し広げるように男根が入り込んで来て、信がくぐもった声を上げた。一番深いところまで入り込んで来て、圧迫感に息が苦しくなる。
互いの性器が馴染んでから、王賁が腰を動かし始めたので、敷布を強く握り締め、信は歯を食い縛った。
腹の内を抉られて、揺すられて、満足するまでそれを続けられるだけだ。すぐに終わる。今までだって耐えて来れたのだから今回だってきっと耐えられる。だから大丈夫だと、信は何度も言い聞かせた。
瞬間。部屋の扉が開かれた音がして、
「…信、俺との約束破ったの?」
聞き覚えのある声に、信が思わず閉ざしていた瞼を持ち上げた。
視線の先に蒙恬が立っていて、信は心臓を鷲掴みにされたような感覚に陥った。どうしてここに彼がいるのだろう。
息を詰まらせて体を強張らせていると、束の間、王賁が止めていた腰を動かし始める。
「あぁっ…!?」
腹の内側を抉られる感触に、思わず声を上げてしまう。
慌てて口に手で蓋をするものの、すでに蒙恬の表情には苛立ちの色が宿っていた。
後ろ手に扉を閉めた蒙恬が口元だけ笑みを携えながら、寝台に近付いて来る。
王賁といえば、蒙恬がなぜここにいるのか興味さえないのか、構わずに腰を揺すり続けていた。
「あっ、ま、まって、ぇ」
制止を求めて王賁の腕を掴もうとするのだが、体に上手く力が入らない。
まさか蒙恬がここに現れるとは思ってもみなかったし、今まさに王賁と身を交えている今の状況で、彼が機嫌を損ねないはずがなかった。
この状況でも情事を続けている二人に、蒙恬の頬がひくりと引き攣った。
「ねえ、信」
低い声で蒙恬に名を呼ばれると、信の背筋に冷たいものが走った。
「ッ…」
暗く淀んだ彼の瞳と目が合ってしまい、まるで術にでも掛けられたかのように動けなくなってしまう。
「取引の内容、忘れた?」
ひゅ、と笛を吹き間違った音が唇から洩れた。
彼が取引の話を持ち出す時は、決まって機嫌が悪い時である。仲間たちの命をちらつかせているのも、単なる脅迫ではなく、本気だということを信は理解していた。
「うッ、んんッ」
怯えた瞳を蒙恬に向けていると、王賁に腰を掴まれて深く男根を叩きつけられる。あまりの激しさに体を仰け反らせた。
そんな信を見て、蒙恬の表情がますます濁っていく。口元に浮かべていた形だけの笑みも崩れていた。
王賁はまるで蒙恬のことなどそこに居ないかのように扱っている。しかし、信を抱いた男が蒙恬であると気づいたようだった。
自分の上でどんどん息が荒くなっている彼と、こちらを睨みつけている蒙恬に視線を交互に向けながら、信は狼狽えることしか出来ない。
王賁が腰を動かす度に、繋がっている部分から卑猥な水音が立つ。熱くて硬い男根が何度も中を突き上げていく感覚に、信の内腿が震え始めた。
これ以上、蒙恬の機嫌を損ねるわけにはいかないと頭では理解しているのに、信は抗う術を持たない弱者だった。
力と名声があれば、もう酷い目に遭うことはないのだと、王騎の養子となったあの日に悟ったというのに、信は弱いままだった。
荒い息を吐きながら、王賁が身体を抱き締めて来たので、信は顔から血の気を引かせる。
彼が絶頂に上り詰める時は、まるで快楽に意識を持っていかれぬよう、縋るものを探すかのように身体を抱き締めて来るのだ。
まさかと思い、力の入らない腕を突っぱねるが、それはろくな抵抗にならない。
「や、…いやッ…!」
瞼の裏に、生まれる前に消え去ってしまった幼い命に懺悔する自分の姿が浮かび上がる。
王賁の子を孕んでも、その命が消え去っても、彼は何も変わらなかった。
本当は気づいていたのだ。王賁にとって自分は道具であり、自分がどうなろうと、何も変わらない。
昔の王賁はもうどこにもいないのだと、自分は彼にとって単なる道具にしか過ぎず、それはこれからも永遠に変わらないことを。
「あッ、やだッ、やだあぁッ」
幼子のように泣き喚き、信は首を振った。腹の奥に熱いものが迸る感覚に、涙が止まらなくなる。
自分がこれからも地獄の中で生き続けることを認めたくなくて、信は声を上げて泣いた。
「え、うそ、中に出したの?最悪」
歯を食い縛って腰を震わせ、信の最奥で射精をしている王賁の姿に、蒙恬が頬を引き攣らせた。
恐怖症 その二
泣きながら顔をぐちゃぐちゃに歪めている信の前髪を掴み、蒙恬がその顔を覗き込んだ。
「あーあ、可哀相。信、泣いちゃってるじゃん」
わざわざ近距離で顔を覗かなくても分かることを、蒙恬はあえて言葉に出した。
「ぃ、たい…」
前髪を掴んでいる手には容赦なく力が込められていて、頭皮が引き攣る痛みに信は顔をしかめる。
「こんな風に泣かされないように、俺を選んでくれたんだと思ってたのに。また嘘吐かれちゃった」
肩を竦めながらそう話す蒙恬だったが、なぜかその口元には笑みが戻って来ている。
涙で歪む視界の中でも、信はそれを察して嫌な予感を覚えた。
「も、蒙恬…ご、ごめ…」
要求されなくても、百回でも千回でも、喉が裂けても、蒙恬の気の済むまで謝罪するつもりだった。
取引に応じなかったことで、隠蔽されている同士討ちの件が明るみに出て、仲間たちの首が飛ぶことだけはなんとしても避けねばならない。
「なに?今さら謝罪も言い訳も聞きたくないんだけど」
しかし、蒙恬の怒りは完全に鎮火出来ないほど広がってしまっているらしい。声色だけでそれが分かった。
「賁、いつまで挿れてるのさ。さっさと退いてよ。俺、信にお仕置きしなきゃならなくなったんだから」
信の言葉を聞こうとせず、蒙恬が王賁に目を向けた。ふん、とつまらなさそうに王賁が鼻を鳴らす。
「ぅうう」
深く埋まっていた楔が引き抜かれる感触に、信は思わず呻き声を上げた。
抜かれた男根の後を追うように、白濁が溢れ出て来るのを感じる。臀部を伝う嫌な感触がして、信は息を飲んだ。
「あ”っ、ぅ…」
早く中に出された精液を掻き出さなくてはと手を動かすのだが、今度は蒙恬から体を組み敷いて来たので、信は顔から血の気を引かせた。まさかという瞳で蒙恬を見上げる。
「久しぶりに王賁と会うっていうから、何となく予想してたけど、本当にその通りだったね」
必要な場所だけ脱ぎ、自分の上で男根を扱く蒙恬の姿に、信が喉を引き攣らせる。
手の中でみるみるうちに硬く上向いていく男根を見るのは初めてではなかったのだが、こんな状況で蒙恬が自分を抱こうとするだなんて信じられなかった。
「ぁッ、いや、だ…!」
泣きながら、信は蒙恬から逃れようと寝台の上で身を捩った。床に足をつけようとした途端、乱暴な手つきで腰を引っ張られる。
「ぅぐッ」
体をうつ伏せにさせられて、蒙恬が情事の際によく取らせる姿勢になると、無遠慮に淫華へ指が差し込まれた。
「あーあ、どろっどろじゃん。随分溜まってたんだね?」
先ほどの王賁の精液を掻き出そうとしているのか、それとも中で馴染ませようとしているのか、鉤状に折り曲げた指を抜き差ししながら蒙恬が苦笑を深めた。
「ひッ…い、いやだ…」
指が引き抜かれて、男根の先端を押し当てられたのが分かると、信は背後にいる蒙恬を突き放そうと腕を突っ撥ねる。
しかし、それを遮るかのように、王賁の手が前髪をぐいと引っ張った。
「んぐっ」
薄く開けていた口元に男根が押し込まれ、目を白黒とさせる。
先ほどまで自分の中に埋まっていたそれを、喫するように命じているのだ。
「ぐ、…ん、うぅ…」
気道を押し上げられ、息苦しさのあまり顔をしかめるが歯を立てることは許されない。身体がそれを覚えていた。
「ふ、ふ…ん、ぅ」
鼻で必死に息を続けながら、頬張った男根に舌を這わせていると、背後で蒙恬が笑った気配がした。
「なにそれ、妬けるんだけど。俺の時は言わないとしてくれないのに」
「お前の使い方が悪いんだろう」
自分を挟みながら頭上で交わされる二人の会話に、まるで自分が二人とって単なる都合の良い道具であることを認めるしかなかった。
双眸から涙を流していると、花弁を押し開いて蒙恬の男根が勢いよく入り込んで来る。
「んんんッ!」
全身を貫いた衝撃に思わず歯を立てそうになり、信は思い切り拳を握った。爪に皮膚が深く食い込み、血が伝う。
ここで抵抗をすれば蒙恬の機嫌を損ねて同士討ちの件が明るみに出てしまうのではないかという恐怖が心を信の縛り上げていた。
同士討ちの件をここで王賁に気付かれる訳にもいかない。二人が満足するまで、自分は道具としての役目を全うしなくてはならないのだと頭では理解しているものの、心は引き裂かれるように痛みを覚える。
(俺、何で…こんなこと、してんだろ)
友人だと思っていた二人に身体を暴かれている状況で、信はどうしてこんなことになってしまったのかと考える。
「ふ、ふぅ、ん、うッ、ぐ…!」
苦しそうな声を上げて口いっぱいに王賁の男根を頬張りながらも、時折後ろにいる蒙恬を振り返り、まるで許しを乞うような瞳を向けて来た。征服感と残虐心を満たしてくれる弱々しい瞳だった。
「んう”ッ」
指の痕が残るほど腰を強く引き寄せると、これ以上ないほど奥を突かれ、くぐもった声を上げた信の身体が仰け反る。
信の腰がこんなにも細いだなんて、信が女だと気づくまでは、今まで考えもしなかった。
男らしい体格を偽装するために、さらしを撒いて胸の膨らみを押さえたり、腰のくびれを隠していたのだから気づかないとしても仕方がなかっただろう。
信が女だと知っている者はほんの一握りだけだ。しかし、よりにもよって王賁が含まれていることに蒙恬は苛立ちを隠せなかった。
ましてや、一度は王賁の子を身籠ったことがあるなんて、許す訳にはいかない。
「う、ぁっ、も、蒙恬っ、やめ、て、くれ」
涙で濡れた瞳で制止を求めるが、蒙恬は無視をして腰を揺すった。
王賁の手が伸びて、信の顎を強引に掴んだかと思いきや、その口を開かせる。
「んぅぅッ」
無理やり男根を咥えさせられて口に蓋をされると、信は振り返って懇願することも制止を呼び掛けることも出来なくなってしまう。
喉奥まで突かれて息が苦しいのだろう、顔を真っ赤にして信が王賁の太腿を軽く叩いた。
しかし、どれだけ苦しくても歯を立てることは絶対にしない。
その仕置きと称して破瓜を破られ、腹に子種を植え付けられた恐怖は今でも根強く信の記憶に残っていた。
「信、叩いたらだめだよ」
子供を注意するような穏やかな口調で、蒙恬は腰を掴んでいた手で信の両腕を後ろから引き寄せて、後ろから激しい律動を始めた。
「~~~ッ!」
咥えた男根を吐き出さないように、王賁の手が強く後頭部を押さえつけられており、信が目を白黒させている。
蒙恬の男根を咥え込んでいる淫華がぎゅうと口を窄ませる。まるで子種を絞り出そうとするその締め付けに、思わず切ない吐息を零した。
「ねえ、信」
呼び掛けながら信の黒髪を後ろから掴んで顔を持ち上げる。
「んうっ、ん、はっ、はあっ、はあ」
それまで王賁の男根で口に蓋をされていた信が苦しげに肩を上下させている。
頭皮が引き攣るような痛みと、後ろから突き上げられる快楽に彼女は顔を歪ませていた。
「俺、すごい傷ついたんだよ?俺のものになるって約束したのに、信が王賁と関係を続けてたこと」
あんな約束を交わしたところで、信が王一族の中では弱い立場のままであり、次期当主である王賁の命令に逆らえないことなど分かっていた。
しかし、抵抗する素振りもなく、王賁に抱かれていたという事実が蒙恬には許せなかった。無様に泣き顔を晒してでも、助けてくれと自分に縋れさえすれば、それで良かったのだ。
それもせず、それどころか、今まで通りに王賁との関係を隠し通そうとするなんて、欲張りな女だと蒙恬は叱責する。
取引の関係が始まってから王賁に抱かれるのは今日が初めてだったのだが、蒙恬がそれを知る由もなかった。
「ごっ…ごめ…ぁぅうッ」
冷え切った刃のような瞳を向けられて、信が怯えたように謝罪を口にしようとしたが、言い切る前に王賁が容赦なく彼女の前髪を掴み上げる。
「所詮は道具だ。こんな物のために、必死になるお前がバカなんだろう」
「なにその言い方。悪いけど、信は俺のお嫁さんになるから、次に手ェ出したら王賁であっても容赦しないよ」
二人に挟まれながら、信は瞠目した。何を言われているのか分からないと言った表情でいるのを見て、王賁が小さく笑う。
「下僕の分際で名家に拾われ、嫁ぎ先も名家とは、見上げた図々しさだな」
信が怯えた瞳で振り返る。目が合うと、蒙恬は軽快に笑った。
「これからは戦に出なくていいし、飛信隊のことも気にしなくて良いから」
その言葉を聞き、信が目を見開いた。
「んんッ、んんぅ、うーっ!」
突き上げられながら、敏感な花芯を指で擦り付けられて、信の目の奥で火花が散った。
恐怖症 その三
内腿をがくがくと震わせながら、目も眩むような快楽に戸惑った信がやめてくれと目で訴えている。その瞳からは堰を切ったように涙が溢れ出していた。
蒙恬は顔に垂れ落ちた自分の髪を手で掻き上げると、信の肩を掴んで、うつ伏せの体を仰向けに倒れさせた。
「けほっ…」
敷布の上に倒れ込んだ信が小さくむせ込みながら、逃げようと身を捩っている。
しかし、蒙恬は容赦なく細腰を掴んで、その体を引き戻した。
「あぅううッ」
正常位の姿勢となり、抜け掛けていた男根を再び奥まで突き挿れた。
「やっぱり、こっちの方が好みだなあ。信の泣き顔もいやらしい所もよく見える」
柔らかい胸を揉みしだきながら、蒙恬があははと笑う。
「ま、って、と、嫁ぐ、なん、て、き、聞いて、ない」
途切れ途切れの言葉を紡いで訴える信に蒙恬は小さく小首を傾げた。
「うん?だって言ってないもん。言ったら逃げただろ?」
口元には相変わらず人の良さそうな笑みを浮かべているものの、瞳は一切笑っておらず、信は蒙恬の冷たい瞳に背筋を凍らせた。
「もう王家には話を通してあるから心配しないで?さっき、二つ返事で了承されたから」
「ッ…!?」
なぜ今日に限って蒙恬が王家の屋敷に来たのか、初めからそのつもりだったのだと分かり、信の瞳が恐怖で大きく揺らいだ。
表情はいつもの蒙恬だが、中味はまるで別人だった。信頼していた友人の姿に似せた別人である。
怯え切っている信の額に口づけた後、蒙恬は自分の男根を咥え込んでいる彼女の薄い腹を擦りながら、
「…次に産まれるのは、俺と王賁のどっちの子だろうね?ま、どのみち俺の子として扱われるんだけどさ」
口元に笑みを携えながら、問い掛けた。
恐怖に凍り付いている信を安心させるように、蒙恬は穏やかな笑みを浮かべた。
「だから、安心して孕んでいいよ」
身を屈めた蒙恬に耳元でそう囁かれ、信の頭の中が一瞬真っ白に染まる。
これまで築き上げて来た将の地位が全て奪われる。父と母の後を追って将軍になる夢も、何もかも全て奪われてしまう。自分以外の人間に、自分の生き場所と死に場所を決められてしまう。
「ま、待って!たの、頼むから…!」
怯えながらも懇願し、信は歯を打ち鳴らしていた。
「黙れ。誰が貴様の発言を許可した」
「お、王賁、さまッ、あ、た、たすけ、んぅっ」
仰向けになった信の傍に身体を滑り込ませ、再び彼女の口に男根を突き挿れる。
くぐもった声を上げながら、信が蒙恬を押し退けようと両手を突っ撥ねた。
「ほら、俺たちこれから夫婦になるんだから、手繋ごうね?」
伸ばされた両手首を引き寄せて指を絡ませると、両手を敷布の上に押さえつけた。優しい声色を掛けながらも、蒙恬は容赦なく腰を前に押し出す。
「ッん、ぅううーッ」
男根の先端に柔らかい肉壁が触れる。子種を求めて子宮が降りてきているのだと分かった。
それほどまでに子種を欲しているのか、まるで搾り取るかのように男根が締め付けられて、蒙恬は堪らず腰を動かし続ける。
「~~~ッ!」
王賁に前髪を引っ張られながら、口淫に集中するよう促されるが、信は二人から逃れようとじたばたと両脚を動かしている。
敷布の上で押さえつけている手に力が込められ、男二人を相手に逃げ出すことも叶わない。
なんとか蒙恬の男根を引き抜こうと身を捩るのだが、信の両足は無意味に宙を蹴るばかりだった。それほどまでに信は無力であった。
「んーッ、んんぅ、ふう、んぁ」
口も手も押さえ込まれた信は大粒の涙を流しながら、唯一自由に動かせる瞳で王賁と蒙恬を交互に見上げている。
助けを求める彼女の無言の行為を二人は嘲笑うばかりで、やめる素振りを少しも見せなかった。
「あ、…もう…イくッ…」
余裕のない表情で息を荒げている蒙恬の言葉を聞きつけて、信が恐怖で目を見開いた。
「やっ、やだッ、や、やあああぁ――ッ!!」
絶叫しながらがむしゃらに暴れて逃れようとする信の体を両腕で抱き押さえ、蒙恬は彼女の最奥へ向けて吐精した。
結合している部分から全身にかけて、快楽が突き抜ける。
「ッ…飲み込め」
「やあぁッ、ん、んんーッ」
王賁も限界だったのか切なげに眉根を寄せると、悲鳴を上げるのに大口を開けていた信の口の中に精を吐き出した。
「…あれ、信?」
それまで静かに啜り泣いていた信の声が途絶えたので、蒙恬は顔を上げて彼女を見た。
汗で張りついた前髪を指で梳いてやると、信は虚ろな瞳で薄口を開けて規則的な呼吸を繰り返していた。
意識を失ったのだと分かり、蒙恬はつまらなさそうに顔を歪めた。
躊躇うことなく蒙恬は右手を振りかぶり、信の頬を打つ。乾いた音がして、信の顔が傾いた。
「う…ん…?」
二発目を浴びせようとした途端、王賁の精液に塗れた信の唇から小さな声が上がる。
まだ体を交えていることを、今の状況を思い出したように信が目を見開いた。
「も、蒙、恬…」
涙を流しながら、許しを乞うように、信が震える手を伸ばして来る。恐怖で色を失ったその手に頬ずりをして、蒙恬は口元だけで微笑んだ。
「信」
低い声で名前を呼ぶと、信が怯え切った瞳を向けて来る。
「俺たち、もう友人じゃなくて、夫婦になるんだから」
その言葉を聞いた信が呆然としている。王賁の白濁で汚れた唇が戦慄いた。
ヒビの入った心を完全に打ち砕くように、蒙恬は言葉を続ける。
「蒙恬様、だろ?」
暗く淀んだ蒙恬の瞳に映る信の表情が、恐怖で凍り付いた。
終
番外編①(王賁×信)はこちら
番外編②(蒙恬×信←桓騎)はこちら