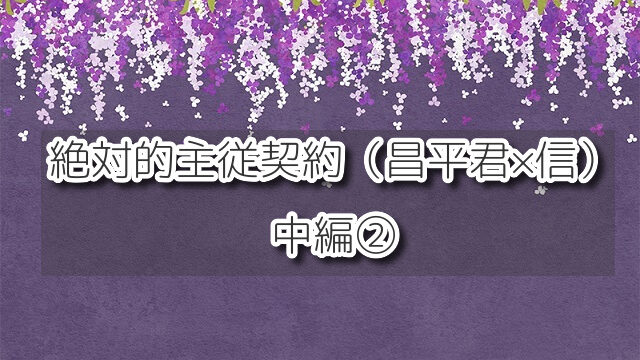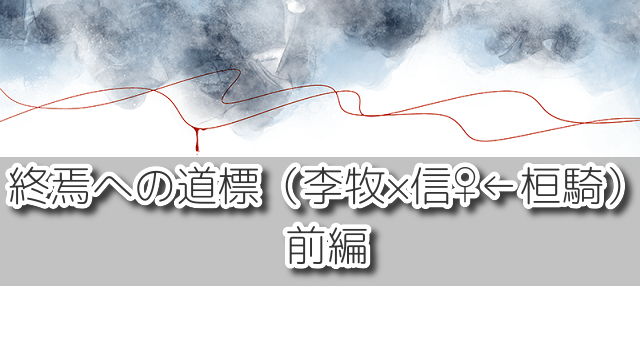- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 桓騎×信/ツンデレ/毒耐性/ミステリー/秦後宮/IF話/ハッピーエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話はアナーキーの後日編・完全IFルート(恋人設定)です。
前編はこちら
決意
向の身の回りの世話をする女官は、侍女頭の敏を含めて、十人程度だ。太后に仕える女官の数に比べると圧倒的に少ない。
秦王の正室であるとはいえ、田舎の出ということで後ろ盾がないのも影響しているのだろう。
向に仕えている女官たちの勤務態度は至って真面目で、向に殺意を向けているような姿は見られない。
幾度も死地を乗り越えて来た信は、人間の敵意や殺意というものには敏感になっているのだが、向の周りにいる女官たちからはそういったものは一切感じられなかった。
毒見役として任命を受けた信は、侍女頭から他の雑務はしなくて良いと命じられたのだった。次の食事の時にでも亡くなる短い命だと思われているらしい。
他の女官たちからも哀れみの目線を向けられたが、信は少しも気にならなかった。
「…信様が傍に来て下さっただけで、なんだかとても安心してしまいました」
腹を擦りながら、向が笑顔を向ける。
毒見以外の仕事がない分、信は話し相手として向の傍につくことになっていた。護衛という役目も担っているため、信にとってはその方が都合が良い。
「後宮も、違う意味で毎日が戦なんだな…」
後宮内の話はあまり聞いたことがなかったのだが、やはり秦王の寵愛を求めて女性たちの争いが絶えないのだという。
正室に選ばれたことや、嬴政の子を身籠ったことを素直に祝福してくれたのは彼女の友人である陽や、他の仲の良い同僚だけだったらしい。
後宮にはそれなりに地位のある貴族の娘も多く、後ろ盾もない田舎出身の向が正室に選ばれたことを気に食わない者も多いのだそうだ。彼女たちからしてみれば、どうして向が選ばれたのか理解出来ないのだろう。
(…動機としては十分過ぎるよなあ)
信は椅子の背もたれにどっかりと背中を預けた。
王騎と摎の養子である信だが、それまでは下僕として生きていた。何の後ろ盾もなく、それどころか地位や人権も存在しないという立場であったなら、その辺と石ころと何ら変わりない命だった。
将としての才能を見出されなければ、今でも下僕として生きていたに違いない。
しかし、後ろ盾のない低い身分であったとしても、後宮で働けるのは運が良いことだ。寝床も食事も給金も与えられるのだから、下僕と違って飢えや寒さに苦しむこともない。
後ろ盾がない弱い立場で、大王の寵愛を受けられないとしても、人として扱われて真っ当に生きていける。
(俺もいつまでいられるか分かんねえが…)
信が後宮で向の護衛と毒見役として滞在する期間は決して長くない。戦の気配があればすぐに呼び戻されるだろう。
しかし、向のやつれ具合を見る限り、まだしばらくは彼女の傍に居た方が良さそうだと信は考えた。
向の友人である陽もこの宮殿には務めておらず、頻繁に会うことが出来ないのだという。心を開ける人物が傍にいないのは辛いことだ。
実際に毒見役の死を目の当たりにしたことで、向は悲しみと疑心暗鬼に陥っていた。
子どもを守るという母親の義務も、后として安易に弱みを見せてはいけないという気持ちもあって、随分と苦しめられていたらしい。きっと嬴政もそれを感じて、信に護衛を頼んだのだろう。
親友であり、秦王である嬴政が頭を下げてまで信に妻を守ってくれと頼んだのだ。秦の未来のためにも、向と子どもの命を守らなくてはならないと信は決意した。
「…向。俺の正体もそうだけど、俺が毒を食っても平気なのは、他の奴らには絶対言うなよ」
「え?」
きょとんと向が目を丸めたので、信は呆れたように肩を竦めた。
「あんまり疑いたくねえけどよ…もし近くに犯人がいたら、俺が居なくなってから毒を盛るに決まってるだろ」
そのために飛信軍の女将軍であることも隠しているのだと告げれば、向は複雑な表情で頷くしかなかった。
毒を盛ることが可能な人間に目星をつけるとすれば、食事を作る者、器によそう者、配膳する者になるだろう。
食事が配膳されるまでの過程で何者かが毒を混入させるということも考えられるが、女官の出入りが多いことから、目撃者がいてもおかしくはない。
桓騎から聞いた毒殺方法を参考にして考えると、向の身の回りの世話をする女官が怪しいと信は睨んでいた。
―――…一度毒殺に失敗したんなら、当然だが全員が警戒する。少し時間を置かねえと動き出さねえだろうな。
褥の中で桓騎が言っていたことを思い出す。
向を毒殺しようとした犯人は、確実に彼女と子供を殺すために、再び毒を盛る機会を見計らっているに違いない。桓騎も信もそう睨んでいた。
毒見
昼食の時間になると、途端に宮殿の中にある重々しい空気が増した。向も女官たちも顔に緊張を浮かべている。
「じゃあ、これ…お願いね」
食膳が運ばれて来ると、侍女頭の敏が小皿に食事を少量移した。葉物を出汁に浸したものだ。
小皿を受け取った信はすぐに口に運ぶことはせず、食事を観察をする。
「………」
並べられている食器は全て銀製だ。よく観察してみるが、変色はない。毒見する分を盛った小皿も銀製だったが、こちらにも変色はみられなかった。
もしも毒が盛られていれば黒く酸化するのだが、それがないということは一見、無害のように思える。
しかし、今回の毒殺事件は特殊だった。食器に酸化がなかったというのに、毒が盛られていた。つまり、食器に変色がなかったとしても油断は出来ないということである。それを分かっているからこそ、女官たちも怯えているのだろう。
「…自分でよそっても良いか?」
「え?」
いきなり信が箸を取ったので、その場にいる女官たちが全員呆気にとられた顔をする。信は返事を待たずに、違う小皿に自分で毒見する分をよそった。
―――毒見役をすり抜けるなら、毒見させる食事をよそう奴を演じても良い。毒が入っている部分さえよけて、毒見役に食わせれば簡単に欺けるからな。
桓騎の声が耳裏に蘇る。
あの日、褥で聞いていた毒殺方法は、十は超えており、まるで物語を聞かせられているかのように、信はいつの間にか寝入ってしまった。桓騎の頭には、一体いくつの毒殺方法があるのだろうか。
様々な毒殺方法があったのは分かったが、疑うのならば、とことん疑った方が良いということだけは理解している。
身近な者たちに紛れて犯人がいるとすれば、食事を作るところから監視しておくべきなのかもしれないが、あからさまに警戒心を剥き出しにしていれば犯人も動けないだろう。
自分で食事をよそった信は迷うことなく、それを口に放り込んだ。ゆっくりと咀嚼するが、鴆酒の時のような痺れは少しも感じない。
「うん、大丈夫だな」
何ともないことが分かると、信は次の料理を自分でよそって勝手に毒見していく。
これほど毒見に怯えず、むしろつまみ食いのように食事を口に運んでいく女官を見るのは初めてだったのだろう、その場にいる者たち全員が驚愕していた。
「全部食っても良いぞ」
毒見で腹が膨れると、信が向に食事の許可を出した。
「ちょ、ちょっと、あなたっ!向様になんて口の利き方をっ」
ずっと傍で見ていた侍女頭の敏が信の頭を軽く叩く。いでっ、と信が顔をしかめると、それまで暗い表情をしていた向がくすくすと笑い始めた。
何ともないことが分かり、安心して食事を運んでいく向の姿を見て、信もほっと胸を撫で下ろす。
食事の度に怯えているなんてキリがない。腹の子のためにも、栄養は摂らなくてはならないのに、その食事に毒を盛るだなんて心無いことをする。
(早く犯人を捕まえられれば良いんだがな…)
複数犯の仕業なのか、一人の仕業なのかも分からないこの状況で、向はよく耐えていたものだと信は感心してしまった。
嬴政に依頼されたのは護衛と毒見役だけだったが、やはり自分が後宮にいる間に犯人を捕えねばと思うのだった。
報告会
食事に毒を盛られることはなく、一週間ほど経った頃。向と二人で茶を飲みながら、寛いでいると、宮廷と後宮を出入りする宦官から信は呼び出しを受けた。
「女官の信だな?」
「ああ。なんか用か?」
宦官たちの仕事着なのか、いつも黒衣と黒い仮面を身に纏っている。宦官だという判別しやすくするためなのか、鼻と口元以外は覆われているため、顔の認識が出来なかった。
声を聞く限り、恐らく信が後宮に来た時から、向の護衛に務めている者なのだろうが、同じ仮面と着物のせいで、全く判別が出来ない。
「大王様から、今宵、伽に来るようにと」
宦官の言葉を聞き、信の顔があからさまに引き攣った。
伽を装って後宮での様子を報告することになっているのは事前に決めていたのだが、それにしても伽という言葉以外に何かなかったのだろうか。
嬴政の妻である向がここにいるというのに、もう少し彼女の気持ちを考慮してもらいたいものである。
分かったと返事をしてから、信は強張った表情のまま、向の下へと戻った。
うんざりした表情で席に座ると、向が困ったように笑みを浮かべる。どうやら聞こえていたらしい。
「あ、あのー、私のことはどうぞお気になさらず…」
「いや、気にするだろ。つーか、なんであいつの方から来ないんだよ」
嬴政の寝室は宮廷だけではない。妻のいるこの後宮にも用意されているというのに、どうして彼の方から来ないのだろうか。
そこまで考えてから、情報漏洩を防ぐためなのかもしれないと信は気付いた。
犯人が後宮にいる可能性が高いと睨み、信を護衛と毒見役として後宮に送ったのだ。後宮で情報交換をすれば犯人の耳に届く可能性があるかもしれない。
「はあ…」
上手くいかないものだと信は頬杖をついた。
向には無事に子を産むことだけを考えてもらいたいのに、やはり秦王の子ということもあれば、王族に襲い掛かる危険とは切っても切れぬものらしい。
(結局誰か分かんねーな…)
食事を作る者、よそう者、配膳する者が怪しいと睨んでいた信だったが、未だ犯人が動き出す気配はなかった。
あの毒殺事件が起きてから、全員が食事を警戒しているのは確かだ。かと言って、今夜の食事に毒が盛られないとは限らないし、絶対に安全という保障はどこにもない。
この一週間は、何も起こらなかった。それもあって、疑うべきは女官だけで良いのだろうかという考えも起こるようになっていた。
もしかしたら複数犯の可能性だって考えられるし、女官でない可能性も十分にある。女官でないとすれば宦官か。
犯人が複数いるとすれば、毒を盛った者だけでなく、それを手引きした者がいるということだ。かなり厄介である。
信は毒を摂取しても何ともない体だが、本来はそうでないがほとんどだ。
毒を盛られるというのは、生きるか死ぬかの瀬戸際であり、恐怖に苛まれてもおかしくはない。向はよく耐えて来た方だと思う。
報告会 その二
夕食にも毒は入っていなかった。信が何ともないと告げると、向は今まで食事が摂れていなかった分を取り戻すように食事を食べていた。
信の存在は向にとっても、余程心強いのだろう。
この一週間で向の顔色は随分と良くなった。それまでは亡くなった毒見役のことを想って、ろくに休むことも出来なかったようだが、夜もよく眠れるようになったらしい。
就寝の時刻になると、信は宦官たちと共に宮廷へ向かった。
大王の寝室の場所を知られないようにするためなのか、後宮を出た後は目隠しをされる。廊下で体を幾度も回されて、方向感覚を失ってから歩かされ、ようやく寝室へと辿り着いた。
目隠しを外されると目の前に大きな扉がある。ここが嬴政の寝室らしい。
幾度も嬴政とは顔を合わせているが、そういえば彼の寝室に入るのはこれが初めてだった。
報告会の建前であるとはいえ、まさか伽で寝室に呼ばれる日が来るなんて夢にも思わなかった。
「入れ」
すぐ背後から宦官に指示をされ、信は扉を開けた。振り返ることも許されないのは、寝室の位置を知られないためだろう。
背後で扉が閉められてから、信はわざとらしい溜息を吐いた。
「…建前だとしても、お前の褥に呼ばれるなんて良い気分じゃねえな」
嫌味っぽく言ってみたが、寝台の上で書簡に目を通している嬴政は無反応だった。書簡を畳みながら、嬴政が顔を上げる。
「向は無事か?」
ああ、と信が頷くと、嬴政は安堵した表情を浮かべた。
部屋にあるのは大きな寝台と、机くらいだ。寝台の端に腰を下ろした信は足を組みながら、後宮であったことを報告した。
「…この一週間、水にも食事にも毒が入ってたことはねえ。身の回りの物も見させてもらったが、別にそれっぽい毒が仕組まれてる気配もなかったな。可能な範囲で宮殿にいる宦官や女官も見てたが、別に怪しい動きもなかった」
「そうか…」
相槌を打った後、嬴政が黙り込む。彼も相当悩み込んでいるようだ。
本来ならば自分の手で向を守りたいと思っているに違いない。もしも、犯人の動機が嫉妬だったとすれば、嬴政が向のために後宮を頻繁に出入りすることは、怒りを煽ることになる。
情報漏洩だけでなく、そういった理由から、嬴政は後宮への出入りを控えているのかもしれない。
後宮には嬴政の寵愛を待ち侘びる女性たちがごまんといるのだ。自分が選ばれなかったことを妬む女性が居たとしても決しておかしいことではない。
そしてそれを動機に、身籠っている后を毒殺しようとするなんて、憎悪の塊である。
(…ちょっと待てよ)
向の身に危険が迫っているのは分かったが、もしも動機が本当に嫉妬だったとしたら、今の自分はどうなるのか。
正体を隠すために、表向きは後宮へ身売りされた毒見役の下女という提で向の傍にいるが、後宮に来て、たかだか一週間の下女が大王の伽に呼ばれたなんて前代未聞だろう。
誰もが振り返る美貌を持っている訳でも、歌や舞が得意という訳でもない。一体何の理由があって伽に呼ばれたのかと不審がる者が居てもおかしくはないはずだ。
…もしかしたら今度は自分が毒殺をされる番かもしれない。
「はあー…面倒臭えな…戦の方が楽だ」
「?」
信の大きな独り言に、嬴政が小首を傾げた。
もしも向ではなく自分に毒が仕向けられるなら願ったり叶ったりではあるが、そうなると犯人はあの宮殿に務める女官たちに絞られる。
なぜなら信が今宵、嬴政の伽に呼ばれたのを知っているのは、信を呼び出した宦官と、向と彼女の身の回りの世話をする女官たちだけだからである。
あまり考えるのを得意としない信は謎の頭痛に悩まされた。
「…おい、そういや俺の寝床は?」
部屋を見渡しながら、寝台が一つしかないことに信は疑問を抱いた。
「ここにあるだろう」
二人が腰掛けている寝台に目を向けながら嬴政がそう言ったので、信は鈍器で頭を殴られたような衝撃を受けた。
「なんでお前と寝なきゃいけねえんだよ。政は床で寝ろよ」
「大王である俺に床で寝ろとは聞き捨てならんな」
先日、嬴政と男女の仲でないことを向に告げたばかりだというに。信が苦虫を嚙み潰したような顔になった。
何もなかったとはいえ、同じ寝台で朝を迎えたなんて、何もなかったという方が疑わしい。向は気にしていないように振る舞っていたが、きっと心は嫌悪していたはずだ。
「はあ…俺が床で寝れば良いんだろ」
野営をすることに慣れているため、信は基本的にどこでも眠ることが出来る。戦では休息が欠かせず、すぐに体を休ませなくてはならないので、眠る環境などいちいち気にしていられないのだ。
伽を命じられている以上は部屋を抜け出して後宮へ戻る訳にもいかず、信は仕方ないと床で寝ようとした。
「風邪を引く。諦めてここで寝ろ」
嬴政に腕を引っ張られ、信は寝台に渋々横になる。上質な寝具を体に掛けると、その温かさに信の瞼がすぐに重くなった。嬴政は書簡を読み終わってから眠るらしい。
(そういや、桓騎…何してんのかな…)
後宮に行く前に様々な毒殺方法を教えてくれた恋人の顔が瞼の裏に浮かび上がったが、信の意識はすぐに眠りへと落ちていった。
朝帰り
日が昇った頃、信は足早に後宮へと戻った。既に他の女官たちは仕事を始めていて、信も朝食の毒見をするために宮殿に向かう。
まだ朝食は準備中のようで、信は眠たい目を擦りながら、向に嬴政とは何事もなかったことを伝えようと彼女の部屋に向かった。
いつも部屋の前で待機している護衛の宦官の姿が見当たらなかったので、信は小首を傾げながら部屋を覗き込んだ。
どうやらまだ向は朝の支度をしているのか、部屋に来ていないらしい。
「あら、戻ったのね」
寝室まで向を迎えに行こうかと考えていると、女官に声を掛けられる。彼女は信と向よりも幾つか年下だったが、この宮殿では働き者として有名だった。
昨夜、信が伽に呼ばれたことを知っていたこともあり、彼女はにやけ顔になって信に駆け寄って来る。
「ねえ、大王様とはどうだった?」
好奇心を隠し切れていない表情が迫って来る。潜めていた声も興奮でやや震えていた。伽に呼ばれたとなれば体を重ねたのだろうと考えるのは普通のことである。
漠然とした質問を投げ掛けられ、信はたじろいた。
後宮には嬴政の寵愛を求める女性が大勢いる。しかし、嬴政が弟の成蟜から政権を取り戻す時からの付き合いである信には、彼をそのような目で見たことは一度もなかった。
端正な顔立ちをしていることはともかく、一度決めたことを覆さないこと、強い志を持っていることなどは確かに王の素質として欠かせないものだろう。
だが、改めて「どうだった」と問われると、何を答えるが正解なのか分からず、信は返事を詰まらせてしまう。
「朝から立ち話はおやめなさい」
「あっ、敏様…!」
振り返ると、敏が目をつり上げていた。
さすが女官たちをまとめる侍女頭と言うべきか、仕事をしていない者には厳しいらしい。
すぐに仕事へ戻っていった女官の後ろ姿を見つめながら、信も何か仕事をするべきだろうかと考える。
毒見役以外の仕事はしなくても良いと言われていたが、向の話し相手だけというのも、正直良いものか分からない。
むしろ、女官の仕事をした方が情報は探りやすいと思い、信は思い切って侍女頭に声を掛けた。
「俺も、そろそろ毒見以外の仕事を…」
「それはいいのよ。向様のお傍にいてちょうだい。あなたが来てくれたお陰で、ようやくお元気になられたようだから」
「………」
そう言われてしまえば、大人しく引き下がるしかなくなる。
「それより…」
敏が声を潜めたので、信は小首を傾げた。
「大王様の伽へ呼ばれたんでしょう?どうだった?」
(お前もかよ)
侍女頭である彼女も好奇心は抑えられなかったらしい。寸でのところで信は言葉を飲み込んだ。
「それにしても…まだ後宮に来て間もないのに、どうやってお眼鏡に掛かったの?最近は大王様も後宮にはお見えにならないのに…」
嬴政に伽へ呼ばれるのは、やはり珍しいことなのだろう。先ほどの女官もそうだったが、羨望の眼差しを向けられて、信はなるほどと思った。
向に続いて自分も呼ばれたとなれば、美貌を持ち合わせている娘や、強い後ろ盾を持つ貴族の生まれの娘たちからしてみれば不思議で仕方がないだろう。
他者より優れた美貌や特技どころか、何の後ろ盾も持たぬ田舎娘が選ばれるだなんて、彼女たちにとっては屈辱に感じることなのかもしれない。
(…少しからかってやるか)
信はにやりとする。自分に大将軍以外の仕事を押し付けた嬴政に、ちょっとした嫌がらせをしてやろうと思ったのだ。
「…昨夜は、とても恐ろしい目に遭った…」
「え?」
信はわざと着物の袖で目元を拭う仕草をした。それから信はすぐさま袖を捲り上げて、傷だらけの腕を侍女頭に見せつける。
「―――ひッ!?」
信の右腕に刻まれている醜い傷跡を見て、敏が分かりやすく青ざめた。
幼い頃から幾度も戦に出ていた信の体は傷だらけであり、中でも、過去の魏軍との戦で、廉頗四天王の一人である輪虎によって、骨が覗くまで斬りつけられた右腕には一番深い傷痕が残っている。
他にも、目も当てられぬような傷ばかりが刻まれているが、右腕は特にひどい。
身売りされた下女がこんな傷だらけであるはずがないのだが、戦とは無縁である後宮の女官ならば、このような傷痕を見慣れていないのも当然だろう。
普段から血を見ることもない人間からすれば、信の体に刻まれている傷は恐ろしいものであった。
「きっと、大王様は、俺のようなみすぼらしい女を痛めつけるのがご趣味なんだ…」
自分の体を抱き締めながら、信は渾身の演技を見せつけた。信の傷だらけの体を見て、侍女頭は青ざめたまま、逃げるように離れていく。
(はっ、これで変な噂が広まれば、政に抱かれたいなんて夢見てる女どもはビビるだろ)
すれ違いで朝の支度を終えた向と、護衛として付き添っている宦官がやって来たので、信は何事もなかったかのように袖を戻した。
「…あの、何かあったのですか?」
血相を変えていた侍女頭を不審がり、向が小首を傾げている。にやっと笑った信は首を横に振った。
「麗しき大王様のご趣味について教えてやっただけだ」
「………」
信が嬴政のことを麗しき大王様と呼んだことに、向は何か嫌な予感を覚える。悪い噂が広まらないことを祈るばかりだった。
「あ、昨日は本当に何もしてねえからな?色々話して寝ただけだ」
身籠っている向に余計な不安を与えたくない。護衛の宦官も傍にいるので、報告会であることは内密に、信は昨夜の出来事を向に伝えた。
体を重ねたことは絶対ないと先日も伝えたのだが、向は信じてくれただろうか。
事件
その後も、水や食事に毒が盛られることはなかった。
念のために化粧品や香も頻繁に確認させてもらっていたが、それらしい毒は見つからない。女官や宦官たちの動きにも不審な点は見つからないし、いよいよ犯人が雲隠れしてしまったかもしれない。
何度か行っている報告会で、嬴政もそのことを危惧していた。
幸いにも隣国が攻めてくるような気配はなく、信は後宮で護衛と毒見役を継続していたが、やはり犯人を捕らえることは出来ないかもしれない。
―――三月ほど日が経つと、信が後宮に来た時よりも向の腹は大きくなっていた。
信のおかげで食事も摂れるようになり、以前のような消沈していた彼女はもうどこにもいなかった。
身重の向に負担を掛ける訳にもいかないと、嬴政も久しぶりに後宮へ姿を見せるようになった。
信の企みで、後宮には一時的に嬴政が加虐性愛だという恐ろしい噂が広まってしまい、伽に呼ばれたらどうしようと不安がる女官が多く現れた。
しかし、後宮にやって来た嬴政の端正な顔立ちと大王としての振る舞いを目の当たりにして、再び以前のように、彼の寵愛を求める者が続出してしまったのだった。
…嬴政の秦王としての素質は、噂如きで揺るぐはずがなかったということである。
後宮に嬴政が訪れた際も、信は女官たちや宦官の動きを見張っていたが、特別怪しい動きをするような者は見当たらない。
全員を疑っていた信だったが、三月も共に生活をすれば情が湧くもので、この宮殿には犯人はいないのではないかとさえ思うようになっていた。
向に仕える者たちが、いかに后へ忠誠を尽くしているかは、後宮に来てから目の当たりにして来たからだ。
「夕食のご用意が出来ました」
食事の支度が終わったと報告を聞き、信と向は頷いた。
これから運ばれて来るのだが、扉の前で見張りをしていた宦官が信に声を掛ける。
「毒見役の女官」
「ん?なんだ」
見張りをしている宦官も無口な男だったが、きちんと仕事をこなしている真面目な男だ。彼に呼ばれるのはあまりないことだったので、信は珍しいなと目を丸める。
「今夜は粥だそうだ」
「…?ああ…」
いきなりそんなことを言われたので、信は戸惑いながら相槌を打った。
「……?」
「………」
用件はそれだけだったらしく、彼は口を閉ざして見張り役に徹している。
何なのだと思いながら、信は部屋に戻って、目の前に並べられていく夕食を眺めていた。主食が宦官が言ったように粥になっている。
「昼間は脂の多い食事でしたから、夕食はお腹に優しいものを作らせました」
侍女頭の敏がそう言ったので、信はなるほどと頷いた。
食欲がない訳でもないのに、どうして急に粥を用意したのかと不思議だったが、さすが后のことを一番に考えている。
(…皿は、大丈夫だな)
銀製の食器に変色は見られない。信は普段通りに小皿に自分で毒見分をよそい、口に運ぶ。
舌にも喉にも痺れは感じない。飲み込んだ後も、症状は出ないことから、信は大きく頷いた。
「……ん、問題ない」
信がそう言ったことに、向も女官たちも安堵したように頷いた。
さっそく粥の入った器を手に取り、向が匙で粥を掬い上げる。その姿を見て、信は胸騒ぎを覚えた。
(…なんだ…?何か…引っ掛かる…)
妙な違和感を覚え、信はつい口元に手を当てて考えた。食事自体には毒がないことは確認出来たのだが、胸騒ぎがするのだ。
信は嬴政に后の護衛と毒見役を任命され、桓騎の屋敷へ泊まったあの日のことを思い出した。
確実な毒殺方法
―――桓騎がにやりと笑った。
「あるぜ」
「え?」
「毒見役の目を誤魔化して、確実に后だけを毒殺する方法だ」
信は疑いの眼差しを向けた。毒見役を演じて、毒を飲ませる方法は聞いたが、さすがにすり抜けるのは無理があるのではないだろうか。
毒見役か、毒見する分の食事をよそう者になれば、怪しまれることはないと言っていたが、さすがにこれ以上の方法など存在しないだろう。
「致死量の毒を飲ませるなんて簡単じゃねえか」
そんな簡単なことだろうか。信は眉間に皺を寄せる。
「んなこと言ったって、本人が食う前に、絶対に毒見役が気付くだろ。…それに、食器だって銀製にしてるんだから、変化があればすぐに毒入りだって気づくはずだ」
向の食事を毒見した下女が毒殺されたことが大きな噂になったのは、どのように毒が用いられたのかが分からなかったからだ。
食事に毒が盛られていたのは明らかだが、銀勢の食器にも変色はなかったという。嬴政から聞いた話を思い出し、信は口籠ってしまう。
「食器の色は変わりなかったっていうのに、毒見役は即死だったんだろ?」
「………」
何も言っていないというのに、桓騎が発した言葉に、信は肯定の意味を込めて沈黙した。相変わらず少ない情報から真相を読み取るのが上手い男だ。
険しい表情を浮かべている信に手を伸ばし、桓騎は彼女の柔らかい頬を軽く引っ張った。ふわっ、と信が情けない声を上げる。
「気付かせねえで致死量を口に入れさせるなら、俺だったら、食事には盛らねえな」
頬を引っ張る桓騎の手を振り払い、信がきっと目をつり上げる。
「は?じゃあ、どうやって飲ませるんだよ」
「…少しは頭使えよ」
桓騎が自分のこめかみをとんとんと指で叩いた。
「食事をする時には必ず使うが、銀製じゃねえ物が一つか二つはあるだろ」
「…?なんだよ、勿体ぶらずに教えろよ」
信が随分と余裕のない表情で迫って来たので、桓騎は口の端をつり上げて、彼女に正解を教えてやるためにゆっくりと口を開いた。
「―――待てッ!」
信が怒鳴ると、口に粥を運ぼうとしていた向が驚いて動きを止めた。
「ふ、ぇ…?し、信さま…?」
いきなり信が大声を上げたので、向だけではなく、その場にいる者たち全員が彼女に注目をしている。
信は立ち上がると、向が握ったままの匙を奪い取った。
その匙を凝視していると、緊迫した空気の中で、一人の女官が足音を立てぬよう部屋を出ようとしている姿が目の端に映り込む。
「おい、そこのお前」
低い声で信が呼び掛けると、部屋を出ようとしていた女官が弾かれたかのように肩を竦ませた。全員の視線がその侍女に集まる。侍女頭の敏だった。
全員からの視線を向けられた彼女はあからさまに狼狽えている。
「…あ、あの、今日の食事を作った者が、誰か、厨房を調べて来ようと…」
こちらはまだ何も尋ねていないというのに、部屋を出ようとした理由を彼女は自ら打ち明けた。
「…部屋から一歩でも出たら后暗殺の疑いを掛ける。疑われんのが嫌なら、そこから動くんじゃねえぞ」
怒気の籠もった信の言葉に、その場にいる者たち全員が生唾を飲んだ。
すぐに叩き斬られてしまいそうな、戦場に立つ時の威圧感を剥き出している信に、侍女たちが怯えていた。
「食事を運んだのは誰だ?」
周りにいる侍女たちを見渡しながら信が声を掛けると、向のすぐ傍に控えていた女官が恐る恐るといった様子で手を挙げた。信が嬴政の伽に呼ばれた翌日に声を掛けて来た女官だった。
気の弱そうな女官だが、向のことを随分と慕っている娘である。働き者だが、少し幼さの残っている顔つきのせいか、向も妹のように彼女を可愛がっている存在だ。
「…この匙を用意したのもお前か?」
信が手に持っていた木製の匙を彼女の眼前に突き出すと、女官は困ったような表情で首を横に振った。
「い、いえ…私が用意したのは、箸です…」
彼女が匙を用意していないと否定したことに、信の中で妙に腑に落ちたことがあった。
食事と共に添えられている何の変哲もない箸を見て、やはりそうかと頷く。
「…じゃあ、誰がこれを用意したかわかるか?」
なるべく怯えさせないよう、穏やかな声色を装って信が問うと、女官は小さく頷いた。
「しょ、食事をお出しする前に…粥なら匙の方が食べやすいと…敏様が…」
侍女頭の名前が出て来たことに、信は振り返った。
「おい、てめえ」
匙を握ったまま、信はずかずかと大股で侍女頭の前へと向かった。
木製の匙の裏一面には、粥とは違った、何かを磨り潰したような、白い粉が付着している。確かめるまでもなくそれが毒であることを信は確信した。礜石から摂取した物だろうか。
もしも知らずに口付けていたら、間違いなく向は倒れていただろう。生まれる前の子の命だって危険に晒されていたに違いない。
一度でも粥を掬ってしまえば、匙に毒が付着しているなど素人では判別出来ない。
しかし、銀製の食器にも異常はなく、毒見役が実際に食事を確認して何ともなかったことから、本人は疑うことなく食事と共に匙に塗られた毒を摂取してしまう。最初からそういった筋書きだったのだろう。
確実な毒殺方法 その二
―――…どんな毒を使うにしろ、確実に致死量を飲ませるなら、俺なら匙を使う。
信の耳奥に、桓騎の声が蘇った。
後宮へ女官として潜入する前夜。褥の中で、桓騎はまるで子どもに物語を言い聞かせるような穏やかな口調で話し始めた。
それは信が考えても分からなかった、銀製の食器と毒見役の確認をすり抜けて、確実に毒を盛って相手を殺す方法である。
―――…全員の意識は食事に向けられる。銀製の食器も、毒見役も何ともないって言うんなら、そいつは安心して食うだろ。だが、銀製じゃねえ匙の裏に毒が塗られてるかなんて、誰も確かめねえからな。
匙を口に運んだ時点で、こちらの勝ちなのだと桓騎は言った。
―――警戒して少しだけ口をつけるにしても、匙で飯を掻き混ぜちまえば、すぐに毒入り料理に早変わりするって訳だ。一口目は運良く免れたとしても、二口目で確実に殺せる。…なんでこんな簡単なことを、バカ共は気づけねえんだろうなあ?
…すべて、桓騎の言う通りだった。
食事に毒が混入していれば、銀製の食器は黒く変色する。しかし、食器に変色は見られず、毒見役である信が食べても何ともないことに安堵した向は、毒が塗られている木製の匙で口に運ぼうとした。
警戒すべきは食事だけではなかったのだ。
まさか桓騎が話していたことが全て目の前で実現したことに信は驚愕したが、今はそんな悠長に過ごしている暇はない。
「…侍女頭の敏、だったな。お前が毒を盛った犯人ってことか?」
侍女頭を睨みつけながら、信が問う。背後で向たちがまさかと青ざめた顔をしていた。
敏という侍女頭も青ざめていたが、反論は出て来ない。
無実だとしたらすぐさま言い返そうとするに違いないが、目を泳がせているところを見ると、何か上手い言い訳を探しているのだろう。
息をするのも重苦しいほどの沈黙が流れる。どうやら上手い言い訳も見つからなかったようだと信は腕を組む。
「…俺は処分を言い渡すような立場じゃない。後のことは上の判断に任せる」
外に待機している宦官へ後のことは頼もうと、信が部屋を出ようとした。
敏の横をすり抜けた時、全身の毛穴が針に突かれるような嫌な感覚がして、信は反射的に振り返る。戦場でしか感じないあからさまな殺意だ。
「向…!お前さえいなければッ」
振り返った時には既に敏が帯の中から取り出した短剣を構えて、向の方へと直進している時だった。
「向!逃げろッ!」
信が叫んだが、伸ばしたその手は敏の着物を掴むことは叶わなかった。
名を呼ばれても愕然としている向はその場から動けずにいる。短剣といえど、凶器には変わりない。腹を刺されでもすれば向どころか、腹の中にいる赤子の命まで危うい。
心を掻き毟られたように慌てた信が、背後から敏を取り押さえようとした時だった。
「きゃあッ」
ひゅん、と何処からか風の切るような音がしたかと思うと、火傷をしたかのように敏の身体が跳ね上がり、その体は仰向けに崩れ落ちた。
何があったのだろう。信も向も、倒れた侍女頭も、その場にいた者たち全員が分からなかった。
「う、ぅう…く、くそッ…!」
敏の左肩に、深々と弓矢が突き刺さっているのを見て、信がはっとなる。
痛みに呻いている敏の手から短剣を奪い取ると、信は愕然としたままでいる向に顔を向ける。
「大丈夫か?」
「は、はい…!」
寸でのところであったが、毒も口にせず、怪我もなかったようだ。
騒ぎを聞きつけた宦官がやって来て、彼が侍女頭の身柄を拘束してから、信はようやく安堵の息を吐き出すことが出来たのだった。
(あの弓矢…一体どこから…?)
妃の毒殺だけでなく殺害まで図ろうとした敏が宦官に連れていかれた後、信は部屋の窓へ駆け寄った。
外を覗き込むと、美しく整備されている裏庭がある。
誰かが通った痕は見つからなかったが、敏の左肩を貫いた弓矢は正面から撃たれたものに違いない。ということは、裏庭からこの部屋に向かって弓矢を撃ち込んだとしか考えられないのだ。
窓にはいくつもの直線の枠が埋め込まれた装飾がされていたのだが、不思議なことに傷一つついていない。
まさかこの複雑な装飾をかいくぐって弓矢を放ったというのだろうか。それどころか、同じ空間にいた向や女官たちを避けて、適切に敏だけを狙ったのというならば、相当な腕前だろう。
弓矢の扱いに慣れているとしか思えない。だが、一体何のために敏を狙ったのだろうか。
向を守るためなのか、はたまた口封じとも考えられる。仕留め損なっただけかもしれない。
しかし、侍女頭だけを的確に狙った腕前があるのなら、口封じのために頭か胸を貫くだろう。わざわざ致命傷じゃない肩を狙うなんてことはしないはずだ。
(ああ、くっそ…!ますます分かんねえ…!)
味方ならば、なぜ姿を現さないのか理由が分からない。疑問が次なる疑問を呼んでいき、信の思考はたくさんの糸が絡まり合っていた。頭痛に襲われ、こめかみを押さえながら目を伏せた。
味方であるという確信がない以上、これからも油断は出来ない。向とその子どもを殺そうとしていた仲間だとすれば、今度は毒以外にも一層の用心が必要となるということだ。
「信様…」
名前を呼ばれて信はすぐに振り返る。他の侍女たちには宮官長たちへの報告を頼んだため、今この部屋にいるのは向と信だけだった。
ずっと自分に付き従っていた侍女頭が捕らえられたことに、向は瞳に涙を滲ませていた。しかし、涙を堪えながら、彼女は信に深々と頭を下げる。
「ありがとうございます。信様のおかげで私も、大王様の御子も無事でした」
きっと裏切られた気持ちで心が引き裂かれるような痛みを抱えているに違いない。しかし、涙を堪えている辺り、やはり嬴政の隣に並ぶのに相応しい女だと信は思った。
「…いや、俺は何もしてねえよ。犯人があの女だって分かった時点で、さっさと縛り上げちまえば良かったのに…」
向の身に怪我がなかったとはいえ、信は侍女頭である彼女がまさか短剣を隠し持っているとは思わず、油断してしまった。
それなりに長い間、向に尽くしていたという忠義心があった侍女頭だったからこそ、全員が油断していたのだ。
厚い忠義を装っていたのは、大王の寵愛を受ける向を妬んでいたのだろうか。
向は田舎の貧しい出であり、この後宮では後ろ盾がない。そういった身分の者がなぜ嬴政の寵愛を受けることが出来たのだと妬む者が多いというのは噂で聞いていたが、まさかこんなにも身近に潜んでいたとは思わなかった。
矢文と宦官
「毒見役の女官はいるか」
先ほど侍女頭を連れて行った宦官が部屋に戻って来た。いつも向の護衛をして、見張り役も行っているあの男である。何かあったのだろうか。
「ああ、俺だ」
信が手を挙げて近づくと、宦官はこちらに来るように手招いた。大人しく従って廊下に出ると、文を差し出される。
「…これは?」
「侍女頭の肩に撃たれた弓矢に括られていた。お前宛てのようだ」
「?」
信は眉間に皺を寄せながらその文を受け取った。先ほど侍女頭の左肩を撃ち抜いた弓矢に文が括られていたらしい。
毒を盛った犯人が身近な人物であったことと、向の命を守ることで必死だったため、弓矢に文が添えられていたなんて気づきもしなかった。
敵か味方かも分からぬ相手からの文を、信はやや緊張しながら開く。
―――后の次は秦王。
そこに並べられていた言葉に、信は総毛が立つ。
(まさか、政まで狙われてるっていうのか!?)
先ほど侍女頭を狙って弓矢を撃った者からの言伝に違いない。やはり向を殺そうとした侍女頭を口封じのために始末しようと企んでいたのだ。
まだこの後宮には、別の犯人がいる。その者が侍女頭を動かしていたのかもしれない。
先ほどの弓矢を見る限り、相当な腕前である。今までは食事ばかり注視していたが、これからはいつ何時、弓矢が向を襲うか注意しなくてはならない。
いや、それよりも向だけでなく嬴政の身にも危険が迫っていることを伝えねばならない。分かってはいるのだが、信の心は雁字搦めになっていた。
(どうすりゃいいんだ…)
先ほどの弓矢が今度はいつ向を狙うか分からないこの状況下で、信は彼女の傍を離れる訳にはいかなかった。
向だけでなく大王も狙われているのだという報せを知り、細心の注意を払うように嬴政に言伝を頼もうにも、手段が見つからない。
向が厚い信頼を寄せていた侍女頭が毒を盛った犯人だったのだ。今のこの後宮で信じられる者など、信には判断が出来なかった。
先ほどの侍女頭の反撃も予想出来なかった自分が、果たして向を守り切れるだろうか。ましてや嬴政にまで危険が迫っているというのに、それを知らせることも出来ない。
(一体どうしたら…)
胸に不安が大きく渦巻き、信が困惑した表情を浮かべる。
矢文を届けた宦官は彼女の表情の変化を見て、仮面の下で微かに口の端をつり上げた。
「…?」
傍で宦官が笑った気配を察し、信は仮面で覆われたその顔を見上げる。
仮面の隙間から覗く意志の強い瞳に見据えられ、信は思わず息をするのを忘れていた。
「か――」
名前を口に出そうとした唇が、宦官の人差し指によって押さえ込まれる。今は喋るな、という合図である。
すぐに口を閉ざした信に、宦官はゆっくりと頷く。
「…これから后の身柄は宮廷で保護する」
目の前にいる宦官の正体が、自分の恋人であることを察した信は安堵と嬉しさが交じり合ったぎこちない笑みを浮かべてしまう。
(そっか…俺、一人じゃねえんだ)
それまで自分一人で全てを守り切らねばという不安と重責を抱えていた心が、羽根のように軽くなっていくのを信は確かに感じていた。
誰を信用して良いか分からなくなった雁字搦めの状況で、宦官に扮した桓騎の存在は、暗闇に差し込んで来た希望の光だった。
いつから桓騎があの宦官に扮していたのかは分からないが、冷え切っていた信の心はすっかり温かくなっていた。
食事が運ばれて来る前に、粥だと告げたのも、匙に警戒しろという忠告だったに違いない。
「…后の身柄を宮廷へ引き渡した後、大王様にも侍女頭の件を報告をして来る」
信が手に持っていた文を桓騎が奪い取り、さり気ない仕草で袖の中にしまう。
犯人が書いたものだとばかり考えていたのだが、冷静になって考えると、自分宛てと言われたはずなのに、信の名前はどこにも記されていなかった。
(…じゃあ、やっぱり、あの文…)
記憶の糸を引き戻すが、やはり侍女頭の肩を貫いた弓矢に文など括られていなかったはずだ。
―――つまり、あの文は犯人が書いたものではなく、犯人の次の動きを読んだ桓騎から信への言伝である。
桓騎は既に、侍女頭の他に別の犯人がいると目星をつけているらしい。侍女頭に矢を撃った者だろうか。
もしも他の者たちにこの文の内容が広がれば、宮廷にたちまち噂が広まり、嬴政の護衛が強化されるだろう。そうなれば嬴政を狙っている犯人が身動きを取れず、隠れてしまうかもしれない。
他に犯人がいることを信以外に告げないのは、確実に犯人を誘き出す意図をあるのだろう。相変わらず味方に作戦を告げない男だと信は苦笑した。
「…それと、大王様から今宵、伽に来るようにと」
「え?」
報告会の呼び出しに、信は驚いて目を見開いた。
侍女頭が向に毒を盛ろうとした犯人であることはまだ嬴政の耳には届いていないはずだが、この適時にその呼び出しが来たのはきっと偶然だろう。
嬴政の身に危険が迫るとすれば、見張りや護衛が少なくなる夜間のはずだ。
もしも犯人の方から寝室にやって来るのなら、迎え撃てば良いだけである。桓騎もそう考えているに違いない。
「ああ、分かった」
「これから后の身柄を宮廷へ移す」
「…大丈夫なのか?」
信は不安げに尋ねた。桓騎が宦官に扮しているのは恐らく独断での行いで、正式な許可を得たものではないはずだ。
後宮に務めている宦官たちは同じ仕事着をしており、仮面で顔を隠しているため、恐らく気づかれてはいないだろう。
しかし、后と行動を共にすれば、いくら顔を隠しているとはいえ、目立つに違いない。もしも桓騎が宦官に扮して後宮に潜入していたことが気づかれれば、騒動になることは目に見えていた。
「心配すんな。何も問題ない」
周りに誰もいないことを確かめてから、桓騎が普段の口調に戻った。
「まあ、それなら、良いけどよ…」
桓騎がそう言うのなら、きっとそうなのだろう。不思議な説得力を持つ彼の言葉に、信は大人しく頷いた。
仮面で覆われており、口元くらいしか分からないのだが、正体が分かるとやはり隠し切れない彼の雰囲気や仕草が浮き彫りになっていく。
「…信」
「ん?」
急に桓騎が体を屈めたかと思うと、仮面で覆われている彼の顔が、視界いっぱいに映り込んだ。
「―――」
唇に柔らかい感触が押し当てられたのはほんの一瞬のことで、信が瞬きをした時には既に桓騎は顔を離していた。
「え……えっ?」
「今夜には全て終わらせる。さっさと帰るぞ」
向がいる部屋に入ると、桓騎は再び別人のように口調を変えて、向に宮廷へ移動する旨を説明し始める。
背後でその声を聞きながら、廊下に残された信は、桓騎に口付けられたのだとようやく理解して、耳まで顔を真っ赤にさせたのだった。