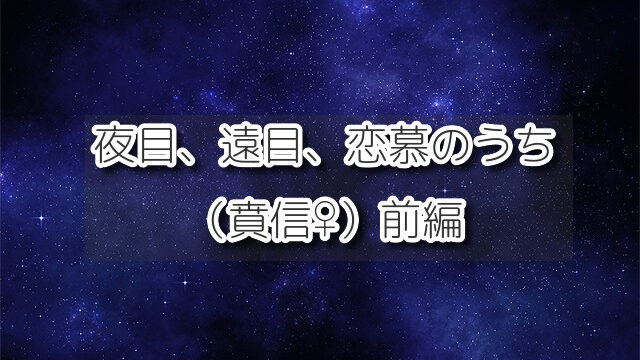- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 李牧×信/シリアス/合従軍/IF話/All rights reserved.
一部原作ネタバレあり・苦手な方は閲覧をお控え下さい。
同盟
合従軍で秦を完全包囲し、侵攻するという同盟の話は、皮肉なまでに円滑に進んでいた。
密林の中に用意した天幕で、楚の宰相である春申君との会談を終えた李牧は、着実に秦を滅ぼす準備が整って来たことを実感する。
「…?」
天幕を出ようとすると、外が何やら騒がしいことに気が付いた。
この天幕がある密林の中に連れて来たのは、必要最低限の護衛と側近のみ。他の兵たちは密林の外で待機している。
会談を互いの国で行わなかったのは秦の者たちに、この同盟を勘付かれないための警戒である。
人目を忍び、何より情報漏洩を防ぐために警戒を行い、この密林で会談を行うよう指示を出したのは李牧本人であった。
味方ならまだしも、もしも秦の何者かに楚と趙の宰相が二人一緒にいるところを見られれば、確実に何か企みがあるに違いないと気づくはずだ。騒ぎの正体が何か分からない以上、警戒も怠ってはならない。
楚の丞相である春申君には状況が分かるまでここに残っているように伝え、李牧は一人で天蓋を出た。
「何事ですか?」
外で待機している側近のカイネに声を掛けるが、彼女の姿が見えない。春申君の護衛を担っている兵の姿もなかった。
「…?」
こちら側にいる人間の合図があるまでは、密林の外に待機させている将や兵たちは動き出さない。
しかし、騒ぎの音がする方向を追えば、兵たちが待機している方ではなく、この密林の中だ。一体何が起きているのか。
李牧は護身用の剣を携えると、護衛たちが通ったと思われる痕を追い掛けて、音のする方へと向かった。
「!」
草木を掻き分けて道を進んでいくと、何かに足を取られた。咄嗟に後ろに退き、転倒は免れる。
黒い鎧を纏っている兵の亡骸だった。楚の宰相の護衛として天蓋の外に待機していた男だ。
首に弓矢が貫通しており、鼻と口から泡の混じった血を流していた。正面から毒矢を受けたのだろう。
太い血管の通っている首を射抜かれた上に、毒が全身を蝕み、苦痛の中で死んでいったに違いない。苦悶の表情がそれを物語っていた。
毒矢を放った者がいるようだ。李牧は周囲の警戒を怠ることなく、兵の亡骸を観察した。
確かこの男は春申君の護衛をするにあたり、毒矢を装備していた。
「………」
兵が倒れている傍に、矢籠と他の毒矢が落ちている。首を射抜いている者と同じ矢だった。
この兵が毒矢で射抜かれたのは間違いないが、相手はこの兵の矢を奪って首を刺したのかもしれないと考えた。
接近戦に持ち込んだということは、まだ相手が近くにいる可能性が高い。
李牧は気配を探りながら、まだ先に続いている足音を辿った。
奇襲だとしたら、すぐに合図があったはずだ。それに、側近であるカイネが自分への報告もなしに追い掛けていったのも気がかりである。
楚の宰相の護衛を務める兵は相当な手練れだった。幾度も死地を駆け抜けて来た李牧が見ただけでそれを察したのだから、間違いない。
そんな彼が毒矢で正面から首を射抜かれていたのだ。背後からではなく、正面から射抜かれていたのを見る限り、相手も相当な手練れに違いない。
ここまで警戒を行った上で始めた楚趙同盟の会談を阻止しようとした者の犯行に間違いない。
(気づかれた?誰に?)
今回の同盟の目的は秦国を滅ぼすことだ。他の五国はほとんど会談を終えており、秦国を滅ぼすことに同意している。
この同盟に利益があるのは五国であり、大きな損失を受けるといえば秦国だけだ。
(秦の者が勘付いた?まさか、ここまで隠し通していたのに)
引き続き周囲を警戒をしながら、思考を巡らせた。
楚の宰相からも既に同盟の返事はもらっている。あとは秦国を攻め立てる戦の準備に移る手筈を整えるだけだというのに。
まさかここに来て秦の者に勘付かれるとは、李牧も予想していなかった。
姿は見えていないが、相手が意図的にこの同盟を阻害しようという意志を持っていたのなら、秦の者に間違いないはずだ。
そこまで考えて、李牧はさらに眉根を寄せた。
(…同盟の邪魔をするなら、なぜ護衛だけを?)
天蓋の側にいた楚の護衛兵だけがやられていることに、李牧は納得出来なかった。
何か異常があればすぐに知らせてくれる側近のカイネの姿が見えないのも気がかりのままである。
声を出す間もなく殺されたのだとしたらと考え、唇を噛み締めた。
「李牧様ッ?」
奥の方から聞き覚えのある声がして、李牧は弾かれたように顔を上げた。カイネだった。
合流
怪我一つしていないのことを確認すると、李牧はようやく安堵の息を吐く。
「心配しましたよ。報告もなしに、どこに居たのですか」
申し訳ありませんとカイネが頭を下げる。
「道に迷ったという妓女がいまして」
「妓女?こんな場所にですか?」
すぐには信じられなかった。
辺り一面木々ばかりで、獣道しかない密林だというのに、どうしてこのような場所に妓女がいるのだろう。
カイネの話を聞けば、その妓女は各地を旅して回っている歌踊団の長らしい。
彼女は仲間たちが野営をしている場所から離れたところにある泉で、一人だけで水浴びをしていたのだという。
しかし、水浴びを終えたところで着物が無くなっていることに気付き、仲間のもとへ戻れずに困惑していたところを、カイネが気配を察知して駆けつけたという経緯だった。
「本来ならば報告すべきだったのですが、申し訳ありません…」
本当に申し訳なさそうにカイネが頭を下げたので、李牧は首を横に振った。
確かに事情が事情だ。もしも報告されたところで、男である自分がしゃしゃり出る訳にはいかず、どちらにせよカイネに対応を頼んでいたに違いない。
「辺りを探したら、木の枝に引っ掛かっている彼女の着物を見つけたのです。風で飛ばされてしまったのでしょう」
「見つかったなら良かったです」
もしも着物が盗まれていたならば、この密林に自分たち以外の第三者が他にも存在するということになる。
野盗の類だとしても、趙と楚の宰相が二人きりで話をしていたとなれば、噂を流される可能性がある。
秦の耳に入らぬよう、慎重にこの会談を進めていたというのに、噂を流されれば勘付かれる原因になるかもしれない。
しかし、他の五か国との同盟はすでに済んでいる。もしも秦国が今から策を練ったとしても、今さら滅ぶ未来は変えられないだろう。
ふと、李牧の瞼の裏に信の姿が浮かび上がった。
馬陽の戦いで、大胆にも敵本陣に奇襲を仕掛けて来た彼女によってつけられた右手の傷痕はまだ残っている。
時折、この傷跡が疼くように痛むことがあり、その度に李牧は秦趙同盟の宴の夜に、彼女と身体を重ねたことを思い出した。
真っ直ぐな瞳で、殺してやると言った彼女のことを、李牧は忘れたことがなかった。
信の存在は記憶に深く刻まれているというのに、もう二度と現世では彼女に会えないのだと思うと、やるせなさが込み上げて来る。李牧が秦を滅ぼそうと決めた理由もそこにあった。
「李牧様?」
束の間、懐かしい思い出に耽っていた李牧はカイネに名を呼ばれ、すぐに思考を切り替えた。今は警戒を怠ってはいけない。
「楚の護衛が、天幕の外で討たれていました」
「えっ…!?」
天幕の外で共に待機をしていた護衛の死に、カイネが焦った表情を浮かべた。すぐに腰元に携えていた剣を鞘から抜き、周囲を見渡している。
「…会談の最中、物音や悲鳴は一切聞こえなかったので、相当な手練れが潜んでいるのかもしれません」
周囲の気配を探りつつ、李牧はカイネと背中合わせの状態で奇襲に備えた。
この密林の中だ。隠れる場所はいくらでもある。もしかしたら近くの木の裏に身を潜め、こちらの首を狙っているかもしれない。
「まさか、秦の刺客ですか…?」
「持っていた毒矢で喉を一突きされていたようですから、我々に気づかれないように殺したのだとしたら、秦の刺客である可能性は高いでしょうね」
信じられないといった表情を浮かべたカイネが、いち早く物音がした方に剣を向けた。
「何者だッ!」
すぐ近くに聳え立つ大木の裏に人影が見えた。
カイネの気迫に押されたからか、それとも諦めなのか、その人物はゆっくりと姿を現した。
再会と罠
現れた女性の姿を見て、李牧は束の間、呼吸をするのを忘れていた。
「…生きて、いたのですか」
ようやく出た声は、動揺のあまり、情けないほど震えていた。隣にいるカイネも愕然として言葉を失っている。
見間違えることはない。目の前にいる女性は、信だった。
最後に会った時よりも随分と髪が伸びていたが、瞳の輝きはあの時と少しも変わっていない。
「いいや?一度死んださ。だから今の俺は秦将じゃねえし、秦趙同盟も関係ない」
李牧の問いに、肩を竦めるように笑う。まるでこちらを挑発するような笑い方に、懐かしささえ感じた。
ほとんど消えかかっていたはずの右手の傷が、彼女の存在を思い出したように疼き始める。
(ここに彼女がいるということは…)
なぜここに信が現れたのか、どうして今なのか、李牧の頭の中でその仮説が次々と導き出されていく。
中華全土に広まった飛信軍の女将軍の訃報を聞き、李牧は彼女の死を信じ込んでいた。
同盟を結んでいる期間とはいえ、敵対関係にあることは変わりない。亡骸をこの目で見るまで、決して彼女の死を信じてはならなかったのだ。
彼女が簡単に死ぬわけがない。
それは馬陽の戦いでも思わぬところで本陣奇襲を掛けられた李牧自身が理解していたはずだったのに、またもや辛酸を嘗めさせられることになってしまった。
「死んだフリをしてたなんて、何が目的だ、貴様ッ!」
カイネに剣の切先を突き付けられると、信が肩を竦めるようにして笑った。
恐らく、信は宰相である自分の首を取るつもりなのだ。李牧の側に、味方が少しもいないこの状況を狙っていたのだろう。
「時間稼ぎだ」
しかし、信が発した言葉は、李牧の命を狙っていることを想定させるものではなかった。
時間稼ぎ。その言葉の意味を李牧が考えるよりも先に、信は空を見上げた。
「こんな密林の中にまで通るなんて、良い風だな」
最後に会った時よりも伸びた黒髪を手で払う。
こんな状況だというのに、まるでこちらへ余裕を見せつけるかのような態度に、カイネが奥歯を噛み締めていた。挑発に乗ってはいけないと自身を制御しているのだろう。
「…!」
風に乗って来た何かの匂いを感じた李牧は、はっとして背後を振り返った。
遠くで煙が上がっているのが見えて、騒がしい声までもが風に乗ってこちらへ漂って来た。
「まさか…」
密林を出た向こう――兵たちを待機させている場所からの方だ。道の途中には、李牧が会談をしていた天幕もあって、まだ中には楚の丞相がいる。
「な、何が起きて…」
李牧の視線を追い掛けたカイネも目を見開いて、向こうで起きている状況が分からずに困惑していた。
「…やってくれましたね」
睨み付けると、信の口角がつり上がった。
焦げ臭い匂いと煙、そして遠くから聞こえる兵たちのざわめきや悲鳴に、李牧は待機している軍に向けて火が放たされたのだと理解する。
今頃、楚と趙の兵たちは大いに混乱しているだろう。密林に火が燃え移り、ますます火の手が大きく上がっていくのが遠目に見えた。
近くに川もない場所だ。消火作業は困難だということをあらかじめ想定した上で火責めを起こしたのだろう。
単独での行動ではなく、協力者がいたのだ。そうでなければあれほどの騒ぎになるほどの火災にはならないはずだ。
「…カイネ、急いで春申君殿の救援を」
「李牧様はっ?」
「すぐに追い掛けます。撤退の指揮も頼みました」
信と二人きりになることにカイネは納得出来ない様子でいたが、李牧が指示を取り消す気配がないことが分かると、頷いて駆け出して行った。
恐らくその気になれば李牧を出し抜いて、カイネの背後を斬ることも出来ただろうに、信は動き出す気配を見せない。
一騎打ちの申し出はなかったが、李牧を討ち取る状況を作り上げたことは間違いないだろう。彼女の背中には、秦国の印が刻まれているあの剣があった。
「…秦国でも、あなたが生きていると知っている者は限られていたはず。協力者は誰ですか?」
あれだけの騒ぎを起こすとなれば、協力したのは一人や二人の話ではないだろう。恐らく軍を動かしたはずだと李牧は睨んだ。
「元野盗で、性格は悪いが、それなりに気が合うやつらが居るんだよ」
「…桓騎軍ですか」
元野盗で秦将の座に就いたといえば、厄介な奇策を使う桓騎だ。下賤の出である者同士、気が合ったのかもしれない。
「…ここで私を討ち取れば、私の悪巧み自体を阻止できるはずだと?」
「山陽の戦いでの桓騎の奇策は聞いたことあるか?」
李牧の問いには答えず、信が質問を返した。
山陽の戦い。それは趙の三大天であったが、その後、魏将となったの廉頗と秦の蒙驁との戦いだ。
桓騎は敵本陣にいる軍師の玄峰を奇策を用いて討ち取ったという。
大胆にも敵兵に扮して、本陣へ潜入し、玄峰たちが油断したところを討ち取ったのだという話を聞いた。
馬陽の戦いで奇襲を掛けて来た信が用いた奇策と同じであることに、もしかしたらあの時の奇策も桓騎から授かったものだったのだろうかと李牧は考える。
ここで桓騎の話を持ち出すということは、恐らく今回もそうなのだろう。李牧は信と桓騎の狙いを理解した。
馬陽と山陽での戦のように、敵兵に扮して接近するという奇策を行ったとすれば、考えられる状況は一つ。
「同盟を組んだはずの合同軍が、秦じゃなくて趙を滅ぼすってなったら…面白いことになるだろうな」
意外にも、信の方から先に正解を教えてくれた。
「…趙を陥れるつもりですか」
何も言わずに、信が薄く笑んだ。
趙兵に扮した桓騎軍が待機している楚兵を殺し、火を放ったのだろう。
楚軍の反撃が起これば、もちろん状況の分からない趙軍も抵抗を行い、たちまち戦が始まる。小さな火種ががたちまち燃え広がったという訳だ。
丞相同士が会談をしている最中にそのような事態が起これば、ましてや楚の丞相である春申君がこの騒動で命を失ったとなれば、これは趙の陰謀だと楚国が誤解するのは必須。
さらには、既に会談を終えている国に、趙が楚を陥れたという報せが届けば、此度の秦を滅ぼす六国の合同軍に歪みが生じることとなる。
自分たちも趙に裏をかかれると警戒し、既に同盟を成している国からは追及の声が上がるだろう。もちろん此度の同盟を進めた丞相の李牧がその責に問われる。
それどころか、秦を滅ぼすために結成した合同軍が、趙に刃を向けることになるかもしれない。
自国に不利益を与えたどころか、滅ぼされる危機に晒したとして、今回の計画を企てた丞相・李牧の処罰が確定するという訳だ。
信の狙いが自分の首を持ち帰ることだとばかり思っていたが、完璧に裏をかかれた。
彼女が仲間たちから自分を遠ざけ、一騎打ちに持ち込もうと信じ切っていた失態だと李牧は悟る。
ここで殺さないのは、此度の騒動の責を李牧に押し付けるために違いない。
自分が手を下さなくても、趙を危険に晒した罪でその首を差し出さなくてはならないと睨んでいるのだろう。
春申君の身に何かあったとすれば、趙での処罰を待たずとも、楚軍が李牧の首を狙いに来るに違いない。
―――どちらに転んでも、李牧が殺されるという筋書きに繋がるという訳である。
彼女が死んだという誤報が李牧のもとに届いてから、全ては信が描いた筋書き通りに事が進んでいたのだ。
再会と罠 その二
「…お見事です、信」
素直に李牧は彼女に称賛の言葉を贈った。
少しも嬉しくないと言わんばかりに信が鼻で笑う。
「この計画はいつから?」
「お前が悪だくみを企んだ時からだよ」
この会談の場を設けるにあたっては最大限の警戒をしていたが、信の口ぶりと周到な準備から、事前に気づかれていたらしい。
秦将である彼女が討たれたという話は、意図的な情報操作だったのだ。
恐らく、彼女はその身を偽って趙に潜入していたに違いない。
戦では仮面で顔を隠していたことで、信の素顔は敵国に知られていない。趙で素顔を知っている人物は、秦趙同盟に訪れた李牧とその一行のみである。
それに、死んだとされる人間が敵国にいるなど、誰も信じないだろう。むしろ信は趙に潜入して、今日という機をずっと伺っていたに違いない。
大将軍の地位と品位を捨てて卑怯者に成り果ててまで、李牧と趙を滅ぼそうとしているのだ。
カイネに目的を問われて「時間稼ぎ」だと言ったのは、混乱の火種が消火出来ないほど大きくなるのを待っていたのだろう。
馬陽の戦いの時に、自分が使った言葉をそのまま返されたというわけだ。
「まさか亡霊になって、桓騎と組むとは思いませんでした」
信がにやりと笑う。
「ああ、一夜の極上の夢と引き換えにな」
予想外の言葉を聞いた李牧は目を丸めた。顎に手をやりながら、咎めるように信を睨む。
「それは感心しませんね。あの夜のように、伽を装って近づいた方が、簡単に私の寝首を掻くことが出来たかもしれませんよ」
李牧の言葉に、信がきっと目尻をつり上げた。
「ですが、あの時の伽で、油断させて私の首を掻き切ることも出来たでしょう?」
李牧が尋ねると、
「…何の話だ?」
口元から余裕の笑みを絶やさず、信はわざとらしく聞き返す。
秦将の信は死んだ。今目の前に立っている女は、同じ見目をしていても信ではない。あの日のことを知っているのは、この世でもう李牧だけである。
彼女の薄い腹に視線を向け、李牧は残念そうに肩を竦めた。
あの時、彼女の中に確実に子種を植え付けておけば、今頃は子を産んでいたのだろうか、自分の妻として今も隣にいたのだろうか。そんなことを考えたが、李牧は首を振った。
「…いいえ、こちらの話です。一度、あなたと見目がそっくりな女性を抱いたことがあるものですから。てっきりあなたが差し向けた刺客かと」
「知らねえな」
信は素っ気なく返した。
向こうで騒ぎがどんどん大きくなっている。火の手も広がって来ており、焦げ臭い香りがどんどん濃くなって来ていた。
カイネは無事に撤退の指揮を執れただろうか。李牧は自分の置かれている状況を十分に理解していたのだが、次なる行動を見出せずにいた。
その場から動き出さないでいる李牧に、信が小さく首を傾げる。
「どうする?秦趙同盟はまだ続いてんだろ?秦に泣きついて、二か国の合同軍で抵抗でもするか?」
「それも面白そうですね」
どうやら予想外の返答だったのだろう、信が目を見張った。彼女の裏をかくことが出来たようだと李牧が口角をつり上げる。
これから起こる出来事は、全て頭の中で描かれている。
ここまで信の策通りに進んでしまったのなら、どのみち李牧の命が狙われるのは明らかだった。
しかし、李牧は慌てる様子を見せず、むしろ冷静な態度を貫いている。
馬陽の戦いで飛信軍に本陣奇襲を掛けられた時も、彼は冷静さを欠かすことなく、龐煖と王騎の一騎討ちが終わるまで時間を稼ぐという選択をした。
「…どうして私が平然としていられるか、不思議ですか?」
「………」
信は何も答えない。しかし、彼女も馬陽の戦いのことを思い出したのだろう、李牧が冷静でいられる理由があるのだと気づいたようだった。
「あなたと同じで、私が卑怯者だからですよ、信」
先ほどの彼女のように、先に正解を教えてやる。
「ッ!」
自分を覆う影に気付き、信は考えるよりも先に後ろに跳んだ。
信が立っていた間に、大きな槍の斬撃が降って来る。李牧ですら数歩後ろに下がるほどの風圧が起きた。
地面が大きく抉れている。その場に信が留まっていたのなら、彼女の身体は無残なまでに切り裂かれていただろう。
顔に大きな切り傷を持つ、赤い外套に身を包んだ武神が、ゆっくりと立ち上がった。
再会と罠 その三
「龐煖ッ…!?」
武神の名を呼んだ信の顔に大きな動揺が浮かんでいる。王騎の仇が現れたことが信じられないといった表情だった。
「なんでここにッ…!」
背中の剣を鞘から抜きつつも、信が狼狽えているのは明らかだった。
李牧を孤立させることや、火を放つことで軍を混乱に陥れるのが目的ではあったものの、強大な戦力で対抗されるとは予想していなかったのだろう。
死んだはずの彼女が襲来するとは李牧も予想していなかったのだが、秦の襲来に備えて龐煖を待機させていたことで信の裏をかくことが出来たようだ。
今からこの状況を覆せるとは思わないが、彼女のその表情を見れただけでも李牧は満足だった。
「ちっ…」
さすがに龐煖と李牧の二人を同時に相手する訳にはいかないと、信が悔しそうにこちらを睨んでいる。
見たところ、信の方には救援が来る様子はなかった。
彼女の中では既に策は成したのだから、あとは逃亡するだけだったのだろう。
しかし、結果的に、龐煖が来るまで李牧が時間稼ぎをしたことで、彼女は逃亡せざるを得ないようだ。
「王騎の娘…!」
信を睨み付ける龐煖の目の色が変わる。王騎を討ち取ったはずなのに、彼は未だ王騎の幻影に苦しめられていた。
彼の養子である彼女とは初対面のはずだが、王騎の存在を連想させたのだろう、龐煖の顔が強張っていた。
二人がそれぞれ武器を構えて腰を低く降ろし、お互いを睨み合う。
「待って下さい」
意外にも、二人に水を差したのは龐煖の存在を用意していた李牧だった。
「ここは私が引き受けます。あなたは軍の救援を」
まさかそのような指示を出すとは思わず、信も龐煖も怪訝そうな顔をした。
ここで信を討ち取るのなら、龐煖と二人がかりで相手にした方が早い。それはこの場にいる誰もが分かっていることだったが、李牧はあえてそれをしなかった。
「………」
李牧の考えが読めないでいる龐煖が無言で視線を送っている。しかし、李牧は表情を変えることもせず、龐煖に救援に向かうよう促した。
やがて、龐煖が背中を見せて、密林の外へ向かって行ったのを見て、信は僅かに息を吐いた。
いつの間にか浮かんでいた額の汗を拭い、それから李牧を睨み付ける。
「あいつを下がらせるなんて何の真似だ」
窮地に陥っていたとしても、龐煖の武力があれば、ここで自分を討ち取るのは容易いことだっただろう。
それなのに、龐煖を仲間たちの救援へ向かわせた李牧の意図が全く分からない。
「…彼の力を借りるまでもなく、私一人で問題ないということです」
信がぎりりと奥歯を噛み締めた。
挑発するような言葉をかけるだけでなく、いつでも斬れと言わんばかりに李牧は信に背中を見せる。どうやら密林の外の様子を伺っているようだった。
「…ああ、どうやら撤退を始めたようですね」
楚軍と趙軍が無事に撤退したのか、騒ぎが遠ざかっているのが分かった。しかし、未だ密林に燃え広がっている火の手は止まらない。
卑怯者たちの未来
そろそろ退却しなくては、自分たちも火の手に飲み込まれてしまう。
しかし、李牧の心はまるで水の中にいるかのように、静かに落ち着いていた。
「…信」
李牧が振り返り、ゆっくりと歩み寄る。
信はその手に剣を構えてはいたものの、李牧を斬ることはしない。そして、それは李牧も分かっていた。
「あ…」
李牧の両手が信の身体を抱き締める。いきなり抱き締められたことで、信は驚き、硬直していた。
束の間、李牧は目を閉じる。
瞼の裏に、初めて彼女と出会った日のことや、身体を重ねたあの伽のことが浮かび上がった。
目を開くと、腕の中で信はあからさまに狼狽え、強張った表情を浮かべている。
しかし、腕を振り解こうとする素振りは少しも見せなかった。
「…、……」
戸惑いながらも、信の手がそっと李牧の背中に回され、着物を弱々しく握る。
彼女が自分と同じ想いでいるのだと知るには、その小さな仕草だけで十分だった。
「…李牧」
瞳にうっすらと涙を浮かべながら、信が名前を呼ぶ。
「趙の、宰相なんか…」
不自然に言葉が途切れたが、彼女が言わんとしている言葉の続きを、李牧は理解していた。
此度の信の策は、李牧の立場を奪おうとしてのことだ。信が一度死んで秦将ではなくなったと言い放ったように、宰相としての李牧も殺すつもりだったのだろう。
彼女が、趙国の宰相でない自分を求めてくれていたことを知り、李牧の胸が焼けるように熱くなる。
このまま彼女の手を引いて逃げてしまおうか。信が望んだ、趙国の宰相でない本当の自分を差し出そうか。
本音を胸の奥深くに閉じ込め、李牧は無理やり笑みを繕った。
「あなたが生きていて、本当に嬉しかったです」
信が何か言いたげに唇を戦慄かせていたが、それは言葉にはならなかった。
そっと彼女の頬に手を添えて身を屈めると、彼女の唇に己の唇を重ねた。柔らかい唇の感触を味わったのは、ほんの一瞬だけである。
「…これは趙の宰相ではなく、何者でもない、ただの独り言だと思ってください」
彼女の耳元に唇を寄せて、李牧が独り言を囁いた。
その言葉を聞いた信が弾かれたように顔を上げ、安堵したように笑う。その瞳にはうっすらと涙が浮かんでいた。
木々が激しく燃える音を聞きながら、卑怯者たちはもう一度、唇を重ね合った。
終
このお話の番外編・回想(桓騎×信)はこちら。