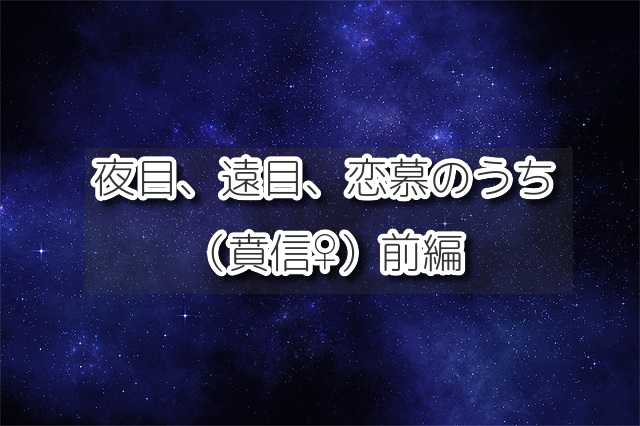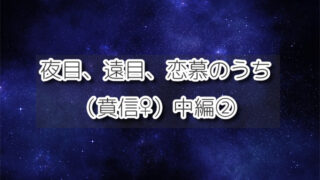- ※信の設定が特殊です。
- 女体化
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 王賁×信/シリアス/甘々/ツンデレ/ハッピーエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
宴の夜
その日は蒙恬の屋敷に招かれて、信は蒙恬と王賁と三人で小さな宴を行っていた。
楽しく酒を飲みながら先日の戦での武功を讃え合っていた時、小気味いい音を立てて王賁の手から杯が滑り落ちたので、信と蒙恬は反射的にそちらへ視線を向けたのだった。
「おい、大丈夫かよ」
幸いにも杯の中身は空だったので、着物を汚すことはなかったが、王賁が急に立ち上がったので、信は不思議そうに小首を傾げた。
「そろそろ失礼する」
「へっ?おい、もう帰んのかよ?」
驚いた信が王賁の背中を呼び止めるものの、彼は振り返ることもしない。
三人で同じだけの量を飲んでいたはずなのに、王賁は顔色一つ変えず、少しも酔いを感じさせないしっかりとした足取りだった。
立ち上がった蒙恬が廊下で待機している従者に声を掛けようとしたが、
「見送りはいらん」
「そう?」
きっぱりとそう言い放って客間を出て行ったので、蒙恬は興味を失くしたかのように、すぐに椅子へ腰を下ろした。
彼がもともと人付き合いが得意でない性格だと知っている信と蒙恬はそれ以上引き留めることはしなかったが、宴は盛り上がって来た最中だったこともあり、まだ物足りなさを感じてしまう。
「…残念だけど、俺たちだけで飲もうか」
蒙恬がそう言って杯を掲げたので、信は頷いて乾杯する。
「ん?」
杯を口につけようとした時、王賁が座っていた席に、きらりと光る何かが落ちていることに気が付いた。
それは鉱物の類で、透き通った青緑をしている美しい石だった。
手の平に収まるくらいの大きさで、赤い紐が括られている。石には小さく光が灯っていて、足元くらいなら照らすことが出来そうだった。
思わず手に取って眺めていると、蒙恬があっと声を上げる。
「蛍石だ。綺麗だね。賁の忘れ物?」
「ほたるいし?」
蒙恬曰く、どうやらこの光沢のある鉱物は蛍石というものらしい。
王賁は装飾品など一切興味のなさそうな男だが、これを持ち歩いているのだろうか。紐が括られていたが、着物にぶら下げていた訳ではなかったらしい。
別に忘れたところで、代わりならいくらでもあるだろう。しかし、彼は戦場を共にする相棒とも呼べる槍が刃毀れしても必ず修繕して使っているし、その点から考えると王賁はこだわりの強い男なのかもしれない。
さらには頑固な性格で、それ考えると蒙家に忘れ物をしたと言い出せずに諦めてしまうかもしれない。そして蒙恬が忘れ物をしたことをネタにして、後日に王賁をからかうかもしれない。
そうなれば自分も確実に巻き添えを食らうし、面倒なことになるのは目に見えていた。
「これ、あいつに届けて来る」
美しい蛍石を手に取り、信は今ならまだ王賁に追いつくはずだと席を立ち上がる。
頬杖をつきながら蒙恬が「信は律儀でいい子だねえ」と笑っていたが、信は構わずに部屋を後にしたのだった。
王賁の隠し事
もうすでに陽が沈んでいるので、柱に取り付けられている灯火器の明かりだけが廊下を僅かに照らしている。
正門へと繋がっている廊下を走っていると、向こうに王賁の姿が見えた。
「おい、王賁…っ!?」
背後から王賁に声を掛けようとした途端、鈍い音を立てて、王賁が柱に顔面から激突したのを見て、信は言葉を失った。
額を押さえながらよろめく王賁を見て、相当な激痛に悶えていることが分かる。
普段から生真面目で、滅多に表情を崩すことのない王賁の珍しい姿に、信は思わず噴き出しそうになった。
もしもこの場を見られたと知ったら、王賁は確実に逆上するだろう。痴態を見られたと自己嫌悪に陥るかもしれない。このことを蒙恬に告げ口をしたらますます怒りを煽ることになるのも分かっていた。
「っ…」
信は咄嗟に口元を押さえて柱に身を潜める。
客間を出る時もしっかりとした足取りだったので、少しも酒に酔っていないと思っていたのだが、もしかしたら相当酔っているのだろうか。
柱からそっと覗き込むが、どうやら王賁は信には気づいていないようだった。いつも気配には敏感な彼が珍しい。
「…?」
額の痛みが落ち着いた後、彼は柱に手を触れながら、ゆっくりと前に歩き出した。
客間を出る時とは違い、歩幅が随分と狭い。柱に触れることで道を確かめているような、どこか不自然な歩き方に信は違和感を覚える。
それはまるで何かを警戒しているような、気を抜けないでいるような歩き方で、普段から見ている王賁の堂々とした歩き方とは大いに違っていた。
「王賁っ!」
疑問を抱きながら、信は身を隠していた柱の陰から飛び出し、彼に声を掛けた。
信に気づいて王賁がこちらを振り返ったが、なぜか視線が合わない。
王賁が意図的に信から目を逸らしているのではなく、こちらは彼の視界に立っているというのに、彼は信の姿を探しているように顔を動かしていたのだ。
昼間はそんな様子はなかったので、さすがにこれはおかしいと思い、信は小走りで彼に駆け寄った。酔いのせいか、それとも額を強く打ち付けたせいかは分からないが、馬車に乗るまで付き添った方が良さそうだ。
「おい、大丈夫か?」
肩を掴んで声をかけると、まるで弾かれたように王賁が顔を上げて、ようやく目が合った。彼の瞳に僅かな濁りが見えて、信ははっとする。
「お前、もしかして、目が…」
言葉を遮るように、王賁が信の口を手で塞いだ。その勢いのまま、柱に体を押し付けられて身動きが取れなくなってしまう。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
「…誰かに話したか」
彼女の手に握られている蛍石を奪い取りながら、王賁が低い声を放つ。
口を塞がれたまま、咄嗟に首を横に振って否定したものの、王賁は疑いの眼差しを向けられたままだった。
「っ…!」
その時、首筋にひやりと冷たいものが押し当てられて、視線を向けると、短剣の刃が宛がわれていた。護身用にいつも持ち歩いているものだろう。
嘘を吐いたら容赦なく斬り捨てるという意志が伝わって来る。蒙恬と違って冗談を言う男でないことを信はよく知っていたし、味方であっても容赦なく斬り捨てることが出来る冷酷さは紛れもなく王翦の血を引き継いでいる証だ。
「……、……」
酒の酔いでほんのりと赤く染めていた信の顔が青ざめていく様子を、王賁は瞬き一つ逃さすことなく見据えていた。
しかし、嘘を吐いている様子はないと感じたのか、すぐに短剣が下ろされる。解放されたことに信は安堵の息を吐いた。
王賁に刃の切っ先を向けられることは初めてではないのだが、何度されても慣れることはないし、心臓に悪い。
「このことは誰にも話すな」
短剣の刃を鞘に納めながら、王賁は低い声で言い放った。もはやそれは命令で、信の意見など許さないという意志が込められていた。
「な、なあ、いつからだ?」
王賁の夜目が弱くなったことを知った信は、眉根を寄せながら尋ねた。
口の堅い彼のことだから答えてくれないと思っていたのだが、王賁は静かに瞼を下すと、
「…先の韓軍との戦で毒を受けた。その影響らしい」
「えっ?」
毒という言葉に、信が思わず驚愕する。王賁や彼が率いる玉鳳隊が毒で負傷したという報告は聞いていなかったはずだ。
戸惑っている信を見て、王賁が静かに言葉を紡いでいく。
…先の韓軍との戦は秦軍の勝利で幕を閉じたのだが、撤退する韓軍の追撃を王賁率いる玉鳳隊が行っていた。
韓軍の殿が玉鳳隊の追撃から免れようと、目を眩ますために黒煙を放ったのである。
玉鳳隊を先導し、殿と戦っていた王賁はその黒煙に目を負傷し、撤退を余儀なくされた。
すでに秦軍の勝利は確定したこともあり、殿からの反撃で撤退したことには特段問題はなかったのだが、どうやらその黒煙に毒の成分が含まれていたらしい。
咸陽に帰還してから、王賁と同じように黒煙を浴びた玉鳳隊の兵たちは毒で肺を蝕まれ、血痰を吐いた。遅延性の毒であったことから、時間が経過してから体に症状が現れたのである。
幸いにも優秀な医師たちが、毒の分析と解毒剤の調合を早急に行ったことで、犠牲は出なかった。毒を受けた者は今も療養を続けているが、快調へと向かっているらしい。
しかし、黒煙を目に受けた王賁の視力だけはどうにもならず、陽が沈むと、途端に視界が暗闇に包まれてしまい、明かりなしでは行動が出来なくなったのだという。
(だから…)
蛍石と呼ばれる鉱物を持ち歩いているのはそのためだったのかと信は納得した。
普段から蛍石を持ち歩いていたのは、太陽の光を当てるためだったのだろう。蓄光し、暗闇で発光させることで足元を照らし、毒にやられた目を補助していたに違いない。
今もなお、毒は王賁の目を蝕んでおり、日に日に視力が低下して来ているのだという。
自分の話であるというのに、まるで他人事のように淡々と語る王賁を、信は呆然と見つめていた。
「じゃあ…このまま、見えなくなっちまうのか…?」
「その可能性は高い。この距離でも、お前の顔がよく見えん」
手を伸ばせばすぐに触れられる距離にいるというのに、王賁の瞳には信の姿がおぼろげにしか映っていなかった。
柱に取り付けられている灯火器の明かりがあっても、昼間と違ってよく目が見えないのだと言われ、信は思わず唇を噛み締めた。
王賁の隠し事 その二
「…調合された毒は、韓の成恢が発案したものだそうだ」
韓の将軍・成恢は、自らを実験台として毒の調合を行うほど、毒を扱うことで有名な男であった。
合従軍戦で桓騎の策に陥れられ、秦の老将・張唐が討ち取ったのだが、どうやら彼が残していた毒の調合に関しての書記は今も韓で利用されているらしい。まさかこんな形で成恢の報復を受けることになるとは思わなかった。
「遅延性とはいえ、強力な毒だ。今さらあがいても意味はない」
「意味はないって…じゃあ、ど、どうすんだよ」
狼狽えた信が王賁に問いかけると、彼は至って冷静に首を横に振った。
「治療法がない以上、諦めるしかないだろうな」
「んな簡単にッ」
言いかけて、信は胸倉を掴まれた。
おぼろげにしか見えていないというのに、迷いなく手を伸ばしたのは、王賁の感情が波立ったからだろう。
「治る見込みもないというのに、何が出来る?」
その言葉は、信の胸に抉るような痛みを与えた。
治療法がない事実も、このまま視力を失うかもしれないという恐れに苦しんでいるのは他でもない王賁だ。
信が掛けた言葉は安易な同情ではないし、同じ将として幾度も戦場に立った王賁もそれは分かっていた。
しかし、治療法がない以上、どうしようもないのだ。
言葉にせずとも、王賁がそう訴えていることに、さすがの信も理解した。
だが、本当にこのまま彼が視力を失えば、将の座を降りることに直結してしまう。
「…?」
その時、胸倉を掴んでいる王賁の手が小刻みに震えていることに気が付いた。
感情の高ぶりによる震えではないと信が見抜いたのは、着物を掴んでいたその手が脱力するように滑り落ちたからだ。
反対の手も同じように震えており、握っていた蛍石が床に落ちてしまう。
(まさか…)
信は咄嗟に王賁の手を掴んだ。未だにその手は小刻みに震えており、しかし不自然な強張りを感じさせる。
指の曲げ伸ばしにも制限が掛かりそうな強張りに、信は先ほど王賁が杯を落とした時のことを思い出した。
落とした杯を拾おうともしなかったのは、すぐに帰るつもりだったからだと思っていたが、まさか手指にまで毒の影響が出ているというのか。
思わず言葉を失い、王賁の手を見つめる。彼は信の手を振り払う素振りも見せず、ただ口を閉ざしていた。
(そんな…)
黒煙に交じっていた毒は王賁の全身を蝕んでおり、視力だけでなく、握力にまで影響が出ている。もう王賁の体を蝕む毒は、容易には取り除けないほど深く根付いてしまっていたのだ。
このままでは将の座を確実に降りることになるだけでなく、命にも危険が及んでしまう。
どうやら王賁もそれを分かっているようだった。
何か方法はないのかと信は必死に思考を巡らせる。
「そ、そうだ!医師団に治療してもらおうぜ。俺が政に頼んでみる!」
「バカか、貴様」
考えた提案をまさか一蹴されるとは思わず、信は目を丸めた。
「治療法がないと言われたのに、今さら医師団を頼って何になる」
こんな状況でも普段通りの言葉を浴びせるのは、この後のことを受け入れているからなのか、それとも虚勢なのか、信には分からなかった。
「じゃあ、このまま何もしないでいるつもりなのかよッ」
つい声を荒げてしまい、信は慌てて口を閉じた。ここは蒙恬の屋敷で、誰が聞いているか分からない。
こちらの問いに何も答えようとしない王賁を見て、信は思わず唇を噛み締めた。
いつものように小難しいことを考えている表情ではあるものの、その瞳には哀愁の色が浮かんでいる。それが諦めだと察した信は、弾かれるように王賁の腕を掴んでいた。
「お前が何を言おうと、医師団に診せる。治療法がなくても、毒の進行を遅らせるくらいは出来んじゃねえのか!この国で最高の医者どもなんだぞ!?」
信の言葉を聞き、王賁は呆れたように肩を竦めた。
もう彼の中では微塵も希望など残っていないのだと分かったが、ここで素直に引き下がることは出来ない。
「今から咸陽宮に行くぞッ!政に頼んで医師団に診てもらう!」
信は王賁の腕を強引に掴んだ。
すぐにその手を振り解こうとするものの、毒のせいで上手く力が入らないのだろう、王賁は険しい表情を浮かべることしか出来ないようだった。
屋敷を出たところで待機してあった馬車に彼を押し込むと、信は御者に王賁の屋敷ではなく、宮廷に向かうよう指示をした。
まさかこんな時刻から宮廷へ行けと命じられるとは思わず、御者は驚いていたが、信が睨みを利かせるとすぐに馬を走らせる。
(…あ、蒙恬に何も言わないで行っちまったな)
せっかくもてなしてくれた蒙恬に何も言わずに出て来てしまったが、今度酒を奢って許してもらおうと考えた。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
宮廷へ
馬車の中では会話らしい会話をすることはなかった。
隣り合わせで座っていたが、特に王賁から文句を言われることもない。医師団の診察に希望を持っているようにも見えなかったが、何を言っても信が引く気配がなかったので仕方なく付き合ってやっているという気持ちが伝わって来た。
自分が出来ることといえば、親友である嬴政に事情を話して、医師団の治療を依頼することくらいだ。
医学に携わっていない自分に治療の手伝いは出来ないし、もしも医師団が匙を投げたとしたら本当にお手上げとなってしまう。
それでも、このまま何もせずに、王賁が将の座を降りるの黙って見過ごすわけにはいかなかった。
共に戦場に立ち、幾度も競い合い、今では安心して背中を任せられるようになった友を、決して捨て置けない。
毒を受けて視力が弱まっていることを他言するなと言った王賁は、恐らく重臣たちにしかこの件を伝えていないのだろう。
彼の父である王翦にも伝えていないのだろうかと考えたが、王賁の重臣がそのような事態を王翦に黙っている訳がない。いくら王賁が王一族の嫡男とはいえ、現当主の座に就いているのは王翦だ。
名家のしきたりだとかそういうことは少しも分からない信だったが、きっと親としての情くらいはあるだろう。王翦も医師を手配したり、何か気遣いを見せたのだろうか。
「なあ」
「父なら何も興味を示さなかった」
まるで信の疑問をあらかじめ想定していたかのように、王賁は冷たく言い放った。
王賁の言葉に、多少は予想していたものの、信は重い溜息を吐く。
父親がどういうものか、顔も名前も知らない戦争孤児の信だったが、王翦の無情さにはつくづく呆れてしまう。
将の座を降りなくてはならないどころか、命にも危険が及んでいるというのに、息子を心配する素振りも見せないなんて。
今度会ったら問答無用で一発殴ってやろうと考える信だが、その考えすらも見抜いたのか、王賁は呆れたように肩を竦めた。
「今の俺では、父の手駒にすらならん」
「おいっ」
まるで自分の命を軽視するかのような発言に、信はつい声に怒気を滲ませた。
あまり感情を表に出さない王賁だが、彼がそんなことを言うのは初めてで、まるで自暴自棄になっているようにも感じた。
睨みつけたものの、今の王賁にはきっと見えていないだろう。もし見えていたとしても、彼が睨み一つで怯むとは思えないが。
腕を組んでむくれ顔をしていたが、不意に瞼が重くなって来た。酒を飲んでいたので酔いが回り始めたのだろう。
宮廷に到着するまで、特に馬車の中でやることはないとはいえ、王賁の秘密を共有したというのに、このまま安易に寝入っていいものだろうか。
重い瞼を擦って何とか眠気を遠ざけようとするのだが、体は正直で欠伸がこみ上げて来る。なんとか噛み堪えるものの、その姿が見えているのかいないのか、王賁が顔を上げた。
「まだ宮廷には着かん。眠っていろ」
どうやら信が睡魔と戦っていることを勘付かれてしまったらしい。
自分から医師団に治療を受けさせると引っ張ったくせに、緊張感がないと思われただろうか。
気まずい視線を向けると、王賁は腕を組んで静かに瞼を下ろしていた。
もしかしたら彼も酒を飲んだせいで眠気を感じていたのかもしれない。王賁が眠るのならと、信も瞼を下す。信の意識はすぐに眠りへと溶け込んだ。
隣から静かな寝息が聞こえて来て、王賁は瞼を持ち上げる。
視界は相変わらず薄暗闇でぼやけているものの、信が眠っているのは寝息と気配で分かった。
まさか信に目のことを気づかれ、宮廷に行くことになるとは思わなかった。医師団の治療を受けさせるというが、もう治療法など残されていないだろう。試すだけ無駄だ。
だが、信の性格を考えると、医師団から治療法がないと言われない限り、きっと諦めないだろう。信がそういう女だと知っていたからこそ、王賁は彼女を諦めさせるために、今回の提案を飲んだに過ぎなかった。
「………」
左肩に重みが圧し掛かって来て、反射的に視線を向けると、眠った信が寄りかかっていた。
こんなにも密着しているというのに、王賁の瞳に彼女の寝顔が映ることはない。
しかし、気持ちよさそうに眠っているのだろうということは静かな寝息から想像出来た。これまでも彼女の寝顔を見たことは何度かあったが、まるで腹を満たした赤ん坊のような、何の不安も抱いていない寝顔であることを覚えている。
王賁は羽織を脱いで、眠っている信の体を包み込んだ。馬車の中とはいえ、夜は冷える。
毒に蝕まれた自分が風邪をひいたところで寿命を縮めるだけだし、それならまだ秦の未来を担う彼女のことを優先したい。
羽織を掛けてやった時に、また手の痺れが強くなっていることに気づき、王賁は溜息を飲み込んだ。
医者の話ではこのまま視力を失い、手も足も動かなくなり、やがては呼吸器官も麻痺していくだろうとのことだった。
遅延性の毒ということもあって、長く苦しみながら死に至るだろうというのは予想していたのだが、それならば早々に命を捨ててしまった方が楽になれるのではないかと考えた。
この苦しみを耐えた抜いたところで、待っているのが死という末路なら、今死んでも後で死んでも変わらないのではないだろうか。
そんなことを安易に口に出せば、きっとバカなことを言うなと信に殴られるだろう。
簡単に彼女の行動を予見出来るようになっている自分に気づき、王賁は思わず苦笑を浮かべた。
信が目を覚ました時には、すでに夜が更けていて、窓から朝日が差し込んでいた。瞼に突き刺さる白い光によって、意識に小石が投げつけられ、信はゆっくりと目を開く。
寝具を使わずに、どんな場所でも眠ることが出来るのは下僕時代に培ったものだ。しかし、体は痛む。
(ん?)
自分の体に青い羽織が掛けられていることに気づいた。それが王賁の羽織だと分かって、信は驚いて顔を上げた。体が冷えぬように気を遣ってくれたのだろう。
「………」
普段から口数が少ない彼の気遣いに、信はもどかしい気持ちを抱く。まだ眠っている王賁の顔をまじまじと見つめ、信は切なげに眉根を寄せた。
医学に携わっていないこともあって、何も根拠はないのだが、王賁が毒如きに負けるとは思えなかった。
(王賁…)
未だ眠っている王賁に羽織を掛け直してやり、彼の肩に頭を寄せる。
胸の底から湧き上がる不安が抑えられず、信は彼の手に自分の手を絡ませた。常日頃から鍛錬を欠かさないタコだらけの骨ばった手だと分かる。
「…大丈夫だ。絶対、助けてやるから」
思わず口を衝いたそれは王賁に向けた言葉でもあったし、彼を心配する自分自身を安心させるためでもあった。
「あ…」
握っていた手に力が込められ、思わず顔を上げると、王賁と目が合った。起こしてしまったのだろうか。
「お、わっ?」
慌てて離れようとしたが、急に肩を引き寄せられた。王賁の胸に顔を埋める形になり、突然のことに、信の心臓が早鐘を打つ。
てっきり問答無用で押しのけられると思っていたのに、抱き寄せられたことに信は頭に疑問符を浮かべていた。
しかし、自分を抱き締めている彼の両腕が震えていることに気づくと、信は堪らず彼の体を抱き締め返す。
その震えが毒によるものなのか、それとも死が迫りつつあることに対する恐怖なのか、はたまた両方なのかは信には分からなかった。
頼みごと
咸陽宮に到着すると、信は大急ぎで親友の姿を探した。官吏たちから嬴政が玉座の間にいると聞き、信は王賁を引っ張って廊下を駆け出す。
「放せ。ここは宮廷だぞ。無暗に走るな」
明るいうちは視力に問題はないと言っていたが、王賁が手を振り払わないところを見ると、手の痺れは不規則に起こっているらしい。
「ごちゃごちゃうるせえな!急がねえと」
信は王賁の手を離さないまま、玉座の間へと向かった。
見張りをしている兵たちも血相を変えた信の姿を見て驚いたものの、拝謁の届け出を出していなかったため、阻まれてしまう。
いくら親友とはいえ、秦王と対面するならば幾つもの手順を踏まなくてはならない。それがしきたりというものだ。
「頼む!通してくれ!政に話があるんだよッ!」
しかし、信はそんなもの知ったことかと言わんばかりに、大声で兵たちに懇願した。後ろにいる王賁も信の無礼としか言いようのない対応に呆れている。
「やかましい!大王様の御前で何事だ!」
兵たちが対応に困っていると、扉の向こうから昌文君の怒鳴り声が響いた。
「オッサン!俺だ!政がそこにいるんだろッ?頼むから話をさせてくれ!」
「その声、信か?」
内側から扉が開けられる。険しい表情を浮かべた昌文君が現れると、見張りをしていた兵たちが頭を下げた。
目が合うと、呆れた表情を浮かべた昌文君が通してくれた。
部屋に足を踏み入れると、玉座に腰かけて木簡に目を通していた嬴政が親友を見て、口角を持ち上げる。
「信、王賁、よく来てくれた」
前触れもなく押しかけたのは信の方だというのに、嬴政は彼女の無礼など少しも気にしていない様子で玉座から立ち上がった。
「突然の拝謁、申し訳ありません」
信に引っ張られた王賁が、即座にその場に膝をつき、拱手と共に謝罪を述べる。嬴政はすぐに顔を上げるように声を掛けた。
「気にするな。どうせ信に引っ張られて来たんだろう」
親友の無礼は今に始まったことではないと嬴政は笑った。信一人ならまだしも、王賁をこの場に連れて来たことに嬴政は急ぎの何か用があるのかと問いかける。
「医師団の力を借りてえんだ」
王賁が口を開くより先に、信が答えた。
「なにがあった?」
秦国一の医療技術を持つ医師団の存在を口に出したことに、聡明な嬴政は重病か重症の者がいるのかと感付いた。
「前の韓軍との戦で、」
これまでの経緯を信が説明しようとした時だった。
立ち上がろうとした王賁が苦悶の表情を浮かべ、その場に倒れ込んでしまったのである。
「王賁ッ!」
驚いた信が駆け寄って声を掛けるが、王賁は額に脂汗を浮かべながら歯を食い縛るばかりで返事も出来ないでいるようだった。
「しっかりしろ、おい、王賁ッ!」
肩を揺すって呼びかけ続ける。王賁が苦しむ姿を見て、嬴政も昌文君も驚いた様子で医師団を呼び寄せた。