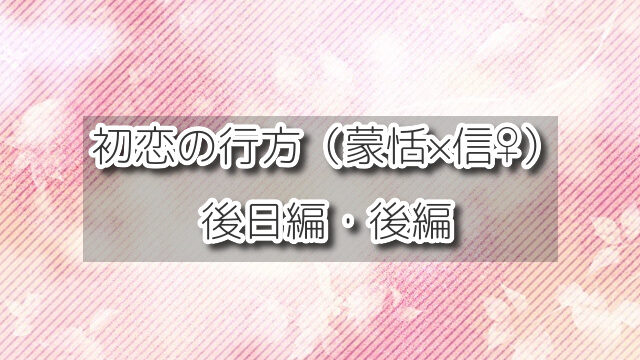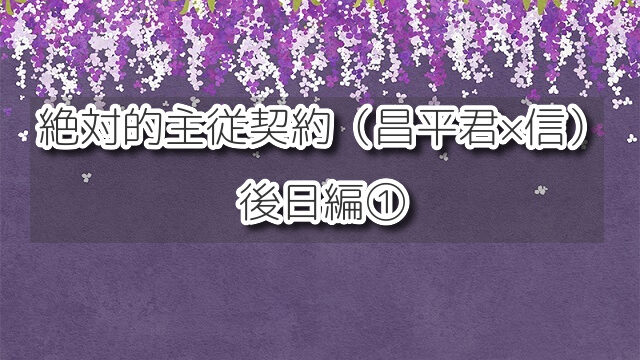- ※信の設定が特殊です。
- めちゃ強・昌平君の護衛役・側近になってます。
- 年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 昌平君×信/特殊設定/媚薬/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は本編の後日編です。
主の失態
(…やられた)
屋敷へと帰る馬車の中で、昌平君が吐いた溜息は深かった。
今日も今日とて呂不韋の外交に同席させられたのだが、まさか酒に薬を盛られるとは思わなかった。
呂不韋だけが楽しめばいいものを、なぜ毎度自分を巻き込むのだろうか。女付き合いに一切興味のない昌平君を、呂不韋は定期的に妓楼に連れていく。
妓楼の女性たちは強い香を焚きつけた着物を身に纏い、髪に艶を出すために桂花や茉莉花といった花の香油を塗っている者がほとんどだ。
さらには、肌を白く見せるために叩くおしろいにも、原料となる鉛白の独特な匂いが混じっている。
ただでさえ強い酒の匂いが堪えるというのに、妓女の人数が増えるごとにさまざまな香りが入り交じり、気分を悪くするのがいつもの決まり事だった。
そんなさまざまな香りを漂わせる妓女たちをいつも周りに侍らせるだけでなく、その肩を抱いたり、膝に頭を乗せたり、抱き締める呂不韋は、もしかしたらとうの昔から鼻が利かなくなっているのではないだろうか。
昌平君はもともとこういった店に興味はなく、女の一夜を買うつもりなどないのだが、呂不韋は大の女好きであり、こういう場には頻繁に足を運ぶのである。
昌平君がこういった華やかな場を苦手としていることは、呂不韋はよくわかっているはずだ。
一人で楽しめばいいものを、自分を誘うのは嫌がらせとしか思えない。断れば後々面倒なことになる。
何度か理由をつけて断っていると、有無を言わさず女の一夜を買わされそうになったことは、不快な記憶として刻まれている。被害を最小限に留めるためには、大人しく付き合うしかないのだ。
妓楼に連れて来られた昌平君の過ごし方といえば、呂不韋が妓女たちと談笑している傍で、静かに酒を飲むだけだった。
もちろん傍についた妓女が酒を注いでくれるのだが、会話らしい会話は一切ない。昌平君の周囲だけが切り取られた空間にいるかのように無音だった。
昌平君が右丞相であり、軍の総司令官という高貴な立場であることは妓女たちも分かっており、さまざまな話題を振ってくれるものの、赤の他人に宮廷や執務に関しての情報を洩らす訳にはいかず、答える気はないことと態度で示してしまう。
…となれば、妓女が振ってくる話題も限られてくる。
当たり障りのない世間話にはもともと興味がないし、時間の無駄でしかない。妓女たちと会話が発展することは一度もなかった。
隣では呂不韋と妓女たちの談笑が盛り上がっていき、やがていつものように部屋を移動する。彼は商人から今の立場まで実力で昇格するほど優れた頭脳を持っているくせに、酔いが回ると、女の温もりを欲するらしい。
呂不韋が妓女と席を立てば、ここに留まる理由はもうないと、昌平君も遠慮なく帰宅出来るのだが、今回は普段と違う点があった。
いつもは隣についた妓女が酒を注いでくれるのだが、なぜか今日は呂不韋が酒を注いだのである。
普段は自分のことなど忘れたように、妓女たちと楽しく談笑しているはずの彼が、自ら酒を注いでくれたことに、昌平君は違和感を覚えた。
何か企んでいるようだと警戒したものの、昌平君は疑うことなくその酒を飲み干してしまった。
酒を飲んだあと、呂不韋は普段通り妓女たちと談笑していたものの、時々こちらを振り返っては体調に変化はないか尋ねて来るので、昌平君は違和感を確信に切り替えた。
ここ最近は呂不韋からの誘いを断っていなかったのだが、一向に妓女と盛り上がらないでいる自分に妙な気遣いを起こしたのかもしれない。
このままでは、呂不韋の未だ明らかになっていない企み通りに事が進んでしまうと危惧した。
国政に関しての重要な執務があることを思い出したと切り出し、昌平君は呂不韋が呼び止めて来るのも無視して、早急に妓楼を後にしたのである。
この時すでに体に異変が起き始めていた。脈は早まり、酒の酔いとは違う、内側からじわじわと燻されるような火照り感があった。盛られたのは媚薬の類だろう。
妓楼についてから口にしたものといえば酒だけだ。そして普段と違うことがあるとしたら、呂不韋が酒を注いでくれたことだけである。
きっといつも通り酒を飲むだけの自分に、妓女の一夜を買わせようと呂不韋が酒に薬を仕組んだに違いなかった。
酒瓶を運んで来たのは、呂不韋と面識のない禿 であったことから、疑いなく飲んでしまったことが悔やまれる。
もしかしたら酒ではなく、酒を注いだ杯の方に細工をしていたのかもしれないが、どちらにせよ、気づかなかった自分の失態である。
呂不韋から逃げ切ったところで、口の中に指を突っ込んでみたものの、すでに症状が出始めていることから、酒と薬が体に吸収されてしまっていたようだ。吐き出しても効果は見られなかった。
吐き出しても効果がないのなら、大量に水を飲んでさっさと排泄するしかない。
待たせていた馬車に乗り込み、竹筒の水を飲み干すものの、移動中の馬車に備えてある水はこれだけだった。屋敷に到着するまでまだ時間はかかるし、そうなれば媚薬は完全に吸収されてしまうだろう。
呂不韋の企みを阻止できなかったことは腹立たしいが、今さら後悔したところでもう遅い。御者に急ぐよう指示を出し、昌平君は屋敷に戻ってからのことを考えた。
このまま帰宅すれば、確実に自分の駒犬である信を襲ってしまうと断言出来た。
屋敷に帰るのは遅い時刻になることは分かっていたので、先に眠っていろと伝えたが、従順なあの子は眠らずに待っていることだろう。
どれだけ眠くても、主が床に就くまで眠ることを駒犬自身が許さないのだ。
目を擦って、自分の帰りを待っている健気な姿を思い浮かべるだけで、昌平君はますます息を荒げた。
性欲に逆らえなかったという理由で、大切な駒犬に無理強いをさせるなど、飼い主失格だ。ならば性欲に打ち勝てば良いだけの話なのだが、一体どこで手に入れたのか、呂不韋が飲ませた媚薬はかなり強力なものだった。
「くそ…」
酒と共に飲まされたことで、早く効果が現れたのだろう。すでに昌平君の男根は着物の下で窮屈になっている。
時間が経てば薬も抜けるに違いないが、性欲は昂る一方だった。主からお預けを食らったときと同じく、どうしようもなくもどかしい。
「っ…」
拳を握って強く目を瞑り、なんとか性欲から意識を逸らそうと試みるものの、瞼の裏に浮かび上がるのは、やはり信の姿だった。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
主の失態 その二
「…!」
遠くから馬の蹄の音を聞きつけた信は、急いで屋敷の正門まで走り、馬車の姿を探した。
それまではほどよい疲労感と眠気に襲われて、重い瞼を持ち上げるのがやっとだったのだが、主が帰って来る気配を嗅ぎつけただけで眠気は吹き飛んでしまう。
呂不韋の外交(という名の妓楼での接待)は夜遅くまでかかるのだが、いつもよりも早い時間帯だったので、もしかしたら昌平君ではないかもしれないと不安を覚えたものの、物凄い勢いでこちらに向かって来る馬車は間違いなく昌平君が乗っているものだった。
二頭の馬に鞭を振るう御者の手つきを見て、よほど焦っていることが分かる。何かあったのだろうか。
馬車が正門の前で止まると、御者がすぐに屋形の扉を開けた。
「…?」
普段なら颯爽と降りて来るはずの主が出て来ないので、信は思わず眉根を寄せる。
気になって中を覗き込むと、昌平君は椅子に腰かけたまま、前屈みになって荒い息を吐いていた。
「!」
呂不韋の外交からこんなに早く帰宅したことは初めてだったのだが、もしかしたら体調が優れずに早急に帰宅したのかもしれない。
信はすぐに中に入り込み、昌平君の腕を自分の肩に回して何とか立ち上がらせた。
「…信、放せ」
荒い息を吐きながら、昌平君が信の体を押しのけようとする。
苦しそうにしているものの、意識があることに安堵しながら、信は主の言葉を聞き入れずに馬車を降りる。
許可を得ていない勝手な行動だという自覚はあったものの、こんなに苦しそうにしている主を前にして、命令を待つ訳にはいかない。罰なら後でいくらでも受けるつもりだった。
いつも送迎をする御者も、信が昌平君の命令がない限り、言葉を発せないことは分かっているので、すぐに家臣たちに声を掛けに屋敷へと駆け出した。
寝室へ続く廊下を歩きながら、信はわざと大きな足音を立て、壁を何度も叩いた。
それは主の命令がなければ言葉を発せない信の合図であり、長年連れ添っている家臣たちもその合図を聞きつけて次々とやって来る。
火照った顔と荒い呼吸を繰り返している当主の異変に気付き、家臣たちがあたふたと侍医の手配をしたり、刺客に襲われたのかと不安を露わにしていた。
…もちろん強力な媚薬を飲まされて悶々としているだけなのだが、それを知っているのは昌平君本人だけで、信を含め、家臣たちは当主の危機だと疑わなかった。
(まずいことになった)
膨れ上がる性欲に苦悶しているのは事実だが、家臣たちの慌てぶりを見て、思ったよりも大事になっていることに昌平君は危機感を抱いた。
あれよあれよという間に侍医の手配までしてくれたようだが、媚薬の効果を打ち消す薬などあるはずがない。これは自分との長い戦いであると昌平君は眉根を寄せた。
「…大事ない」
寝室に運び込まれたあと、家臣たちを安心させる言葉をかけてみるものの、誰一人として聞き入れてくれない。
普段は自分の顔を見れば考えていることを読み込んでくれる信さえも、一体何を言っているのだと疑惑の眼差しを向けており、少しも信じてくれそうになかった。
たしかに、こんな真っ赤な顔をして、荒い息を吐きながら「何ともない」と言っても説得力は皆無だ。頭では理解しているものの、他に伝える術がなかった。
…布団を被せられたおかげで、下半身の主張には誰も気づいていないのは幸いであった。
「酒に酔っただけだ。一晩眠れば治るだろう」
苦し紛れの言い訳だと自覚はあったが、酒を飲まされたのは事実だ。
しかし、呂不韋に妓楼へ連れて行かれたことは家臣たちも知っているので、酒に酔ったという当主の言葉を聞き、誰もが腑に落ちたような表情を浮かべる。
昌平君は飲酒を習慣にしていないものの、酒豪である旧友との定期的な付き合いがあるせいか、それなりに酒は強い方であり、酔い潰れることは滅多にない。
もともと華やかな宴の場を得意としないし、右丞相と軍の総司令という立場であることから早急に指示を仰がれることもあるため、軽い酔いを感じた頃に飲酒を中断するようにしている。
しかし、誘いを断れない呂不韋によって、普段よりも多く無理やり飲まされたのだろうと家臣たちは勝手に納得し、同情までしてくれた。
…自分のことを健気に心配してくれる家臣たちに少々罪悪感を覚えるが、事実を打ち明けたところで困惑させるだけだろう。
侍医は昌平君の触脈を行い、脈が速まっていることを指摘し、他の症状はないか問診する。頭痛や胸の痛みはないことを知って、命に別状はないと判断したらしい。
昌平君の主訴通りに酒の酔いだろうと誤診してくれたおかげで、下半身に起こっている異常については気づかれずに済んだ。
酔いを早く覚ますには、ひたすら水を飲んで排泄を促すしかないと、侍医は酔い覚ましの煎じ薬と大量の水を用意してくれた。
「心配するな。なにかあれば信を遣わせる」
家臣たちはいつ何時も主の傍から離れない駒犬の忠誠心を信頼しているので、昌平君の言葉を聞いて、ようやく部屋を出て行ってくれた。
主の失態 その三
「………」
家臣たちが部屋を出て行ってから、信は寝台に横たわっている昌平君に近づくと、首筋にあたりまで顔を近づけてすんすんと鼻を鳴らした。
酒に酔ったと言ったくせに、主の体から酒の匂いをあまり感じられなかったので、本当に酔っているのか疑っているのだろう。
酒を飲んだのは事実だが、量としては呂不韋に注がれた一杯だけだ。昌平君から酒の匂いがしないのも当然だろう。
信は医学に携わっていないものの、主以外の人間を見分けられない目を補っているのか(昌平君以外の人間は顔に靄が掛かって見えるらしい)、観察眼ならぬ観察鼻を持ち合わせている。
「……、…」
信が顔をしかめる。疑惑の眼差しが強まったのは、昌平君の嘘を見抜いたことを物語っていた。
心配しているというよりは、不快感を露わにしている嫌悪の色が見て取れた。着物に染みついていた妓女たちの香りが気に障ったのかもしれない。
昌平君が呂不韋の外交を断れないことを、信も理解しているものの、執務以外で自分以外の誰かが主の傍につくことが許せないらしい。
外交に行く度に駒犬が拗ねる理由が、そんな愛らしい嫉妬だったと知った日には何度体を重ねても足りないほどだった。
自分たちが身を繋げるのに、薬など不要だ。この愛おしさがあれば、一つになりたい気持ちなど無限に湧き上がるのだから。
「…呂不韋に薬を盛られた」
「!」
正直に白状すると、信がはっと目を見開いた。
「待て。行かなくていい」
すぐに侍医のもとへ向かおうとする彼の手首を掴み、昌平君は腕の中に閉じ込める。赤く火照った体に、自分よりも体温の低い肌が気持ちが良かった。
「……、……」
横たわる昌平君の体に圧し掛かるような体勢になり、信が困ったように眉を寄せる。これほどまで苦しんでいるのだから休ませてやりたいという気持ちもあるのだろうが、昌平君の両腕は信の体を離さなかった。
それに、何の薬を盛られたのか気になるようで、信の視線が狼狽えている。
「安心しろ。毒の類ではない」
命に別状はないと侍医も診察していたし、毒ではないと聞かされて安心したものの、信の視線はなにかに導かれるよう下がっていった。
「…!?」
密着していることで、硬く張り詰めているなにかが触れて、その正体に気づいた信がぎょっとした表情になる。
布団越しとはいえ、何度もその身に咥え込んだことのある主のそれに、信が気づかない訳がなかった。
言葉を発さずとも、表情を見れば信が何を考えているかなどすぐにわかる。彼は顔に表情が出やすいのだ。
自由に発言出来るはずの昌平君の方が、感情に表情が伴っていないせいで、何を考えているか分かりにくいと蒙恬から指摘されたのはつい最近のことであった。
「っ…!」
主の顔と下半身に視線を交互に向け、薬を飲んでいないはずの信の顔も、昌平君と同じように赤く染まっていく。主が媚薬を飲まされたのだと気づいたようだった。
何とか呼吸を整えようとするが、媚薬の効果はまだ切れそうになかった。しかし、このまま信と密着していると、性欲に負けてしまいそうだ。
普段は褥を共にしているが、今夜だけは別の部屋で休むように指示を出そうとした時、体を起こした信が布団を捲り上げたので、昌平君はまさかと顔をしかめる。
その予想は的中し、次に信は帯を解こうと手を伸ばしたのである。
「信、よせ」
駒犬の手を抑えようとするのだが、媚薬で火照る体は倦怠感も伴っており、普段よりも反応が遅れてしまう。
信は慣れた手つきで帯を解くと、無遠慮に着物を開いて、硬く張り詰めた男根の前に身を屈めたのだった。
切なげに眉根を寄せるその表情を見る限り、悪戯やワガママで困らせているのではなく、薬で苦悶している主を楽にしてやりたいという慈愛が見て取れた。
「信っ…いい加減に、」
やめさせようとしたのだが、媚薬で敏感になっている先端に温かく染み渡るような感触が走り、言葉が途切れてしまった。信が鈴口を掃くように舐め上げたのである。
「ん…」
柔らかい唇で先端をやさしく啄まれる。あたたかい口腔の粘膜に亀頭が包み込まれると、反射的に切ない溜息を零してしまう。
頭を動かしてゆっくりと咥え込み、優しい舌使いが陰茎を撫でつけた。男根が唾液塗れになったあと、信は一度唇を離して、陰茎を優しく握り込んだ。
亀頭部と陰茎のくびれ部分や裏筋のあたりを扱きながら、時折、熱い吐息を吹きかけられる。
「はあっ…」
雲の上を歩くような高揚感に、思わず喉が引きつり、腰が落ち着かなくなる。
こんなにも敏感になっているのは媚薬のせいだと理解しているものの、この調子では一度達したところで性欲は落ち着きそうもない。
もしも理性が効かなくなったら、大切な駒犬を乱暴に扱ってしまいそうで、昌平君は歯を食い縛って快楽を耐えた。
「信、もう放せっ」
余裕のなさを声と表情に出しながら、信の体を突き放そうとしたのだが、
「待て」
「ッ…!」
信から急に低い声で命じられ、昌平君は反射的に手を止めてしまう。
体が無意識で命令に従ってしまったその瞬間、二人の主従関係は本来のものに逆転するのだった。
「言い訳は聞かない」
僅かに怒気が含む低い声を向けられて、咄嗟に昌平君は頬を引きつらせた。
飼い主の立場に戻った信は、その口元に妖艶な笑みを浮かべる。男根を弄ぶ手指の動きにも淫蕩さが増したのはきっと気のせいではないだろう。
まず感じたのは、喜悦よりも危機感であった。
「…呂不韋の企みを見抜けなかったのは、たしかに私の責だが、決して間違いは犯していない」
喉から押し寄せて来たのは、主からの信頼を失われないための、事実を織り交ぜた主張である。
自分が呂不韋の外交を断れないことを信も分かってくれているはずだし、妓女と一夜を共にしてないことは、早急に帰還したことが何よりの証拠である。
むしろ自分は被害者で、あれは不可抗力だったと無実を訴えながら慈悲を乞う昌平君に、信の瞳がにたりと細まった。
こめかみに青筋が浮かび上がっているのは見間違いではないだろう。
「油断したお前が悪い」
慈愛に満ちた眼差しではなく、扇情的なその熱っぽい瞳を向けられて、昌平君はますます頬を引きつらせる。
躾なのか、仕置きなのか、八つ当たりなのか、それとも全てか。ともかく、昌平君は信の中の苛立ちを感じ取り、身の危険が迫っていることを察したのだった。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
少しざらつきのある舌腹で亀頭部を擦られたあと、尖らせた舌先が鈴口を穿るように突かれる。
「っ、く…」
情けない声を上げないように歯を食い縛る昌平君を、信がその瞳に喜悦を浮かべて、上目遣いで見つめている。
「ん、ん」
涎じみた先走りの液をちゅうと吸い上げると、信は頭を前後に動かしながら、陰茎に舌を這わせる。
「はあっ…」
唇が覆い被さって来て、あたたかい感触に包まれると、無意識のうちに熱い吐息を零してしまう。
口淫をしている最中に、頬にかかる髪を邪魔だと耳にかける仕草さえも昌平君の情欲を煽った。
性欲と感度が高まっているせいで、普段よりも早く射精の衝動が駆け上がって来る。
しかし、ここで安易に達してしまうなんて、男としての尊厳に傷がつく。恐らく信の狙いはそれだろう。油断して媚薬を飲まされた自分を行動で責め立てているのだ。
「く、…ぅ…」
主の思惑を阻止するために、顎が砕けそうになるほど歯を食い縛って、昌平君は吐精感を堪える。
自分が負けず嫌いな性格だと知ったのは、今のように本来の主従関係が戻った時、信に指摘されたからだった。
必死に吐精を堪える昌平君に、信が男根を咥えながら挑発的な視線を向ける。
普段は駒犬として大人しく従っているせいか、本来の主従関係に戻ると、信は本当の飼い主は自分であることを知らしめようと、やや威圧的な態度を取ることがある。まさに今がその時だった。
男根を口から離した信は、まるで玩具でも弄ぶかのように、指先で鈴口をやさしく突いて反応を楽しんでいる。そんな僅かな刺激にさえも、快楽の波として押し寄せた。
互いの唇が触れ合いそうな距離で、信は駒犬が苦悶する表情を見つめながら、男根を扱き続ける。
「っ…う、…くっ…」
血走った眼で見据えるものの、信の愉悦を煽るだけだった。
強弱をつけた刺激を与えられ続けていき、堪え切れないほどの大きな吐精感が押し寄せて来た時に、ようやく信は手を放してくれたのだった。
「はぁッ…」
安堵したのは束の間で、信は口淫を再開するつもりもなければ、もう男根に触れようともしない。
まさかと息を飲んだ昌平君から目を逸らし、信は興味を失くしたように立ち上がる。
「っ…!」
そのまま部屋を出て行こうとする信の手を掴んだのは、ほとんど無意識だった。
目が合うが、信は手を振り払うこともしなければ、新たな命令を下すこともしない。その表情に嫌悪の色が浮かんでいないことに安堵し、昌平君は掴んだ手を引っ張って、信の体を抱き締めた。
一言でも拒絶すれば、昌平君が従うしかないことを信も分かっているだろう。
それをしないということは、自分と同じで、きっと信も続きを期待しているのだと疑わなかった。
信は昌平君に跨ると、中途半端に脱がされていた着物の衿合わせに手を掛けた。
胸板を確かめるようにまさぐられ、昌平君はそれを合図に信の着物の帯を抜き取った。躊躇うことなく、唇を重ね合いながら、お互いの着物を脱がせ合う。
「ふ…ぅ…」
信の舌使いから焦燥感が感じられた。早く欲しいと訴えているのはすぐに分かった。唇と舌を絡め合うだけで、腰が蕩けてしまいそうになる。
着物を脱いで露わになった信の肌には、先日昌平君がつけた赤い痣がまだ残っている。体を重ねる度に、もっと信を欲してしまう。自分のものだと証を残したくなる。
駒犬という立場で烏滸がましいが、他の誰にも首輪と引き紐を渡さないでくれと懇願してしまうのだ。
それが醜い独占欲だというのは自覚しているが、気持ち一つで抑制出来るものではない。それほどまでに信の存在は、昌平君の中で強く根を張っているのである。きっと信も同じだろう。
「ん、っ…!」
上体を起こした昌平君は信の首筋に唇を押し付け、舌を首筋に這わせる。それから耳の中をくすぐるように尖らせた舌先をねじ込むと、信がぶわりと鳥肌を立てた。
「は、ぁ…ぁ…」
耳の粘膜をくすぐっているだけだというのに、信の体が小刻みに震え始める。
足の間にあるそれが褲 を押し上げているのを見て、昌平君は自分に跨っている信の肩を押しのけて、そっと寝台に横たえた。
「あっ、おいッ…!」
後ろに倒れ込んでしまった信が驚いているうちに、昌平君は褲を乱暴に脱がしてしまう。
自分と同じように、信の男根は硬く張り詰めていて苦しそうだった。駒犬の視線が下肢に向けられたことに気づいたのか、信は焦ったように口を開く。
「あっ、待っ…!」
命令されるよりも先に、昌平君はその男根を口に咥え込んでいた。
待てと命じられたならば、即座に手を止めなくてはいけないのだが、主から命令を下される前に動けばいいだけのことだ。
この手法を用いるのは初めてではない。ずる賢い知恵を得たものだと信から呆れられていたのだが、昌平君は構わなかった。
「んんっ…!」
陰茎の根元に指を絡ませながら、先端に舌を這わせると、信の体が仰け反った。すでに硬く張り詰めていた男根はあっという間に昂り切る。
すぐに「待て」が来ると思ったのだが、意外にも信は口に手で蓋をした。声を堪えるのは、従者たちに聞かれないようにするためなのだろうか。
「ぁっ…ん…!」
口の中で舌を動かす度に信の腰が震えた。
睫毛を恥ずかしげに伏せ、切なげに顔を歪める主を見て、昌平君はもっと乱れさせてやりたいと情欲を膨らませる。
主の失態 その四
頭を前後に動かして、口の中で信の男根を扱き始めると、信が大きく首を横に振った。
「だ、めだ…!待て…っ!」
口に蓋をしていた手指の隙間から、苦しげな声が零れる。主から待てと命じられた昌平君は諦めて口を離した。
身を捩って昌平君の下から抜け出した信は、彼の肩を乱暴に掴む。横になれという合図だった。
命令をされる前に行動を起こすのはやり過ぎただろうかと、内心反省しながら仰向けに横たわると、信が再び腰の上に跨って来る。
何をするのかと見据えていると、驚くべきことが起きた。
まだ後孔に触れてもいないというのに、信が昌平君の男根を咥え込もうとしていたのだ。
「信、待て」
今は自分が駒犬の立場だ。信に「待て」は通用しない。
しかし、慣らしもしていないのに、自分を欲していることによほど余裕がないことが分かる。何度も男根を腹に受け入れているとはいえ、入り口は狭いし、女と違って自ら濡れる機能を持っていないので、無理をすれば裂けてしまう。
昌平君が止めようとしたものの、すでに信は彼の男根をしっかりと掴んでいて、硬い先端を自分の後孔に導いた。
「ふ…ぅ…は、ああぅ…」
硬い男根の先端が後孔を押し入ると、信が溜息のような吐息を洩らす。
粘膜の温かい感触に包まれて、信がゆっくりと腰を下ろしていき、騎乗位の姿勢で男根を奥へと引き込んでいく。
潤み切った肉癖が蠢くように男根を包み込むこの感覚は、何度味わっても、男に狂気じみた快楽と喜悦を与えてくれる。
「うぅ、…ん…!」
男根を全て腹に咥え込むと、信がその瞳にうっすらと涙を浮かべていた。身を繋げると信はよく瞳に涙を溜める。その表情が男の情欲を煽ると知っているのだろうか。
「ふ、はぁ…ぁ…」
腹に咥えたばかりの男根が馴染むまで、信は呼吸を整えていた。
昌平君自身もまだ動くつもりはなかったのだが、ひとつ気になることがあり、ゆっくりを身を起こすと、信の腰を包み込むように優しく掴んだ。
女と違って自ら濡れることのない其処は、なぜか奥までよく濡れていた。いつもは固く口を閉ざしているはずなのに、入り口も中も、柔らかく男根を包み込んで来る。
「…私が帰るまで、自分で中を弄っていたのか?」
「ッ」
それはほんの些細な疑問だったのだが、信がぎょっとした表情で視線を左右に泳がせる姿を見れば、正解を聞かずとも理解した。
普段は中に唾液や香油で潤いを与えながら、時間をかけて存分に解してから挿入するのに、その手間を省いたのは、信自身が昌平君を受け入れる準備をすでに済ませていたからだったのである。
「ぁ…う…」
僅かな明かりだけが部屋を照らしているというのに、信が湯気が出そうなほど顔を赤らめているのはすぐに分かった。
呂不韋の外交に行くたびに、信は必ずと言っていいほど不機嫌になる。昌平君が誘いを断れないことも知っているので、苛立ちをぶつける先がなく、態度に出てしまうのだろう。
自分の帰りを待ちながら、どんな気持ちで後孔を弄っていたのだろう。
情欲に負けて淫らな行為に耽るだけではなく、きっと自分のことを考えていたに違いない。
信の心情を想像するだけで、昌平君は莫大なる優越感に陶酔する。酒の酔いとは比べ物にならいほそ、気分の良い酔いだった。
「寂しい想いをさせたな」
口角がつり上がりそうになるのを堪えながらそう言うと、それまで顔を赤らめていた信が急にむくれ顔になった。
「わかってる、…から…」
一人でいるときの不安や寂しさを押し隠そうと平静を装っている姿に、昌平君の胸は締め付けられるように痛んだ。
しかし、信も昌平君の立場を理解しており、自由に発言が許される飼い主の立場に戻ってもそれを訴えることはない。
普段は駒犬としての責務を全うし、気丈に振る舞って見せるものの、それはただの虚勢だ。
呂不韋の誘いを断れないとはいえ、寂しい想いをさせるだけでなく、我慢までさせてしまっていることに、昌平君は改めて罪悪感を覚えた。
「信」
「あ…」
繋がったまま、両腕でしっかりと信の体を抱き締めて肌を密着させる。犬らしく頭を摺り寄せると、信が少し躊躇いながら頭を撫でてくれた。
上目遣いで見上げると、信は恥ずかしそうにしながらも、両手で頭を抱き締める。視線が絡まり合い、引かれ合うように唇を重ね合った。
「ん、ぅう、んっ」
唇と舌を絡ませながら、信は腰を前後に動かし始めた。ぐずぐずに蕩け切った媚肉が男根を締め付けて来る。何度も繋がったことで自分の形を覚えて、嬉々として締め付けて来るのだと思うと、ますます男根が熱く昂ってしまう。
「ふあ、あぁ…」
腹の内側を擦られ、気持ちよさそうにうっとりと目を細める。口づけをしながら、夢中で腰を動かしているせいか、息が続かず、信は体を慄かせた。
「はあっ、ぁ、んっ、ぁあっ」
前後に動かすだけでは物足りなくなったのか、今度は寝台に足裏をつけて腰を上下に揺すり始める。寝台の軋む音に、信の喜悦交じりの嬌声が混じった。
動けという指示をされない以上、昌平君は主に身を任せるしかないのだが、あまりの気持ち良さに頭の芯までもが痺れて来る。
もうこれ以上ないほど信のことを求めているというのに、淫らな姿を目の当たりにするだけで、ますます情欲が駆り立てられる。
首輪と引き紐だけじゃ足りない。このまま体だけでなく、本当の意味で一つになってしまいたいという恐ろしい気持ちが膨れ上がっていく。
頭の中でふつりと何かが切れた音がして、気づけば昌平君の両手が信の腰をしっかりと掴んでいた。信の腰の動きに合わせて、下から突き上げるように腹の内を穿つ。
「あッ、また勝手に…!」
命令を出していないのに勝手をする駒犬を叱りつけるように、信が目をつり上げた。腰を掴む両手を外そうとするものの、奥を抉ってやると、手指から力が抜けてしまう。
快楽に打ちひしがれる主の姿に、もう制御が効かなくなってしまい、昌平君は勢いのまま信の体を押し倒した。
「悪く思うな」
薬のせいだと言い訳がましい謝罪をし、昌平君は獣のように腰を前に突き出した。
「んううっ、あ、んっ、はあっ」
喘ぎ声と共に、熱い吐息が鼻を抜けた。切羽詰まったその声さえ、昌平君の欲望を煽る。
「っ…!」
息を止めて怒涛の連打を送り込むと、腕の中汗ばんだ体が大きく仰け反った。
「あっ、も、もう…、――ッ!」
焼いた鉄でも押し当てられているかのように、信が必死の形相で身を捩る。内腿を生暖かいものが濡らす感触があって、絶頂を迎えたことが分かった。
連動するように男根を痛いくらいに締め上げられる。絶頂の余韻に打ち震える信の体を抱き押さえながら、頭の芯まで快楽が突き抜ける。
「くッ…」
熱い粘液が男根の芯から駆け上がって来る。目が眩んでしまうほどの衝撃に襲われ、信の腹の内に熱い精を注いだ。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
飼い主と駒犬の失態
熱い子種が腹に注がれるのを感じながら、信は絶頂の余韻に浸りながら息を整えていた。
自分の苗床でその子種が実ることはないが、自分の体で昌平君を絶頂に導くことが出来た何よりの証であり、幸福だと感じる。
今も腹の内に昌平君の男根を感じながら、信は静かに目を伏せた。
「…信、大丈夫か?」
幸福感で胸が満たされると、なぜか涙が溢れてしまう。涙を流す信を見て、心配そうに昌平君が顔を覗き込む。
媚薬を飲まされて苦しい想いをしているのは昌平君の方なのに、こんな状況でも自分の心配をする駒犬に、信は胸が締め付けられた。
「っ…」
昌平君の頭を掻き抱き、信は腰に脚を絡ませる。
自分こそが昌平君の飼い主だというのに、駒犬を演じる期間が随分と長かったせいか、甘える方が得意になっていた。
「…ん?」
吐精して少し萎んだはずの男根が、また腹の内側を押し広げるように硬くなったのを感じ、信は思わず目を開いた。
咄嗟に昌平君が目を逸らしたのを見ると、どうやら勘違いではなかったらしい。まだ媚薬の効果は健在なのだ。
気まずい沈黙が二人の間に横たわるものの、信は昌平君の体を押しのけることはしなかった。
「…ははっ、仕方ねえな」
諦めたように信が笑い、昌平君の背中に回した腕に力を籠めた。
「………」
目が合うと、昌平君から許しを強請るような眼差しを向けられる。
絶頂を迎えたばかりでまだ息も整っていないこともあって、随分と余裕のない表情だった。昌平君のこんな弱々しい姿は自分しか知らないだろうと思うと、優越感を覚えてしまう。
「…良いぞ」
信が許可を出すと、昌平君は止めていた腰を再び動かし始めるのだった。
媚薬の効果が消えるまで、今日は終わらないだろう。
そんなことになれば二人とも起きられなくなって執務が溜まり、困るのは昌平君自身だというのに、信も湧き上がる情欲を抑えられなかった。
…結局、朝方まで行為が続いたのは、媚薬の効力がそれほど強力だったのか、それとも媚薬の効力が消えてもなお、駒犬の性欲が消退しなかったからなのか、気を失うように寝入ってしまった信にはわからなかった。
終
おまけ後日編「~好敵手の失態~(昌平君×信←蒙恬)」(7900文字程度)はぷらいべったーにて公開中です。
このシリーズの番外編①はこちら(昌平君×信←桓騎・現在連載中)