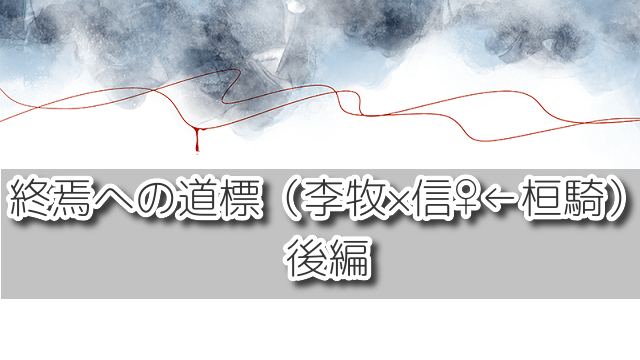- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 昌平君×信/ツンデレ/ミステリー/IF話/ハッピーエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は軍師学校の空き教室の後日編(恋人設定)です。
芙蓉閣:咸陽にある信が立ち上げた保護施設。戦争孤児や行く当てのない女子供を保護している。元は王騎と摎が住まう予定の民居だった。名前は王騎が生前好んでいた花から信が名付けた。
燈:芙蓉閣に保護された女性。現在は芙蓉閣に住まう女性たちに織り子の仕事を教えながら、まとめ役を担っており、信からの信頼も厚い。商人の夫がいる。
宸:芙蓉閣で失踪した男児。芙蓉閣に保護された戦争孤児で、信を姉のように慕っており、飛信軍に入ることに憧れていた。
涵:芙蓉閣で生まれた少女。宸の妹のような存在で、失踪した彼の行方を案じている。手先が器用で織り子の仕事を手伝っている。
肖杰:太后が後宮権力を思うままに操っていた時代に、後宮に務めていた宦官の医者。後宮を追放され、現在は咸陽で街医者として働いている。民たちから慕われており、芙蓉閣の出入りも許されている。
生還
目を覚ますと、最初に覚えたのは喉の渇きだった。
「う…」
寝台の近くにある水差しを取ろうとして、上体を起こすと手首に引き攣るような痛みが走る。右の太腿にも鈍い痛みがあった。
手首に包帯が巻かれているのを見て、信の頭に目を覚ます前の記憶が一気に雪崩れ込んで来た。
部屋は薄暗く、寝台の近くに蝋燭の明かりが灯っていた。
「目が覚めたか」
寝台の傍にある椅子に座っていた昌平君が、木簡に目を通しながら声を掛ける。
「…俺…」
薬を嗅がされたことで喉を腫らされて、声が出せないようにされていたのだが、あれから時間が経ったからなのか、ようやく声が出るようになっていた。
木簡を手にしたまま立ち上がった昌平君が寝台に近づき、信に水差しを手渡す。受け取って水を飲むと、乾き切っていた喉がつんと沁みた。
喉の腫れは引いたようだが、まだ少しだけ違和感が残っている。きっとこの違和感も時間が経てば消えるだろう。
「肖杰は…?」
「然るべき場所へと送った。あの屋敷の庭から、子供たちの亡骸も見つかっている。あとはお前の証言が揃えば、すぐに罰せられるだろう」
端的に答える辺り、肖杰へ慈悲を掛けることは一切しないようだ。
「そっか…」
寝台に倒れ込み、信はぼうっと天井を見上げる。見覚えのない部屋だと気づき、信は目だけ動かして昌平君を見た。
「そういや、ここは?」
「芙蓉閣の一室だ」
昌平君がここまで運んでくれたのだろうか。
意識を失った自分の手当てもしなくてはならず、かといって肖杰の診療所に留まる訳にもいかなかったのだろう。
診療所からそう遠くない距離にある芙蓉閣ならば、二人とも顔が利く。信の救援に駆け付けたのは昌平君と彼の近衛兵たちだけでなく、救護班も同行していたのだという。
救護班による手当てを受け、今は芙蓉閣の一室で眠っていたという訳だ。
「手当ても終わって寝てるだけなんだから、わざわざ付き添わなくても良かっただろ」
「………」
指摘すると、昌平君は聞こえないフリをしているのか、黙って木簡に目を通している。二人きりしかいない密室で聞こえないはずがないのにと信は苦笑した。
右丞相や司令官、軍師学校の指導者など多くの執務を抱えている昌平君は、屋敷に帰るよりも宮廷で寝泊まりをすることが多かった。
本来ならこの騒動は、右丞相として優先するようなものではない。捕史たちに犯人探しを命じるだけで、昌平君自らが出る必要などなかったのだ。
「………」
しかし、信の瞼の裏に、肖杰に殺されそうになった寸前で駆け付けてくれた昌平君の姿が浮かぶ。
他の誰でもない自分のために、彼は駆けつけてくれたのだ。
「…ありがとな」
先ほどよりも声を潜めたというのに、礼の言葉はしっかりと耳に届いたらしい。昌平君は顔を上げると、持っていた木簡を信に手渡した。
彼の手を借りながら、信はゆっくりと上体を起こす。蝋燭の明かりに目を凝らし、木簡の内容に目を通した。
「これは…」
信の瞳が驚愕のあまり、見開く。
渡された木簡には、肖杰が犯した罪について記されていた。
「後宮にいたんじゃなかったのか?」
彼は医者という職に就いているものの、後宮には務めていなかった。宦官になるために去勢をされたのではなく、宮刑によって去勢されたのだ。
宮刑とは、男は去勢、女は監房への幽閉のことを指す。子孫を残せないという意味では、死刑に次ぐ重罰とも言われている。
さらに驚いたのは彼の罪状だ。それは他ならぬ母親を自らの手で殺めたというものだった。
動機についてまでは記されていなかったが、身内を殺した罪により、宮刑に処されたらしい。
信は顔を上げると、狼狽えた表情で昌平君を見た。
「で、でも、あいつ、年老いた母親がいるって……」
「………」
何も言わずに昌平君が首を横に振った。言葉のないその返答に、信は全てを悟る。母親を自らの手に掛けたことを、肖杰は覚えていないのだろう。
「すまなかった」
昌平君の謝罪の理由が分からず、信が目を丸める。
「お前には奴隷商人に目をつけていると告げたが、私は初めからこの男に目をつけていた」
「はっ?な、なんで…」
予想もしていなかった言葉に、信はただ驚愕することしか出来なかった。
「芙蓉閣と関わりを持つ者の中で、前科がある者に限定すると、この男が一番に浮上したからだ」
「………」
「宮刑まで受けた者が、素直に心を入れ替えて生き長らえているとはどうしても思えず、色々と探らせていた」
信の手から木簡を受け取り、昌平君が言葉を紡いでいく。
「…当時のことを知る者から報告を聞くと、肖杰には妻子がいた。しかし、流行り病で二人は亡くなり、それからは年老いた母親と二人で暮らしていたそうだ。あとは記されている通り」
「…そうか」
肖杰は妻子を失ってから、すでに狂っていたのだ。だからこそ、母親も手に掛けてしまったのだろう。
「あの迷信についても、執念深く調べているという報告を受けていた。だが、調べているという情報だけで、容易に屋敷へ踏み入ることも出来ず、様子を伺っていた。…無理やりにでも押し通っていれば、子供たちの犠牲も防げたかもしれない」
本人も狂っているという自覚がなかったのだから、本性を見抜けないとしても無理はない。
信が無理やりにでも彼の屋敷に侵入しなければ、子供たちが殺された証拠は見つけられなかっただろう。
彼が後宮に務めていたのも嘘だと分かったが、男としての生殖機能がないのは宦官として働いていたからだと伝えれば、誰も宮刑を受けた罪人だとは思うまい。
表向きは多くの民から慕われる医者として、しかし、罪を犯したことで彼は苦しんでいた。
妻子を失ったことから気が狂い、自分が殺したはずの母親も死んでいないと思い込み、子孫を残すためにと、あの迷信を信じて子供たちを殺し、その臓器を喰らった。
境遇には同情するものの、これだけの罪を犯した彼の死刑はもう免れないだろう。
お守りの絹紐
「すまなかった」
もう一度謝罪すると、昌平君は静かに目を伏せた。今回の件で彼に謝罪をされるのは何度目だろうと信は複雑な表情を浮かべる。
初めから肖杰を警戒しておくよう忠告していれば、信があのような危険な目に遭うことはなかったのだと、昌平君は悔恨の念に駆られているらしい。
「…いいって。もうこれ以上の被害が出ることはないだろ。お前のお陰で助かった」
信が笑顔でそう言うと、少しは救われたのか、昌平君もどこかほっとした表情を浮かべる。
「でもよ、本当によく来てくれたよな」
信が肖杰の屋敷に行くことは昌平君も知っていた。しかし、まさか近衛兵である黒騎団を率いてまで救援に来てくれるとは予想外だった。
「…もともと、私も黒騎兵と共に、肖杰の屋敷に踏み入る準備をしていた」
「え?そうなのか」
芙蓉閣で信と別れた後、昌平君はいよいよ肖杰の調査に本腰を入れるつもりだったらしい。
それまでは様子を見ているばかりだったが、涵から他の子供たち肖杰の屋敷を出入りしているという情報を聞き、昌平君もいよいよ肖杰の屋敷へ踏み入れることを決めたのだという。
肖杰に前科があることから犯人だと疑っていることを信に伝えれば、彼女は証言欲しさに肖杰を刺激してしまうかもしれない。
人攫いの可能性として、奴隷商人の調査をしていたことは本当だが、昌平君は意図的に彼に前科があることを信には告げなかったのだ。
万が一にも彼を刺激しないようにという気遣いが裏目に出てしまった訳だが、結果としては肖杰を捕らえることが出来たし、子供たちを弔うことが出来た。
黒騎兵たちと共に屋敷に乗り込むのがあと少しでも遅れていれば、確実に信は殺されていただろう。
それを思うだけで昌平君は背筋が凍り付きそうになった。しかし、その不安を信に告げることはしない。
「…これが正門の前に落ちていた」
着物の袖に手を入れて、昌平君が青い絹紐を差し出した。
草木染という手法で美しく青色に染まった絹紐は、涵が作ってくれたのと同じ物である。
「え?あれ…落としてたか?」
青い絹紐を受け取り、信がきょとんと眼を丸めた。
「俺のは、駿の手綱に結んでおいたはずだ。…それに、俺は裏門から入ったぜ?」
「なに?」
怪訝そうな顔で、昌平君が信の手の中にある絹紐に視線を落とした。
信が最初に肖杰の屋敷を訪れた時は、確かに正門から入った。
しかし、再度侵入を試みたのは裏門で、絹紐は駿の手綱に結び付けていたし、正門にこの絹紐を落とすはずがなかった。
それに、絹紐とはいえ、鮮やかな青色が目を引く代物だ。落ちていたとすれば絶対に気づくだろう。
「これは…」
昌平君が拾った絹紐をよく見ると、赤黒い染みがついており、それが血だとすぐに分かった。
正門前に落ちていたこの絹紐を見るなり、昌平君は信が危険に晒されているのだと察知して屋敷に飛び込んだのだという。
自分の手の中にある青い絹紐を、信はもう一度よく見返した。
―――宸のお兄ちゃんにも、お守りで同じのあげたの。だからあげる。
この絹紐を受け取った時の涵の言葉を思い出す。
まさかと信は目を見開いた。
「これ、宸の…絹紐か?」
肖杰に殺された子供の名前が出たことに、昌平君が眉根を寄せた。
「…なぜあの場に落ちていた?」
宸が失踪したのは一週間ほど前のことだ。今になって彼の持ち物が出て来たことに、二人は疑問を隠せなかった。
―――先生!お願いです!どうか診て下さい!
―――先生ッ、お願い!開けて!
肖杰に殺されかけた時、屋敷の門を叩いて急患の診療を頼む子供たちの声を思い出した。姿は見えなかったが、あの声はどちらも少年のものだった。
ちょうど屋敷に来た昌平君たちと、その少年たちが入れ違いになったかもしれない。信は何となく、その少年のことが気になった。
「そういや、屋敷の敷地内か周辺にガキはいなかったか?ちょうど昌平君たちが来る前に、肖杰が追い返すか診療をしてたはずだ」
少し考える素振りを見せてから、昌平君は首を横に振った。
「…いや、そのような者は見ていない。屋敷に出入りする者も、敷地内にも誰も居なかったはずだ」
「………」
その言葉を聞いて、信は手の平にある絹紐に視線を落とした。
肖杰の屋敷に一度訪れ、手がかりがないことに肩を落としながら帰ろうとした時、門の向こうに子供たちの姿を見た。
あの時は見間違いだろうと思っていたが、まさか宸たちは、命を失ってからもあの屋敷でずっと自分のことを待っていたのだろうか。
「っ…!」
もしかしたら、自分を助けるために門を叩いて肖杰の気を引いたり、昌平君にこの絹紐を渡して居場所を知らせてくれたのかと思うと、信の瞳にみるみるうちに涙が溢れて来た。
都合の良い解釈かもしれないが、自分に懐いていたあの子たちならやりかねないと思えた。
赤黒い染みを見つめ、宸や他の子供たちが一体どれだけ苦しんで殺されたのだろうと考える。
助けてやれなかった自分を恨むどころか、肖杰から自分を助けようとしてくれた子供たちの気持ちを想うと、胸が引き裂かれそうになる。
「……バカなこと言ってるって自覚はあるんだけどよ…」
鼻を啜りながら、信が青い絹紐に視線を下ろしたまま言葉を紡いだ。
「俺、あの屋敷で、ガキどもを見た気がするんだ」
「………」
何も言わずに昌平君はじっと話を聞いていた。
「殺されそうになった時、門を叩いて、肖杰を呼ぶガキ共の声がして…俺を、助けようとして、くれたのかも…」
青い絹紐を握りながら涙を流している信を見て、昌平君がそっと体を抱き締めてくれる。
「う…ぅうッ…!」
彼の胸に顔を埋め、信は堰を切ったように溢れ出る涙を流し続けた。
添い寝
ようやく涙が落ち着いた頃には、昌平君の着物が涙で湿ってしまっていた。
「あ、あの、悪い…」
真っ赤に充血した目で見上げるが、昌平君は何も気にしていないようだった。
「落ち着いたか」
穏やかな声色を掛けながら、昌平君が信の目元を指でそっと擦ってくれる。
泣き続けて腫れ上がった目元には、彼の指はひんやりと冷たくて気持ち良かった。
気の利いた言葉を掛けられなくても、ずっと傍にいてくれる彼の優しさが、信には嬉しかった。
「今夜はもう休め」
そう言って昌平君が寝台の上から立ち上がったので、信は戸惑った視線を向けた。
「宮廷に戻るのか?」
「いや、朝になったらここを発つ。今回の件の事後処理が残っているからな」
昌平君は信が目覚めるまで座っていた椅子に再び腰を下ろした。
肖杰の罪が記されている木簡を再び開きながら昌平君がそう答えたので、まさか彼は朝までそこで過ごすのだろうかと驚いた。
「他に客間があったはずだ。寝るならそこで…」
「案内人から聞いている」
燈のことだろう。客間で休むよう言われていただろうに、昌平君は信が寝つくまで傍にいてくれるらしい。
言葉に出さないが、先ほどのようにずっと抱き締めてくれていたように、彼の優しさが心に染み渡った。
「ん…」
傷に響かないようにゆっくりと寝台に横たわった信は、身体を端に寄せる。これでもう一人分の寝床が確保できた。
「昌平君」
もうとっくに覚えたであろう内容が記されている木簡に目を通していた昌平君が顔を上げる。
「ん」
ぽんぽんと寝具を叩いて呼び寄せると、昌平君は無言のまま何度か瞬きを繰り返した。
「…大人しく寝ていろ」
わざとらしく溜息を吐いていたが、木簡を折り畳んだのを見ると、信の誘いに応じてくれるようだ。
ゆっくりと昌平君が寝台に横たわると、彼の胸に頭を摺り寄せ、信は目を細めるようにして笑った。
「へへ、あったけえな」
「………」
昌平君がそっと頭を撫でてくれる。彼の方が年上なのはもちろん分かっているが、こうしていると、恋人ではなくて、まるで子供扱いされているような感覚になる。
無性に恥ずかしくなって、信は彼の手首を掴もうとした。
「ッ…!」
包帯で包まれている手首が引きつるように痛み、信は顔をしかめた。
縄を切ろうとした時に誤って傷つけてしまった箇所だ。止血はしているが、まだ傷は塞がっていないため、まだ無理に動かすことは出来ない。
「痛むか?」
「少し…でも、平気だ」
昌平君の骨ばった大きな手が、信の手首をそっと包み込む。
包帯に血が滲んでいないことを確かめると、彼はその手首に唇を寄せて来た。
柔らかい唇の感触を包帯越しに感じて、信は視線を泳がせる。唇が触れただけだというのに、不思議と痛みが和らいだ。
「あの男、ここまでお前を追い詰めるとは…」
声に怒気が込められていた。この傷は肖杰によってつけられたものだと昌平君は勘違いしているらしい。
そういえば、薬で喉が腫れていたせいで、細かに状況の詳細を伝えていなかった。
絶体絶命だったあの状況にいた信を見れば、この手足の傷は肖杰にやられたのだと誰もが誤解するだろう。
「いや、これは俺が自分でやったんだ」
薬で喉を腫らされたこと、拘束していた縄を切ろうとしたこと、朦朧とする意識を取り戻すために自ら足を斬りつけたことを伝えると、昌平君の顔つきがますます険しいものになっていく。
不安と心配と怒りが混ざったような複雑な表情だった。
子供たちの犠牲を防げなかっただけでなく、大切な恋人の命までもが奪われそうになった事実を知り、自責の念に駆られているようだ。
きっと今の関係を築いていなければ、昌平君がそのように考えていることを信は気づけなかっただろう。
「…その、俺は昌平君が来てくれたお陰で助かったんだし、あんまり自分を責めるなよ」
信の言葉を聞き、昌平君は何も言わずに、彼女の体をそっと抱き締める。
自分は生きているのだと安心させるために、信は彼の広い背中をそっと擦ってやった。
しばらく昌平君は信の体を抱き締めたまま、口を閉ざしていた。
「…昌平君」
肩に顔を埋めている恋人を呼び掛けるが、顔を上げようとしない。こうなれば、しばらくは喋らないだろう。
いつもなら昌平君が甘やかしてくれるのに、今日は逆の立場に立てたようで、どこか新鮮な気分になる。
「…はあ…」
少ししてから、信の体を抱き締めていた昌平君が小さく溜息を吐いたので、信はようやく顔を上げた。
途端に唇を重ねられ、驚きのあまり口を開いてしまう。すぐに舌が入り込んで来た。
「っん、ぅ…」
戸惑った信が昌平君の胸を突き放そうとするが、強く抱き締められて、情熱的な口づけが深まっていく。
舌を絡め取られて、歯列をなぞられると、信の背筋が甘く痺れた。
視界いっぱいに映っている恋人の端正な顔も、唇の柔らかい感触も、ざらついた舌の表面も、口づけの合間に洩れる吐息も、何もかもが愛おしい。
彼の胸を突き放そうとした信の手が、もっと口づけを強請るように、弱々しく紫紺の着物を握り締めた。
「…は、ぁ…」
ようやく唇が離れると、信は肩で息をしていた。
「う…」
手首と右足から多く血を流したせいだろうか、軽く眩暈を覚えて、信は昌平君の胸に凭れ掛かる。
「大丈夫か?」
心配そうに尋ねて来る昌平君に、信は無理やり笑みを繕った。
ただでさえ今日は心配ばかり掛けたのだから、今くらいは安心させてやりたかった。
「…もう休め」
先に仕掛けて来たのはお前の方だと、信が煽るように昌平君を上目遣いで見た。
潤んだ瞳を向ければ、酒を飲んでいなくても昌平君の理性が揺らぐことを信はもう理解している。
もちろん昌平君自身もその自覚があるようで、僅かに顔を強張らせていた。
「…傷に障る」
「お前の技量次第だろ」
煽るようにそう言えば、昌平君の瞳が大きく揺らいだ。
添い寝 その二
起き上がった彼が身体を組み敷いて来たので、どうやら挑発に成功したようだと信はにやりと笑った。小癪な女だと昌平君が内心毒づく。
しかし、信がここまで厄介な性格をしていなければ、昌平君も彼女に興味を引かれることはなかったかもしれないと冷静に考えていた。
信の着物を脱がす手に、迷いは微塵もなかった。
襟合わせを開くと、傷だらけの肌が露わになる。小さな傷から、致命傷になりえたものまで、彼女が死地を生き抜いて来た証拠がそこにあった。
この傷跡だらけの肌が、堪らなく尊いと思う。しかし、自分がつけた傷痕でないと思うと、憎らしくもあった。
「っ…」
胸元にある傷痕に沿って舌を這わせると、信がくすぐったそうに顔をしかめる。
この傷を上書きすることは叶わない。それどころか、信が将であり続ける限り、新しい傷は今後も増え続ける。
ならばせめて、傷痕ごと彼女を愛そうと、肌を重ねる度に昌平君は思う。
傷痕に沿って指と舌を這わせていると、信の息が少しずつ乱れていった。頬が紅潮している彼女の顔が見える。
まだ傷痕にしか触れていないというのに、まるで焦らすような愛撫に信が甘い吐息を零していた。
身体を重ねる度に、昌平君が愛撫するものだから、初めの頃より感度が高まっているらしい。
破瓜を破った時は痛みに打ち震え、昌平君の腕の中で啜り泣いていたというのに、今ではもうその面影もない。
初めて信の体を拓いたことと、彼女の身体をここまで変えたのは他でもない自分だという優越感があった。
それを指摘すれば、きっと信から頭突きされるだろうと分かっていたので、昌平君はその事実を自分の内に秘めている。
「ふ、…うっ…」
手の平でそっと胸を揉みしだくと、信の鼻奥でくぐもった声が上がる。胸の中央にある芽を指の腹で擦ると、すぐに固く尖ってきた。
「ぁあっ」
上向いたその芽を二本の指で挟むと、泣きそうな声が上がる。その声に、嫌悪の色が混じっていないことに、昌平君の口元はつい緩んでしまう。
柔らかい肌に顔を寄せて胸のふくらみを揉みしだき、時折、上向いた芽を指で愛撫する。
どこか期待を込めた眼差しを頭上から感じ、昌平君はその欲望を叶えてやることにした。
「っひ、あ」
胸の芽を唇で咥え、舌を這わせる。ざらついた舌の表面と唾液の滑った感触が気持ち良いのだろう。信の表情に恍惚としていた。
口と舌で愛撫される気持ち良さは理解出来る。不慣れながらも信が男根を口と舌で愛撫してくれる時には、昌平君も声を堪えるのに必死になる。
ましてや、愛しい者が自分ためにしてくれてるのだと思うと、それだけで快楽が全身を貫くものだ。
「んっ…うぅ…」
反対の胸を手で攻められると、信が強く目を瞑って、唇を固く引き結んでいた。
誘ったのは信の方だというのに、声を堪えようとする姿が健気に思え、欲を煽られる。何としても鳴かせてみたくなった。
一度、身体を起こして、昌平君は彼女の耳元に唇を寄せた。
「信」
静かに耳元で名前を囁けば、まるで火傷でも負ったように信の身体が大きく跳ねる。
「しゃ、喋んなッ…」
組み敷いている体に鳥肌が立ったのが分かった。彼女の敏感な部分は幾度も知り得ている。信は耳元で囁かれるのも、吐息を吹き掛けられるのも弱いのだ。
肩を竦めるように力み、敏感な耳への耐えようと敷布を強く握り締める。
まだ手首の傷も癒えていないというのに、そんなことをすれば傷口が開いてしまうと、昌平君は耳から顔を離した。
「信、力を抜け」
「うぅ…」
できないと首を横に振って意志表示をする姿がしおらしく、昌平君の口元が意地悪な笑みを浮かぶ。
笑い声を聞きつけ、信が切なげに眉を寄せた。
「こんな時に、笑うなっ…」
笑っている顔はたまに見るくらいで良いと言ったのは信のはずなのに、どうやら気に障ったらしい。
彼女が指摘するまで、昌平君は口角がつり上がっていたことに気づかなかった。
恋人の愛らしい姿を見て表情を変えない男など、果たしてこの世に存在するのだろうか。そんなことを考えながら、昌平君は敷布を握り締めている彼女の手に指を絡ませた。
指と指を交差しているだけだというのに、繋がっている気持ちが形としてそこに現れたかのように、胸が熱くなる。
右丞相と大将軍という立場ゆえに付き従う者も多く、今思えば、信とこのように身体を密着させられるのは、人目のつかない場所だけだった。
軍師学校の空き教室、お互いの私室、そしてこの芙蓉閣の密室。
本当ならばもっと彼女と身を寄せ合っていたいし、この女は自分のものなのだと周囲に言い示してやりたい。それが私情であり、醜い独占欲だということを、昌平君も十分に理解していた。
信のことを想うからこそ、独占欲で勝手を起こす訳にはいかない。
そのせいか、信と二人きりになると、今まで抑制していたものが簡単に溢れてしまうのだ。彼女に煽られて、すぐに身体を組み敷いたのもそのせいである。
年齢も立場も自分の方が上なのに、信と二人きりになると、余裕など微塵もなくなる。
余裕のなさを理由に、彼女に無理強いをしていないか不安になることだってあった。
独占欲
「信」
懲りずに昌平君はもう一度、彼女の耳元で囁く。愛の言葉よりも、彼女の名前を呼ぶ回数の方がはるかに多かった。
下唇を噛み締める信を見て、昌平君がその唇に舌を伸ばす。
「はぁっ…」
薄く開いた唇から信の赤い舌が覗く。舌を絡ませ合いながら、昌平君は右手を彼女の下腹部に伸ばした。
「っ、う、んん…」
引き締まった腹筋からさらに下に手を這わせる。足の間に辿り着くと、そこは淫華はもうぐずぐずに蕩けていた。
こちらはまだ触れてすらいなかったのに、こんなにも自分を求めていたのかと思うと、優越感に胸が満たされた。
「あ…」
蜜を絡ませて指を進めていくと、信の身体がぴくりと跳ねる。根元まで押し進めると、まるで待ち侘びていたかのように、柔らかい肉壁が指を締め付けて来た。
「ひっ、ぅ」
中で指を鉤状に折り曲げて、腹の内側を優しく掻き毟られると、信が切なげに眉を寄せる。
こうして腹の内側を刺激されると、尿意にも似た何かが迫り来る感覚があるらしい。その感覚が苦手らしく、信が力なく首を振ってやめてくれと訴えた。
しかし、前戯もろくにせず男根を押し込むのが気が引けた。
何度も身を重ねているとはいえ、女にしかない繊細な部位を手荒く扱うつもりはない。ましてや大切な恋人を、自慰の道具のように、自分の欲望の捌け口になどしたくなかった。
「んんッ…」
しつこいほどに中で指を動かしていると、固く引き結んでいる唇からくぐもった声が洩れていた。
今度は首を振るのではなく、何かを訴えるように見据えて来る。
彼女の昂りから、指ではなくて別のものが欲しいと訴えているのは分かったが、昌平君は指の数を増やすだけで望みを叶えようとはしなかった。
焦らしているつもりはない。これは信のためだと自分に言い聞かせながら、昌平君も己の昂りを自覚していた。彼女の喘ぐ姿を目の当たりにして、痛いくらいに男根がそそり立っている。
どうやら信もそれを察したようで、腕を伸ばし、着物の上から男根を愛撫して来る。
行為の最中に信は男根を手や口を使って愛撫してくれることもあるが、肖杰の屋敷で負った傷のことを考えると、今日はそのような真似をさせる訳にいかなかった。
淫華から指を引き抜く。前を寛げて男根を取り出すと、信がとろんとした瞳を向けて来る。
「ん…」
男根の先端を淫華に押し当てると、信が身体を強張らせたのが分かった。挿入の瞬間はいつも初夜のように身を固くするのだが、その恍惚の表情を浮かべている。
褥でしか見せない、この世で自分しか知らない信の顔だと思うと、昌平君はそれだけで堪らない気持ちになった。
「ぁああっ」
短い悲鳴が上がったが、構わずに昌平君は最奥を突いた。
全身を貫いた快楽に信が昌平君の背中に腕を回し、強くしがみ付いて来る。隙間なく下腹部が密着した後、お互いの性器がなじむまで動かずにいた。
しかし、待ち切れなかったのか、信が腰を押し付けるように前後に揺らし始める。まさかそんな淫らな技を得ていたことに昌平君は驚いた。
寝具に踵をつけて腰を動かしているのを見て、右の太腿の傷に障るのではないかと心配になる。
「信」
うっすらと包帯に赤い染みが滲んで来たのを見て、昌平君は彼女の名を呼んだ。
「う…?」
痛みよりも快楽に支配されているらしく、信は傷口が開きかけていることに気付いていないようだった。
「足の傷に障る」
細腰を両手で押さえつけて動きを止めると、昌平君は彼女を気遣いながらその体を抱き起こした。
「で、でも…ぅわッ?」
向かい合う体制で座らされ、驚いた信が慌てて昌平君の背中に両腕を回した。何度か行ったことのある体位だが、今日は不安そうに瞳を揺らしている。
「あ、ま、待って…怖い…」
目の前の体にしがみつきながら、信が声を震わせる。
「大丈夫だ。つかまっていろ」
「そ、じゃなくて…」
弱々しく信が首を振ったので、昌平君は小首を傾げた。
「これ、深く、入ってくる、から…良過ぎて…こわい」
「………」
その言葉がどれだけ男の性を煽っているのか、信には自覚がないらしい。
「ひ、ああーッ」
下から突き上げられ、信は甲高い声を上げる。たった一突きされただけだというのに、目の奥で火花が散った。
この体勢のせいで、自重によって子宮が下りて来ており、いつもより深く男根が突き刺さる。
ぎゅうとしがみつきながら、信はどうにかして目まぐるしく襲う快楽から意識を背けようと、昌平君の背中に爪を立てる。
この客間は、芙蓉閣に住まう女子供たちとは遠い部屋にあるのだが、それでも誰が聞いているか分からない。
彼の肩に顔を押し付けながら、何とか声を押さえようと必死になっている信を見て、寝台の上では見られなかった彼女の新しい表情に、昌平君はさらなる興奮を覚えた。
「んんッ、んーッ」
首を横の振って、必死に制止を求めている。
顔を真っ赤にして、やめてくれと言葉に出す余裕もないのだと思うと、ますます攻め立てて鳴かせてやりたいと思うのが男の性だった。
右足の傷や両手首の傷の負担にならないようにと思ったはずが、今ではすっかり性の虜になってしまっている。
もう一人の自分が、昌平君の余裕のなさを指摘するが、もう止められそうになかった。
これ以上ないほど男根は深く入り込んで、信の中を支配しているというのに、さらに奥へ進もうとする。
「んううッ、んぅーッ」
声を堪えようと、信が埋めている肩に歯を立てて来る。制止を聞いてくれない昌平君に抵抗しているようにも見えた。
血が滲むほど歯形を刻まれて、その痛みさえ愛おしいと、昌平君は口元に笑みを浮かべていた。
後日編
肖杰の屋敷から戻った後、信は芙蓉閣の一室で療養していた。昌平君の手配により、医師団も派遣されていた。
処置をしたはずの傷痕がなぜか開いてしまったことで、療養の期間は一時的に延長となったのだが、今ではもうすっかり傷も癒えている。
療養のせいで厩舎に預けっぱなしだった愛馬の駿の迎えが遅くなり、ようやく迎えに行った時には駿は信に苛立ちを見せて、その背中に乗せてくれなくなってしまった。
人の言葉が分かっている賢い馬であり、信が何度も謝罪をして今回の事件について語ると、渋々と言った様子で背中に乗せてくれ、ようやく屋敷へ帰ることが出来たのだった。
涵からもらった青い絹紐も、駿はちゃんと預かってくれていた。
信が療養をしている期間に、肖杰の屋敷の庭から見つかった子供たちの亡骸は、然るべき場所へ弔われた。
月日が経っていたせいか、ほとんどが白骨化していたのだという。まだ白骨化していない亡骸を検死すると、女児は子宮を、男児は心臓を抉り出されて殺されていたらしい。
信の予想通り、肖杰の庭から見つけ出された亡骸は芙蓉閣の十人だけではなかった。
城下町に来ていた子供が何人か行方不明になっていたようで、他の亡骸は恐らくその子供たちだろう。
此度の騒動で肖杰は死刑が決まり、現在は独房に幽閉されているのだと昌平君が教えてくれた。
(久しぶりだな…)
子供たちの失踪事件がようやく終息した後で、信は久しぶりに芙蓉閣へと訪れた。
ここのところは戦の気配もなく、穏やかな日々が続いている。そのせいか、咸陽の城下町は普段よりも賑わっているように見えた。
「あ、信さま!」
回廊を歩いている信の姿を見つけ、涵が笑顔で駆け寄って来る。いつもは二つ結びにしている髪が、今日は一つ結びになっていた。
信は彼女がくれた絹紐のおかげで命拾いしたことを思い出し、唇に苦笑を浮かべた。
「よお、涵。元気だったか?」
頭を撫でてやると、彼女は後ろで一つに括られている自分の髪を指さした。
「お姉さんみたいでしょ?」
「そうだな。いきなりどうしたんだ?」
いつもは髪を二つ結びにするのがお気に入りだと話していた彼女が珍しいと信は目を丸めた。
「私、もうちょっとしたらお姉さんになるの!」
その言葉に信は疑問符を浮かべた。涵が嬉しそうに、奥の部屋で女性たちに織り機の使い方を指導している燈の方を見やったので、納得したように頷く。
「そうか…」
燈はあと数か月後に出産を備えている。
この芙蓉閣では一番若い年齢だと言っても良い涵に、いよいよ妹分か弟分が出来るのだ。きっと嬉しくて堪らないのだろう。
信は懐から絹紐を取り出した。
昌平君が涵から買い取った絹紐は、今は信の髪に結ばれている。今、信が手にしているのは、宸にお守りとして渡した方だ。
もしも宸がこの絹紐を、昌平君に信の居場所を知らせるために使ったのだとしたら、間違いなくこれはお守りとしての効力を発揮したに違いない。
宸や他の子供たちの命を救ってやることは叶わなかったが、子供たちに助けられたこの命を大切にしていかなくてはと信は改めて思うのだった。
「…ほら、後ろ向け」
侍女に頼んで血を洗い流してもらった青い絹紐を、信は涵の髪紐の上から結んでやった。
「涵」
名前を呼ぶと、涵は不思議そうに円らな瞳をさらに丸くする。
身を屈めて、信は彼女を真っ直ぐに見つめた。
「宸は…」
「お兄ちゃん?戻って来るの?」
満面の笑みを向けられて、信は言葉を詰まらせた。
このままでは嘘を見破られてしまうと思い、彼女は空を見上げる。雲一つない、どこまでも青い空だった。
「…今な、飛信軍の下っ端としてこき使ってやってるんだ。だから、もうここには戻って来ない」
「えーっ」
納得いかないのだろう、涵が頬を膨らませた。彼女の小さな頭を撫でてやりながら、信は笑みを繕った。
「宸が一人前になるまで、俺が厳しく育ててやるから、心配しなくていい。な?」
目を覗き込みながら言うと、涵はしぶしぶ納得したように頷いた。
「この紐も、お前が持ってて欲しいんだとよ」
髪に結んでやった青紐を指で撫でつけながら信が言うと、涵は再び頬を膨らました。
「お守りで作ったのに!」
「ああ、そうだよな…でも、お前に持っててもらいたいんだとよ」
信の言葉を聞き、涵はようやく笑顔を見せてくれた。
「…会えなくても心配すんなって、言ってたぞ」
そう言うと、涵はぱちぱちと瞬きを繰り返した。それから涵は、信に抱き着いた。
目を閉じて、信の薄い腹に耳を押し当てている。
子供というのは案外鋭いものだ。まさか宸が殺されたことを察したのだろうかと信は不安を抱いた。
しかし、顔を上げた涵は笑顔で口を開く。
「お兄ちゃんなら、ちゃんとここにいるよ?」
「え?」
「大丈夫!私、みんなのお姉さんになるから!」
彼女が話す言葉の意味は分からなかったが、悲しんでいる様子がないことに、信はほっとする。
…その後、信の懐妊が分かり、昌平君が誰にも見せたことがない驚愕と喜悦の表情を見せたというのは、また別のお話。
終
昌平君×信のBL話はこちら