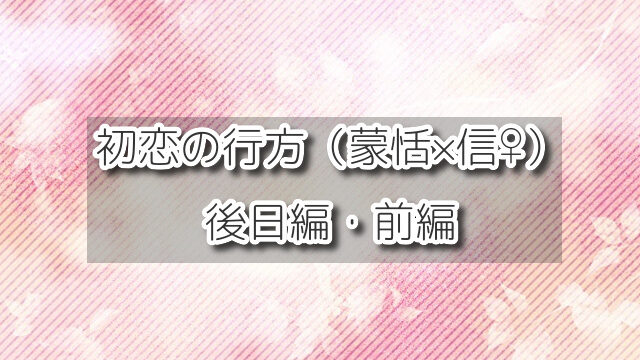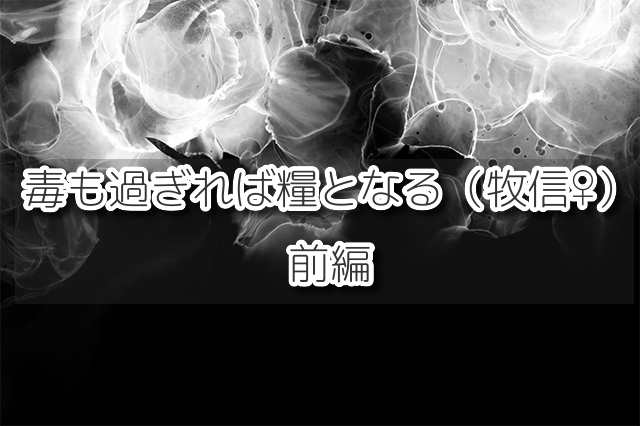- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 桓騎×信/蒙恬×信/年齢操作あり/年下攻め/ギャグ寄り/甘々/ハッピーエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は「平行線の終焉」の桓騎×信の後日編です。
恩人
このお話の本編はこちら
芙蓉閣にいた時、飛信軍の副官になれば、信を守ることが出来ると桓騎は疑わなかった。
しかし、残念ながらそれは、彼女自身に阻止されることとなる。
体力試練も受けずに飛信軍に入るのは、贔屓だの縁故採用だと言われてしまうからと話していたが、本当にそれだけだったのだろうか。
自分に告げた理由の他に、何か別の理由があったのではないかと、桓騎は彼女と結ばれた今になってから考えるようになっていた。
白老・蒙驁の容体が優れないという。
山陽の戦いで廉頗と派手にやり合って左腕を失い、合従軍との防衛戦にも力を尽くした。年齢もそうだし、無事でいる方が不思議なくらいだ。
いよいよ死期が近づいているのかと、桓騎は腹を括ることにした。
蒙驁の容体が優れないという報告は魏の慶都に入ってから聞いていたのだが、引き返して見舞いにいくようなことはしなかった。
今さら自分が顔を出したところで、人の死期というものは変えられない。この汲の城を落とすことで、白老への手向けにしてやろうと考えたのである。
副官として彼に貢献はして来たが、会いたがっている訳でもないだろうし、きっと王翦も自分と同じで見舞いなど行かないだろう。
白老と親しまれた彼のことだから、身内や多くの家臣たちに見送られるに違いなかった。最期に立ち会うのは、彼と共に過ごした時間が長い者たちが相応しい。
汲の城を落とした後、制圧の事後処理を側近たちに任せ、手に入れたばかりの城の一室で、桓騎が優雅に酒を煽っている時だった。
「お、お頭!大変!大変だよ!」
いつも落ち着きのないオギコが普段以上に慌てながら、血相を変えて本陣に駆け込んで来たのだ。
「どうした、オギコ」
桓騎は視線だけをそちらに向けた。
城の制圧は終えているし、敵兵も大方片付けている。他に何か問題になるようなことがあるとすれば、敵の増援だろうか。
王翦の方も城を落としたという報告は聞いていたし、今さら二つの城を取り戻すために魏軍が兵を割くとは思えなかった。
「何でか分からないんだけど、信が来たの!もうそこまで来てる!」
「信が?」
突然の訪問者に戸惑っているのはオギコだけではなく、他の兵たちもだった。
そしてまさかここで信の名前を聞くとは思わず、桓騎自身も呆気にとられてしまう。
此度の侵攻戦に出陣したのは桓騎軍と王翦軍だ。飛信軍は出陣を命じられていない。
それに、李牧率いる合従軍との防衛戦に勝利してから、信はずっと自分の屋敷で療養しているはずだった。
山の民たちが救援に駆け付けるまでの七日間、彼女は死力を尽くして秦王と蕞を守り抜いたという。
さらにはそんなぼろぼろの状態であるにも関わらず、王騎の仇である龐煖とも死闘を繰り広げたというのだから、桓騎は彼女の死すらも覚悟していた。
合従軍との戦いで任された桓騎軍と飛信軍の持ち場は異なり、彼女の死を見届けるという約束も叶わぬのかと途方に暮れたものだ。
しかし、結果的には生きていたのだから、信の生命力には感服してしまう。それは秦国と秦王を守り抜くという彼女の意志強さが証明したものだろう。
まだ完治していないというのに、どうしてこの地に彼女自らやって来たのだろうか。
城を落とすにあたって苦戦することなど何一つなかったし、救援を頼んだ覚えなどなかった。信自らやって来るとは、何か用があってのことだろう。
逆に言えば、何か用がなければ信は自分のところへ来ない。芙蓉閣にいる時もそうだった。だからこそ、幼少期の桓騎は色々と面倒事を起こし、お説教という用件を作っていつも彼女を呼び寄せていたのである。
そんな彼女と今では恋人同士になったというのに、未だに用がないと会いに来てくれないだなんて随分と寂しいものだ。
戦にまで赴いたのだから、総司令から伝令でも頼まれたのかもしれない。
信を出迎えるために桓騎が立ち上がった時、彼女はすぐそこまでやって来ていた。
「桓騎!」
城の制圧は成したとはいえ、ここは未だ魏の領土である。だというのに、信は数人の護衛しか連れていなかった。
随分と不用心だと思ったが、それだけ火急の用なのだろうか。
「お前、こんなところで何してんだよ!」
「…は?」
汲の城を落とすという大役を終えたばかりだというのに、労いの言葉を掛けられるどころか、まさか開口一番そんなことを問われるとは思わなかった。
「見りゃ分かんだろ。立派にお役目を果たしたところだ」
事実を告げたまでだというのに、その言葉が癪に障ったのか、信が大股でずんずんと近づいて来る。まだ体のあちこちに包帯が巻かれており、傷が治りきっていないのは明らかだった。
すぐ目の前まで迫って来た顔は幼い頃から見慣れているはずだが、何度見ても可愛らしげのない顔だと思う。
それでも自分が惚れた女であることには変わりなかった。
「蒙驁将軍の報せを聞かなかったのかよ!後のことは俺が引き受けるから、早く行ってやれ!」
「……は?」
まさか今から蒙驁のところに向かえと言うのか。
知将と名高い桓騎であっても、これほど先の読めない言動をするのは後にも先にも信だけだと断言出来た。
頬杖をつきながら、桓騎は足を組み直し、長い息を吐く。信の口から蒙驁の話が出るとは思わなかった。
「…わざわざそのために来たのか」
「それ以外に何があるんだよ?王翦将軍もいるんだし、城を落とすのに救援なんかいらねえだろ」
当然のように答えた信に、桓騎は謎の頭痛に襲われ、思わずこめかみに手をやった。
労いの言葉の一つもないのは、逆に言えば信が桓騎の実力を認めているからだと言えるだろう。
しかし、もしも信がここに来た理由が、自分に会いに来たという愛らしいものであったのなら、今すぐにでもこの制圧した城の一室でその体を隅々まで愛していたに違いない。
残念ながらその期待は大いに裏切られてしまった。
「王翦将軍の方も俺たちが引き受ける。早く行ってやれ」
…とことんおせっかいな女だ。道端で死に掛けていた素性の知らない子供を保護しただけのことはある。
城の制圧に関しては側近たちに任せていたし、確かに今から馬を走らせれば間に合うかもしれない。
「急げよ。きっと蒙驁将軍もお前のことを待ってる」
すぐに動き出す気配のない桓騎に、信が苛立ったように声を荒げた。
蒙驁に恩がないといえば嘘になる。
もともとは信が彼のもとに身柄を引き渡したことで出来た縁ではあるが、規律に縛られるのを好まない自分の性格をよく理解し、その上で自由にさせてくれた。きっと信もそれを見越して、蒙驁将軍に頼んだのだろう。
飛信軍に入れずに拗ねていた時期もあったが、信と同じ将軍の座に就いている今なら、それが当時の彼女なり心遣いであったことが分かる。将軍という立場は色んな責任を問われる面倒なものだ。
しかし、それでも桓騎は腰を上げる気にはなれなかった。
「…手向けならここでもできる」
蒙驁へ行くつもりはないという桓騎の言葉を聞き、信のこめかみに青筋が浮かび上がった。
「桓騎ッ」
感情的になりやすい彼女に凄まれるものの、桓騎が怯むことはない。
幼い頃から彼女に幾度も叱責を受け、げんこつも平手打ちも一切の加減されることなく受けて来たのだ。今さら凄まれたところで何とも思わない。
眉一つ動かすことのない桓騎に、先に折れたのは信の方だった。こうなれば意地でも従わない頑固者だということを思い出したようだ。
「…じゃあ、王翦将軍にお前の分も頼んで来るからいい」
踵を返した信の腕を掴んだのは、ほとんど無意識だった。
敵対心
それまで話に興味を示さなかった桓騎から急に引き止められたことに、信は驚いて振り返った。
「なんだよ、放せよ」
睨まれるものの、桓騎は黙って信の腕を掴んでいた。
信がここに来たのは総司令に命じられた訳でもなく、ただの善意だ。恩人である白老に礼を言う機会を授けてくれようとしているのだろう。
日頃から白老には、武功を挙げることで恩を返していたつもりだ。それは言葉で伝えるものよりも、分かりやすい感謝であると桓騎は思っていた。王翦も同じことを考えているだろう。
それぞれの軍でそれぞれの規則があるように、自分と白老の関係性も他と一括りには出来ないのである。
しかし、信は昔から忠義に厚い将だ。
世話になった者には、武功を挙げて自分の活躍を知らしめるだけでなく、言葉で感謝を伝えるという礼儀正しい一面も持っている。それはきっと、養父である王騎からの言いつけなのだろう。
(王翦のとこに行かせる訳には行かねえな)
自分はともかく、王翦にも白老のもとへ行くよう伝えにいくのは見逃せなかった。
信は将の中でも王翦と同等の立場だが、いつも仮面を被っていて何を考えているのか分からないあの仏頂面男が得意でないらしい。
しかし反対に、戦の才を持つ者なら何だって手に入れたい王翦から、信は一目置かれている存在である。今も目を付けられているのは変わりない。
確かあれは、桓騎が五千人将に昇格したばかりの頃だ。
五千人将へ昇格したことに祝杯を挙げてくれた信が、以前王翦から誘いを受け、二人きりで酒を飲み交わしている時に、ずっと自分の軍に来るよう口説かれていたと話したのである。
その時の信は、王翦が独自で軍を作ろうとしているなんて迷惑な話で、いつ秦王へ反旗を翻すか分からないと愚痴を零していた。
その話を聞いて、桓騎は激怒した。
幼い頃、信に保護されてから、桓騎がずっと彼女に想いを寄せていることを王翦も知っていたはずなのに、その上で彼女を手中に収めようとしていたのだ。
怒りを抑えられず、王翦の屋敷に怒鳴り込みに行き、軽くあしらわれたのも、信が慌てて追い掛けて来たのも、今となっては懐かしい思い出である。
しかし、未だ王翦は信のことを諦めた気配を見せていない。
さらには趙の宰相である李牧にまで目をつけており、信と李牧を手中に収めようとまで企んでいるらしい。信も李牧も承諾するとは思えなかったが、絶対にそんなことはさせまいと桓騎はいつも王翦を目の敵にしていた。
王翦も厄介だが、李牧と信の二人を会わせたくなかった。もしもそんなことになれば、比喩ではなく、本当に嫉妬のせいで腸が煮え切ってしまいそうだった。
「…王翦には俺から伝えておく。それなら良いだろ」
渋々ではあるものの、妥協案を口にすると、信が目を真ん丸にした。
「えっ?あ、ああ…」
二人で白老の見舞いに行けと言いに来たのだから、桓騎の妥協案を断る理由はなかったのだろう。呆気に取られた顔で信が頷く。
オギコに馬を用意するよう伝えてから立ち上がった桓騎は、まるで一つの動作のように、自然な手付きで信の体を抱き締めた。
「か、桓騎っ!?」
いきなり抱擁されるとは思わなかったようで、信が腕の中で硬直している。
他の兵たちの目もあるというのに迷うことなく彼女を抱き締めた桓騎は、離れていた時間を埋めるように、信の温もりに浸っていた。
桓騎が幼い頃から信に想いを寄せていたことも、秦趙同盟の後にめでたく結ばれたということも秦では誰もが知る周知の事実であるので、他の兵たちは少しも気にしていない。
長年の想い人と結ばれた時、仲間たちが三日三晩かけて盛大な祝いをしてくれたのは良い思い出である。あの時は誇張なしに全員が吐くまで飲んだ。
「お頭~!準備出来たよ~!早く信を放してあげて!」
ばたばたとやって来たオギコに言われ、桓騎はようやく信のことを解放した。
この場を見られたことに信は顔を赤らめていたが、オギコ自身は少しも気にしていない。今となっては周りの目を気にしているのは信だけである。
「王翦には俺から伝える。城の制圧に関しては摩論に任せてあるから、お前はここにいろ。王翦のとこには行くなよ」
「あ、ああ…分かった…」
大人しく頷いてくれた彼女を褒めるように、桓騎は穏やかに笑んだ。
自覚がなかったのだが、どうやら仲間たち曰く、「こんなお頭、見たことがない」と驚愕するほど優しい笑顔らしい。普段からどんな面をしていると思われているのだろうか。
「オギコ、摩論たちにも伝えておけ」
「わかった!いってらっしゃい!」
城を出る時に背後から信の視線は感じていたが、振り返ると一緒に連れて行ってしまいそうだった。用意されていた馬に跨ると、手綱を握る手に力を込めて自分を制する。すぐに横腹を蹴りつけて馬を走らせた。
そしてもちろん、王翦がいる城には寄らずに、桓騎は早々に白老の屋敷を目指したのだった。
見舞い
屋敷に到着すると、従者はすぐに白老の部屋へと案内してくれた。
喪を想像させる黒い布は屋敷のどこを見ても掛けられていない。従者たちの落ち着き払っている様子を見る限り、どうやら間に合ったらしい。
来訪を伝えてから部屋に入ると、寝台で上体を起こしている白老がゆっくりとこちらを振り返った。
「フォ?お主が来るとは珍しいのう。王翦と共に魏の城を落としに行ったのではなかったか」
「………」
てっきり意識もないのだとばかり思っていたのだが、呑気に茶を啜っている白老を見て、桓騎は呆気にとられた。
おいクソジジイと言い掛けて、寸でのところで言葉を飲み込む。
彼の副官という立場になってから、規律に縛ることなく好き勝手にやらせてくれた恩を感じている手前、乱暴な言葉遣いは慎むようにしているのだ。
「……危篤と聞いていたんだが?」
顔を引き攣らせながら問いかけると、もともと細い目をさらに細め、蒙驁がフォフォフォと高らかに笑う。
「危篤だったのは嘘ではない。しかし、今は見ての通りじゃ」
「………」
こめかみが締め付けられるように痛み、桓騎はつい皺が寄ってしまった眉間をほぐすために指を押し当てた。
信が蒙驁の危篤の報せを知って、桓騎のもとに駆け付けるまで数日。そして、入れ替わりで桓騎が蒙驁のもとへ駆けつけるまで数日。どうやらその間に、蒙驁は危篤状態を脱し、随分と持ち直したらしい。
本当に危篤だったのかと疑いたくなるほど元気そうな彼を目の当たりにして、桓騎は肩透かしを食らった気分になった。
確かに最後に会った時と比べるとやつれた印象はあるが、呑気に茶を啜っている姿を見る限り、元気だと言って良いだろう。
「わざわざ足労掛けてすまんのう。まだ臥せっている時にお主が来てくれたなら、泣き顔を見せてくれただろうに。残念じゃのう」
誰がてめえのために泣くかよと心の中で毒づきながら、桓騎は腕を組んで蒙驁をぎろりと睨んだ。
「…そんだけ口達者なら、しばらくあの世からの迎えは来なさそうだな」
溜息交じりに呟き、近くにあった椅子に腰を下ろした。
わざわざ駆けつけてやったというのに、まさかここまで回復しているのなら、制圧の手続きを終えてからでも良かったではないか。
信のお節介を迷惑だとは思わないが、こんなことなら王翦にも声を掛けて、いっそ道ずれにするべきだったと後悔すら覚える。
「フォフォ、せっかく来てやったのに損したという顔じゃな」
帰還するまで会えないと思っていた信と会えたのは、蒙驁の危篤のおかげだと頭では理解しているものの、なぜか心は釈然としなかった。相変わらずこちらの調子を狂わせる男だ。
多くの家臣や兵たちから白老と慕われる人柄は、桓騎は嫌いではなかったのだが、自分でも気づかぬ間に彼の手の平の上で転がされているような感覚がどうも好きになれなかった。
奇策を用いて敵味方を自分の思い通りに動かす桓騎には、相手の思惑通りに動かされるのは不慣れなのである。
「そんだけ無駄口叩けるなら。改まって話すこともねえな。もう行くぜ」
無駄足だったとは言わないが、これだけ体調が回復したのなら、また話す機会は多くあるだろう。
立ち上がって部屋から出ようとした時、蒙驁が思い出したように顔を上げた。
「そういえば、恬が魏の汲へ向かったようじゃが…お主、会わなかったか?」
恬というのは、蒙驁の孫にあたる蒙恬のことである。
軍師学校を首席で卒業するほど聡明な頭脳を持っており、たちまち武功を挙げて昇格していく功績は、名家の嫡男として誇らしいもので、蒙驁にとっても自慢の孫だ。
あの美貌に惹かれる女は大勢いるようで、縁談話が絶えないのだと何故か蒙驁が自慢げに語っていたことを思い出す。
蒙武と顔つきも体格も少しも似ていないことから、初めは養子かと疑ったのだが、本当に血の繋がった息子だという。母親の顔が見てみたいものだと思ったのは桓騎だけではないだろう。
次の戦で武功を上げれば、蒙恬は五千人将へ昇格だという話は聞いていたのだが、彼が魏に行くよう命じられた話は初耳だった。
自分と王翦の二つの軍だけで城の制圧も成し遂げたし、救援など頼んだ覚えもない。
信のように独断で事を起こすような、感情に左右される男ではないと思っていたし、だとすれば蒙恬が魏に行く理由とは何だろうか。
「何で白老の孫が…総司令から指示でもあったのか?」
茶を啜った後に、白い顎髭を撫でつけ、蒙驁がゆっくりと口を開いた。
「信の補佐に行くと話しておったから、恐らく独断じゃろうな」
「なッ…!?」
これはさすがの桓騎も予想外だった。
まさかここで再び信の名前が出て来るとは思わなかったし、この機に蒙恬が信と接触を図ろうとしていただなんて想像もしていなかった。
(あのクソガキ…!)
思わず奥歯を噛み締める。
蒙驁の孫とはいえ、さして付き合いもなかったので、桓騎と蒙恬はお互いの存在を認知し合う程度だった。
過去の戦で楽華隊を動かしていたことはあったが、蒙驁の孫である手前、捨て駒として扱う訳にはいかず、蒙恬自身もその聡明な頭脳で敵を出し抜き、それなりに武功も挙げていた。
自分と数えるくらいしか歳の差は離れていないのだが、桓騎は蒙恬のことを毛嫌いしている。
その理由は無論、蒙恬が信のことを、異性として意識しているからだ。
数え切れないほどの縁談話が来て、女に不自由することのないはずの蒙恬は、どうやら信に気があるようだった。
直接それを本人に問い質したことはない。しかし、蒙恬が信を見つめるあの目は、一人の男として女を見る目だと断言出来た。
きっと蒙恬が今まで相手にして来た女には、信のような女は一人もいなかったに違いない。だからこそ彼女に惹かれたのだろう。
男に媚を売ることも知らぬ、自分の目指すべき道をひたすらに歩む信に惹かれる気持ちはよく分かる。
しかし、相手が蒙恬であっても、李牧であっても、桓騎は信を誰にも渡すつもりはなかった。
「やれ、恬のあの女好きは一体誰に似たのか…まさか信に惚れるとは思わなんだ」
どうやら蒙驁も、蒙恬が信に想いを寄せていることを知っているらしい。
そういえば、婚約者というような堅苦しい肩書きではないものの、信と自分が男女の仲になったことを蒙驁に伝えていなかった。
正式に婚姻が決まったならば、報告すべきだと考えていたのだが、まだ信から求婚の承諾を得られていないのである。
秦趙同盟の後、信への片想いがようやく実ったことが秦国ではいつの間にか広まっており、城下町を歩けば民たちから祝福の言葉を掛けられることも珍しくなかった。
流行り物に詳しい蒙恬が、自分たちのその噂を知らぬはずがない。その上で信に接触を図るということは、自分への挑発も兼ねているのだろうか。
蒙驁の容体が回復したことと、蒙恬が信へ接触を図ろうとしていることが、何か関係があるような気がして、桓騎は嫌な予感を覚えた。
特に気になるのは、大切な祖父の容体が持ち直したばかりの状況で、蒙恬がなぜ信の補佐を優先したのか。
「…信は見舞いに来たのか?」
気になっていたことを尋ねると、蒙驁は大きく頷いた。
「覚えてはおらんが、儂がまだ眠っている時に来てくれたようじゃ。それですぐに魏にいるお主のもとへ向かったと聞いておる。恬が魏へ行ったのは、儂が目を覚ましてからじゃ」
なるほどと桓騎は顎を撫でつける。
信が桓騎のもとへ向かうのを蒙恬は知っていた。そして蒙驁の容体の回復を見届けてから、蒙恬が信の補佐へ向かったのだとしたら、やはりこれは自分を出し抜くための策だと言える。
確実に自分という邪魔者が居ない間に、信と二人きりになる機会を見計らっていたに違いない。
蒙恬が信を見るあの目が、一人の男として女を見る目だと気づいた時から、桓騎は蒙恬の存在を危険視していたのだが、それは正解だったようだ。
新たな恋敵
名家の嫡男であり、初陣を済ませてからたちまち武功を挙げていく蒙恬が、大勢の娘から縁談を申し込まれているのは噂で聞いていた。
しかし、蒙恬は結婚適齢期であるにも関わらず、妻になる女性を見極めたいだとか適当な理由をつけて縁談を受けることはせず、好みの女をとっかえひっかえに褥を共にしているのも有名な噂話だ。
きっと結婚相手を見定めたり、世継ぎを作る素振りを見せることで、家臣たちを安心させていたのだろう。
しかし、確実に蒙恬の狙いは信だ。彼女を手に入れるために、自分を出し抜く機会を虎視眈々と狙っていたに違いない。そしてそれがまさに今というワケだ。
(よくもこの俺を出し抜きやがったな)
さすがに蒙驁の前で、彼の大切な孫に暴言を吐く訳にはいかなかったので、桓騎は強く歯を食い縛って暴言を飲み込んだ。
きっと蒙恬は桓騎と信の男女の関係には気付いているだろうが、まだ婚姻を結んでいないこの機を狙って、信にちょっかいを掛けようとしているに違いない。
信は腕っぷしの強い女だ。男に迫られても、簡単にその身を委ねるようなことはしないと断言出来た。
しかし、残念ながらそれは相手による。いくら信が強いとはいえ、蒙恬のような男に策を講じられれば、簡単にその体を組み敷かれることになるだろう。
そして鈍い信のことだから、彼に上手く丸め込まれ、全てが終わってから、ようやく騙されたと気づくことになるかもしれない。それでは手遅れなのだ。
あの男は自分の端正な顔立ちと、甘え上手な性格をこの上ない武器として攻め立てるに違いない。
相手の懐に入り込むのを何よりも得意とする蒙恬が、いつ信に襲い掛かるかと思うと、それはもう気が気ではなかった。
彼女と李牧の過去を知っているのは今のところ桓騎だけだが、何かの拍子に信がそんな古傷を抱えていることを蒙恬に知られれば、奴は間違いなくそこを狙って信の心を盗み取るだろう。
李牧との過去を知らなかった時でさえも、桓騎は蒙恬と信が接触しないよう、今まで手を回していた。
蒙恬率いる楽華隊が飛信軍の下につくことが決まった時も、上手く根回しをして桓騎軍の下につくようにしていたのは、他でもない信を守るためである。
蒙驁は桓騎の裏工作に関して何も言わなかったが、きっと見て見ぬフリをしていたのだろう。
…くれぐれも誤解のないよう言っておくが、自分が蒙恬と李牧に敵わないというワケではない。信が彼らの卑怯な策略に陥る可能性が高いだけである。
いくら信の心に自分という存在が刻まれていようとも、彼女の鈍い性格だけは変えられないし、信が女である以上、男に敵わない部分が出て来るのも変えられない事実だ。
「妾も込みで、さっさと結婚させとけ。こっちは迷惑してんだ」
苛立ちを隠し切れずに、桓騎は蒙驁を睨みつけた。
「フォフォ。信が嫁に来てくれたら、それはそれで蒙家は安泰なんじゃがのう」
自分が信にずっと想いを寄せていることは蒙驁も昔から知っているくせにと、桓騎は顎が砕けそうなほど歯を食い縛った。
人の良さそうな顔をしておいて、腹の内に隠し切れない黒さを抱えているのは確かに蒙家の血筋だと思われる。このクソジジイにしてあのクソガキありというわけだ。
むしろ腹の内の黒さを一切感じられない蒙武こそが、本当に蒙家の血筋なのか疑わしくなる。
(信が食われるかもしれねェ)
蒙恬がいつまでも縁談を受けずにいる理由が、信との婚姻を狙っているのだとしたら、彼が考えていることは一つだ。
それは信と婚姻に至るための既成事実を作り上げることである。
もしも信が蒙恬との子を孕めば、いや、孕まずとも一夜を共にしたとすれば、蒙恬の思惑通りに婚姻へ運ぶことが出来る。
単純なことだ。蒙恬は信の善意を利用しようとしているのである。
凌辱であろうが、言葉巧みによる誘いであろうが、どちらにせよ彼に抱かれれば、恋人である桓騎を裏切ってしまったと信はひどく落ち込むだろう。
その傷ついた心を埋める役割も蒙恬が担い、心身ともに自分のものにするつもりに違いない。
名家の権力を自由に扱い、情報操作も得意とする男だ。外堀を埋めるためにせっかく秦国に広めていた自分たちの恋物語の噂も簡単に塗り替えられてしまうかもしれない。
信を手に入れるための努力が踏み躙られるどころか、水の泡になってしまうと思い、桓騎はすぐにでも信のもとへ駆けつけようとした。
「…ああ、そうじゃ。桓騎よ。縁談と言えば…」
普段は見せることのない桓騎の慌てた表情を見据えながら、蒙驁が楽しそうに目を細めた。
予期せぬ来客
魏の慶都にある汲の城の制圧は、桓騎軍の参謀である摩論が中心となって取り仕切っている。
この城の一室で待っているよう摩論に言われてから、どれだけの時間が経っただろうか。
桓騎も摩論に後のことは一任していると話していたし、信は口を出すつもりもなかったのだが、未だ制圧手続きが完了しないことに、苛立ちが増していくばかりだった。
(遅い…!)
立ち上がって、部屋の窓から城下を見下ろす。投降した兵たちや、汲に住まう民たちを取りまとめている秦兵たちの姿があった。
捕虜たちは戦力の補充として宛がわれる。捕虜の中にも怪我人がいたが、差別なく救護班が手当てを行っていた。
手に入れた領土は、税制や支配機構を設定した上で管理をしなくてはならない。今後、汲の城も戦略のために改修する必要がある。
帰還後には城内の構造や、手に入れた物資、はたまた投降兵たちの記録の提出と報告をしなくてはならないため、制圧をしてからもやることはそれなりにあるのだが、それにしても時間がかかり過ぎている。
信がこの地に到着した時にはすでに城は落としていたし、すでに制圧手続きは始まっていた。
桓騎がここを出立してからすでに数日が経ったというのに、未だに制圧手続きが終わっていない。一体何にそんな時間をかけることがあるのだろうか。急がなければ夜になってしまうではないか。
一刻も早く帰還したいのに、未だ城の制圧を終えたという報告が入らず、信は苛立ちを隠し切れずに大声を上げた。
「おいっ、まだ終わんねえのかよ!いつまでかかってんだッ!?」
信の文句を聞きつけ、部屋の外にいたオギコが驚いて飛び込んで来た。
「信、怒らないで~!摩論さんたちも頑張ってるんだから!オギコが肩揉んであげる!ほら座って座って!」
オギコに宥められ、信はやれやれと椅子に腰を下ろす。
摩論が何かと理由をつけて城の制圧手続きを長引かせているのは、きっとめぼしいものを見つけたに違いない。
桓騎軍の者たちは元野盗の集団だ。金目の物には特に目がなく、桓騎も好きにしろと自由にさせているらしい。きっとそういう規律に一切興味がないところが彼らには好印象だったに違いない。
元野盗の集団を仲間にしたと聞いた時は寝首を掻かれるのではないかと危惧していたが、それは無用な心配だった。
縛られることを何よりも嫌う桓騎と元野盗たちは随分と性格が合うようで、たちまち「お頭」と慕われるようになって、今や大勢の元野盗団が桓騎軍に集結していた。
彼らを配下に従える時は、何度か器を試されるようなことはあったようだが、何の問題もなく従えているところを見る限り、桓騎は仲間たちからその器を大いに認められたのだろう。
人を惹き付ける魅力を備えているのだと思うと誇らしかったのだが、まさか気性の荒い野盗集団たちまで手懐けてしまうとは思いもしなかった。
「………」
桓騎と王翦を蒙驁の見舞いへ行かせることが出来て良かったと思うものの、今際に間に合っただろうか。
蒙驁の危篤の報せを聞き、桓騎のもとへ駆けつける前に、信も馬を走らせて見舞いに行った。言葉を交わすのは最後になるかもしれないと思ったからだ。
かろうじて返事はしてくれたものの、蒙驁が目を開けることはなかった。きっともう長くはないだろう。戦場で多くの死と対面して来た信に、直感のようなものが走った。
すぐに桓騎に知らせなくてはと思い立ったのもその時で、此度の将軍交代は完全なる信の独断である。きっと総司令である昌平君は目を瞑っていてくれるだろう。
その後、蒙驁の容体に関しての報告は来ていない。
ここから帰還した後で、実はもう亡くなっていたという報せを聞くことになるのではないかと信は不安を抱いていた。
「いでででッ!オギコ、力入れすぎだ!」
溜息を吐いた拍子に、両肩に激痛が走り、信は飛び上がった。
「あれれっ、ごめんね?お頭は強めが良いって言うから、つい…もっと弱くするね!」
「ジジイかよ、あいつは…」
オギコに肩を揉まれながら、信は溜息を吐いた。
桓騎のことを任せられたのは、蒙驁のあの人柄を信頼してのことだ。
それは決して間違いではなく、自由にさせていたことで桓騎の才を芽吹かせてくれたのも彼のおかげだと信は思っている。
桓騎自身も言葉にはしていないが、蒙驁には恩を感じているようだし、伝えたいこともあるだろう。
見舞いに行った時に、桓騎の面倒を見てくれたことには大いに感謝を告げたのだが、信も長年世話になった立場として、出来ることなら蒙驁の最期の瞬間を看取ってやりたいと考えていた。
もしも蒙驁が亡くなれば、悲しむ家臣たちは大勢いるに違いない。
(そういや…)
ふと、信は蒙驁の孫にあたる蒙恬のことを考えた。
彼は桓騎よりも幾つか年下だが、さすが蒙驁の孫であり、蒙武の息子と言ったところか、初陣を済ませてからあっと言う間に昇格していった。
次の戦で武功を挙げれば、蒙恬はいよいよ五千人将に昇格となり、将軍への昇格もあと少しとなる。
蒙驁の見舞いに行った時、彼は大切な祖父の危篤に悲しげな表情を浮かべて、ずっと蒙驁の手を握り続けていた。
最愛の祖父に将軍になる姿を見せてやれないと悔やんでいる蒙恬と、自慢の孫の成長を見届けることが叶わない蒙驁のことを思うと、信は胸が締め付けられるような痛みを覚えた。
「ん?」
馬の嘶きが窓から聞こえて、信は反射的に顔を上げた。
それからこちらに近づいて来る足音が聞こえたので、ようやく制圧き手続を終えたという摩論からの報告だと信は疑わなかった。
待ちくたびれたと長い息を吐いていると、
「信将軍!」
「…は!?」
しかし、扉を開けて入って来たのは摩論でも他の側近でもなく、蒙恬だった。
白老が危篤だというのに、ここに蒙恬がいることをすぐには信じられず、信はもしかしたら白昼夢でも見ているのかと思った。
「えっ、ええーっ!?信、なんで!?何でこの人ここにいるの!?」
肩揉みをしていたオギコも同様に驚いていることから、夢ではないことを知る。
蒙恬はにこにこと笑顔で近づいて来ると、礼儀正しく供手礼をする。
「祖父の見舞いに来て下さったこと、感謝します。お陰で峠は超えました。まだ全快とは言い難い状態ですが…」
「え?そ、そうなのか?」
蒙恬自らが蒙驁の容体について知らせてくれたことに、信は呆気に取られてしまう。危篤は脱したらしいが、まだ心配な状態らしい。
しかし、そこでふと気づく。
大切な祖父が危篤を脱したとはいえ、今はまだ彼の傍についているべきではないのだろうか。伝令を寄越してくれればよかったのに、どうして蒙恬自ら伝えに来たのだろうか。
「…蒙恬…わざわざそれを伝えに来たわけじゃねえよな?」
「ええ、目的は他にもあります。制圧と撤退の補佐をしに馳せ参じました」
そんなことを言われるとは思わず、信は溜息を吐いた。
制圧の手続きは摩論に任せているし、撤退の指揮に補佐など不要だ。どうせ帰還するだけなのは兵たちも分かっているだろう。
「俺一人でも十分だ。お前は蒙驁将軍の傍についていてやれ。峠を越えたからって、いつ何があってもおかしくないんだろ」
せっかくここまでやって来た蒙恬の気遣いを無下にしないよう、信は言葉を選びながら返した。
「……そうしたいところなんですが…」
「?」
素直に従わない蒙恬を見て、信は他に何か別の目的があるのかと考える。
「実は、祖父との約束があるんです」
「約束…?」
はい、と蒙恬が切なげに眉根を寄せた。
あの蒙武の息子とは思えないほど端正な顔立ちである蒙恬が、そんな悩ましい表情を見せれば、女も男も性別は関係なく理性が揺らぐだろう。
しかし、信は桓騎と同様で、幼い頃から蒙恬のことを知っていることもあって、少しも心が揺れ動かされることはなかった。
蒙恬が蒙驁との大切な話を持ち出したことから、信は後ろにいる兵たちに目線を送って下がるように指示を出す。
心配そうにオギコがこちらを見ていたが、彼も兵たちと共に部屋を出ていった。
扉が閉められて、二人きりになったことを確認してから、蒙恬はゆっくりと口を開く。
「俺…祖父に、お嫁さんを見せてあげるって、約束していたんです」
「ああ、結婚の話か。そういやお前、許嫁も居なかったよな?」
あっさりと聞き返したのは、その約束の内容が自分と少しも関係性がないことを確信したからだった。
しかし、蒙恬が縋るような眼差しを向けて来たので、信は嫌な予感を覚えた。
「お願いします。フリだけで良いんで、俺のお嫁さんになってください」
「…はっ?」
蒙恬に深々と頭を下げられて、信はようやく彼から「自分の妻になってくれ」と頼まれていることを察したのだった。
「いや無理だろ!何言ってんだお前!?」
即座に断ったものの、蒙恬が縋りつくように上目遣いで見上げて来る。
「お願いします。こんなこと、信将軍にしか頼めなくて…」
こういう時に端正な顔立ちを使って甘えて来るのは、自分の顔が良いことを自覚している何よりの証拠だ。信は後退りながら何度も首を横に振った。
「頼む相手を間違えてるだろッ!」
名家の嫡男であり、この美貌と、将としての武功がある蒙恬ならば、縁談話は山ほどあるに違いない。
わざわざ自分じゃなくたって、その中から好みの女を選べばいいはずだ。
しかし蒙恬は「いいえ」ときっぱり首を横に振る。
「信将軍が嫁に来てくれるなら蒙家も安泰だって、祖父を安心させてやりたいんです」
もっともらしいことを言われるが、さすがに蒙驁を騙すなんて良心が痛むことに協力する訳にはいかなかった。
「悪いが、お断りだ」
「そんなっ…」
即座に拒絶すると、蒙恬が泣きそうな表情になる。
「じゃあ、俺…じいちゃんとの約束、守れないんだ…最後まで、じいちゃんを心配させてばっかりで…」
「お、おいっ?」
両手で顔を覆い、めそめそと女のように泣き始める蒙恬に信は狼狽えた。
もしも蒙恬にこんな顔をさせたことを、彼の配下に知られでもしたら確実に面倒なことになる。
名家の嫡男として、それはもう大切に育てられた男である。家臣や従者たちが今も蒙恬を大切に想っているのは変わりなかった。
彼が引き連れて来た護衛達は部屋の外で待機しているが、蒙恬の声を聞いて、よくも主を泣かせたなと襲い掛かって来るのではないかと不安になる。
「俺じゃなくても、本当に嫁になってくれる女なんて大勢いるだろ!」
蒙驁を安心させてやりたいという蒙恬の気持ちに応えてやりたいとは思うものの、桓騎という恋人がいる以上、安易には承諾出来なかった。
妻のフリをする候補どころか、本当に妻になってくれる女性など、縁談の数だけいるはずだと伝えてみるが、蒙恬は首を横に振る。
「俺のことを慕ってくれる女性たちに、祖父を安心させたいからという理由で結婚するなんて…そんな道具みたいに扱うこと、俺には出来ません…!」
「俺は良いのかよッ!?」
結婚適齢期であるにも関わらず、蒙恬は多くの美女と褥を共にしているという噂を聞いており、信は蒙恬が結婚相手の女性を見定めているのだとばかり思っていた。
名家の嫡男であり、秦の未来の担う将である。下心を持つような女を妻にする訳にはいかないのだろう。
妻となる女性がどんな人物か見定めるのも大変だなと信は思っていたのだが、桓騎から「遊んでるだけだろ」と教えられたことがある。
女性を食い物にしているといえば語弊があるかもしれないが、色んな女性と褥を共にして、人生を謳歌しているらしい。
まさか蒙恬がそんなことをする男だとは思わず、信は桓騎の話を聞いて驚いた。
それでも蒙驁との約束を守りたいという姿は、祖父想いの優しい孫にしか見えない。
「お願いします…祖父を安心させてあげたいんです…!」
幼い頃から蒙恬を知っている信は、その優しさを踏み躙ることが出来ず、狼狽えてしまう。
初陣に出る前の蒙恬は「信!」と親を追う雛鳥のように自分の周りを付き纏って来て、家臣たちが目の保養にするのも頷けるくらい愛らしい子だった。
いつも生意気なことを言ったり、自分を呼び寄せるために何かと芙蓉閣で騒動を起こしていた桓騎と違って無邪気で愛らしかった蒙恬が、どうしてこんな桓騎にも引けを劣らぬ面倒な性格に育ってしまったのだろう。
自分の端正な顔立ちと甘え上手な部分を武器に出来るのだと気づいてから、蒙恬は途端に可愛げがなくなったように思える。もちろん本人には口が裂けても言えないが。
狼狽えている信を見て、蒙恬はあと一押しだと悟ったのか、さらに泣き落としを始めた。
「…祖父はずっと、俺のお嫁さんになる女性に会うのを楽しみにしていたんです…最後まで、その約束を果たせられないのかと思うと…」
「うううっ…」
このままでは渋々承諾してしまうと信も薄々勘付いていた。
これは蒙恬のためではなく、蒙驁のためだと自分の良心を説得してしまいそうになるが、信の瞼の裏に桓騎の姿が浮かび上がる。
扉が勢いよく開けられたのは、その時だった。