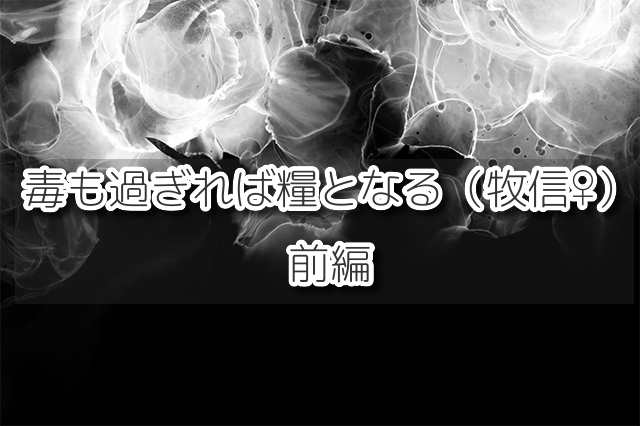- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 李牧×信/桓騎×信/毒耐性/シリアス/バッドエンド/野営/IF話/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は「毒も過ぎれば情となる」(桓騎×信)のバッドエンド番外編です。
罠
国境調査を開始してから三日。
まだたったの三日しか経っていないというのに、予期せぬ事態の連続に、信は将としての判断を迫られていた。
国境調査に連れて来た三百の兵たちが、ほぼ壊滅状態に追い込まれていたのである。
敵の襲撃に遭った訳でもない。災害に見舞われた訳でもない。国境調査を開始し、拠点を設置したあとから、次々と体調不良を訴える兵が現れた。
いかに厳しい体力試練を乗り越えて鍛錬を積み重ねている屈強の兵たちとはいえ、病には敵わない。
体調不良の原因は、長時間の移動による疲労や冷え込みによるものかと考えたのだが、眩暈や嘔吐といった冷え込みと関連性のない症状を主訴にする兵が大半であった。
ただでさえ冷え込みが厳しくなっている中で、物資も限られている。拠点近くに生えている植物を薪代わりにし、暖を取るように指示をしていたのだが、今思えばそれがいけなかった。
火を焚けば焚くほど兵たちに体調不良者が広まり、症状が悪化していく一方で、救護班たちも倒れていく。
なにかしらの病の感染が広まっているのだと思っていたが、こんな短期間にこれだけの感染力を持つ病などあるのだろうかと考え、信は独自に原因の調査を行った。
暖を取るために薪代わりにしていた植物は、竹のような長い葉と桃のような花をつけた特徴的な植物であったのだが、その煙を吸った時、信は鼻の奥に独特な痺れを感じたのである。
幾度か感じたことのあるその痺れの正体が毒であると気づいた時には、信以外の全員が毒にやられており、そのほとんどが息を引き取っていた。
家族のもとに帰ることが出来なくなった彼らの亡骸を手厚く葬り、謝罪の言葉を掛けていると、まるでこちらが壊滅状態になるのを待っていたと言わんばかりに、崖下から趙軍の伏兵が現れる。
生き残っている兵たちも毒が回っており、とても武器を振るうことなど出来ない。応戦は無理だと即座に判断した。
すぐに撤退を命じたのだが、毒に侵されて衰弱した兵たちは逃げることもままならない。
突然の襲撃に対抗できる兵力はもう残っておらず、信はたった一人になっても武器を振るい続け、やがて力尽きたところを取り押さえられた。
…この地に拠点を作ることも、冷え込みを警戒して周囲の植物を薪代わりにすることも、全ては趙軍の策だったのだと信が気づいた時には、すでに何もかもが手遅れであった。
捕虜
…目を覚ました時、信はまさか自分が生きていると思わず、状況を確認するために辺りを見渡した。
「っ」
鎧は脱がされていて、着物姿のまま両腕は後ろで拘束されている。両足も自由に動けぬように縄で一括りに拘束されていた。
客室と言っても頷いてしまうほど丁寧に整えられ得た部屋に、信は違和感を覚える。寝かされていたのも床の上ではなく、寝台の上だった。
拷問にかける、もしくは殺すだけならこんな部屋に連れて来ないだろう。
血の処理のために藁を敷いている訳でもない。黴臭い地下牢ならまだしも、この部屋はあまりにも綺麗だった。
もちろん武器は奪われていたが、手足を拘束しておきながら、このような部屋で寝かせておくなんて、捕虜にする扱いには思えない。
「っ、ぅ…」
舌を噛み切ってやろうと思っていたのに、その考えを読まれたのか、信は口に布を噛ませられていること気づいた。後ろ手に拘束されているので、轡も外すことは出来ない。
(この布…なんだ?それに、この味…)
咥えさせられた布は初めから濡れていた。歯を食い縛る度にそれが口の中に絞られる。
脱水にならないように、かと言って飲み水を飲ませる時に布を外した隙を突いて舌を噛ませぬために、あらかじめ布を濡らしていたのだろう。
てっきり飲み水で湿っているのだとばかり思ったのだが、幾度も慣れ親しんだその味が鴆酒であると、今の信には気づく余裕などなかった。
しかし、捕虜になったことは間違いないだろう。生かしておいたのは何か目的があるからに違いない。
パチッと火が弾ける音が聞こえ、信は音がした方に顔を向けた。
「…?」
部屋の隅に青銅の火鉢が置かれている。部屋を暖めるために火が焚かれていることが分かる。
これから拷問でも掛けて機密情報を吐かせようとしているのかと思ったが、まるで冷えた体を温めるような気遣いに、信は思わず眉根を寄せた。
(くそ…)
敵に情けを掛けられるなど、屈辱でしかない。
どんな拷問を受けたところで絶対に情報を教えるつもりはなかったし、無様に首を晒されるくらいなら、潔く自分で命を絶つつもりでいた。
その後で首を晒されぬように屍が見つからぬ場所か、顔が認識されないよう粉々になってしまうような死に方が良い。
しかし、手足を拘束された今の状態では不可能だろう。信は火鉢に目を向けて、公衆の面前で首を晒されても自分だと分からぬように、顔を消してしまおうと考えた。
頭から火鉢に顔を突っ込めば火傷は免れず、それでいて絶命出来る。火傷の浮腫によって気道が塞がれるからだ。
苦痛を伴う方法ではあるが、無様に殺されるより何倍もマシだと思い、信はさっそく行動を起こした。
「んっ…!」
寝台から転がり落ち、身を捩って少しずつ火鉢へと近づいた。
口は布で塞がれているものの、目と鼻は自由が利く。火鉢に近づくにつれ、嗅いだ覚えのある香りが鼻腔を漂い、信は思わず顔をしかめた。
(?…この匂い…)
鼻についた煙の匂いには覚えがあるのだが、木炭ではない。ゆっくりと体を起こし、火鉢の中を覗き込み、その匂いの正体を探った。
(まさか…この植物…!)
灰の中に竹のように長い葉と桃のような花が見えて、自分たちが拠点を作っていた周辺に生えていたあの植物だと気づく。
あの植物――夾竹桃――を燃やすと強い毒性がある煙が出ると気づいたのは、兵たちの体調に異変が起きてからだった。
(まずい…!)
このまま毒煙を吸い続ければ、毒の副作用――まるで媚薬を飲まされた時のように性欲の増強と感度が上昇する――を起こしてしまう。
どの程度この毒煙を吸い込めば症状が起きるのかは分からなかったが、かなり強力な毒性を持っていることのは兵たちが苦しむ様子を見て分かっていた。
部屋に充満する毒煙を吸わないようにと思うものの、轡を噛まされているせいで鼻で息をすることしか出来ない。結果的に火鉢に近づいたせいで濃い毒煙を吸い込んでしまう。
この部屋に寝かされていた時からずっと火は焚かれていた。
眠り続けている間も煙を吸い込んでいたとすれば、副作用を起こすまできっとあまり時間は残されていない。
「ううッ…!」
毒煙を吸い込まないように火鉢から顔を背けたが、毒煙は部屋に充満していく一方だ。
煙のせいで息がしづらくなってくる。布を咥えながら咳き込むものの、夾竹桃が燃え盛っていく度に部屋の煙が濃くなる。
毒の成分だけならまだしも、煙が充満していくせいで上手く息が出来ない。
拘束されている手足で何とか体を動かし、扉の前まで向かおうとするが、意識が朦朧としてきた。
ここでようやく信は地下牢ではなく、この部屋に閉じ込められた理由を悟った。
地下牢では鉄格子があり、密室にならない。この毒煙を利用するために、この部屋に連れて来たのだろう。
信が毒への耐性を持っていることを知っている者は秦国でも限られている。しかし、敵国で知っている者といれば、ただ一人だけ。
全てがその男の策だったのだと信が気づくのは、もう少し後のことである。
「ううっ…」
煙が目に染みて涙が止まらなくない。新鮮な空気を求めて勝手に開いてしまう口から濃い煙が入って来て呼吸が阻害された。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
毒煙
夾竹桃が燃え尽きた頃を見計らい、李牧はその部屋を訪れた。煙が充満した部屋は噎せ返るようなほど、甘い香りに包まれていた。
夾竹桃は美しい花と葉を持つだけでなく、白粉のような優しく湧き上がる甘さを漂わせる植物だが、その美しい外見と甘い香りとは反対に、強力な毒性を兼ね備えている。
青銅の火鉢の傍で信が倒れ込んでいた。手足を拘束して寝台に寝かせていたはずだが、火鉢に灰に顔から突っ込んで自害でもするつもりだったのだろう。
鴆酒を染み込ませた轡を噛まされた上に、両手を拘束された状態で自害を試みるのなら火鉢を利用するというのは李牧の読み通りだった。
しかし、残念ながら夾竹桃の毒煙を強く吸い込む結果となってしまったらしい。
「う…ん、…」
苦しそうに肩で息をしていたので轡とを外してやったが、意識は戻らない。
ずっと火鉢の傍にいたからか、信の体は焼け付くように熱かった。見たところ、火傷は負っていないようで安堵する。
火照っている彼女の体を抱きかかえ、李牧は寝台へと連れて行く。
すでに火は消えているとはいえ、毒煙に満たされた部屋である。しかし、李牧は布や手で顔を覆うこともしなかった。毒煙を吸い込んでも、彼は顔色一つ変えない。
寝台に信の体を寝かせると、李牧は身を屈めて彼女の薄く開いたままの唇に己の唇を押し当てた。
「…ああ、やっと口づけられました」
秦趙同盟の際は毒を受けることを警戒して、鴆酒を飲んだ彼女と口づけることは叶わなかったのだが、こんなにもあっさりと叶うとは思いもしなかった。
手足の縄を外してから、恋人同士のように信の手に指を絡ませて、口の端を濡らす唾液を舌で舐め取り、李牧は何度も唇を重ねる。
酒は得意な方ではないのだが、鴆酒の味はやけに甘く感じるものであった。菓子のような甘さとはまた違い、奥深くて優しい口当たりだった。
もしも毒という物質がこのような甘味だったなら、夢中になってしまうのも分かる。秦趙同盟のあとの宴で、信が美味そうに鴆酒を飲み干していたのも納得出来た。
解毒剤を内服していなければ違った味だったかもしれないが、それでも信と同じように毒酒の味を分かち合うことが出来たことに、李牧の胸は満たされていく。
「ん…」
柔らかい唇の感触を何度も味わったあと、李牧は白い首筋に強く吸い付いて、赤い痕を残していった。
「は、ぁ…」
まだ意識は戻っていないが、信の体は反応を見せ始めた。彼女の肌が赤く上気しているのは火鉢で暖められたせいではないようだ。
「毒の耐性を得ることは不可能かもしれませんが、時間と材料さえあれば、解毒剤を作ることは可能なんですよ?…聞こえていないでしょうが」
「ふぁ、あ…んぅ、…」
眠りながら喘ぐ信を見下ろしながら、李牧が肩を竦めるようにして笑う。
よほど強く毒が回っているのか、信は口を閉じられず、幼子のように唾液を流していた。
李牧は唾液さえも逃がさないと言わんばかりに舐め取った。無色透明なそれが甘美な味をするのは、きっと気のせいではないだろう。
李牧の策
秦国が国境調査を行う場所は以前から調べがついていた。
見晴らしの良い崖上に拠点を作り、定期的にこちらの動きを探ることを秦の総司令が指示をしていることも密偵から報告を受けていたのである。
国境調査を任されるのは名のある将ばかり。それは趙国を常に警戒している表れとも言える。
李牧があの地に夾竹桃を栽植するよう指示したのは、秦趙同盟を終えてからだ。
理由としては、毒に耐性がある不思議な体質の信と出会って、彼女に興味を抱いたからであり、ただの好奇心でもあった。
普通の人間でいう致死量の毒を盛られたところで信は痛くも痒くもないらしいが、媚薬を盛られたかのように性欲と感度が上昇するらしい。秦趙同盟のあの夜に、李牧は自らの目でそれを確認していた。
冬になれば薪の消耗が激しくなるので、栽植しておいた夾竹桃を薪にしようと考える。この植物を燃やすと強力な毒煙が発生することを知っている者は少ない。何の疑いもなく薪代わりに利用することだろう。
冷え込みの激しい過酷な環境下で、治療は困難を極める。薪として使用している夾竹桃が毒の源であると気づかなければ被害は拡大する一方だ。
案の定、なにかの病だと誤解したことで、原因の除去への対応が遅れてほぼ壊滅状態へと追いやられてしまう。
もしもこの罠に陥るのが飛信軍であったのなら、毒に耐性を持つ信を捕らえられるし、他の軍だったのならば簡単に一掃することが出来る。どちらが掛かっても趙が優位に立てる李牧の策であった。
結果、仕掛けておいた罠に引っ掛かったのは信だった。それは李牧にとって、運命を感じさせる結果でもあった。
飛信軍の壊滅と、信を捕らえたという報告を聞いた時、蜘蛛の巣に飛び込んだ蝶がもがく姿が李牧の脳裏に浮かんだ。
信は李牧を敵国の宰相であることのほかに、養父である王騎の仇としてその首を狙っている。
だが、秦趙同盟の際、呂不韋の企みで李牧は鴆酒で毒殺されかけたのだが、寸でのところで信が阻止したのである。
鴆酒で苦しむ自分をせせら笑い、見殺しにすることは容易かったはずだ。だが、信はそれをしなかった。
養父の仇である自分を恨みはするものの、決して卑怯な方法では報復しない彼女の信念に惹かれたのである。この戦乱の世でそのような綺麗事を貫ける彼女がどこまで行くのか、成長を見届けたいとも思った。
信を傍に置いておきたいと思うようになったのはいつからだっただろう。
趙の宰相と秦の女将軍という敵対関係にある立場は、平行線のように交わることのない関係性だ。
それでも戦や軍政で接点を得ることがある。信を手に入れるのなら、彼女を罠に嵌めるのが一番手っ取り早い。
秦王に厚い忠誠を誓っている彼女が、敵国である趙に決して平伏しないと断言出来た。
人質になることで秦国に不利益を与えたり、辱めを受けるくらいなら信は自ら命を絶つに決まっている。だが、それでは意味がないのだ。
抵抗の意志を削ぐ方法など幾らでもある。まずは彼女の身柄を抑えることが最優先だった。
しかし、夾竹桃の栽植という手の込んだ指示は事前に行っていたものの、信を手に入れるとなると、随分余裕を欠いてしまう。
それほど彼女に恋焦がれているのだと、嫌でも自覚せざるを得なかった。
帯を解いて果物の皮を剥くようにして着物を脱がせていくと、相変わらず傷痕が目立つ肌が現れた。
(これは、矢傷ですね。ここは…剣で裂かれたのでしょうか)
瘢痕の大きさをみると、相当な深手だったことが分かる。鎧を着ておきながらこれだけの深手を負っただなんて、よく死ななかったものだと感心してしまう。
初めて彼女と身を繋げた時にも、彼女の裸体は見たことがあったが、あの時に比べると傷痕は圧倒的に増えていた。
それを決して醜いとは思わない。むしろこの醜い傷があるからこそ、信の勇ましさを感じとることが出来た。
「う、…ん…」
戦乱の世を生き抜いてきた証とも言える傷痕を指でなぞっていると、信がくすぐったそうに身を捩った。
ただ指を這わせているだけなのにそんな反応を見せられると、今すぐにでも強引に体を繋げたくなってしまう。
「んんっ、ぅ…は、ぁ…」
唇を重ねると、意識を失っているはずの信が切なげな吐息を零した。
舌を差し込むと、もどかしげに膝を擦り合わせる。意識は眠りの世界に落ちているものの、自分という存在を感じてくれているのだと思うと、李牧は思わず目を細めた。
将軍として多くの兵たちを導いている彼女の体には、必要な部位にしっかりと筋肉がついている。しかし、胸の膨らみは紛れもなく信が女である象徴だ。
すくい上げるように胸をそっと掴むと、手の平いっぱいに柔らかい感触が広がって、夢中になって揉み込んだ。
信が生娘でないことはあの夜から知っていた。体に刻まれている傷の数は増えていたが、胸の芽が素肌に溶け込んでしまいそうな桃色なのは変わりなかった。
胸の膨らみを愛でていると鼻に抜ける声が聞こえて、李牧は視線を持ち上げる。
「うっ…ん、っ…!」
くすぐるように乳輪をなぞり、芽を指で弾く。指で優しく摘まんでやると、少しずつ硬さが増して来た。
あっという間に立ち上がった胸の芽を今度は舌で可愛がってやる。
「ふ…ぅ…」
くすぐったそうに信が身を捩った。胸に触れられるのが好きなのかもしれない。
片方の胸の芽を吸いつき、舌で転がしながら反対の胸を弄っていると、しきりに信が膝を擦り合わせる回数が増えて来た。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
発覚
「…信」
頬に口づけながら、李牧は着物から覗く彼女の脚の間に手を伸ばした。
「あっ…」
内腿に指を這わせただけだというのに、甘い声が洩れる。
男の欲を掻き立てるその声に気分を良くしながら淫華に指を伸ばすと、すでにそこは蜜を垂れ流していた。
「う、んん…あ…?」
信が薄く目を開いたことに気づき、李牧は自然な手つきで彼女の両手首を握り込んだ。
あれだけ毒を吸い込ませたのだから、体に力が入らなくなっているとは思うのだが、彼女の忍耐強さには幾度も辛酸を舐めさせられた。
養父の仇である自分に恥辱を受けるとなれば最後まで抵抗を続けることだろう。喉笛を食い千切って逃げるかもしれないし、抵抗が敵わないと分かれば自ら舌を噛み切るに違いない。
目を覚ました彼女が今の状況をどう受け入れるかで、李牧もこの後の予定を変更するつもりであった。
何とか瞬きを繰り返してから、信は不思議そうに李牧の姿を見つめている。夾竹桃の毒煙のおかげか、まだ意識は朦朧としているようだ。
「あ…ぇ…?桓、騎…?ま、た、鴆酒ぅ…?」
聞き覚えのあり過ぎるその名前を聞いた途端、李牧ははっと目を見開く。
「も、たらふく飲んだから、いらねえって…お前が飲めよ…」
まだ意識がはっきりしていないせいで、信は李牧のことを桓騎と勘違いしているようだった。
桓騎に鴆酒を飲めと促す言葉に、李牧は一つの仮説を立てた。それは毒への耐性を持っている者が、信の他にもいたということである。
しかもその人物があの首切り桓騎となれば、なかなか厄介だ。他の兵たちは一掃出来たとしても、毒への耐性を持っている彼を消し去ることは出来ない。
面倒だとは思いながらも、彼に接触する前にその情報を得られることが出来たので、ある意味においては収穫である。
そして、桓騎と信の関係性についても情報を得ることが出来た。毒耐性という共通点から、二人は特別な関係性を築いているに違いない。
毒を摂取し過ぎることで媚薬を飲まされたかのように体が敏感になるようだし、異性であることを考えればそのようなことが起きても不思議ではない。
そこまで考えて、李牧は秦趙同盟の夜に信を抱いたとき、彼女の体に刻まれていた赤いあの痣は桓騎がつけたものだったのだと気づいた。
あの首斬り桓騎にとって信が特別な存在にまで昇格しているのなら、ますます信には人質としての価値が深まる。
強大な戦力を持つ信と桓騎の二人を同時に始末することは、趙国にとって大いなる利益があった。
自然と口角がつり上がってしまうのは、思わぬ収穫が得られたことによる優越感のせいだろう。
思わず笑みを噛み堪えて、李牧は赤く上気している信の首筋に唇を押し当てた。
重い瞼を持ち上げた時、信は意識を失う前のことをすっかり忘れていた。
柔らかい寝具の上に寝かされて、誰かに体を組み敷かれていたので、桓騎と鴆酒を飲んでいたのかと思い込んでしまう。
(あれ、俺…寝てたのか…?)
頭が鈍く痛んで、それが酒の酔いだと信は疑わなかった。
もしかしたら鴆酒を飲んで眠ってしまったところを桓騎が寝台に運んでくれたのかもしれない。
もう鴆酒はいらないと声を掛けたものの、桓騎は自分の上から降りる気配がない。それどころか身を屈めて、首筋に唇を押し付けて来たではないか。
「ん…」
柔らかい唇の感触が気持ち良くて、下腹部が甘く疼いてしまう。もっとして欲しいという気持ちが湧き上がって来る。
普段なら叱りつけるところだが、毒酒が入った状態で体を組み敷かれると、桓騎に触れてほしいという気持ちになってしまうのだ。そんな風に桓騎を求めるのは、酒の酔いのせいだと疑わなかった。
(…?)
身を委ねるために体から力を抜いていると、自分の首筋に顔を埋めている桓騎の香りに違和感を覚えた。
まだ酔いと眠気で重いままの瞼を擦ろうとしたのだが、両手首を押さえられている。
何度か瞬きを繰り返しているうちに、ぼやけていた目の前の景色がはっきりと移り込んで来た。
自分を組み敷いている男がゆっくりと顔を上げ、それが何者であるかを認識した瞬間、信は心臓の芯まで凍り付いてしまいそうになった。
「桓騎、じゃ、ない…」
どうしてここに養父の仇であるこの男がいるのだろう。
顔から血の気が引いていくのが分かり、頭にかかっていた靄が一瞬で消え去った。
「久しぶりですね、信。おはようございます」
こちらの動揺を煽るかのように、李牧から軽快な挨拶を返される。
なぜ自分が敵である趙国の宰相に組み敷かれているのか、今の状況が少しも理解出来なかった。
「は、放せッ!」
状況を理解するよりも先に抵抗を試みたのは、目の前のこの男が養父の仇だということが一番の理由だった。
力の入らない腕で李牧の体を押し退けようとするものの、両手首はすでに押さえ込まれており、彼の下から抜け出すことが叶わない。
着物もほとんど脱がされていて、唾液のべたついた感触が肌に残っていることに気づくと発狂しそうになった。
一度この男とはすでに身を繋げているのだが、あれは毒酒のせいで魔が差しただけだ。
過去の清算と養父の仇を討つのために、何としてもこの男の首は取らなくてはと思っていたのに、二度も組み敷かれるなんて思いもしなかった。
「クソ野郎!殺してやるッ!」
恐怖の感情の次に湧き上がったのは怒りだった。
自分でも驚くほどの怒鳴り声を上げると、両手首を押さえているから耳に蓋を出来なかったのだろう、李牧は眉間に深いしわを刻む。
「…残念ながら、私を殺せなかったから、あなたは今ここにいるのですよ」
冷静に李牧に諭されても、信は彼を殺意を込めた瞳で睨み続けた。
「無知なあなたが殺めたのは、大勢の味方兵たちだったと思うのですが?」
ひゅ、と信が笛を吹き間違ったかのような音を口から洩らした。
全滅
怒りで真っ赤になっていた顔が再び血の気を引いて青ざめていく。
その様を楽しそうな視線で眺めていると、信の体が震え始めた。どうやら国境調査で起きた事態を思い出したようだった。
「へ、兵たちは…」
「残念ながら、全滅したという報告を受けました」
少しも残念などとは思っていないし、追い打ちをかけるつもりはなかったのだが、律儀に質問の答えを返してやる。
それまで憎悪と殺意を秘めた眼で睨みつけていた信は初めて目を泳がし、呼吸を乱し始めた。
国境調査という名目のため、普段の戦で率いるよりも兵数は少なかったが、それでも三百の損害である。
投降兵や女子供には手を出さない信にとっては、軽く受け流すことが出来ない事実だったようだ。
「仕方ありませんよ。この冷え込みが激しい時期に火を絶やす訳にいきませんから」
「……、……」
「ただ、薪として代用した植物に毒が含まれていたのは不運でしたね」
夾竹桃のことを告げると、信の瞳が大きく開かれた。
まさかという視線を向けられて、李牧はゆっくりと口角を持ち上げる。
「全部、お前が…仕組んだのか…?」
「ええ」
李牧は迷うことなく頷いた。
てっきり逆上すると思っていたのだが、呆然とした表情で見上げられる。唇を震わせて、掠れた吐息を零していた。
どうやら全てがこちらの策通りだったのだという事実を知って怒る気力もなくなってしまったらしい。彼女の愚鈍さに堪らなく愛おしさが込み上げて来た。
李牧は信の顎に指をかけると、唇が触れ合いそうなほど顔を近づける。
「残念ながら、もう手遅れですよ。なにもかも」
涙を浮かべている信の瞳を覗き込みながら、李牧はにっこりと微笑むと、静かに唇を重ねたのだった。
続
更新をお待ちください。
①毒酒で乾杯を(桓騎×信)
②毒杯を交わそう(李牧×信)
③毒を喰らわば骨の髄まで(桓騎×信←王翦)
④恋は毒ほど効かぬ(桓騎×信←モブ商人)
⑤毒も過ぎれば情となる(桓騎×信)