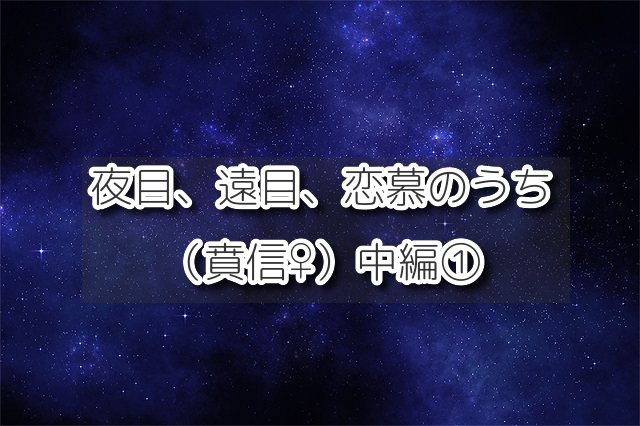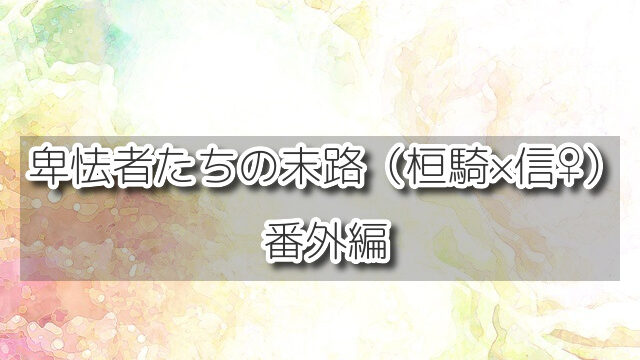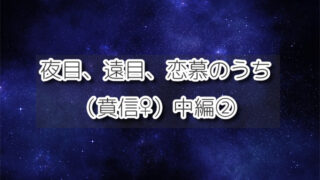- ※信の設定が特殊です。
- 女体化
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 王賁×信/シリアス/甘々/ツンデレ/ハッピーエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
診察
すぐに医師団の診療が始まり、信は王賁の体が毒に蝕まれていることを説明した。
秦国一と言われる医療技術を持つ医者たちは、苦しそうに呼吸を繰り返す王賁の脈を測ったり、舌の色を見たり、瞼を持ち上げて眼球の動きを確認している。
こちらからの呼び掛けには頷いて応じるものの、会話をするほどの余裕はないらしい。瞼を持ち上げるのも辛そうだ。
一人の医者が王賁の指先を刃物で小さく傷つけ、銀針の先端に血を付着させている。銀針の先端の色を見て、何かを考えているようだった。
(おいおい、もしかして、かなりまずいのか…?)
ここに連れてくればきっと何とかなると思っていた信だったが、王賁の診察をしながら医者たちが何とも言えない複雑な表情で互いに目線を合わせていたことに、なにか嫌な予感を覚える。
どうやら王賁の診察が終わったのか、嬴政と信の前に並んだ彼らは報告を始めるべく、頭を下げた。
「毒の症状がかなり進行しています」
その言葉を聞き、信は苦虫を噛み潰したように顔を歪めた。
毒を受けた王賁本人が自覚していたことだし、今さら驚くことではないが、医師団に言われてしまうと事態は相当深刻になっていることを認めざるを得ない。
「な、なあ、治るんだろ?」
縋りつくように信は医者たちに尋ねたが、その声にも不安が滲んでしまう。
誰よりも不安で仕方がないのは王賁だと分かっているのだが、問わずにはいられなかった。
「…銀針が反応しませんでした。恐らく、これは奇毒です」
「え?」
奇毒という言葉に、信は思わず息を飲んだ。
毒の有無は、銀の色の変化によって判断することが出来る。
その知識は過去に食事に毒を盛られた経験のある嬴政から聞いたことがあったので、信も理解していた。
礜石は比較的入手しやすい毒物であり、王族の毒殺だけでなく、貴族たちの世継ぎ問題などでも利用されるのだそうだ。この毒は銀製のものに反応を示す。
そのため、食器を銀製のものにしたり、食前に銀針を浸すなどして、色の変化がないことを確かめてから食事をするらしい。王族はこの確認方法だけでなく、さらに毒見役もついている。
しかし、医師団の見立てによると王賁の血液に触れさせた銀針は、色の変化がなかった。
このことから、王賁が受けた毒は、砒霜の類ではないことが分かる。
王賁が受けた毒が砒霜でないとすれば、まずはその毒の正体を突き止めた上で解毒を行わなくてはならない。
鍵穴に適した鍵がないと扉が開かぬように、毒にも適した治療法を用いらねば解毒することが出来ないのである。
「ただ、今から毒を分析して、解毒法を探すとなれば…」
寝台に横たわる王賁に聞こえぬよう、医師団が声を潜めながら言葉を濁らせた。信と嬴政は互いに顔を見合わせ、言葉を失った。
「そ、そんな…」
もっと早く王賁を医師団へ連れて来ることが出来ればと、信は目の前が暗くなり、膝から力が抜けてしまう。
「信っ」
咄嗟に嬴政が体を支えてくれたので倒れ込むことはなかったが、まるで頭から冷水を浴びせられたように体が竦んでしまう。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
抗毒血清
秦国一と称される医師団でさえも王賁の毒を取り除くことが出来ないということは、あとは彼が死に至るの待つだけなのだろうか。
「他に方法はないのか」
嬴政が険しい表情を浮かべて問いかけると、一人の医者が前に出た。
「恐れながら、一つだけ方法が…」
深刻な事態であることは重々承知しているし、秦王を前に匙を投げるわけにはいかなかったのだろう。
「構わぬ。話せ」
嬴政が発言を許可すると、男の医師は恐ろしいほど厳粛で、神妙な顔つきのまま口を開く。
「人を百毒にあたらせ、体内で血清を作り、その者の血を解毒剤として飲ませる方法があります」
医学に携わったことのない者でも理解できるよう、その男は説明を始めた。
今から王賁の体を蝕む毒の正体を調査し、そこから解毒薬を調合始めるのでは間に合わない。
そのため、異例ではあるが、強力な抗毒血清を人間の体内で製薬して治療を試みるとのことだった。
王賁の体を蝕む毒よりも、さらに強力な毒を体に投与し、その者の体内で免疫を作るということだ。そしてその免疫を持つ血を解毒剤として王賁に飲ませる。
確実に助かるかどうかはやってみないと分からないが、このまま王賁を見殺しにするか、その治療法を試してみるかの二択しか残されていなかった。
「ただし、血清を作る過程で、かなりの危険を伴います。耐えられるかどうかは…」
医師の忠告に、嬴政と信が顔を見合わせる。
誰かが血清をその身で作らねばならないので、王賁が受けた毒よりもさらに強力な毒を受ける必要がある。
血清というのはその字の通り、血液で作られるものだ。
百毒に耐えられた者から血を採取し、それを薬として王賁に飲ませることで解毒を試みると医師は言った。
「………」
信は重々しく眉根を寄せた。
「じゃ、じゃあ、解毒薬を作るために、毒を飲んだやつは、死ぬのか…?」
「毒の作用に苦しむのは確実でしょう。しかし、王賁様に血清を飲ませるためには何としても生きてもらわねばなりません」
もしも血清を作る者が毒を受けて死んでしまった場合、王賁に薬を与えることは出来ない。だからこそ、毒に負けぬ体力と自信を持つ者を人選しなければ、この治療法は望めないと医師は言った。
「もちろん、王賁様の解毒が完了次第、その者の解毒も行います。こちらはすでに解毒方法は分かっているので、王賁様の解毒が終わるまで持ち堪えられる方でなければ…全力は尽くしますが…」
「………」
不自然に医師が言葉を切ったので、信は複雑な気持ちを抱いた。
つまり、王賁の解毒治療をする過程において、犠牲が出るかもしれないとうことである。
事情を知っている王賁の重臣ならば、喜んで身を差し出す者もいるだろう。しかし、迷っている時間はなかった。苦しげに呼吸を繰り返している王賁の姿を見て、信は力強く拳を握る。
「…分かった。俺が王賁の解毒薬になる」
「信…」
親友が危険な提案に名乗り出たことに、嬴政は体の一部が痛むように顔をしかめた。
もしかしたら秦の未来を担っている王賁と信を失うことになるかもしれないのだ。引き留めることはしないが、賛同出来ないのも無理はない。
事態は一刻を争うものの、信と嬴政の親友という関係性は秦国で知らぬ者はいない。医者は確認するように嬴政を見やる。引き留めるなら今しかないと、その眼は訴えていた。
しかし、信は一度決めたことを引き下げることはしないことを、嬴政は昔からよく知っていた。だからこそ、彼は反対しなかった。
「信」
「ん?」
嬴政に名前を呼ばれ、信は反射的に振り返った。
「死ぬなよ」
短いが、決して軽くないその一言には、嬴政の全ての想いが秘められていた。
まだ中華統一は出来ていない。道半ばで息絶えるのは決して許さないと、嬴政の瞳が力強く物語っている。
親友の想いをしっかりと受け止めた信は拳を持ち上げた。
「当たり前じゃねえか。ここらで王賁に恩を売っとくだけだ。それもこれも全部、中華統一を果たすためなんだからな」
二人の間に横たわっていた緊迫した空気を和ませるように、信がカカカと笑う。
嬴政はそれ以上何も言うことはなく、同じように拳を持ち上げて、信の拳とぶつけあった。
製薬
医者に連れられて、信は部屋を出た。
日頃から医師団が在住している建物は宮廷の敷地内にあり、そこでは患者の治療や製薬を主として行っている。王賁もそちらへ身柄を移され、常に医者の目が届くその場所で療養することとなった。
寝台の上で苦しそうに呼吸を繰り返す王賁を見て、信の胸は締め付けられるように痛む。
意識はあるのだが、倦怠感が強く、固く閉ざされた瞼を持ち上げるのも億劫のようだった。
もしも信が毒を受けて抗毒血清を作るとなれば、王賁は全力で止めるだろう。借りを作りたくないだとか、色んな言葉を並べて、解毒剤を飲むのを拒絶するかもしれない。王賁とはそういう男だ。
だから彼には信の体で抗毒血清を作る話は黙っていてもらうことにして、解毒剤の調合していることだけを伝えてもらった。
「信将軍」
医者に名前を呼ばれて、信は弾かれたように顔を上げた。神妙な顔つきで見つめられて、どうやら準備が出来たらしいことを悟る。
信は頷いて、寝台に横たわる王賁の姿をもう一度見つめた。
「…王賁、待ってろよ」
なるべく笑顔を繕って、信は王賁に言葉を掛けた。それが虚勢だというのは信自身も分かっていたが、王賁の前で怯える姿など絶対に見せたくなかった。
案内された別部屋に足を踏み入れると、その部屋は他と違ってなぜか湿気が多かった。
この部屋だけ窓がないことも気になったのだが、棚に並べられているそれらを見て、信はぎょっと目を見開く。
「へ、蛇ッ…!?」
棚にはいくつもの竹で出来た長方形の籠が並べられていたのだが、その中に一匹ずつ蛇が収容されているのだ。
初めて見た訳ではないのだが、竹籠に収容されている蛇はどれも種類が違い、初めて見る蛇も多かった。一体何のためにこれだけの数を飼育しているのだろうか。
「すべて毒を持っています。不用意に触らないようにお気を付けください」
「あ、ああ…」
まさか全部が毒蛇だとは思わず、信は狼狽えた。
今回の王賁のような毒は特殊だが、戦で毒を受けることは珍しくない。ここでこんなにも毒蛇を飼育している理由には、治療に用いるからなのだろう。
「信将軍」
医者は一番奥の棚に置かれていた竹籠を手に取り、それを抱えて信の前へとやって来る。
その竹籠の中にいた蛇は、他の蛇に比べると随分と小柄な蛇だった。全長は子供の腕ほどしかない。全身は白いのに、舌と瞳だけは血のように赤く、気味が悪い。
眠っていたところを起こされて機嫌が悪いのか、その蛇は目をぎらりと光らせて、信のことを睨みつけていた。
「この中で一番強力な毒蛇です」
「え?こんな小せぇ蛇が?」
これだけの数がいるというのに、こんな小さな白い蛇が一番強力な毒を持っているということに、信はすぐには信じられなかった。
実力を見た目だけで計り知れないのは人間だけでなく、蛇も同じらしい。
「毒性を考えれば一噛みされれば十分ですが、王賁様に症状の改善が見られなければ、さらに噛まれる必要が出て来るかもしれません」
「………」
信も毒を受けたことがないわけではなかったが、自らが望んで毒を受けることになるのはこれが初めてであった。
口ごもった信を見て、医師の男は確認するように彼女の顔を覗き込む。
「…代わりの候補者を探すのなら、今ならまだ間に合います」
「だ、大丈夫だ!」
どうやらまだ迷っていると誤解されたようで、信は咄嗟に言い返す。
彼女の覚悟を受け入れたのか、医師の男は力強く頷いた。
「では…」
蛇が入っている竹籠の蓋を開け、信に差し出す。
赤い目をした白蛇は小柄な体格に似合わず、大口を開けて威嚇をしている。まるで触るなと警告しているようだ。
「う…」
信は籠の中に右手を入れようとして、すぐに左手へすり替えた。もしも毒のせいで腕を落とすことになったら、利き腕が使えなくなるのは困ると思ったからだ。
恐る恐る左手を蛇の目前に伸ばすと、
「あいたッ!」
親指の付け根をカプリと噛まれ、咄嗟に悲鳴を上げた。しかし、噛まれた痛みはさほど強くなかったのは幸いだった。
反射的に手をひっこめたのと同時に、すぐに医者が竹籠の蓋を閉じる。棚に蛇を戻すと、信が噛まれた左手をまじまじと観察する。
血は出ていなかったが、小さな二穴があり、蛇の牙がしっかりと食い込んだことが分かる。患部を見ると、左手がずきずきと痛み始めた。
見舞い
「これから一刻もしないうちに、ひどい悪寒が来るでしょう。熱が上がる前兆ですので、部屋でお過ごしください」
「あ、ああ。その前に、王賁に会うことは出来るか?」
「はい。ただ、今は処置中かと…」
「一目見るだけでいい」
治療の邪魔はしないというと、医者は王賁がいる部屋に案内してくれた。
彼は寝台に横たわっており、数人の医者が彼に鍼を施している最中であった。
抗毒血清を飲ませるという治療方針で決定したというのに、何をしているのかと問うと、王賁の体内にある毒を一か所集めているのだそうだ。
「気血の流れを整えながら、全身に回っている毒を両目に集めています」
信はぎょっとした。
「りょ、両目って!んなことしたら、本当に目が見えなくなっちまうんじゃ…!」
「俺の意志だ。余計な口を出すな」
信の疑問に答えたのは王賁自身だった。瞼が閉じられていたので眠っているのかと思ったが、どうやら起きていたらしい。
玉座の間で倒れた時と違い、今は楽に呼吸をしていたので医師団の処置のおかげで少しは落ち着いたようだ。
「お前の意志って…なんで目なんだよ」
他に候補があったのではないかと信が聞き返すと、今度は王賁の鍼を施している医者の一人が信の疑問に答えた。
毒を一か所に集めるにあたっては、心臓と頭から離れた場所が候補となる。
王賁の希望を聞き、彼は武器を握る両手から離れたところ、戦場を駆ける両脚から離れたところにして欲しいと答えたのだそうだ。
療養中は医師団が近くにいるし、夜目が弱くなっていたのは随分と前からなので、今さら視力に影響したとしても問題はないという理由から目を選んだそうだ。
しかし、信は不安な表情を隠せなかった。
(もし、解毒剤が効かなかったら…)
言いかけて、信はその言葉をぐっと飲み込んだ。
自分が不安を口にしたところで、何も変わらない。それに一番不安なのは王賁のはずだ。
「…今、医師団たちが薬を作ってくれるからな。それまでへばるんじゃねえぞ」
自分が抗毒血清を作る材料になったとは言わず、信は力強く王賁を励ました。
王賁は何も答えなかったが、僅かに口角を持ち上げたのを見て、信もつられて微笑む。
「っ…」
そのとき、まるで冷水でも浴びせられたかのように、全身に突き刺すような寒気を感じた。先ほど医者が言っていた熱が出る前兆の症状だろう。
「…信?」
僅かに信の動揺を聞きつけたのか、目を閉じたままの王賁が怪訝そうな表情を浮かべる。
「な、なんでもねえ!それじゃあ、俺は用があるから…あ、でも宮廷にはいるから、なんかあったら呼べよな!」
王賁が両目を開いていたのなら、もしかして普段から嘘を吐けない信の顔を見て、何か隠していると勘付いたに違いない。
こればかりは王賁が目に毒を集めると選択してくれたことに感謝した。
医者に案内された部屋は、王賁が治療を受けていた部屋と同じ構造になっていた。
「うううー…さみぃ…」
何重にも重ねられた布団の中で、信は自分の体を両腕で抱き締める。寒くて堪らないのだ。
真冬に着る厚手の羽織も借り、青銅の火鉢で部屋も暖めているというのに、まるで氷の中に閉じ込められているような悪寒のせいで、体の震えが止まらない。
寒さが落ち着けばすぐに熱が上がると医者は言っていたが、幼少期から大きな病にかかることなく、ずっと健康体で生きていた信にはこの寒さは随分と堪えるものだった。
多少の風邪なら経験したことはあるが、こんな悪寒を経験するのは初めてだったので、信はつい弱音を吐いてしまいそうになる。
しかし、顎が砕けてしまいそうなほど強く奥歯を噛み締めて、声を堪えた。
(負けてたまるか!)
たかだか悪寒如きに弱音を吐くなんて情けないと自分に喝を入れる。
王賁は毒を受けてから今もなお苦しんでいるのだ。抗毒血清を作って彼を助けるためにも、こんなところで負けるわけにはいかない。
少しでも寒さを紛らわそうと、両手で体を擦った。
医者の話では、体が毒に対する免疫を作るために、これから高い熱が出るのだという。その熱が引いた頃に血を採取し、まずは一度目の抗毒血清としてそれを王賁に飲ませる。
五日間、血清を飲ませ続けて王賁の症状が改善すれば、すぐに信の解毒治療も始めるとのことだ。もしも王賁の症状が改善しなければ、信の解毒治療は後回しになるどころか、もう一度あの毒蛇に噛まれなくてはならない。
あの白蛇の解毒法は分かっているというが、あまりにも強力な毒が体内に留まっていれば王賁の症状が改善する代償に、自分の臓器や手足が壊れてしまうのではないかという不安があった。
二度と戦場に立てなくなるのは自分か王賁か、二人の命が天秤にかけられていた。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
一度目の投薬
一刻ほど経った頃、信はそれまでの悪寒が嘘だったのではないかと思うほど暑さに襲われ、布団を除けた。
「あ、あっちい…」
全身の毛穴からどっと汗が噴き出て来る。肌が火照っているのが分かり、吐く息も熱かった。
体内の水分が全て出ていってしまうのではないかと思うほど汗が止まらない。用意されていた水甕から杯に水を注いで一気に飲み干した。
「はあ…」
喉は潤ったが、倦怠感が凄まじく、頭がぼうっとする。
先ほどまで悪寒で震え、間を置かずに発熱したせいだろうか。まるで養父の王騎と一戦交えた時のような激しい疲労感もあった。
「う…?」
羽織を脱ごうとして腕を動かすと、左手に力が上手く入らないことに気づく。あの白蛇に噛まれた親指の付け根は青痣のように変色していた。
試しに左手で掌握をしてみたが、こわばりが強く、上手く指を曲げ伸ばしすることが出来ない。
(…利き腕はやめておいて正解だったな)
咄嗟に右手を庇って、代わりに左手を噛ませた自分を褒めてやった。
解毒すれば左手も問題なく使えるようになるだろうか。もしも使えなくなったり、左手を落とすことになったらと色々と不安はあったが、信は考えないように別のことに意識を巡らせた。
熱が出たのも、左手に症状が出たのも、今まさに体内で毒に対する免疫が作られている証拠だ。
高熱のせいでぼうっとする頭で解熱剤の処方をしてもらえないかと考えたが、部屋に案内されるときに、王賁に飲ませる解毒剤の効果の妨げになる可能性があるから、薬を飲むことは許されないと医者が話していたことを思い出す。
王賁が薬を飲み続ける五日間、自分は毒に苦しまなくてはならないということだ。
(わかっちゃいたけど…結構キツいかもなあ)
息を荒げながら、信は天井を見上げた。
しかし、自分が耐えた先に王賁が救われるのだから、なんとしてもあと五日は耐えねばならない。
高熱のあまり、意識が朦朧としていたのだが、眠ってしまっていたらしい。
小さな物音に意識を引き戻されて重い瞼を持ち上げると、男の医者が何か処置の準備をしている姿があった。
眠る前よりは体の倦怠感は幾度か楽になっていた。
暑さを感じなくなっており、どうやら熱が引いたらしい。汗を流し過ぎたせいか、肌寒さを感じるほどだった。
「………」
声を出すのも億劫だったので見つめていると、信が目を覚ましたことに気が付いたのか、医者の男が頭を下げた。
「これより、王賁様に一度目の投薬を行います」
医師の男が短剣を手に近づいてきて、そっと左手首を掴まれた。
失礼しますと、毒蛇に牙を立てられた親指の付け根に短剣の先端が突き立てられる。
僅かな痛みに顔をしかめたが、痛みは長くは続かなかった。
左手から流れる血液を数滴だけ器に流し、器の中にもともと入っていた薬湯とかき混ぜる。どうやら採取する血液は少量で十分らしい。
簡単に止血をした後、医者の男は製薬したばかりの解毒剤を王賁に飲ませるために部屋を出て行った。
王賁を苦しめる症状が少しでも改善するように、信は祈らずにはいられなかった。
「うー…?」
先ほど短剣で傷をつけられた左手に再びこわばりが現れる。肘から先の感覚が鈍くなっていて、力が入りづらい。
眠る前よりも青痣の範囲が広まっているような気がして、信は思わず目を背けてしまった。
王賁の解毒が終わるまでは何としても耐えねばならない。
まさか毒を受けた初日からこんなにも苦しい想いをするとは思わなかったが、弱音を吐く訳にはいかなかった。
二度目の投薬
目を覚ました信は窓から差し込む日差しを見て、すでに昼を回っていることに気づく。
起き上がろうとしたのだが、倦怠感がひどく、上体を起こすのもやっとだった。
寝台に手をついた時、蛇に噛まれた左手の青痣が広まっていないことに安堵する。昨夜よりは手のこわばりも軽くなっていた。
「うう…」
時間をかけてなんとか体を起こしてみたものの、立ち上がる気力が湧かない。ずっと横になっていたいという欲求が凄まじいほど、鉛を流し込まれたかのように体が重かった。
昨夜、蒙恬の屋敷を出てから何も口にしていないので、胃は空っぽになっていたのだが、食欲は全くなかった。
寝台の傍にある台に食事が用意されていたのだが、手をつけることなく、信は再び寝台に横たわる。
熱が上がる前にたくさん汗をかいたので、体がべたべたとして気持ちが悪い。湯浴みをしたかったが、支えなしではとても一人で動けそうになかった。
(王賁は…)
昨夜、医者が王賁に薬を飲ませてくれたはずだが、どうなったのだろうか。
あと四日間は薬を飲ませ続けなくてはならないので、初日に飲ませただけではまだ改善していないかもしれないが、少しでも楽になっていてほしい。
「…王賁…」
這ってでも王賁の様子を見に行きたかったのだが、信は再び起き上がるほどの体力も気力もなく、気づいたらそのまま意識を失うようにして寝入ってしまった。
「…様、王賁様」
何度か名前を呼ばれ、王賁ははっと目を開いた。
「っ…」
しかし、目を開いているはずなのに視界は真っ暗で、王賁は思わず息を詰まらせる。
それから今は医師団の管理下で治療を受けていることを思い出す。
一時的に毒を両目に集めており、外部から入る光さえも刺激として与えぬよう、今は両目を包帯で覆われているのだった。
暗闇の世界では今が昼なのか、それとも夜なのか、王賁には分からなかった。
「お薬をお持ちしました」
昨日薬を飲ませてくれた男の医者の声がする。支えられながらゆっくりと体を起こすと、左手に薬の入った器を、右手に匙を握らされた。
何も映ってはいないのだが、両手の感覚はしっかりとしている。王賁は匙で中に入っている薬をすくい上げた。
色々な薬草を磨り潰して製薬したのか、水気の多い薬であることは昨日口にして分かった。何色をしているのかは分からないが、とにかく苦みが強い。鉄さびのような味も混じっている気がする。
しかし、昨日よりも体が楽になっている感覚は確かにあった。視界が利かないのは仕方ないことだが、手のこわばりもないし、息苦しさやだるさもない。
昨日は器と匙を渡されたものの、手のこわばりが強かったため、医者が薬を飲ませてくれたのだが、まさかこんなすぐに効果があるとは思いもしなかった。
匙を使って薬を口に含む王賁の姿を見て、医者がほっとしたように息を吐いたのが聞こえた。
苦みを堪えながら、何度かに分けて薬を飲み切ると、医者が王賁の手首に触れ、脈を測った。
「…脈も落ち着いております。昨日よりも顔色が良くなりましたな。この調子なら薬を飲み切ることが出来れば、解毒が叶うやもしれません」
「一晩で随分と楽になった。感謝する。貴重な薬草を使ったのか?」
医師団の技術は鍼治療に特化していると聞いたが、こんなにも体が楽になったのは毒を一か所に集めることと、調合してくれた薬のお陰だろう。
「ええ、まあ…」
薬の原料について問うと、医者は僅かに言葉を濁らせる。しかし、そのことを王賁は大して気に留めなかった。
「快方に向かった際は、どうぞ信将軍に今のお言葉をお伝えください」
「…そうだな」
王賁は素直に頷いた。
彼女がここに連れて来てくれなかったのなら、治療を受けることは出来なかった。
きっと毒に蝕まれて、視力や手足を失い、将としての立場も、生きる希望も失っていたことだろう。
解毒の治療が終わり、視力が元に戻ったのなら、真っ直ぐに彼女の目を見て感謝を伝えようと王賁は考える。
…薬湯の後味は、未だ口の中で尾を引いており、王賁は思わずその苦みに溜息を零した。