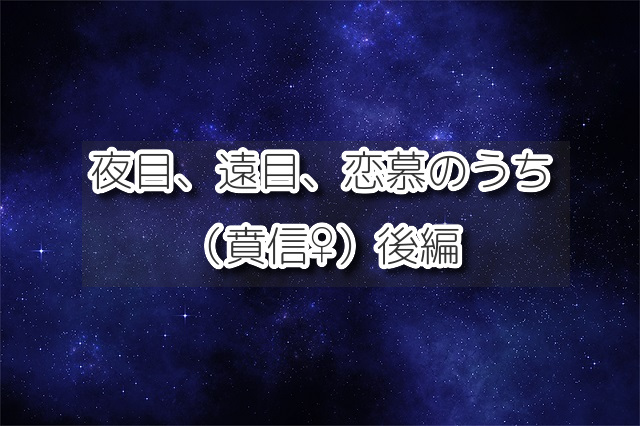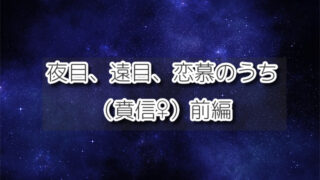- ※信の設定が特殊です。
- 女体化
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 王賁×信/蒙恬×信/シリアス/甘々/ツンデレ/ハッピーエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
解毒
医師団の治療を受けて五日目の夜。陽が沈んだあとに、王賁はようやく両目の包帯を外された。
「ゆっくりと目を開いてみてください」
指示通りにゆっくりと瞼を持ち上げると、部屋の明かりが差し込んで瞳がずきずきと痛んだ。
しかし、その痛みが落ち着いてくのと同時に、少しずつ色を映し出す。これまで靄が掛かっていた視界がすべて洗い流されたように目の前の景色をはっきりと映していた。
「…見える。手指も、不自由はない」
視力だけでなく、両手の震えや痺れもなくなっていた。掌握をしてみるが、問題なく力も入る。
毒を受ける前の自由な体を取り戻したのだと実感し、王賁は長い息を吐いた。医者も大層安堵した表情を見せた。
「解毒は完了したようです。また何かしらの症状が出るかもしれませんので、あと数日はこの部屋で安静にしていらしてください」
「感謝する。これで将としての未来を潰えずに済んだ」
「いえ、とんでもございません。…そのお言葉はどうぞ信将軍にお伝えください」
深々と頭を下げ、医者は他にも執務があると言い、部屋を後にした。
部屋は灯火器の明かりで照らされていたが、以前のように、視界が暗闇に邪魔されることはない。
今までは蛍石の明かりを頼りにしていたが、それも不要になるほど視力が戻ったのである。
「………」
以前のように、目の前の景色を映してくれる両目に対して安堵の感情が込み上げて来て、放心状態になっていた。
信が嬴政と医師団を頼んでくれなかったら、もうこの両目が光を映すことはなかっただろう。
医者に言われたように、信に感謝を伝えなくてはと思うのだが、気恥ずかしさがあるのは彼女に弱みを知られてしまったからかもしれない。
このまま将の座を降りるしかないのだと諦めていた自分に、彼女が喝を入れてくれなかったら、今でも自分は蛍石の僅かな明かりに縋って夜道を歩いていただろう。
これからも信と蒙恬と肩を並べて将の座に就いていられるのだと思うと、胸に歓喜が湧き上がって来る。
礼を言うならすぐにでも伝えるべきだ。あまり日が空くと気恥ずかしさのせいで、伝えられなくなってしまうかもしれない。
自分の治療は宮廷に滞在していると信は話していた。しかしもう夜は遅い。明日必ず感謝を伝えようと心に決め、王賁は寝台に横たわった。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
真相
翌朝。目を覚ましても視界は変わりなかった。寝台から降りて体を動かしてみても、両手は自由に動かせる。
解毒によって症状が消失したとはいえ、しばらくは安静にするようにと医師から言われており、療養に専念しなくてはならない。
「っ…」
窓から差し込む陽の光が目に当たり、突き刺さるような痛みが走った。眩しくて目が開けていられないのだが、医者が言うにはそれも時間が解決するという。
窓から差し込む温かい光くらいならば、問題なく目を開けられるし、はっきりと色も分かる。
槍を振るうのもしばらく控えるよう言われたものの、治療を乗り越えて視力を失わずに済んだ王賁にとって、この療養期間は少しも苦痛ではなかった。
しかしこの五日間、ずっと横になっていたせいで下肢の筋力も衰えていることを自覚し、王賁は一刻も早く戦に出陣出来るように体を取り戻さなくてはと考えた。
しかし、まずは信に礼を言わなくてはならない。
見返りに何を要求されるのかは分からないが、彼女のことだから美味い酒と料理を要求されそうだ。僅かに口角を持ち上げ、王賁は部屋を出た。
広い宮廷を歩き回ったものの、どこにも信の姿がない。礼を伝えようと思ったのだが、先に屋敷へ戻ってしまったのだろうか。
信も自分も将としての執務がある。いつまでも宮廷に留まっている訳にもいかなかったのだろうと勝手に納得し、王賁は自分の屋敷へ帰還することを決めた。
書簡で礼を伝えるわけにはいかない。一度屋敷に帰還したあとに、信の屋敷に訪ねようと考えた。
療養の間に借りていた部屋で荷を纏めていると、蒙恬が訪れた。
「元気そうで何より」
本当にそう思っているのか疑わしいほど不満気な顔で、快気祝いの言葉をかけられた。
先日見舞いに来た時は、軽口を叩きながらも心配してくれていることが声色から察していたのだが今日は違う。
言葉と態度がつり合っていない時の蒙恬は、大抵本心を隠している。それなりに長い付き合いなので分かっていたが、今の状況に限っては悪い冗談とも思えなかった。
「何の用だ」
「まさか帰るつもりか?まだ信に会ってないだろ」
王賁は頷いた。宮廷のどこにも彼女の姿がなかったから、屋敷に戻っているのだと王賁は信じ込んでいた。
しかし、どうやら蒙恬の口ぶりから察するに、まだ信は宮廷にいるようだ。
「…賁。今回の解毒治療について、俺の口から説明してあげる」
「そんなものは不要だ」
もう解毒は出来たのだから、その経緯など知ったところで意味はないと王賁は言い捨てる。構わずに荷を纏めていると、
「聞け」
蒙恬はそれを許さないと言わんばかりに、王賁の肩を掴む。肩に指が食い込むほど強く力を込められて、思わず眉根を寄せた。
「信は、お前に飲ませる血清を作るために、自ら毒を受けたんだ」
「…は?」
その言葉を聞き、王賁はまさかと目を見開く。
眦が裂けんばかりに目を開いた蒙恬に睨まれ、決して冗談ではないことを悟る。
医学に携わっていない王賁でも、血清に関しての知識は浅く持っていた。体に毒を入れることで免疫を作り、その血を抗毒血清と呼び、すなわち解毒剤にするのだと。
―――快方に向かった際は、どうぞ信将軍に今のお言葉をお伝えください。
治療を開始したばかりの頃に、医者がそう言った言葉を思い出す。昨日包帯を外された時も、医者は似たようなことを言っていた。
あの時は嬴政と医師団の協力を求めた信の行動のことを指しているのだとばかり思っていたのだが、そうではなかった。
そして、医者が解毒剤の詳細を語ろうとしなかった理由と真相が結びついた。
信が抗毒血清を作るために自らの身を差し出したからで、恐らくその事実を医師に口止めをしていたからだ。
蒙恬は幾度か王賁の見舞いにも来ていたし、信にも会ったと話していたが、彼女の詳細については語ろうとしなかった。蒙恬自身も信から口止めをされていたのだろう。
信の心情は分かる。もしも自らを犠牲にして解毒剤を作るなど言ったら、王賁は確実に止めていたし、その解毒剤を飲むことはしなかった。きっと自分ならそうしたに違いないと王賁は断言出来た。
「…今、信は医師団の監視下にある。お前を助けた代わりに、信が死ぬかもしれない」
殺意に近い怒りが込められた瞳に睨まれながら、信じられない事実を教えられ、王賁は心臓の芯まで凍り付いてしまいそうになった。
普段から冷静沈着な友人があからさまに狼狽えている姿を見て、蒙恬は「やっぱりそうか」と溜息を吐いた。
「…まあ、信のことだから全部黙ってると思ったけど…俺も口止めされてたし」
予想通り、蒙恬は今回の件を信から口止めされていたらしい。
真実を打ち明けた蒙恬は、もうこれ以上隠しても意味はないと悟ったのか、今までの経緯を語り始める。
毒に侵された王賁に一刻の猶予も残されていないと知るや否や、信は自分が血清の材料になると医師団に名乗り出た。
抗毒血清を作るために協力してくれる人材を選別をする時間も惜しいと、信は医師団を説得したのである。
「医師団も手を尽くしてくれているから、どうなるかは信次第だろうけれど…でも、お前は今すぐ会うべきなんじゃないか。信に言うことがあるはずだろ」
最後まで蒙恬の言葉に耳を傾けることなく、王賁は弾かれたように駆け出していた。
激昂
宮廷を走り抜けて、医師団の仕事場がある建物に向かった王賁はそこで信の姿を探した。
今回のことで礼を言うために宮廷を探し回ったが、医師団のもとにいるとは全くもって盲点であった。
自分の世話をしてくれた医者を見つけ、信のことを問い質すと、彼はこれまでのことを白状したのだった。どうやら彼も信から口止めをされていたらしい。
だが、素直に打ち明けたということは医者の見立てでも、信の状態が良くないということだろう。王賁は氷の塊を背中に押し付けられたような感覚に陥った。
すぐに信にいる部屋に案内させると、そこには変わり果てた彼女の姿があった。
信は寝台の上で眠っていたのだが、胸が上下に動いていなければ、つまりは呼吸をしていなければ死人だと見間違えてしまうほど、その顔色は悪かった。
「信…」
やっと喉から絞り出した声は情けないほどに震えていて、しかし、名前を呼ぶのが精いっぱいだった。
まるで笛を吹くようなか細い音が信の口から洩れている。今にも止まってしまうのではないかと思うほど呼吸は弱々しい。
布団を掛けられていたが、覗いている左腕は包帯で覆われていた。
包帯の隙間から見えた手指は人間のものとは思えないような紫色になっており、今にも張り裂けてしまいそうなほど膨れ上がっている。
これはもう手遅れだと王賁は直感した。
「なぜ、ここまで…」
膝から力が抜けてしまい、王賁はその場にずるずると座り込んでしまう。
「…お前の解毒が終わるまで、信は毒を受けた体で五日間も過ごしたんだ」
どうやら追いかけて来ていたらしい蒙恬が、ゆっくりと背後から近づきながらそう言った。
王賁の解毒治療に必要な血清を提供するために、信は五日間も強力な毒を受けた状態で過ごしていた。
無事に王賁の解毒が完了し、すぐに信の解毒治療も始まったのだが、これほどまでに根付いた毒を取り除くのは容易ではない。
適切な解毒薬を飲ませているというのに、症状が少しも改善しないのだそうだ。
わざわざ蒙恬から説明を受けなくても、今の彼女の状態を見ればそんなことは嫌でも理解出来た。
包帯に包まれた左手に触れると、血液が通っていないのではないだろうかと思うほど、氷のように冷え切っていた。
そこが毒蛇に噛まれた箇所らしい。利き手ではなく左手を選んだのは信らしいなと思うが、今はそれどころではない。
「…誰が、お前に助けを求めた」
腹の底からせり上がって来たのは、怒りだった。
このまま信が死んでしまうかもしれないという恐れの感情よりも、怒りが勝ったのである。
それは信の死が自分のせいだと認めたくない罪悪感の裏返しでもあった。
「俺のことなど、捨て置けば良かっただろうッ!」
毒に蝕まれ、二度と戦場に立てなくなった役立たずの将など見殺しに出来たはずだ。
蒙恬の屋敷で酒を飲み交わしたあの夜、信に気づかれなければきっとこんなことにはならなかった。
もう治療法がないと諦めていたが、信はそうではなかった。嬴政と医師団の力によって、最後の治療法を見つけてくれた。
それがまさか信自身の命と引き換えという治療法だったなんて、誰が想像出来ただろう。
解毒剤と言われて飲まされていたあの苦い薬の正体が信の血だったのだと思うと、王賁は喉を掻き毟りたい衝動に襲われる。
しかし、どれだけ信に罵声を浴びせたところで、彼女の体を蝕む毒が抜けることはない。
信が無理やりにでも自分を宮廷へ連れて来たおかげで解毒が出来たことに、強い感謝の気持ちが込み上げたのだが、彼女の命と引き換えに生き長らえたことだけはどうしても認められなかった。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
危機
「もう、助からないのか」
自分でも驚くほど冷静に、王賁は医者に訪ねていた。
王賁の背後で医者は深々と頭を下げながら、重い口を開く。
「解毒剤の量を増やし、全てお飲み頂ければ、確実に軽快するのですが…ただ…」
「構わん。続けろ」
言葉尻を濁らせたので、王賁は続けるように指示する。
「もう呼びかけにも反応がなく、薬を口に含ませても飲み込むことが出来ずにいるのです。水や食事も…」
解毒剤だけでなく、水や食事も飲み込めぬほど衰弱しているのだと聞かされ、王賁は鈍器で頭を殴られたような感覚に襲われた。蒙恬も体の一部が痛むように眉根を寄せている。
医者の手には今煎じたばかりの解毒剤があった。口に流し込んでも飲み込む力がなく、眠りながら吐き出してしまうらしい。
口に流し込むのは簡単だが、飲み込ませるのは医者でも至難の業だ。少量でもいいから解毒剤を飲ませないと、もう命の灯は消えゆく一方なのだと医者は宣告した。
「…貸せ」
解毒剤が入った器をふんだくり、王賁は迷うことなく口に含んだ。
濃い緑色のどろりした煎じ薬の苦さが舌の上に広がった瞬間、反射的に吐き出してしまいそうになった。しかし、王賁は強く拳を握り締めてそれを堪えると、信に唇を重ねた。
血色の失った唇も氷のようで、人間と唇を重ねているとは思えないほど冷たかった。
信と唇を重ねたのはこれが初めてではない。以前、酒の酔いによって魔が差したのだ。
互いに忘れようと誓った過去だが、あの時の口づけとは比べ物にならないほど、無機質なものだった。
「ん…」
薬を口移しで流し込むものの、信が喉を動かす気配はない。意識がないのだから当然だ。
しかし、王賁は信の頬をしっかりと掴んで顔を固定させると、解毒剤を嚥下するまで唇を塞いだままでいた。
「っ…うぅ、ん…」
僅かに呻き声が洩れる。唇を塞がれて息苦しさを感じているのかもしれない。
しかし、僅かに信の喉が上下に動いた気配を感じ、王賁は唇を離そうとした。その時、
「う…!」
きりきりと下唇が摘ままれるように痛み、思わずうめき声を上げた。
「賁?」
その声を聞き付けた蒙恬が心配そうに駆け寄って来る。
咄嗟に王賁は信から顔を離したが、口の中に解毒剤ではない苦みが広がって、下唇の痛みが尾を引いている。手で拭ってみると血がついていた。どうやら信に下唇を噛まれたらしい。
「優しい口移しのつもりが、噛まれたんだ?」
下唇に血が滲んでいるのを見て、蒙恬が肩を竦めるように笑う。
気にせずに王賁が信に目を向けると、彼女は解毒剤を飲み込んでくれたようだった。意識がない中でも苦みを感じているのか、僅かに眉を寄せている。
毎度噛みつかれるのはごめんだが、口移しなら解毒剤を飲ませることが出来そうだ。医者もほっとした表情を浮かべている。
「王賁だとまた噛みつかれるかもしれないから、次は俺が飲ましてあげるよ」
明るい声色で蒙恬が提案する。顔は笑っているが、目が本気だったので決して冗談ではないことが分かった。
「いらん。俺がやる」
「えー?信は賁からの接吻嫌がってるみたいだけどなあ。俺は信になら舌を噛まれてもいいけど」
「………」
無言で睨みつけると、恬がこちらの怒りをますます煽るように蒙恬が軽快に笑った。
「冗談だって。信に救われたお前が、責任もってちゃんと解毒剤を飲ませてやれよ」
「無論そのつもりだ」
その返事を聞いた蒙恬は満足そうに頷いた。
「唇が使い物にならなくなったら俺が代わってあげるから、いつでも呼んだらいい」
「貴様はとっとと帰れ」
殺意を感じ取ったのか、蒙恬はさっさと踵を返して部屋を後にした。
風前の灯火
次に薬を飲ませる時刻に部屋を訪れると、驚くことが起きた。相変わらず顔色は悪いままだったが、ずっと眠り続けていた信が僅かに目を開いていたのである。
「信!」
寝台に駆け寄ったのはほとんど無意識だった。
「分かるか」
「…、……」
声を掛けると、信が唇を震わせた。しかし、唇の隙間から掠れた空気が洩れるばかりで、声にはなっていない。
台の上に置かれていた水差しを手に取って、それを彼女の口元に当てようとして、王賁は自分の口に水を含んだ。虚ろな瞳で信が王賁の行動を見つめている。
「っん…」
薬を飲ませた時のように水を口移しすると、信の目が大きく開かれた。
「ぅ、ん、んんっ…」
氷のように冷え切った手で力なく体を押しのけようとしたので、王賁は彼女の両手を押さえ込んで水を流し込む。
「ッ…!」
反射的に喉を動かして水を飲み込んだ信は、またもや抵抗しようとして、王賁の唇に再び噛みついたのだった。先ほどの傷口が再び開いてしまう。
唇が血が滴り、信の口の中に流れ込んでしまったのか、彼女は血の味にますます顔をしかめていた。
「………」
なんとか顔を離すと、信がぼんやりとした表情で王賁の事を見据えている。瞳は開いているはずなのに、目は合わなかった。
「…信?」
声をかけても反応がない。それどころか、瞼がゆっくりと閉ざされていく。
やっと感謝を伝えられると思ったのに、自分を助けた代償を信がその命で払おうとしているなんて、認めたくなかった。
「信っ…目を覚ませ!」
泣きそうな声で名前を呼んだあと、王賁は思い出したように台の上にあった解毒剤を口に含んだ。
慣れることのない苦みに再び吐き気が込み上げるが、構わずに口づける。
「ん…ぅ」
解毒剤を流し込んでも飲み込む気配はまるでなかった。それどころか薄く開いたままの口から解毒剤が溢れ出てしまう。
「飲めッ!ここでくたばるのは許さんぞ」
しっかりと顔を固定させながら、王賁は口移した解毒剤を飲むように指示をした。つい声に怒気が籠ってしまう。
彼女の耳にこの声が届いているのかどうかは分からないが、怒鳴らずにはいられなかった。
毒蛇の傷痕
「…、……」
信は薄口を開いたまま眠り続けていた。王賁は再び解毒剤を口に含むと、先ほどよりも乱暴に彼女の顔を押さえ込んで口移す。
「う…」
僅かな呻き声がしたものの、もう噛みつかれることはなかった。噛みつく気力もなくなってしまったのだと思うと、それだけで王賁は心臓の芯が凍り付いてしまいそうになる。
「…、っ…」
心の中で何度も解毒剤を飲むように訴えながら、王賁は信と唇を重ねたままでいる。
…やがて信の喉が上下に動いたのを察して、王賁はようやく唇を離した。
「こほっ…」
小さくむせ込んだ声を聞き、王賁が視線を下ろす。涙で潤んだ瞳と目が合った。
「信?」
「お、う…ほん…?」
掠れた声で名前を呼ばれた途端、王賁の瞳に熱く込み上げるものがあった。
目を覚ますようにと何度も願っていたはずなのに、いざそれが実現されると何を話すべきなのか分からなくなる。
しかし、意外にも先に口を開いたのは信の方だった。
「よか、った」
まさかこんな状態で彼女からそんな言葉を掛けられるとは思いもしなかった。
自分の身を案じるのではなく、王賁が解毒治療を終えたことに安堵しているらしい。
「なにが良かっただ、このバカ女ッ」
安堵した束の間、先ほどよりも怒りが込み上げて来て、王賁は彼女の体を抱き締めた。氷のように冷え切った体に、王賁は自分の体温を分け与えるように包み込む。
「だ、って、こうする、しか」
言い訳じみた言葉に、王賁はますます苛立ちを覚える。自分を助けるために、彼女が命を懸けたのは紛れもない事実だ。
「お前の犠牲で生き長らえただなど、王一族の恥だ。もしもこのまま死んだら舌を噛み切って死んでやる」
「な、んで…素直に、感謝、でき、ね、んだよ」
せっかく助けてやったのに自害を宣言されるとは信も予想外だったようで、顔に苦笑を浮かべていた。
寝台に腰かけたまま、王賁は信の左手を持ち上げた。
毒蛇に噛ませたそこは紫色で下手に触れれば弾けてしまうのではないかと思うほど腫れ上がっていた。
信が普段武器を握るのは反対の腕だが、もしも隻腕になったら戦では不利になる。馬の手綱を握りながら武器を振るうことが出来なければ、騎馬戦は特に不利だ。
「………」
このまま腕を切り落とすことにならないことを祈りながら、王賁は彼女の左手をそっと握り締める。
普段の自分ならば絶対にそんなことはしないと断言出来たのだが、包帯を外したあと、手の平に唇を押し当てた。どこか呆けた様子で信がその姿を見つめている。
「お、王、賁…?」
蛇の歯形が残っている親指の付け根の辺りにも唇を押し当て、強く吸い付く。まだここに毒素が残っているのなら、少しでも吸い出して楽にさせてやりたかった。
しかし、歯型は残っているものの、毒は吸っても出て来ない。未だ信に噛まれた唇がひりひりと痛むが、王賁は構わずに強く吸い付いていた。
「あつ、い…」
急に熱いと言われて、王賁は彼女の左手からようやく唇を離した。ずっと唇を当てて吸い付いていたからだろうか。
これほどまでに冷え切った手に、熱いという感覚は未だ残っている。それだけでも分かって安心した。
王賁は懐から以前まで肌身離さず持ち歩いていた蛍石を取り出した。左手首に紐を通すと、腫れ上がった手指にその石を握らせる。
夜目が利かなくなった王賁が持ち歩いていたものだと思い出したようで、信が何か言いたげな視線を向けて来た。
蛍石の贈り主
「…父から贈られたものだ」
「え…?」
王翦からの贈り物だったのだと知り、信は驚いたように目を見開いた。
先の戦で毒を受けたことを伝えたというのに、彼は何の興味も示さなかったと話していたはずだ。
医者の手配どころか見舞いにも来なかったという王翦に、信は無性な苛立ちを覚えていたのだが、やはり彼は父親として息子のことを気に掛けていたのだ。
王翦のことだから、王賁が夜道を照らすのに使っていたように、そちらの使い道を主旨として贈ったように思う。
御守りとして送ったというのなら、それはそれで父親としての愛情に違いないが。
「………」
蛍石を握らせた信の左手ごと包み込み、王賁はじっと目を伏せた。
言葉に出さずとも、早く信が良くなることを祈ってくれているのが分かる。
(あ、まずい…)
不意に強い眠気が瞼に圧し掛かって来て、信はいけないと思いつつ、瞼を下ろしてしまった。
次に目を覚まさなかったらどうしようという不安を感じる間もなく、信の意識は眠りの世界へと溶けていってしまった。
静かな寝息が聞こえて来て、王賁は目を開いた。
先ほどとは違って、どこか安らいだような寝顔をしている信の姿がそこにあり、王賁は複雑な気持ちを抱く。
「信…?」
名前を呼ぶが、反応がない。
解毒剤を飲み込んだことで症状が回復に向かっていくのなら良いが、今の状態で深い眠りにつくことで、二度と目を覚まさないのではないかという不安があった。
蛍石を大切そうに握り締めてくれているのを見て、王賁はただ彼女の無事を祈るしか出来なかった。
もしも彼女の解毒に犠牲が必要だと言われたのなら、王賁は躊躇うことなく自分の命を差し出しただろう。
せっかく助けてやったのにと信から怒鳴られるのは目に見えていることだが、彼女の命を奪ってまで生き長らえるつもりなどなかった。
それは信も同じ考えなのかもしれないが、だからこそ分かってほしかった。
本当に信の命がこのまま散ってしまったのなら、王賁は自ら舌を噛み切って命を絶つという先ほどの言葉通りにするつもりだった。
愛しい女の命を犠牲にしてまで生き長らえた弱者に、戦場に立つ価値などない。
これからも共に生きたい。まだ彼女に伝えていない言葉がたくさんある。感謝の言葉だって伝えそびれてしまった。
「…死ぬな、一緒に生きろ」
王賁は僅かに開いている彼女の唇に、再び自分の唇を重ねたのだった。
…それから、驚くべきことが起きた。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
もう一つの抗毒血清
「王賁様!」
翌朝。信の世話をしていた医者が王賁の部屋に飛び込んで来た。
信に何かあったのだと直感する。最悪の状況が頭に思い浮かび、顔から血の気が引く。
医者の話を聞くよりも先に、王賁は部屋を飛び出していた。
(死ぬなと言ったのに)
一方的に取り付けた約束とはいえ、裏切られた気分だ。自分の許可なく勝手に死ぬなんて絶対に許さない。
「信!」
扉を蹴破る勢いで開けると、昨夜とはまるで別人のような信の姿がそこにあった。
「数日とはいえ、まともに食ってなかったから、どれだけ食っても足りねえ~!お代わりだ!」
それは王賁が良く知る信そのもので、実は毒を受けていなかったのかと思うほど元気に寝台の上で食事を頬張っていたのである。
右手に箸を、左手には椀をしっかり握っており、さらにはお代わりまで所望している始末。
「…は?」
部屋に入るなり、その豹変ぶりを目の当たりにした王賁は、夢でも見ているのではないかと思わず自分の頬を捻った。夢ではなかった。
「あ、王賁!」
何杯目かのお代わりの最中らしいが、王賁の来訪に気づいた信が満面の笑みで手を振る。
左手は未だに青みがかっていたものの、腫れはすっかり引いており、昨日よりも随分と改善したように見えた。手首には蛍石が括られた紐が巻かれている。
状況が理解出来ない王賁に、追いかけて来た医者が説明を始めた。
…どうやら、信の抗毒血清を飲んで王賁が解毒をしたように、信も王賁の抗毒血清によって解毒が叶ったのではないかという。
遅延性の毒を受けていたことで、図らずとも王賁の中で抗毒血清が出来ていたらしい。しかし、彼女に血を飲ませた覚えはなかったはずだ。
昨日までのことを思い返してみると、
(まさか)
王賁は信に口移しで解毒剤を飲ませていた。その際、下唇に噛みつかれ、血を流したことを思い出す。
たった数滴だったかもしれないが、それが強力な解毒剤の役目を果たしていたのかもしれない。
それだけではない。腫れ上がっていた左手にも、早く治るように願掛けの意味を込めて唇を押し付けた。
もしかしたら毒蛇に噛まれた傷口に血が付着したことで、抗毒血清が働き、図らずとも解毒が叶ったのかもしれない。
医者の見解を聞きながら納得した反面、幾度となく信に口づけをしていたのを他者に見られていたのだと思うと羞恥が込み上げて来る。
しかし、信といえば王賁の気持ちなど露知らず、今度は湯浴みをして来るとまで言い出して寝台から立ち上がった。
「おわッ」
「信!」
信の足元がふらつき、王賁は咄嗟に駆け出して彼女の体を抱き止めた。昨日と違って、人間らしい温もりが戻っていた。
信の体を抱き締めたまま、つい長い溜息を吐いてしまう。
「わ、悪ぃ…」
腕の中で顔を上げた信は、申し訳なさそうに謝罪する。
これだけ元気になったとはいえ、ずっと寝たきりの状態でいたのだ。信の意志と反して、体は随分と弱っている。そして数日の間で随分と痩せたようだ。
王賁も解毒治療を終えてから筋力が衰えたことを実感していたので、無理はさせられなかった。
「王賁?」
抱き締めたままでいると、不思議そうに信が名前を呼んだ。
はっと我に返り、王賁は慌てて彼女から手を放した。振り返ると、医者が一礼して、物音を立てぬように部屋を出ていく姿があった。気を遣わせてしまったようだがありがたい。
「…そうだ。これ、返すぜ」
昨日彼女に渡していた蛍石を差し出される。
昼間の内に陽の光を存分に浴びたそれは、夜には美しく光り輝くことだろう。しかし、王賁はもう足元を照らす必要はなかった。
「いい。お前が持っていろ」
左手はまだ青みがかっており、ひんやりと冷たかった。一晩でこれだけ回復したのなら、数日で左手も改善するだろう。
左手の状態によっては、体にこれ以上毒が廻らないように切り落とすことになるのではないかと危惧していたが、杞憂で済みそうだ。
しかし、完治するまで御守りとして持っておいてほしかった。
「そんじゃあ…もう少しだけ、借りとく。ちゃんと返すからな」
素直に蛍石を受け取った信は少し照れ臭そうに笑った。
「もうこれで夜道を照らす必要はないんだよな?」
確認するように信が王賁を見上げた。頷くと、心底安堵したような表情を見せる。
今は自分が解毒治療を受けている最中だというのに、信は王賁が助かったことを本当に喜んでいるようだった。
(そういうところだ)
いつだって自分を犠牲にして、誰かを救おうとする信に、王賁は無性に苛立ちを覚えた。同時にそれを上回る愛おしさが込み上げて来る。
「夜になっても、ちゃんと俺の顔、見分けられるんだよな?」
その問いにはどんな意図があったのだろう。
考える前に、王賁は彼女の顎をそっと持ち上げていた。
「たとえこの目が潰えたとしても、お前のことなら見分けられる」
唇を重ねる瞬間、信が恍惚とした瞳に涙を浮かべ、ゆっくりと瞼を下ろしていく姿が見えた。
終
ボツシーン・プロット(1470文字程度)はぷらいべったーにアップしてます。
現在このお話の後日編を執筆中です。更新をお待ちください。
王賁×信←蒙恬のバッドエンド話はこちら
嬴政×信のバッドエンド話はこちら