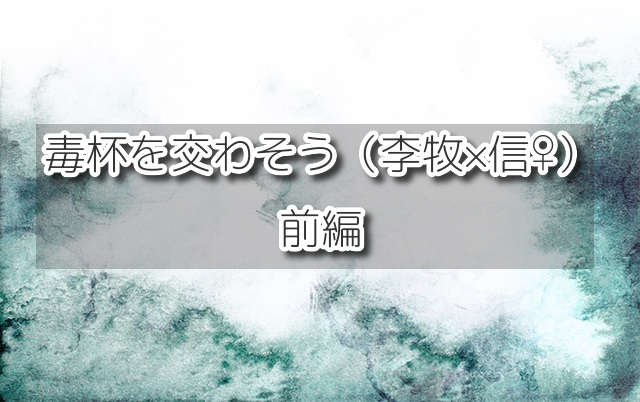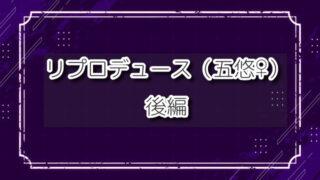- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 李牧×信/毒耐性/シリアス/IF話/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は毒酒で乾杯を(桓騎×信)の番外編です。
毒の盃
秦趙同盟が結ばれた宴の席で、李牧は息をするのも重苦しい不穏な空気を察していた。
天下の大将軍と中華全土に名を轟かせていた王騎の仇でもある自分が歓迎されていないのは当然理解している。
首を守ることは叶ったが、代わりに城を一つ失った。よりにもよって韓皋の城であり、宴を楽しむ気になどなれるはずがなかった。
しかし、目の前にいる呂不韋という男は、この不穏な空気を微塵も察していないのか、両脇に美しい妓女を侍らせて笑顔を見せている。
酒を飲んで気分が良くなっているのだろう。自分の命を奪おうとしていた男と同一人物とは思えなかった。
李牧の隣にいる側近のカイネが何か言いたげに呂不韋を睨んでいたが、李牧は視線を送って彼女を宥めた。
韓皋の城を失う代わりに犬死は免れたのだ。ここで事を荒立てる訳にはいかなかった。
悔しいが呂不韋の交渉の話術には、趙の宰相である李牧でさえも白旗を上げるしかなかったのである。
自分たちが殺された後、人質である春平君も殺され、趙に侵攻するつもりだったのかもしれない。そうなれば秦国の思うつぼだ。
韓皋の城を明け渡すことになったとしても、これ以上、趙の領土を奪われる訳にはいかなかった。
妓女たちと楽しく過ごしていた呂不韋が思い出したように李牧の方を見る。
「めでたい宴ということで、特別な酒を用意したのだが、いかがかな?」
何がめでたい宴だと、隣でカイネが奥歯を噛み締めていたが分かった。李牧は困ったように笑う。自分が素直に感情を露わにしない分、側近たちが怒ってくれるのだと思うと、それだけで心が温かくなった。
「…お気持ちは嬉しいのですが、私はあまり酒が得意ではないのです」
どうぞご勘弁をと丁重に断ったのだが、酒に酔った呂不韋は引く気配を見せない。頬を紅潮させて大らかに笑うところを見ると、相当酔っていることが分かる。
此度の交渉に勝ったことが相当嬉しいのかもしれない。
傍に控えていた侍女に何か告げると、一度席を外した侍女が酒瓶を抱えて戻って来た。
「一杯だけでも御飲みになると良い。宴はまだ続くのだから」
呂不韋が杯に酒を注ぐと、有無を言わさず李牧に突きつけて来た。
先ほど酒が苦手だと言ったばかりなのに、酔ったこの男には耳がついていないのだろうか。
心の中で毒づきながらも、李牧はその杯を受け取らざるを得なかった。
「それでは、一杯だけ」
李牧が酒が苦手なのは本当だったが、こうなっては仕方がない。一杯だけなら良いかと、彼は杯を傾けた。
「え…?」
杯に唇が触れる寸前、横から伸びて来た手によって杯が奪われる。酒が苦手なことを知っている側近の仕業だろうか。
反射的に振り返ると、そこにいたのは、見知らぬ女だった。
妓女でも侍女でもない、赤色の生地と金の刺繍で彩られた華やかな着物に身を包んでいる黒髪の女が、豪快に喉を鳴らして李牧が飲むはずだった酒を飲んでいる。酒豪にも劣らぬ豪快な飲みっぷりだった。
杯を奪われた李牧だけでなく、その場にいる者たち全員が瞠目していると、その女は化粧で彩られた双眸をにたりと細めた。
彼女も既に酒に酔っているのか、頬が紅潮している。自分の唇についた酒をべろりと舌で舐め取り、女は妖艶な笑みを深めた。
「こりゃあ美味い鴆酒だな?どこの鴆者に作らせた?」
女から鴆酒という言葉を聞き、李牧たちははっとした表情になる。
鴆酒というものは一般的に出回らない貴重な酒だ。
なぜ一般的に出回らないのかといえば、鴆酒は酒ではなく、毒として扱われているからである。嗜好品ではなく、暗殺の道具として用いられるものだ。
宴の間に入る時、武器の類は全て預けていた。それは趙の自分たちだけではなく、秦の者たちも同じである。
まさか刃を使わずに、毒を用いて殺そうとするとは、呂不韋はとことん隙のない男だ。
韓皋の城を明け渡したことで、命は見逃してもらえたと思ったのだが、まさか宴の場で暗殺されようとは思いもしなかった。
やはり敵国の地で油断するべきではなかったと李牧は内心舌打つ。
李牧一同が呂不韋に鋭い眼差しを向けると、呂不韋は大して表情を変えずに、顎髭を弄っていた。先ほどまで気分良く笑っていたくせに、今は神妙な顔つきになっている。
「貴様ッ!李牧様を殺そうとしたのかッ!」
カイネの怒鳴り声にも動じず、呂不韋は小さく笑った。
「これは物騒なことを言う。鴆酒というのは、飲んだ相手を即座に殺す毒酒であろう?」
「ああ、そうだ」
李牧から杯を奪った女が頷くと、呂不韋の目が鋭く光った。
「…ならば、なぜそなたは生きていられる?飛信軍の信」
その名前を聞き、李牧は目を見開いた。呂不韋に憤怒の表情を向けていたカイネも、その名前に反応したのか、彼女の方を凝視している。
(飛信軍の、信将軍…?)
飛信軍の信といえば、天下の大将軍である王騎の娘だ。魏の輪虎をも討ち取った彼女の強さには、過去に趙国も辛酸を嘗めさせられている。
秦国だけでなく、中華全土にその名を轟かせている女将軍が目の前にいることに、さすがの李牧も驚いていた。
戦では仮面で顔を覆っているせいで、強さ以外は謎に包まれた女将軍であったが、化粧と派手な着物で彩られているせいか、どこぞの貴族の娘だと言われても頷ける。
しかし、天下に名を轟かす大将軍としての威厳を兼ね備えており、その立ち振る舞いは堂々としていた。
男のような口調と振る舞い方だが、黙っていればその端正な顔立ちに見惚れてしまう男が現れるに違いない。
彼女と道ですれ違ったのなら、きっと振り返っていただろう。李牧はそう思った。
「………」
呂不韋の問いに答えず、信は開けたばかりの酒瓶を手繰り寄せ、まだ飲み足りないと言わんばかりに直接口をつけていた。
女性がそのような振る舞いをするなんてと李牧は驚く。王家といえば名家の一つだが、教養というものを身につけていないのだろうか。
鴆酒は即効性の毒で、解毒の方法が未だ解明されていないものである。一口でも飲めば、たちまち毒が体内に回り、死に至らしめるというものだ。
しかし、呂不韋の言葉通り、信は少しも苦しがる様子を見せていない。
「言いがかりは良してもらおう」
信を睨みつけながら、呂不韋が腕を組んだ。
「もしもそれが鴆酒なら、既にそなたは死んでいるはずであろう?そなたが生きていることが、その酒が毒ではない何よりの証拠ではないか」
「………」
呂不韋の言葉は確かに頷ける。
もしも本当に鴆酒だったとすれば、それを飲んだ彼女は毒に苦しめられて死に追いやられているはずだ。
それがないということは、彼女が李牧から奪った酒が鴆酒でないということになる。
しかし、李牧には一つの疑問があった。
(なぜ彼女は私を助ける真似を…?)
もしも渡された酒が本当に毒だとすれば、信が李牧からそれを奪う理由は何なのか。
彼女の父親である天下の大将軍である王騎は、李牧が軍略で討ち取った。李牧は彼女にとって父親の仇だと言っても過言ではない存在である。
自分を父の仇だと憎んでいるのならば、黙って飲ませていれば良かったはずだ。毒に藻掻き苦しむ自分を見下ろして、せせら笑うことだって出来ただろうに。
からかっている様子は微塵も感じられないし、脅している様子も見られない。この酒が本物であれ偽物であれ、どうして信は鴆酒だと告げたのだろうか。
李牧が怪訝していると、まだ半分ほど残っている酒瓶を呂不韋に突き出し、信がにやりと笑った。
「…確かに俺は死ななかった。…だが、これが鴆酒じゃないって言うんなら、お前もこの酒を飲めるはずだよな?呂不韋」
呂不韋の表情は少しも揺らがなかったが、僅かに彼の瞳が泳いだのを李牧は見逃さなかった。
「………」
信に突き出された酒瓶を受け取ろうとしない呂不韋に、その場にいる者たち全員が視線を向ける。賑やかな宴の席が、重い空気と沈黙に満たされた。
舞台で舞を披露していた妓女たちも、楽器を演奏していた芸者たちも、不安そうな顔でこちらを見つめている。
「…どうなんだ?こんなにも美味い酒なんだ、俺としてはぜひ口移しで飲ませてやっても良いくらいなんだがな」
挑発をするように信が言葉を投げかけ、瑞々しく紅が塗られた唇が歪む。思わず生唾を飲んでしまうほど、妖艶な笑みだった。
「………」
返す言葉がなくなったのか、呂不韋が悔しそうに奥歯を噛み締めたのを見て、やはり本物の鴆酒だったのかと李牧は察した。
「貴様ッ!やはり李牧様を!」
主を毒殺しようと企てていた呂不韋に、カイネが再び憤怒の表情を浮かべて立ち上がる。武器を回収されていなければ、すぐに鞘から剣を抜いていただろう。
「カイネ」
「しかしっ、李牧様!」
落ち着くよう声を掛けると、彼女は納得いかないといった表情で食い下がって来た。
鴆酒を飲ませようとした呂不韋が次にどのような行動に出るのか李牧が警戒していると、あろうことか、彼は肩を震わせて笑い始めた。
「いやあ、これは誠に申し訳ないことをした!贔屓にしている酒蔵から仕入れた珍酒だとばかり思っていたが、まさか猛毒の方の鴆酒だったとは…」
「………」
手のひらを返したように、べらべらと言い訳を始める呂不韋に、やはり食えない男だと李牧は苦笑を浮かべた。
今さら取り繕ったところで、呂不韋が李牧に毒酒を飲ませようとしたことは変わりない事実である。
「ふん」
潔くこの酒が毒だと認めたことに信も納得したのか、飲み掛けの酒瓶を片手に彼女は宴の間から出て行った。
何はともあれ、飛信軍の女将軍のおかげで命拾いをした訳である。
「…すみません、少し席を外します」
側近たちに呼び止められたが、李牧は構わずに宴の間を飛び出した。
廊下に出ると、重苦しい空気から解放された気がして、李牧はようやくまともな呼吸が出来るようになった。
恩
長い廊下を歩いている信の後ろ姿を見つけ、李牧は足早に彼女を追い掛けた。
「飛信軍の信」
名前を呼ぶと、信が面倒臭そうな表情で振り返る。片手には先ほどの酒瓶を持ったままで、先ほどよりも中身は減っていた。まさか鴆酒だと分かりながら、また口をつけたのだろうか
。
毒であるはずのそれを飲みながら、なぜ平然としていられるのか。理由は一つしかない。
突然変異などで毒物に耐性を持つ者がいるということは聞いていたが、彼女はまさにその特殊体質なのだろう。毒が効かぬ体を持つ者に出会ったのは初めてだった。
「…まずは感謝を。あなたのおかげで命拾いしました」
頭を下げながら拱手礼をすると、信は何も言わずに酒瓶に口をつけた。
着物の価値が分からぬものでも高価なものだと分かる着物に身を包み、化粧で美しく象られた顔だというのに、男と何ら変わりない立ち振る舞いに、李牧は苦笑を滲ませた。
酒瓶から口を離すと、彼女は李牧と目を合わせることなく言葉を紡いだ。
「…お前を助けた訳じゃない。俺は鴆酒が飲みたかっただけだ」
おや、と李牧が片眉を上げる。
「鴆酒が飲みたかったのなら、私が死んだ後でも、飲むことは出来たはずでしょう?」
自分を見殺しにすることは出来たはずなのに、なぜそれをしなかったのか尋ねると、信は居心地が悪そうな顔を浮かべた。
信が李牧を殺す動機を持っていることは、誰が見ても明らかである。
李牧が敵国の宰相であること、天下の大将軍と称えられる秦将の王騎を討つ軍略を企てた張本人であること。そして何より、李牧は信にとって親の仇に等しい。
あの場で信が鴆酒を奪わなければ見殺しに出来たはずなのに、一体どうして彼女はそれをしなかったのか、明晰な頭脳を持つ李牧も分からなかったのだ。
沈黙が二人を包み込む。先ほどの宴の間で感じていた嫌な沈黙と違い、李牧には妙に居心地よく感じるものだった。
やがて諦めたのか、信がわざとらしい溜息を吐き出す。
「…これ以上、呂不韋のせいで秦国が卑怯な連中だと思われるのは癪だからな」
「え?」
予想していなかった言葉に、李牧はつい聞き返した。
二度は言わないという意志表示なのか、信は李牧に背を向けて歩き出す。李牧は無意識のうちに、彼女の腕を掴んでいた。
腕を掴まれた信が眉根を寄せて、鬱陶しそうに李牧を見上げる。
「なんだよ」
「…卑怯なのは私の方です。お相子ですから、どうぞお気になさらず」
腕を掴んだ理由にはなっていないのだが、李牧の言葉を聞いた信の瞳がきっとつり上がった。
卑怯だと言ったのは、李牧が王騎を陥れた軍略を企てたからだと気づいたのだろう。
「放せッ」
乱暴に腕を振り払うと、信は歩きながら自分の怒りを宥めるように酒瓶に口づけた。
「毒が効かないとは、不思議な体質ですね」
「………」
背中を追い掛けながら声を掛けるが、信は振り返る素振りを見せない。
ついて来るなという意志表示なのだろうが、李牧は構わなかった。逃げられたら追い掛けたくなるのは男の性分なのかもしれない。
「私は酒があまり得意ではないのですが、鴆酒とはどのような味なのですか?」
「………」
「やはり猛毒ですから、何か特別な味がするのでしょうか?」
「………」
「鴆酒が飲めるのなら、他の毒酒や毒物を口にしても問題はないのですか?」
「………」
信は何も答えずに歩き続ける。そして、李牧も彼女と一定の距離を保ちながら、声を掛け続けていた。
…やがて、李牧の問い掛けの数が十を超えたあたりで、廊下の突き当りに到着してしまい、逃げ場所がなくなった信は憤怒の表情を浮かべながら振り返った。
信の弱点
「お前、しつこいぞッ!さっさと失せろ!」
真っ赤な顔で怒鳴られるが、李牧は少しも怯まない。
純粋な興味があって質問をしているだけだというのに、何一つ答えようとしない信がようやく振り返ってくれたことに、李牧は歓喜の表情を浮かべていた。
「一応、私は客人として招かれている立場なのですが…」
怒鳴られたのに笑顔を浮かべている李牧に、信が気味の悪いといった視線を向けた。李牧がゆっくりと口を開く。
「あなたは私の命の恩人ですから、何かお礼をさせてください」
「要らねえよ。お前にとっては命の恩人でも、俺にとっては違う」
決して馴れ合うつもりはないと言われ、李牧は寂しそうに顔を歪ませた。
厳しい言葉を掛けたはずなのに、李牧が去る気配を見せないので、信は諦めたように酒瓶に口をつける。
手に持っている酒瓶には中身がまだ残っている。さっさと李牧と分かれて、残りを飲み干したかったのかもしれない。
(面白い子だ)
李牧の思考は、あっと言う間に目の前の少女のことでいっぱいになっていた。
飛信軍の秦といえば、秦の六大将軍である王騎と摎の娘であり、仮面で顔を隠して戦う女将軍という情報しか知られていない。
しかし、実際に話してみると、信は一人称も口調も素振りも完全に男を真似ている。王家は名家として知られている存在だというのに、一切の教養を感じられないのだ。
毒に耐性があることももちろんだが、李牧はそのことにも興味を抱いた。
女が将軍の座に就くことはそう珍しいことではない。しかし、名家の生まれでありながら、男に嫁がなかったのは、両親が大将軍だったからなのだろうか。
まだ若い年齢でありながら、中華全土にその名を轟かせるほどの強さを持つ彼女は、秦に欠かせない強大な戦力だ。
是非とも趙に欲しい人材ではあるのだが、李牧が王騎の仇である以上、信が秦を離れることはないだろう。
「…さっさと宴に戻れよ。側近たちが心配してるんじゃねーのか」
廊下の突き当たりにある扉に背を預けながら、信が素っ気なく言う。
呂不韋の企みを阻止して李牧の命を救っただけでなく、まさか宴の間に残して来た側近たちを心配しているとは思わず、李牧は苦笑した。
「随分とお人好しなんですね」
「はあ?」
お人好しという言葉が気に食わなかったらしく、信が鋭い眼差しを向ける。しかし、彼女の睨みに怯むことなく、李牧は言葉を続けた。
「忠義に厚い将なら数多く見て来ましたが、敵の宰相を気遣うなんて、あなたのような将は珍しい。さすが、天下の大将軍の娘だ」
王騎と摎の存在を出すと、信の瞳が再び憤怒の色に染まる。
(やはりそうか)
この数刻の間で、李牧は既に信の情報を幾つか掴んでいた。毒に耐性があるということと、もう一つは弱点についてである。
本能型の将軍に分類される彼女の弱点は、感情的になりやすいということだ。
それが分かっただけでも、優位に策を立てることが出来る。
戦の最中、秦兵の亡骸を見せしめに使えば、罠を疑うこともなく、怒りに我を忘れて簡単に姿を現すに違いない。いかに冷静な副官や兵たちが引き止めたとしても、彼女の行動は抑えられないはずだ。
こちらは韓皋の城を明け渡したのだから、引き換えに秦国の強大な戦力である将軍の弱点を知るくらい安いものだろう。
飛信軍の女将軍の弱点をこうも簡単に入手できるとは思っていなかった。
常に自分たちが優位に立つ情報を探っている李牧の腹の内を、信はきっと見抜くことは出来ないだろう。優秀な軍師がいるのならば話は別だが。
…酒に陶酔すると、人間というものは簡単に口を開くようになる。
李牧が酒を苦手としているのは体質的に酔いやすいというのもあったが、安易に口を開くようになることを嫌悪しているからでもあった。
嫌がらせ
「さっさと戻れよっ」
壁に背中を預けながら、信は去ろうとしない李牧を睨み付けていた。
少しでも手を伸ばせば引っ掻いて来そうな、野良猫のような彼女に、李牧はつい笑みを深めてしまう。
「すみません。夢中であなたを追い掛けて来てしまったので、宴の間がどこだったか忘れてしまいました。案内してくれませんか?」
まさかまだ一緒にいなくてはならないのかと信の顔が強張る。
「私が一人で宮中をうろついていたら、何をしているのかと色々と疑われてしまうでしょう?」
もっともらしい理由をつけて道案内を頼もうとすると、信は腕を組み、顔ごと李牧から視線を逸らす。もう関わりたくないという意志の表れだった。
嫌われているのは分かっていたが、ここまであからさまな態度を取られると、何としてでも捻じ伏せたくなってしまう。
彼女を自分に跪かせたいという征服感が浮かぶのは、李牧が趙の宰相である前に、男という生き物だからである。
「…では」
野良猫のような彼女に引っ掻かれるのを覚悟で、李牧は信のすぐ後ろにある壁に両手をつき、体で完全に逃げ場を塞いでしまう。
「二人で何をしていたのだと、一緒に疑われますか?」
ゆっくりと顔を近づけて、甘い声で囁いた。
普通の女性だったのならば、趙の宰相という地位に上り詰めた男に迫られて顔を赤らめるだろう。
しかし、信は違った。それは敵同士である立場というのもあったが、普通の女性とは大いに違う生き方をしていたせいかもしれない。
唇が触れ合う寸前で、信が片手で自分の口に蓋をする。咄嗟に口づけを防いだ信は、李牧の双眸をじっと見据えた。
「…お前、死にたいのか?」
口を押えていない方の、酒瓶を持っている手が李牧の体を押しのける。
(ああ、そうでした)
一歩後ろに下がってから、李牧は思い出した。
毒に耐性がある彼女はその口で鴆酒を飲んでいた。口づけをしたら、たちまちその毒をもらい受け、絶命していただろう。
少しからかってやるつもりが、いつの間にか彼女に夢中になっていた自分に驚いた。
僅かに戸惑った李牧の表情を見て、信の口元が妖艶につり上がる。
「俺は構わないぜ?これは卑怯でも何でもなく、お前の意志だからな」
「………」
李牧は困ったように肩を竦めた。
咄嗟に信が口づけを防いでくれなかったら、今頃は毒が身体を巡り、苦しみにのたうち回っていただろう。毒から守ってくれたのは、これで二回目だ。
まさかこの短時間で二度も死を回避することになるとは思わなかった。信の弱点を知り、随分と良い気になってしまっていたのかもしれない。
これからやるべきことは山ほどあるというのに、こんなところで自ら死を選ぶところだった。
信が再び酒瓶に口をつけた。
宴の間で、李牧から杯を奪った時はあんなにも美味そうに飲んでいたというのに、今は李牧と二人きりでいる気まずさを紛らわすように、仕方なく飲んでいるように見える。
「あーあ…」
あれだけ量が入っていた酒瓶がすっかり空になると、信は楽しみを失ってしまったかのように、残念そうに溜息を吐いた。
過剰摂取
こんな小柄な女が酒瓶を一つ丸々空にするなんて、中身が毒酒だとしても、信は随分と酒に慣れているらしい。
大の男でも簡単に酔ってしまいそうな量だというのに、まだ飲み足りないと言わんばかりに信はつまらなさそうな表情を浮かべていた。
「…お前もさっさと仲間のとこに戻れよ」
「残念ながら、迷子になってしまったので、道案内をしてもらわないと戻れません」
「………」
ここまでしつこくされると、信も諦めた方が賢明だと察したらしい。
今来た道を戻り出した信の後ろ姿を追い掛けながら、李牧は楽しそうに目を細める。
こちらのしつこい要求に諦めただけなのだろうが、律儀に案内してくれている彼女に、李牧はますます興味が湧いた。
無言で歩き続けていると、遠くから聞こえる楽器や談笑が聞こえた。随分と宴の間から離れてしまったらしい。
「…信?」
自分の前を歩いている信が息を荒くしていることに気付き、李牧は彼女を呼び掛けた。
猛毒である鴆酒を酒と何ら変わりなく飲む彼女だが、酔ったのだろうか。それにしても様子がおかしい。
「大丈夫ですか?」
どうしたのだろうと思い、彼女の肩を掴んで振り向かせようとすると、その手は叩き落とされてしまう。
「う…」
「信ッ?」
手を振り払った後、信は壁に手をついてその場にずるずると座り込んでしまう。李牧は焦った表情を浮かべた。
回り込んで彼女の前に膝をつき、様子を観察するが、まるで高い熱でも出しているかのように顔を真っ赤にして、苦しげに肩で息を繰り返している。
力なく手放した酒瓶を見て、まさか鴆酒の影響だろうかと考えた。毒に耐性があるようだが、こんな大きな酒瓶を一人で空けたのだ。それだけ大量の毒を摂取したということである。
いかに毒の耐性を持っているにせよ、身体が苦しんでいるのかもしれない。
「しっかりしてください。すぐに医師を頼んで来ますから」
ここは宮廷なのだから、皇族専用の優れた医師が常駐しているに違いない。李牧が助けを呼ぼうとした時、後ろから着物を掴まれた。
「放っておけ…死ぬ訳じゃ、ない…」
苦悶の表情でそんなことを言われても説得力がない。しかし、と李牧が言葉を紡ぐと、信はうっすらと涙を浮かべた瞳で李牧を睨み付けた。
「いいんだッ」
「………」
凄まれると、李牧は口を閉ざすしかなかった。
床に座り込んだままでいる信に、せめてどこか横になれる場所に連れて行こうと、李牧は彼女の背中を膝裏に手を回す。
予想以上に彼女の体が軽いことに李牧は驚いた。
「なっ、おいっ…!」
急に体を抱き起された浮遊感に信の瞳に怯えが走る。
「せめて安静になれる場所に連れて行くくらいは許してください」
「………」
腕の中で、信はぷいっと顔を背けた。もう抵抗する気力が残っていないのか、好きにしろとでもいうような態度だった。
彼女の体を抱えながら宴の間があった方まで歩いていくと、料理や酒を運ぶ従者たちが忙しなく廊下を歩いている。
そのうちの一人に声を掛け、用件を伝えると、すぐに空いている客室へ案内してくれた。
案内された部屋は咸陽宮へやって来た李牧たち一同のために用意していた部屋だったのだろう、とても綺麗に整えられていた。
信の体を寝台に横たえると、彼女は不満そうな表情で李牧を睨み付ける。
「…お前、道覚えてないって言ってたよな…」
「宴の華やかな音が導いてくれたんです。運が良かっただけですよ」
返事をするのも億劫だと言わんばかりに、信が顔ごと目を逸らす。
横になってもまだ苦しそうに呼吸をしている彼女を見下ろして、このまま離れて良いものかと李牧は躊躇った。
恐らく、信としては早く一人にしてほしかったに違いない。しかし、李牧は寝台の端に腰を下ろしたのだった。
背中を向けていても李牧が部屋から出て行こうとしないことを察したのだろう、信がわざとらしく溜息を吐いた。
「…早く戻れよ。本当に疑われるぞ」
「いいえ。そちらの丞相殿にちょっとした嫌がらせですよ」
呂不韋の行動を咎める者もいれば、李牧が死なずに残念がる者もいるだろう。
此度の訪問は、悼襄王から寵愛を受ける春平君を救い出すために、宰相の李牧が駆り出されたと言っても過言ではない。
春平君を取り戻すために必ずこちらが動き出すのを想定した上で、呂不韋は彼を利用したのだろう。
商人の出であるあの男にしてやられたという訳だ。損得勘定や交渉術に関しては中華一かもしれない。
韓皋の城を明け渡す代わりに、こちらも命を保証されたとはいえ、こんな気分で宴など楽しめるはずがなかった。
ましてや、向かいの席には辛酸を嘗めさせられた男が座っているのだから、なおさらのことである。
付き添ってくれた側近たちには申し訳ないが、宴に出たくないと子どものようなことを考えてしまった。
嫌がらせ再び
お互いに背中を向けており、表情は見えない。しかし、李牧はもう信が自分に嫌悪感を向けていないことを察していた。
どちらも口を閉ざしてしまったので、部屋に沈黙が広がる。しかし、この沈黙は決して重いものではなく、むしろ李牧の心を穏やかにさせるものだった。
「ん…はぁ…」
信の悩ましい吐息が聞こえるが、呂不韋の笑い声より何倍も良い。
寝台のすぐ傍にある台に水差しと杯が置いてあり、李牧は信に水を渡そうと考えた。酒の酔いを解くのに水は必要不可欠だ。
信が飲んだのは猛毒である鴆酒だとしても、彼女にとっては酒であることに変わりないのだから、水を飲ませれば少しは落ち着くかもしれない。
「信」
杯に水を汲み、李牧は彼女の肩に触れる。まるで火傷でもしたかのように、信の肩が竦み上がったので李牧は驚いて杯を寝台に落としてしまった。
「あっ」
寝台の上に横たわっている信に水をぶちまけてしまい、李牧は焦った表情を浮かべた。上質の着物を濡らしてしまったことと、酔っ払いに水を浴びせてしまった罪悪感に襲われる。
慌てて懐から手巾を取り出して、濡れた箇所を拭こうとするが、信がその手を押さえつける。
「さ、わるな…頼む、から」
「信?」
前髪で表情を隠した信が声を絞り出すように訴えたので、李牧は瞠目した。
手首を掴んでいる信の手が震えていることに気付く。
毒で苦しんでいる様子は少しもないが、この反応は一体何なのだろうか。他者に触られると、困ることでもあるのか。
本当に医師を呼ぶべきなのではないかと思い、李牧は信の顔を覗き込んだ。
両腕で自分の身体を抱き締めながら悩ましい息を吐き、頬を紅潮させて耳まで真っ赤になっていた。寝ぼけ眼のようなとろんとした瞳からは、女の色気が籠っている。
膝を擦り合わせているのが見えて、李牧はまさかと息を飲んだ。
決して悪戯をしたいという気持ちはなく、李牧は彼女の項にそっと指と這わせた。
「は、ぅッ…」
悩ましい声を上げ、信の身体がぴくりと跳ねる。
その反応を見て、彼女の身に何が起こっているのか、李牧は確信したのだった。
酒を飲むと饒舌になったり、陶酔感に浸ったり、様々な変化がある。中には内に秘めていた性的欲求に従う者もいる。
恐らく、信はその類なのだろう。毒に耐性のある彼女には媚薬のようなものなのかもしれないと李牧は考えた。
先ほどから頻繁に早く一人にして欲しいと訴えていたのは、一時的に増した性欲のせいに違いない。
感情的になりやすいという弱点だけでなく、こんな情報まで手に入れてしまった。
毒に耐性があることを知っていたとしても、今のような状態になることを知っている人物は秦にも少ないかもしれない。
まるで新しいおもちゃを買い与えられた子どものように、李牧の目は好奇心で輝き、口元には笑みが浮かんでいた。