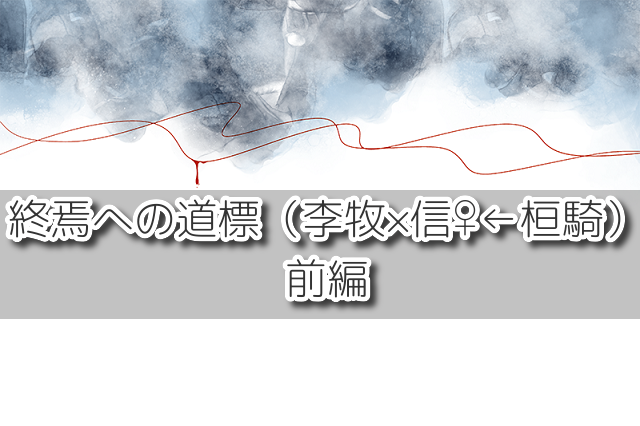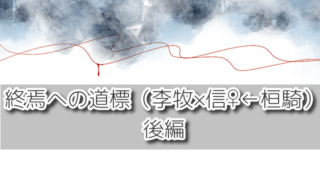- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 李牧×信/桓騎×信/年齢操作あり/ヤンデレ/執着攻め/合従軍/バッドエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は「平行線の終焉」の牧信IFルートです。
防衛戦の成功
お前が好きだと口に出したのは、酒の酔いのせいだっただろうか。それとも口を滑らせたからだったか、よく覚えていない。
その時はまだ、李牧が自分のもとを去るだなんて思いもしなかった。
だからあの時、ずっと胸の奥に秘めていた想いを告げてしまったことを、信は少しも後悔していない。
胸に秘めたままにしていたら、きっと後悔していたに違いないと、今ならそう思う。互いに違う道を歩むことになると分かっていたとしてもだ。
ただ、時々思うことがある。
もしもあの雨の日に、全てを捨てて李牧を追い掛けていたのなら、彼と共に笑い合う未来が待っていたのだろうか、と。
合従軍による秦国への侵攻は、失敗で終わった。
被害は膨大であったが、此度の防衛戦成功は、秦王嬴政の中華統一の夢を中華全土に知らしめたと言っても過言ではないだろう。
嬴政自らが蕞を訪れ、兵に偽装した民たちを奮い立たせることがなければ、戦が始まる前の士気の差から、秦の敗北は決まったようなものだった。
救援に駆け付けてくれた山の民たちに感謝の言葉を贈った後、手当てを受けながら、信は物思いに耽っていた。
(李牧…)
撤退を始める合従軍の中で、信は無意識のうちに李牧の姿を探していた。
彼が本気で彼が秦を滅ぼそうとしているのだと知り、同時に彼の軍略の恐ろしさを痛感した。
まさか水面下でこのような計画を企てていたとは思わなかったが、秦趙同盟の時に再会したあの時にはすでに李牧の中では決まっていたことだったのだ。
―――秦国はいずれ滅びる。そうなる前に、趙に来るんだ。
今思えば、あの時の彼の言葉は、すでに秦を滅ぼす計画を企てていたものだったに違いない。
だからこそ、彼は自分を趙へ来るように説得したのだろう。
それが李牧からの情だと気づいてはいたのだが、秦将である立場をそう簡単に手放すことは出来ず、信は彼との決別を決めた。
きっと李牧からしてみれば、秦を滅ぼすうえで、自分という存在が唯一の心残りだったに違いない。
信がそれを拒絶したからこそ、彼は合従軍の同盟を成してまで、本気で秦を滅ぼしにやって来たのだ。
「………」
信は途端にやるせない気持ちに襲われた。
防衛戦の成功に涙を流して喜ぶ兵たちや、歓喜の声を上げる蕞の民たち。そして勝利の喜びを分かち合うことも出来ぬ多くの犠牲。
もし、秦趙同盟のあの時に李牧の計画を見抜いて、彼を止めることが出来たのなら、こんなにも大勢が血を流すことはなかったのだろうか。
意志の固い彼に、自分が何を言っても聞き入れてくれることはなかっただろうが、それでも何かは出来たはずだ。
後悔と罪悪感に襲われ、信は唇を噛み締めて、拳を握りしめた。
信と李牧の関係を知る者は、今は亡き養父である王騎と、それから桓騎だけ。
最後まで秦を守り抜いた忠義の厚さから、まさか趙との密通の疑いなど掛けられることはないだろうが、趙の宰相である李牧と信に接点が合ったことを知れば、良からぬことを考える輩はきっと出て来る。
桓騎もそれを見越して、周りに二人の過去を告げ口することはしないでいてくれたのだろう。
「はあ…」
大きな息を吐いて、信はその場に座り込んでしまった。
限界まで酷使した体がもう休みたいと悲鳴を上げており、気を許せばすぐにでも意識の糸を手放してしまいそうだ。
合従軍が撤退したとはいえ、もしもまた時期を置いてから、水面下で合従軍に攻め込まれるようなことがあれば、次こそ覚悟しなければならない。
李牧はただでは転ばぬ男である。きっとこの秦国の中で、それを知っているのは自分だけだろうと信は考えた。
しかし、合従軍を結成したのも、秦を滅ぼすための侵攻も、全ては李牧が企てたことであり、此度の責任を取らされるのではないかという不安が募る。
撤退をしていく合従軍とそれを追撃する秦軍を見つめながら、信は李牧の無事を祈っていた。
まだ自分の心には李牧という存在が根強く残っている。そのことを、信は理解していたものの、取り除く術を知らずにいた。
李牧の処刑
蕞の防衛に成功した後、兵たちは被害を受けた領土の復旧作業を中心に行っていた。深手を負った信は、屋敷で療養する日々が続いている。
その日々の中で、李牧の処刑が決まったという書簡を信へ送ったのは、他ならぬ李牧自身であった。
(まさか、そんな…)
木簡の内容を目にした信は、たちまち青ざめる。此度の戦での責任を取らされるのだとすぐに察した。
丞相という地位の剥奪だけで済むことを祈っていたのだが、やはり合従軍を率いてまで持ち掛けておきながら敗北した代償は大きかったようだ。
此度の戦は、初めから秦国に勝ち目のない戦だと誰もが思っており、だからこそ他国も協力したに違いない。
趙の宰相と軍の総司令を務めた李牧の首で、此度の敗北の埋め合わせをするつもりなのだろうか。
彼が仕えている悼襄王が一切の情けを掛けない男であることは噂で聞いていた。
皮肉ではあるが、信の養父である王騎を討つ軍略を授け、趙国に多くの貢献をもたらしたというのに、まさかこんなにも容易く李牧の命まで斬り捨てるとは思わなかった。
(処刑の日は…)
木簡には処刑の日が記されており、場所は雷環広場であるとも記されていた。もう指で数えるほどしか日数は残されていない。
「李牧…!」
心臓の芯までもが凍り付くような感覚に、信は思わず木簡を落としてしまい、その場に膝をついてしまう。
戦で疲弊した傷だらけの体より、心が痛かった。
共に過ごしたあの日々が、目の裏に走馬灯のように目まぐるしく駆け巡る。
激しく脈を打つ胸を押さえながら、まだ自分の中では李牧に対する情が少しも消えていないことを自覚する。彼と決別するには、まだ長い時間が必要だった。
このままでは言葉を交わすことも出来ずに、今生の別れとなってしまうのか。
李牧に対する未練の感情が、信の胸を強く締め上げた。
見舞いのために、桓騎は信の屋敷を訪れた。
顔見知りの従者たちは信と桓騎の関係を知っている。門の見張りをする兵に止められることもなかったし、我が物顔で屋敷を歩いていても従者たちは何も言わない。
桓騎は幼い頃、咸陽で行き倒れていたところを信に保護され、彼女が立ち上げた芙蓉閣という女子供の保護施設で育った。その後、蒙驁のもとで知将の才を芽吹かせた桓騎は、今では秦国に欠かせない将軍にまで成長した。
長年の片思いが実り、信とめでたく結ばれることが出来たのは、今や秦国では民たちにまで広まっている有名な話である。
当然のように、桓騎が信の部屋に入ると、床に座り込んでいる恋人の姿があった。
「…信?」
戦で受けた傷が痛むのかと思ったが、どこか虚ろな表情をしている彼女の異変に気づく。
何があったと問うよりも前に、信の前に落ちている木簡に目がいった。
彼女が落としたらしいその木簡を拾い上げて、内容に目を通すと、みるみるうちに桓騎の顔が強張っていく。
最後に李牧の名前が記されていることに気づき、桓騎もその顔から僅かな動揺を隠し切れずにいた。
(李牧が送って来たのか?)
まさかここで李牧の名前を見ることになるとは思わなかった。
信も彼から書簡が送られて来るとは、ましてやそれが処刑の知らせだったとは予想もしていなかったことだろう。
「あ…桓騎…?」
ようやく桓騎が訪れたことに気付いたのだろう、信が青ざめた顔を持ち上げた。
切なげに寄せられた眉と、弱々しい色をした瞳に涙が浮かんでいるのを見て、桓騎は思わず奥歯を噛み締める。李牧のことが心配で堪らないといった顔だった。
「李牧が…」
未だ体のあちこちを包帯で覆われている信がゆっくりと立ち上がる。
青ざめた顔で、体をふらつかせているところを見れば、まだ療養が必要であることが分かる。
函谷関の防衛を命じられていた桓騎も、蕞と秦王嬴政を守り抜いた信の活躍は聞いていた。
李牧も自ら蕞に赴き、その場で将と兵たちに指示を出していたという。
もちろん兵力から分かるように、合従軍が優勢であり、その勢いのまま落とされると思われていた蕞は、駆けつけた山の民の救援によって守り抜くことが出来た。
しかし、もしも蕞が落ちていたら、李牧は信を殺していたのだろうか。それとも趙へ連れて行ったのだろうか。
そもそも李牧が秦を滅ぼそうとした目的が、彼女と関係していることだとしたら…考えたくもない話だ。
戦以外で二度とあの男の名前を、ましてや、信の口から聞きたくもなかった。
こんな書簡を信に送り付ける李牧が何を考えているのか、考えただけでも反吐が出る。
「ちッ」
木簡を握る手に力を込め、勢いに任せて左右に押し開く。
紐が千切れ、繋がっていた木簡がばらばらに広がってしまい、小気味良い音を立てて床に散らばった。
「桓騎っ?」
何をするのだと驚いた信が床に散らばった木簡と桓騎を交互に見上げる。
「まさか、あいつを助けに行くつもりか」
息を整えながら、桓騎は冷静に問いかけた。すると信は、何度か視線を彷徨わせた挙句、口籠ってしまう。
この国を滅ぼそうとした張本人である男を救出する意志を固めつつある信に、桓騎は罵声を浴びせそうになった。
疑惑
「行くな」
信の腕を掴んだ桓騎は、指の痕が残るくらい強く握り、決して彼女のことを放そうとしなかった。
「で、でも…!」
痛みを堪えながら、見過ごすわけにはいかないと訴えると、桓騎はまるで体の一部が痛んだかのように、切なげに眉根を寄せる。
「…俺がガキの頃、芙蓉閣で騒ぎを起こしてた理由を知ってるか?」
いきなりそんなことを言われ、信は瞠目した。
「はあ?今そんなこと話してる場合じゃ…」
幼い頃の桓騎が芙蓉閣で起こした騒動など数え切れないほどある。
名家の子どもたちを売り物にしようとした奴隷商人を叩きのめして財産を奪ったことや、芙蓉閣で保護されている女性の身内が暴れたのを取り押さえたりしていた。
大人に任せておけばいいものを、桓騎は子どもながらに、それらの騒動を制圧したのだ。
どうして今になってそんな話を持ち出すのかと、信が困惑していると、
「騒ぎを起こせばお前が来ると分かってたからだ。あいつも分かっててそんな報せを寄越したんだろ」
思いもしなかった言葉を告げられ、信は驚愕した。
「寄越したって…何言ってんだよ!それじゃあ、まるで…」
信を呼び出すために幼い桓騎が芙蓉閣で騒動を起こしていたのと、李牧がこの木簡を送って来た真意は同じだと桓騎は言う。
「李牧が…わざと、俺を、趙へ来させようとしてるっていうのか…?」
いくら桓騎の言葉とは言え、とても信じられなかった。
まさか李牧が自分に趙に来させるためにこのような木簡を送って来たというのか。なんのためにそんなことをするのか。信には李牧の考えも、桓騎が言わんとしていることも分からなかった。
しかし、桓騎は李牧の行動の真意を裏付けるように、言葉を紡いでいく。
「なんでわざわざ敵国の、それも、お前だけにそんな報せを寄越したと思う?それに、処刑される本人に、執行日なんて普通は前もって知らせねえだろ」
その問いに、信は思わず息を詰まらせる。
此度の戦の敗北の責任を取るために趙の宰相が処刑されることになったとしたら、秦だけでなく、趙と同盟を組んだ他の国にもその報せが行き届くだろう。
しかし、信も桓騎もそんな報せは知らず、初めてこの木簡で処刑を知らされた。そしてそれを知らせたのが李牧自身だということにも矛盾を感じる。それに、処刑される本人に執行日は直前まで知らせないものだ。
執行日を意図的に伝えぬことは、処刑される側の心情を配慮しているのかもしれないが、迫り来る命の期限への恐怖を味わわせているという見方も出来る。
しかし、李牧は事前に処刑の執行日を知り、身内でもなければ敵国の将である信に、執行日を記した書簡を送ることまで許された。趙の宰相という立場にあったとはいえ、本来ならあり得ぬ優遇だ。
だからこそ、これは意図的な情報操作だと桓騎は信に訴える。
「…自分が処刑されるって言えば、お前が趙に来るのを分かってるからこんな書簡を送って来たんだろ。バカでも少し考えりゃ分かるだろうが」
言葉はやや乱暴だが、冷静になれと諭される。
ようやく桓騎の言葉の意味を理解した信は、心臓の芯まで凍り付きそうな感覚を覚え、呼吸を乱すことしか出来なかった。
「う…」
眩暈がして、足元がふらついてしまう。再び床に座り込んでしまいそうになる体を桓騎の両腕が抱き止めた。
「り、李牧が、そんな、こと…」
血の気が引いた顔で、信が尚も否定しようとする。
桓騎の言葉が真実である確証はない。
だからこそ、李牧のことを信じたかったのに、これが彼の策であることを否定する言葉は喉に張り付いて上手く出て来てくれなかった。
王騎を討ち取った策を企てたあの男ならやりかねないと、もう一人の自分が囁いている。李牧が持っている戦での才も、明晰な頭脳も、信はよく知っているはずだった。
だが、一体何のためにそんなことをするというのか。李牧の行動の真意だけがどうしても分からない。
「…あいつの処刑が事実かどうか、確かめる方法は一つだけだ。趙に行かなきゃいい」
どうしたらいいか分からないといった顔をしている信に、桓騎は穏やかな口調で答えた。
これが李牧の策だとしたら、彼が処刑されると言うのは真っ赤な嘘だ。だから趙に行かずに様子を見ていればいいと、桓騎は冷静に諭す。
趙国に李牧という存在は欠かせない。宰相という立場だけでなく、軍の指揮を執る総司令を担っている彼をそう簡単に排除出来るはずがない。
「けど…」
未だ不安を拭えず、信は弱々しい声を発した。
「もし、…もしも」
―――処刑が本当だったら?
確信を得られずにいるのは、李牧に対する情が深く残っているからだろう。
李牧に対しての情がなかったのならば、この報せを聞いても動揺することはなかったはずだ。
だが、もしも本当に李牧が処刑されることになっていたら、これが最後のやり取りになってしまう。彼は最期のその瞬間まで、自分を待っているかもしれない。
彼が趙の宰相となって自分の前に現れた時に、決別は済ませたはずだった。しかし、それは秦将としての建前だと言っても良い。敵対関係にあるからこそ、儀式的に行ったもので、信の中でそれは本当の決別ではなかった。
説得にも応じず、狼狽えるばかりの信を見て、桓騎はわざとらしく溜息を吐いた。
「…お前、まだあいつのことを忘れられねえんだな」
桓騎に指摘されなくても、李牧との決別を未だ受け入れられず、彼の存在が自分の心を巣食っていることは十分に自覚していた。
「っ…」
喉元に熱いものが込み上げて来て、目頭が沁みるように痛む。涙が溢れそうになって、信は咄嗟に前髪で顔を隠した。
もしも李牧が処刑されてしまったら、もう二度と彼に会えなくなる。考えるだけで脚が竦みそうになるほど恐ろしくて、不安と後悔で胸が押し潰されそうになる。
まさかこんな急に別れが来ることになるだなんて思わなかった。
あの雨の日に、突然自分のもとを去っていった時と同じ悲しみに胸が支配され、頭の中は李牧との思い出一色に染まってしまう。
突然自分のもとを離れていったとはいえ、しかしあの時は何処かできっと生きているはずだと信じていた。
だが、処刑の話が本当ならば、どれだけ無事を願ったところで、二度と彼には会えない。
こんなことになるなら、秦趙同盟の後に再会したあの日にもっと話をしておくべきだった。そうすればきっと、何か今と違った未来が待っていたかもしれないという後悔が信の心を縛り上げる。
たとえ桓騎が何を言っても、信の頭と心はもう、李牧のことしか考えられなくなっていた。
嗚咽が零れそうになって奥歯を食い縛っていると、いきなり桓騎に腕を掴まれたので、驚いて顔を上げてしまった。
「趙には行かせねえぞ」
声色は憤怒に染まっていたが、桓騎はなぜか切なげな表情を浮かべている。
「行くな。行けばお前は、趙から一生出られなくなる」
殺されるという言葉ではなく、まるで幽閉されるような言葉を使ったことに、信は訝しんだ。
返答に迷っていると、桓騎の両腕が信の身体を強く抱き締めた。
「か、桓騎?」
「…行くな」
何処か怯えているような、懇願するような桓騎の言葉を聞き、本気で彼が自分のことを想っていてくれているのだと分かった。
広い背中に腕を回して、安心させようとするものの、逆に自分の不安が伝わってしまったのか、桓騎は決して信のことを放そうとしない。
「えっ?」
背中と膝裏に手を回したかと思うと、いきなりその体を横抱きにして歩き始めたので、信は驚いて声を上げた。
「な、なにすんだよっ?」
どこに連れていくつもりだと聞いても桓騎は何も答えない。目的地はすぐに到着したようで、寝台に身体を落とされた。
体を組み敷かれたかと思うと、着物の帯を解かれたので、信はまさかと青ざめる。
「お前っ、こんな時に何考えてんだよッ!」
こんな時にふざけるなと信は怒鳴り、桓騎の体を押し退けようと腕を突っ張った。未だ治り切っていない傷がずきりと痛む。
しかし、桓騎は少しも表情を崩さないし、退く気配を見せない。言葉を発さずとも、趙には行かせないと双眸が強い意志を宿していた。
秦趙同盟で李牧と決別をしてから、桓騎と恋人となり、幾度も体を重ね合った。この国を滅ぼそうとした敵将ではなく、恋人である桓騎を優先すべきだと、彼の言葉に従うべきだと頭では理解しているのに、信は狼狽えてしまう。
「ま、待てって!本当に、今はこんなことをしている場合じゃ!」
何とか説得を試みようと言葉を紡いだ途端、乾いた音がして、信の視界が大きく傾いた。遅れて左の頬がじんと痺れるように痛み、熱を帯びていくのを感じる。
「っ、え…?」
思考と視界が真っ白に染まり、少しずつ色を取り戻していく。桓騎に頬を打たれたのだと気づくには、しばらく時間が掛かった。
躊躇うこともなく頬を打ったことから、容赦なく力を込めていたのだろう、口の中にじわりと血の味が広がった。
「冷静になれ。お前が趙に行って、李牧の策が成ったら、秦は今度こそ滅びるぞ」
血の味を噛み締めながら、信は桓騎が脅しではなく、本気で訴えているのだと察した。
「お前がいなくなったこの国に、俺は興味なんてない」
函谷関では得意の奇策を用い、膨大な被害を受けながらも防衛に成功した桓騎ではあるが、信がいない秦国など守る義理も価値もないと言い切った。
容赦なく秦国を見捨てるつもりでいる桓騎を、信は呆然と見上げている。
信も桓騎もいない状況で、再び合従軍のような強大な戦力から侵攻を受ければ、今度こそ秦は滅びることになるだろう。
国を守るのか、一人の男の命を選ぶのか。残酷な選択肢を天秤に掛けられ、信の胸は鉛を流し込まれたかのように重く痛んだ。
こんなにも悩むのは、李牧の処刑が彼自身が企てた策なのか確信が持てないせいだ。
もしも処刑が本当なら、信は何としてでも李牧を救出して、その身柄を保護するつもりだった。
だが、もしかしたら、それさえも策なのではないかという疑惑が信の中に滲み出て来た。
李牧が秦国を滅ぼすためにあらゆる手段を用いる男だというのは、今回の合従軍の侵攻から誰もが理解したことだろう。
それでも、李牧のことを救いたいと思うのは、未だに彼を愛している何よりの証拠だ。
もちろんそれが自分の弱さであることも信は理解していたのだが、だからと言って簡単に李牧を見捨てるような真似も出来なかった。
そんな簡単に、彼への想いを切り捨てられていたのなら、こんなに悩むことはなかったはずだ。
李牧が合従軍を引き連れて秦を攻めて来た時に、迷うことなく彼の首を狙っていたに違いなかった。
慰留
苦悶の表情を浮かべている信に構わず、桓騎は彼女の着物の襟合わせを開く。首筋に舌が這う感触に、信ははっと我に返った。
「やッ、やめろ、桓騎ッ…!」
抵抗する両手で桓騎の体を押し退けようとするものの、頭上で一纏めに押さえ込まれる。
こんな強引に組み敷かれるのは、秦趙同盟の時に桓騎が李牧と信の関係を知って、今までずっと李牧の身代わりにしていたのかと逆上された時以来だ。
「放せって…!」
どれだけ力を込めても、桓騎は放してくれなかった。
桓騎は片手で両手首を押さえているだけだというのに、未だ治り切っていない傷を抱えた体では抵抗もままならない。男女の力量差を見せつけられたような気さえした。
「単純な二択だ。李牧を選ぶか、それとも秦を選ぶか」
「っ…」
李牧の命と国の命運を問われ、信は狼狽えた。
ここで天秤に掛けたのが桓騎自身ではなく、祖国にしたのは、信の心を大いに揺さぶるためであった。秦国には自分だけではなく、彼女の大切な仲間たちの命も全て含まれているのだから。
もちろん時間稼ぎの目的もある。
こうして迷っているうちにも、李牧の処刑がどんどん迫っていく。もしも李牧の処刑が策ではなく事実だとしても、李牧が死ぬだけだ。桓騎にとってはそれだけの話だった。
秦将の立場であるならば迷うことなく祖国を取ると答えるのに、それが出来ないのは過去に愛していた、いや、今も愛して止まない男を助けたいという情があるからだ。
秦将である前に、信も一人の女である。それこそが、彼女に正常な判断を出来なくさせているのだ。
桓騎の中で憎らしい気持ちが込み上げる。それが妬みという感情だというのは桓騎も分かっていた。
「桓騎…俺は…」
縋るような視線を向けられ、桓騎は舌打った。
「お前にとっては二択だ」
だがな、と桓騎は言葉を紡いだ。
「お前をこの国に留める方法なんざ、俺は幾らでも知ってる」
「か、桓騎…?」
信が怯えたように瞳を揺らす。
何も言わずに桓騎は信の両手を押さえている手を放し、代わりに彼女の右足を掴んだ。
左手でしっかりと足首を握り締め、右手は指の付け根の辺りをしっかりと掴む。両手に力が入りやすいよう、足裏を胸に押し当てた。
「…足が壊れちまえば、趙に行きたくても行けねえよなあ?」
すぐにその行動の意図を察した信が途端に青ざめた。
彼女を李牧のもとへ行かせないのなら、足を砕けばいい。手綱を握れぬよう手を落とせばいい。
手足を落とすことまでしないにしても、何処にも行かせぬよう、閉じ込めてしまっても良かった。
それが信の心を壊すことになろうとも、彼女から拒絶されることになろうとも、確実な方法である。
「ま、待てッ!やめろッ、桓騎!」
冷や汗を流しながら、自分の右足を掴んでいる桓騎の手を振り解こうとする。
しかし、無情にも桓騎は、彼女の右足を捻り上げるために両手に力を込めた。
きっと捻り上げるだけじゃない。そのまま骨を折る気だと直感で察した信は無意識のうちに口を開け、叫ぶように誓っていた。
「行かないッ!」
束の間、沈黙が二人を包み込む。右足を掴んでいる桓騎の手から、僅かに力を抜けたのが分かった。
しかし、まだ足から手を放そうとしないところを見る限り、確信を得るまでは解放するつもりはないらしい。
「い…行かない…趙へは、行かねえよ…」
声を震わせながら、もう一度同じことを言うと、桓騎は何かを考えるように口を噤んだままでいた。
右足を掴む両手から力が抜けたが、まだ安心は出来ない。
少しでも彼の疑心を煽る行動をすれば、間違いなく足を折られるだろう。心臓が激しく脈を打つのを感じながら、信は黙って桓騎を見つめていた。
「…なら、今すぐ足開けよ」
ようやく右足を放してくれたかと思うと、桓騎は残酷な言葉を発した。
「なんで…」
狼狽えた視線を向けられて、桓騎は舌打った。
彼女が過去に愛した男の処刑が迫っているというのに、そんな状況で抱かせろと言っているのだから困惑するのは当然だ。
趙へ行かないことを強要させたのは、足を折る脅迫まがいなことをしたせいであって、信の本心ではない。
まだ彼女の中では、李牧に対する情が強く根強いている。
きっと自分が少しでも目を離した隙に、きっと彼女は趙へ行くだろう。他でもないあの男を助けるために。
処刑が事実だとしても、趙へ行けば確実に信は殺される。いかに彼女が強さを秘めていたとしても、一人で敵地へ飛び込めば命はない。李牧もろともその首を晒すことになるだろう。
そして、この処刑は李牧の策であると桓騎は疑わなかった。彼の手中に陥れば、信は二度とこの国に戻って来れなくなる。
それこそが李牧の狙いであることを、どうして気づかないのかと苛立たしくもあった。
合従軍を使ってこの国を滅ぼそうとしたことも、そしてその敗北さえも全てを利用して信を手に入れようとしている。その執着心は恐ろしいほどに根強い。
きっと信の中では、李牧はそんなことを企てる男でないと未だに思っているのだろう。
彼女と李牧が共に過ごしている時間、どれだけ彼女は甘い夢を見せられていたのだろうか。そして、今でもその幻影に狂わされているのだと、どうして理解しようとしないのか。
「聞こえなかったか。足開けって言ったんだよ」
もしも少しも信が迷うことなく、自分と秦国を選んでくれたのなら、きっとこんな手段に出ることはなかった。
慰留 その二
狼狽えてばかりで一向に言うことを聞こうとしない信に、桓騎は舌打ちながらその体を組み敷く。
こうなれば、無理やりにでも彼女をこの場に繋ぎ止めるしかない。
それが信の意志を無視することになると分かっていながら、桓騎はやめようとしなかった。
目を離した隙に、信が李牧のもとへ行ってしまうのなら、たとえ彼女を傷つけることになったとしても阻止しなくてはならない。
「あっ、や、やめろッ」
膝を掴んで足を開かせようとした途端、抵抗の悲鳴が上がる。
どこまで自分を拒絶するつもりだと腹立たしくなり、桓騎は再び右足首を掴んだ。
足を折るなど容易いことだ。道具など必要ないし、その気になればいつだって出来る。
「桓騎ッ」
それだけで桓騎の行動の意図を察した信は顔を歪める。許しを乞うような、今すぐ泣き出してしまいそうな弱々しい子どものような顔だった。
いっそ自分を殴りつけて、本気で抵抗してくれたのならば、こちらも心置きなく凌辱を強いることが出来るのに、信は小癪にも理性に訴えかけて来る。
理性に訴え掛ければ、こちらが躊躇うことを無意識のうちに知り得ているからこそ、信は本気で抵抗をしない。普段は鈍いくせに、こういうところが厄介だった。
「やめろ…今は、頼む…」
哀願する信の言葉に右足を掴んでいた手を放してしまい、自分にもまだ良心というものが残っていたことに驚いた。それはきっと、相手が信だからだと断言出来た。
それでも、ここで自分が引けば信は間違いなく李牧のもとへ向かうだろう。だからこそ、桓騎はやめるわけにはいかなかった。
彼女の体を両腕で抱き込むと、桓騎は無理やり唇を重ねる。
「んんッ…!」
信が嫌がって首を振る。強引に彼女の顎を掴み、桓騎は口の中に舌を差し込んだ。
逃げ惑う彼女の舌を追い掛け、絡め合う。
「ぅ…ふ、ぁ…」
唾液と舌を絡ませているうちに、信の息が乱れ始めていく。
信の瞳に浮かぶ哀願が情欲の色にすり替わったのを見て、桓騎の口角がつり上がった。
絶対にあの男には渡さない。この女は自分だけのものだ。
独占欲に胸を掻き立てられながら、桓騎は信の着物に手を掛けたのだった。
裏切り
桓騎の腕の中で目を覚ました時、窓の外が薄闇になっていることに気が付いた。
「………」
瞼が重いのは疲労による眠気と、泣き過ぎたのが原因だろう。
散々彼に抱かれたせいで声を上げた喉もひりひりと痛む。水を飲んだらもう一眠りしたいと身体が訴えていた。桓騎自身も疲れてしまったのか、目を覚ます気配がない。
「……、……」
目を覚まさないことを祈りながら、信はゆっくりと桓騎の腕の中から抜け出し、床に足をつけた。
「っ…」
立ち上がろうと体に力を入れた時、脚の間からどろりと粘り気のある白濁が零れる嫌な感触が伝い、信は青ざめた。
嫌だと叫んだのに、桓騎はあの時と同じように、この腹に子種を植え付けたのだ。
秦趙同盟で李牧と再会したあの日の夜、桓騎に犯された時は孕まずに済んだ。
幾度も戦場で命の危機に晒される体は激しい侵襲を受け、月経が途絶えることも不思議ではなかった。孕みにくい体質だったことが幸いしたのである。
しかし、二度目は分からない。万が一にも備えて堕胎薬の調合を医師に依頼しようかとも考えたのだが、今の信はそれよりも優先すべきことがあった。
着物を身に纏うと、信は寝息を立てている桓騎を振り返る。
(…悪い、桓騎)
心の中で謝罪したものの、きっと彼は自分を許さないだろう。そのために自分の脚を折ろうとまで考え、この身を暴いたのだから。
それでも信の心は、李牧を忘れることが出来なかった。
声を掛けることをしなかったのは、桓騎を起こさないための気遣いと、秦国を裏切ろうとしている自分が、言葉を掛ける資格などないと思ったからだ。
趙に寝返るつもりなど微塵もない。
それでも、趙の宰相を助けようとする行為は、裏切りと同等の行為である。
李牧の命を救うことだけが、今の信を動かしていた。
処刑は彼の偽装工作だと桓騎は言ったが、もしも本当だったのなら見過ごすわけにはいかない。
それにもし処刑が本当なら、信がしようとしている行動は、趙宰相の地位を剥奪された一人の男の命を救うこと。
李牧の命を救うことを正当化する戯言だと、信にも自覚はあった。それだけ彼の存在が深く心に根強いているのだと、認めざるを得なかった。
信は部屋を出る時も、屋敷を出てからも、一度も後ろを振り返らなかった。
※前編の桓騎×信のヤンデレバッドエンドルート(4700字程度)はぷらいべったーにて公開中です。