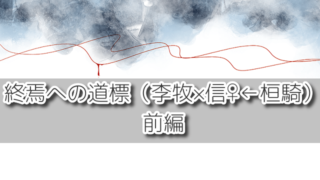- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 李牧×信/桓騎×信/年齢操作あり/ヤンデレ/執着攻め/合従軍/バッドエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は「平行線の終焉」の牧信IFルートです。
従順な彼女
目を覚ますと、隣に信の姿がなかった。
「…信?」
辺りを見渡すが、室内のどこにも彼女の姿は見つからない。
腕の中にも寝具の中にも彼女の温もりは残っておらず、李牧が目を覚ますよりも前に褥を抜け出していたのだと分かる。
(まさか…)
目を覚ました時に、信が失われていた記憶を取り戻しており、自分から逃げ出したではないかという不安に襲われた。
従者たちには常時見張りを頼んでいたし、両手が使えない信が扉を開けて逃げ出すようことはないと思っていたのだが、彼女を捕らえたという報告は聞かれていない。
主が眠っていたとしても、従者たちがそういった報告を怠るとは考えられなかった。
しかし、従者たちの目を盗んで逃げ出したということも考えられる。
もしも脱走していたとすれば、すでに褥に温もりが残っていないことから、恐らくはもう屋敷を抜け出したに違いない。
とはいえ、秦へ戻るにしても、あの両腕では馬の手綱を引くこともままならないだろう。一度は安心したものの、幾度も死地を生き抜いた経験がある信なら、決して不可能ではないと思うと、李牧の胸は不安に駆り立たれた。
(一体どこに…)
すぐさま着物を身に纏い、部屋を飛び出す。
まずは従者たちに信を見ていないか話を聞こうとしたのだが、
「あ、李牧」
李牧の予想に反し、廊下に出たところで、あっさりと信と再会を果たした。
「信?」
二人の侍女に支えられながら、この部屋に戻って来る途中だったらしい。
しかし、逃亡を企てたような様子はなく、付き添っている侍女たちの表情も穏やかなものだった。
信の髪が濡れており、頬が赤く上気しているのを見て、湯浴みをしていたことが分かる。情事の後で身体を清めたかったのだろう。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
「李牧?」
自分を見据える信の眼差しには怒りや恐怖の色はない。
まだ記憶を取り戻していないのだと分かり、李牧はほっと胸を撫で下ろした。心配は杞憂で済んだらしい。
「えっ、うわっ、な、なんだよっ?」
目の前の体を抱き締めていたのは、ほとんど無意識だった。
いきなり抱き締められたことで信は戸惑い、すぐ後ろにいる侍女たちの目線も気にして、李牧の体を突き放そうとする。
侍女たちも気を遣ったのだろう、笑顔で一礼し、何事もなかったかのように下がっていった。
しばらく腕の中で暴れていた信だったが、李牧が少しも放してくれる気配がないことが分かり、諦めたように両腕を下ろした。
「李牧…?」
声を掛けても放してくれない李牧に、信が不思議そうに首を傾げる。
彼女の体をしっかりと抱き締めながら、李牧は切なげに眉根を寄せていた。
「…お前が、居なくなってしまったかと思った」
素直にそう答えると、信が驚いたように顔を上げた。
「少しは思い知ったかよ」
僅かに怒気を込めながら彼女がそう言ったので、李牧は言葉を喉に詰まらせてしまう。体の一部が痛むかのように顔が強張った。
あの雨の日に行先も告げずに去っていった自分のことを、信はまだ恨んでいるのだとすぐに察した。
信の肩を掴み、真っ直ぐに彼女の瞳を見据える。
「…あの時は、すまなかった」
突然目の前から居なくなったことを、今更ながらに謝罪した。もしも彼女が許してくれなくても、それは当然のことだろう。信のためとはいえ、彼女を裏切ったことには変わりないのだから。
「…もういい。仕方ないから、許してやる」
返って来た声色は随分と明るかった。
目が合うと、信が歯を見せて笑ったので、李牧もつられて笑った。
「う…」
その直後、李牧の胸に凭れ掛かるように、信が膝から力を抜いてしまったので、反射的にその体を抱き止めた。
「信?」
「わ、悪い…なんだか、目の前が…揺れて…」
眩暈が起きているらしい。その言葉を聞くや否や、李牧はすぐに彼女の体を横抱きにした。風呂に入って赤く上気していたはずの顔が、今は少し青ざめている。
すぐに部屋へ戻って、寝台にその身を横たえてやると、信が力なく笑った。
「心配、すんな…風呂でも…同じだったんだ…」
それで侍女たちに支えられていたらしい。
「…昨夜は無理をさせた。すまない」
三日ぶりに目を覚まし、未だ傷も治り切っていない彼女に、昨夜は無理を強いてしまった。浅ましい情欲を抑え切れなかったことを今さらながら恥じる。
信はちいさく首を横に振ると、左手を伸ばして、そっと李牧の頬に触れた。
「…嬉しかった」
「え?」
まさかそのような言葉を言われるとは思わず、つい聞き返してしまう。
信は恥ずかしそうに目を逸らすと、泣き笑いのような顔で言葉を紡いだ。
「俺のことが、嫌になって、居なくなったって…ずっと、そう思ってたから…」
「あり得ない」
すぐに否定した李牧は身を屈めると、お互いの吐息がかかる距離まで顔を寄せた。
「お前を忘れたことなんて、一度もなかった」
その言葉を聞いた信の瞳にうっすらと涙が浮かぶ。
今の彼女は、李牧が趙の宰相になったことを知らない。自分のもとを離れた理由も知らないのだと思い出し、李牧は言葉を続けた。
「…目的も告げずにお前のもとを去ったことは謝る。だが、お前を想う気持ちは何も変わっていない」
秦趙同盟の時も、李牧は決別の言葉と一緒に、今までもこれからもずっと愛し続けていることを伝えた。
もちろんそれは嘘ではなく、離れている間も、李牧が信を愛する気持ちは微塵も揺らぎはしなかった。
「じゃあ、なんで」
どうして自分のもとを去ったのだと信が問うのは必然だった。
しかし、彼女は途中で口を閉ざすと、静かに首を横に振る。問い掛けるのをやめたことに、李牧は瞠目した。
「…信?」
涙を堪えるように、信は幾度か視線を彷徨わせながら、呼吸を整えて、再び李牧を見た。
「俺のため…だったのか?」
語尾に疑問符がついている辺り、確信を突いたとは言い難いが、信がこちらの目的を察したことは間違いなさそうだ。
「何故そう思った?」
すぐには頷かず、穏やかな声色で理由を尋ねる。
少しだけ口を噤んでから、信はゆっくりと話し出す。視線は合わなかったが、彼女が自分のことを考えてくれていることは手に取るように分かった。
「…お前がすることは、いつだって、俺のためだったから…って、そんなの、自惚れだよな」
恥ずかしそうに答えた信に、鼓動が早鐘を打つ。
「自惚れじゃない」
李牧は込み上げる愛おしさに突き動かされるまま、信に口付けていた。
昨夜無理をさせたことを先ほど反省したばかりだというのに、溢れ出る想いは止められなかった。
手首から先のない右手を動かし、李牧の想いに応えるように、信はの背中に腕を回してくれた。
従順な彼女 その二
…その後の信は、李牧のよく知る従順な彼女に戻っていった。
馬陽から一切の記憶がない、つまりは李牧を趙の宰相だと知らないのが大きな理由だろう。
屋敷の中で療養していることもあって、ここが敵地である趙国だとも気づいていないようだった。
政務や軍務で屋敷を空けることも珍しくない李牧は、従者たちに信の世話を任せている。
自分の留守を任せている間の信の様子を報告を聞くものの、記憶を取り戻した様子もなければ、脱走する様子も見られない。
しかし、傷が癒えるにつれて、そろそろ王騎のもとへ帰りたいと愚痴を零しているらしい。
馬陽での敗走により、深手を負った養父のことが心配なのだろう。
もしも信が屋敷の外に出て、ここが趙国だと気づかれれば、彼女はなんとしても自分を敵国に連れて来た理由を探るはずだ。
今は祭祀儀礼に携わると身分を偽っているが、李牧が趙の宰相であり、王騎はもう討たれた後だと知られるのは時間の問題である。
しかし、そんな不安を覆いつくすようにして、李牧の胸を埋め尽くしていたのは幸福感だった。
今まで離れていた時間を埋めるように、夢中になって信と身を繋げ、その腹に子種を植え付けることで、彼女が記憶を取り戻すかもしれないという不安など塵のように消し飛んでしまう。
幸福感の正体は、自分の子種が信の腹で芽吹けば、どのような未来になっても彼女は自分から離れられないという安心感だった。
いずれ芽吹くそれが頑丈な鎖となって、いつまでも信を自分の傍に繋ぎとめておいてくれると、李牧は信じていたのである。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
「李牧、帰ったのか」
数日ぶりに屋敷に戻ると、侍女から報告を受けたすぐに信が出迎えてくれた。
「ああ、留守を任せてすまなかったな」
屋敷に帰って来ただけだというのに、信は満面の笑みを浮かべた。
不思議なことに、その笑顔を見るだけで執務の疲労や重責なんて消え去ってしまう。
「退屈していただろう」
「んー…まあ、ちょっとはな」
敷地内の庭園に出るくらいの外出は許可しているが、屋敷から出るのは、傷が完全に癒えてからだという約束をしている。王騎たちのもとへ顔を出すのもその時にしようと話していた。
従順な彼女が約束を破ることはないと分かっていたが、記憶を取り戻したのならばきっと脱走を試みるに違いない。
ようやく彼女を手に入れたはずなのに、李牧はいつも不安に襲われていた。
「傷の具合はどうだ」
自分の意識を不安から逸らすように問いかけると、信があははと笑った。
「薬湯をもらってからは調子が良い。まあ、すっげえ苦ぇけど…」
失った右手が痛むことがあると、信が訴えたのは先月からだった。
右腕を落とした時に処置をしてくれた侍医に依頼し、薬湯を調合してもらっているのだが、それを飲むまでは寝台から起き上がれないほどの強い痛みがあったという。
切断面の傷口は順調に塞がっていたのだが、失ったはずのその先が痛むのだと、幼子のように泣きながら訴えて来た信の姿は今でも覚えている。
侍医に相談すると、一時的な幻肢痛だろうと言われ、痛み止めと称して気分が落ち着く薬湯を調合してくれた。万が一を考えて、妊婦が服用しても問題ないものだ。
薬湯を飲むと痛みが和らいだと言うので、痛みがひどい時には同じ薬湯を飲ませるように従者たちに指示をしている。
実際には痛み止めの作用が含まれていないというのに、効果があったということは彼女の精神的なものが関与しているのかもしれないと侍医は言った。
それはきっと、二度と戦場に立てぬという信の中の葛藤が引き起こしているのかもしれない。
将としての未練がまだ根強く残っているのは分かっていたが、いずれ自分の妻として生きることを受け入れれば、幻肢痛もなくなるだろうと李牧は考えていた。
薬湯を飲んでも痛みが引かぬ時には、眠りの作用がある香を焚いて、彼女の意識を無理やり痛みから引き離していた。
何をきっかけに記憶を取り戻すか分からない彼女を逃がさないためであったが、それらの処置が全て李牧の気遣いによるものであると信は疑うことなく信じているらしい。
「…ありがとな」
照れくさそうに信に感謝される。
そのはにかんだ笑顔を目の当たりにすると、心が掻き立てられるように、李牧は無意識のうちに両腕を伸ばしていた。
「わっ、何だよ?」
つい彼女の体を抱き締めると、驚いた信が腕の中で身じろぐ。周りにいる侍女たちの目を気にしているだけなのはすぐに分かった。
食事の支度があるからと、自分たちを気遣った侍女たちが下がっていき、誰も居なくなってから、信は背中に腕を回して来た。
自分の胸に顔を埋めて、幸せそうに笑みを浮かべている信の姿を見て、二度と放したくないという想いはますます膨れ上がるばかりだった。
「…なあ、俺、そろそろ」
信が何を言わんとしているのかは手に取るように分かった。
「まだ傷は完全に癒えていないだろう」
屋敷へ帰るという彼女の言葉を掻き消すように、李牧は言葉を発すると、信は少し不満そうに眉根を寄せた。
傷が癒えてから外に出る約束を交わしていたが、王騎たちのもとへ顔を出すのもその時だという約束を交わしていた。ただし、彼女は右手が使えないので一人で乗馬は出来ない。
執務が落ち着いたら、馬車を手配するから二人で会いに行こうと何度も伝えているのに、信は李牧の執務を気遣ってか、一人で帰ると聞かないのだ。
「左手があるんだから手綱も握れる。一人で戻れるって」
「もしも馬に振り落とされたら?以前のように動けると思うな」
「でも…」
まだ食い下がろうとする信に、李牧がわざとらしく溜息を吐く。
「あ…」
僅かに怯えの色を浮かべた信を見下ろし、李牧は口を閉ざした。
言葉にせずともその態度を見れば、李牧に見捨てられれば行き場を失ってしまうことを信は理解しているようだった。
「わ、悪い…俺…」
元より、武の才能を見出されて王騎に引き取られた彼女は、右腕を失ったことで将としての未来が潰えた。すなわちそれは、将として王騎の期待に応えることが出来なくなったということだ。
常日頃から王騎と嬴政のもとへ顔を出したいと話している彼女が、武器を持てなくなったことを何と伝えようか悩んでいることも知っている。
それまで将としての地位を築いていたというのに、もう秦の戦力にはなれないのだと知った仲間たちに落胆されるのが恐ろしいと感じていることも、李牧は分かっていた。
幻肢痛にうなされながら、朦朧とする意識の中で、彼女は何度も仲間たちに謝罪していたからだ。
李牧の腕の中が、これから自分の唯一の居場所になるのだと信は分かっている。
だからこそ、李牧の機嫌を損ねて、自らその居場所を失うような真似はしたくないのだろう。
「り、李牧の執務が落ち着いてから…一緒に、…」
一人ではなく、二人で一緒に帰ると話した信に、李牧の機嫌はようやく戻った。
「ああ、王騎には書簡を出しておく。心配するな」
心配をかけぬようにと、李牧は定期的に王騎へ書簡を送っていると伝えていた。もちろん送り主はすでにこの世にいないので、そんな書簡のやり取りなど行っていないのだが、信は李牧の言葉を健気に信じ込んでいる。
「と、父さ…王騎将軍から、返事は?」
その問いには答えず、李牧は食事の支度が出来たと知らせに来た侍女の方へ向き直った。
王騎からの返事がないことに、信の心が不安に蝕まれていることは分かっていた。どうやら、右手を失ったことで養父から見捨てられたと思い始めているらしい。
こうして信の周りにいた者たちの存在を蹴落としていけば、ますます彼女の心の拠り所は自分という存在だけになっていく。
隣から不安そうに顔を歪める信の視線を感じていたが、李牧は気づかないふりをして背中を向け、薄く笑んだ。
違和感
あれから数か月が経ったが、未だ信の記憶が戻ることはなかった。
傷が癒えてから屋敷の外に出るという約束を交わしていたのだが、外出中に右手が痛んだらと思うと、信も外出が億劫になってしまったらしい。
無理はしなくていいと伝えたが、李牧にとってはとても都合が良いことだった。
恐らくは李牧の機嫌を損ねないように、外出を控えることを選んだのだろう。王騎たちのもとに顔を出したいと言わなくなったのも、李牧の執務が落ち着いてからと共に行くのだと、健気に信じているようだった。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
「あ、ま、待ってくれ…」
その日の夜も、寝台に信の体を横たえると、戸惑ったように彼女は左手で李牧の肩を押し返した。
珍しく抵抗の色を見せたことに、李牧は瞬きを繰り返す。
「…最近…その」
何か言いづらいことがあるのだろうか、信が言葉を選ぶように目を泳がせている。
下腹に手を当てていたので、もしや懐妊したのではないかと李牧は期待に胸を膨らませた。
この屋敷で信の世話を任せている医師や侍女たちからは、その類の報告を受けていなかったが、もしかしたらと考える。
「どうした。体調が優れないのか?」
それを表情に出すことはなく、李牧は冷静に話を聞き出すことに務めた。
彼女を趙に連れて来てから、自分たちは未だ婚姻を結んでいない。夫婦になる前だというのに、子を孕んでしまうことを信は気にしているのかもしれない。
しかし、今の記憶が混雑している信は、馬陽の戦いの後、李牧の屋敷で療養していると信じ切っている。ここが趙国であることも、そして李牧が趙の宰相であることも信は知らないのだ。
本来なら、趙の宰相と秦の将軍という敵対している者同士での婚姻は許されるはずがないのだが、もちろんそんなことは李牧も分かっている。
だからこそ、李牧は彼女の死を偽装したのである。
切り落とした右手を、信が秦王から賜った剣と共に送ってやったし、趙や他国でも飛信軍の信の訃報は広まっている。首を晒すことはせずとも、そのような話が広まったのは李牧による情報操作によるものだった。
信の死が中華全土に広まってから、李牧は何者でもなくなった彼女と婚姻を結ぶ手立てを講じていた。
信が趙に来てから、密偵に秦の動きを追跡させていたが、大々的に彼女の葬儀を執り行った以外で特に動きはないらしい。
…もっとも、秦国で彼女の死を認めぬ者が、邪魔立てをしないとは限らない。
だが、彼女一人のために戦を起こすことや、単騎で取り戻しに来るような愚か者はいないだろう。それが例え、桓騎だとしてもだ。
聡明な頭脳を持つからこそ、桓騎が単騎で取り戻しに来るとは考えられなかった。かといって、信の死をその目で確かめるためだけに、独断で軍を動かすとも思えない。
慢心してしまう状況にあるのは当然だ。この状況下で信を取り戻されることは絶対にないと断言出来るからである。
信が生きる道は、もう自分の腕の中にしかない。
国と共にその身を滅ぼすような愚かな真似はせず、自分の妻としての役目を果たせば良い。そのために、李牧は一度は彼女を裏切ったのだから。
従者たちから、妻の扱いを受けていることには未だに慣れないようだが、李牧が不在の間も逃げ出す素振りはないという。
そしてこの屋敷で過ごす間に、信に月事が戻って来たのも、侍女から報告を受けていた。
長年ずっと戦に出ていた侵襲からか、月事が途絶えることは彼女にとって珍しいことではなかったという。桓騎の子を孕まなかったのもそれが幸いしたのだろう。
将として生きる道が途絶えたことで、愛する男との子を産むという女の幸せを手に入れようとしているのだと、彼女の腹が自分の子種を求めているのだと、李牧は決して疑わなかった。
「え、と…」
言葉を待っていると、信は顔色を窺うように、上目遣いで見上げて来た。
「その、最近、なんで…中で…出すんだ…?」
「…は?」
どうして中で射精するのかという問いに、その胎に子種を植え付ける以外の回答があるのかと李牧は瞠目した。
瞠目している李牧を見ると、信は恥ずかしそうに俯いて、それから両手を自分の胸の前で挙げた。
右手は手首から先がなく、止血のために焼かれた断面は痛々しい。火傷自体の治療は終わったものの、今も包帯を巻いているのは傷跡を直に見ないようにするための配慮だ。
左手の親指は、正しい位置に骨を戻されて完治していたが、時折引き攣るような痛みがあって、上手く動かせない時があるらしい。未だ包帯で固定しているのはそのせいだった。
どちらも馬陽での戦で受けた傷であると、信は李牧の言葉を疑うことなく信じている。
落馬によって左手の指を骨折したこと、右腕は傷口が化膿したせいで落とすより他に方法がなかったと言えば、記憶のない彼女も受け入れるしかなかったらしい。
もしも、二度と武器を持たせぬために落としたのだと言えば、信は憤怒するだろうか。
「お、俺…今、手がこんなだから…うまく、中の、あの…掻き出せなくて…」
予想もしていなかった言葉を掛けられて、李牧はしばらく言葉を失った。
そういえばここ最近の情事の後、目を覚ますと信が居なくなっており、湯浴みをしていたのだと話していたことを思い出す。
着替えを手伝っていた侍女たちの証言もあったので、そこまでは気に留めていなかったのだが、それは失態だった。
記憶が戻ったことを内密にしており、水面下で逃亡を企てているのではないかという心配は絶えず、今も従者たちには動きを見張らせている。
しかし、まさか情事を終える度に、自分が腹に植え付けた子種を掻き出していたとは思わなった。
彼女の両手が不自由であることから、侍女に身の回りの世話は任せていたが、湯浴みの手伝いは不要だといつも断られていると報告があったことを思い出す。
それは常日頃から手を借りている侍女たちに対して、ただの遠慮だと思っていたのだが、その時に気付くべきだった。
未だに褥で肌を重ね合うのも恥じらうくらいなのだから、浴室で精液を掻き出す姿を誰にも見せたくなかったのだろう。
確実な避妊方法とは言い難いが、まさか自分の目を盗んでそんなことをしていたとは思わず、李牧は眉根に不機嫌の色を浮かべる。
右手を落として数日ぶりに目覚めた信と体を重ねた翌朝も、彼女は傷だらけの体を引きずって湯浴みをしていた。
それもすべて腹に植えつけた子種を掻き出すためだったのかと思うと、李牧はひどく裏切られた気分に陥った。
「あ…李牧…?」
急に黙り込んだ李牧に、信が顔色を窺うように見上げて来る。
人の顔色を気にするような女ではなかったのに、この屋敷で過ごすうちに、信は随分と臆病な性格に変わっていた。
「…いつも俺が見ていないところで、子種を掻き出していたんだな?」
まるで責めるような口調で詰め寄られ、信は怯えたように肩を竦ませた。
「だ…だ、って、もし、孕んだら…」
「孕めばいい。何も問題はないはずだ」
どうやらその答えは信にとっては予想外だったのか、あからさまに狼狽えていた。
手首から先のない彼女の右腕を掴むと、
「…この腕では、どのみち将に戻ることは出来まい。俺の妻として生きればいいと、何度も言っているだろう」
婚姻を結ぶのは簡単だが、未だ信の傷が完全に癒えていないこともあり、彼女の体調が落ち着いてから行う予定だった。
しかし、信にその話は幾度となくしていたが、彼女は後ろめたさがあるのか、いつも返事を濁らせるばかりだった。
きっと将としての未練が心に深く残っているのだろう。
右手を失い、馬にも乗らず、武器を持たぬことで衰えていく筋力を見れば、信も将として再び戦場に立つことは叶わないのだと分かっているはずだ。
「で、でも、…まだ…」
しかし、まだ子を孕むことには抵抗があるような素振りに、李牧の苛立ちは増すばかりだった。
「父さ…王騎将軍にも、仲間たちにも、何も、伝えてないし、それに、政にだって…」
将としての未練があるとは直接言わず、養父と秦王から将の座を降りることを告げていないと言った。義理堅い彼女が考えそうなことだ。
「そんなこと、もう戦に出られないお前が気にすることではない」
今の信は王騎の死を知らない。そして間もなく秦国が滅びゆく未来も知ることはない。
しかし、李牧にとってそれは些細なことだった。
隠蔽を決めたのは、事実を告げることで信が記憶を取り戻すことになり兼ねないという配慮からである。
信を戦から遠ざけることさえ出来れば、李牧はそれで良かったのだ。
「何が不満だ?もう将への未練はないはずだろう」
どうして普段のように自分の言うことを聞かないのかと、声色に苛立ちを滲ませると、信が弱々しい瞳で見上げて来た。
「な、なんか…お前、最近、怖いぞ?」
引き攣った笑みを口元に浮かべ、信が恐る恐るといった様子で、しかし李牧を怒らせたくないのか、どこか茶化すような雰囲気を滲ませながら問う。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
「怖い?」
聞き返すと、信が小さく頷いた。
目を合わせようとしないのは、こちらの機嫌を損ねたくないからなのだろうか。
「前まで、そんなこと…妻になれなんて、言わなかった、のに…」
そういえば共にあの屋敷で過ごしていた日々では、彼女を身体を重ねることも、想いを告げることはあっても、面と向かって求婚をしたことはなかった。
その当時の記憶のままでいる信は、急に李牧から妻のような扱いを受けることに戸惑っているらしい。
「信」
言葉を遮ると、信が泣きそうなほど顔を弱々しく歪めて、口を噤んだ。
「今のお前の務めは、なんだ?」
小癪にもまだ将への未練を残している信に、低い声で問い掛ける。
「……、……」
何度か唇を戦慄かせるものの、信はそれを言葉にする前に、諦めたように口を噤んでしまう。
答えを強要することは簡単だ。だからこそ、彼女の意志で言わせなければ意味がない。
右手を失ったことはもう受け入れているのだから、きっと以前のように従順になると思ったのだが、そうではなかった。
秦将として祖国を守ることは彼女の生きる道でもあったのだから、そう簡単に取り除くことは出来なさそうだ。
時間さえ経過すれば、そのうち忠義も風化していくとばかり思っていたのだが、戦から遠ざけようとすればするほど信は将への未練に執着してしまう。
いっそ、馬陽で王騎を討ち取ったことも、秦が間もなく滅びることも告げてやろうかと考え、その度に言葉を飲み込んでいた。
馬陽の後から記憶を失っている彼女にその残酷な事実を告げれば、それをきっかけに記憶を取り戻すことになるかもしれない。
もしもそんなことになったら、彼女は自ら命を絶つに違いなかった。
過程はどうであれ、信が自らの意志でこの腕の中に戻って来てくれたのだ。二度と失いたくはない。
「信、今のお前の務めは何だ?」
自分でも驚くほど低い声で、もう一度同じことを問いかける。
綻び
しばらく沈黙を貫いていた信だったが、口元に力なく笑みを繕うと、
「…李牧と、一緒にいる」
乾いた声でそう答えたのだった。
答えとしては上々。あとはその胎に自分の子を宿してくれたのなら、もう将としての未練も断ち切り、李牧の妻として生きる道を歩んでくれることだろう。李牧はずっとそう思っていた。
「けど…」
か弱い声で言葉を紡いだので、李牧はまだ未練があるのかと眉根を寄せた。
「政や、父さんにも、伝えねえと…」
義理堅い信は、将の座を退くにあたって、他にもやり残したことがあると訴える。
「それに、芙蓉閣にも、顔出さねえと…あれからずっと、顔出してねえから、桓騎が…色々文句言って来そうだし…」
秦王や王騎の名前はともかく、今の信から桓騎の名前が出て来るとは思わず、李牧は驚いて息を詰まらせてしまう。
気づけば信の両肩を掴んでいて、李牧は血走った目を向けていた。
「痛ぇってッ…李牧っ…!」
急に力強く肩を掴まれたことで、信も驚いている。
「桓騎のことを思い出したのか」
「は…?」
低い声で囁いた李牧に、信は訳が分からないといった表情を浮かべた。
「お、思い出すも、何も…桓騎は、咸陽で保護したガキだ…ずっと面倒見てたんだから、忘れるわけがないだろ」
以前、間者を送り込んで徹底的に桓騎の素性について調べさせたが、特に情報は得られなかった。
親もおらず、戦争孤児となって咸陽で行き倒れていたところを信が保護し、彼女が立ち上げた女子供の保護施設である芙蓉閣で育てられたのだという。
初陣を果たしてからみるみるうちに知将の才を芽吹かせた桓騎は、初陣でも功績を上げてみるみる昇格していった。馬陽の時はまだ将軍ではなかったものの、その後はすぐに将軍昇格を果たしていたし、今では秦国欠かせない強大な戦力である。
そして桓騎は信を恩人として慕うのではなく、女として見ていた。そして、信も桓騎を愛していた。
李牧がそれを知ったのは、秦趙同盟を結んだ後のことである。
彼女の体調が優れないことを指摘したのは李牧自身だったし、自分と再会したことを気に病んで、きちんと休めているのかが心配だった。
信が療養している部屋に向かうと、扉の隙間から聞こえた嬌声に、思わず立ち入るのをやめてしまったのだが、桓騎とまぐわっている姿がそこにあった。
甘い声で鳴く信の姿に、自分と離れている間にあの男と恋仲になったのかと、李牧はやるせない想いに駆られたことを思い出す。
理由も告げずに彼女のもとから去っていった自分への罰だと思った。
―――…李、牧…
しかし、信は桓騎の愛撫に甘い声を上げながら、あの時、確かに自分の名前を呼んだのだ。
その瞬間、桓騎は驚愕し、そして信も我に返ったかのように桓騎と身体を繋げていることに青ざめていた。
―――…なら、お前が誘ったのは俺じゃなくて、李牧だったってことで良いんだな?
それまで自分を求めていた女とは思えないほどの豹変ぶりに、桓騎は冷酷に尋ねていた。
その問いに、信は分かりやすく狼狽え、そしてそれが肯定だと分かったのは桓騎だけでなく、李牧もだった。
今でも信は、自分のことを愛しているのだ。
途端に愛しさが込み上げて来て、叫び出しそうなほど、李牧は喜悦した。
しかし、後日になって快調した信のもとを訪れ、趙に来るように告げた時、彼女はそれを拒絶した。
あのとき既に、信は過去を断ち切り、自分と別の道を歩み始めていたのである。
綻び その二
未だ秦王たちに会いに行くのを諦め切れないでいる信が、縋るように李牧を見た。
「あいつらに顔を見せて、安心させてやらねえと…」
「お前の近況を記した書簡なら出したと言っただろう」
一向に書簡の返事が来ないことを彼女が気にしていることも分かっていた。もちろん書簡のやり取りなど行っていないのだから、返事など来るはずがない。
屋敷を出る許しが得られないのだと分かり、信が泣きそうな表情を浮かべる。しかし、そんな表情一つで李牧の心が揺れ動くことはなかった。
「…全部終わったら、ちゃんと、ちゃんとするから…頼む…」
ここで引いておけば良かったものを、信は諦めずに説得を試みることにしたらしい。
ちゃんとするというのは、自分との婚姻を受け入れることだと分かったが、李牧は彼女の言葉を受け入れようとはしない。
縋るように、信が涙目で見上げて来た。
「飛信軍のことだって…桓騎軍のことも、信頼出来る奴らに任せねえと」
馬陽の戦いで記憶が途切れている信が、桓騎軍と言ったことに、李牧は違和感を覚えた。
「今、桓騎軍と言ったな?」
聞き返すと、信は不思議そうに頷く。
「あ、ああ、言った…え、あれ…?軍…?」
今の信の中では、桓騎はまだ将軍へ昇格していないはずだ。だというのに、なぜ桓騎軍の存在が出て来るのか。
それを疑問に感じたのは李牧だけでなかった。
「え…な、なんで、俺、桓騎が将軍みたいなこと…まだあいつ、そこまで…」
どうして桓騎軍と口に出したのか、信自身も疑問を隠せないでいるらしい。
記憶が混在しているのだと李牧は冷静に考えたが、もしかしたら少しずつ失われた記憶を取り戻そうとしているのかもしれない。
「信」
早鐘を打つ心臓を押さえながら、李牧は信の両肩を掴む。
「な、なんだよ」
怯えたように信が声を震わせる。
「…信」
今の彼女があるのは、秦国を裏切る選択をしたからこそだ。
全てを捨てて自分を選んだのは信自身なのだから、その事実を受容させなくてはならない。
信が本当に愛しているのは桓騎ではなく、この自分だと、李牧は何としてでも彼女に理解させようと考えた。
「思い出せ。王騎は馬陽で死に、お前は桓騎と秦国を裏切って俺を選んだ」
真っ直ぐに信のことを見据えた李牧は、静かに呪いの言葉を言い放つ。
封じられた記憶の扉を開ける鍵の役割を担っているその言葉を、信は愕然とした表情で聞いていた。