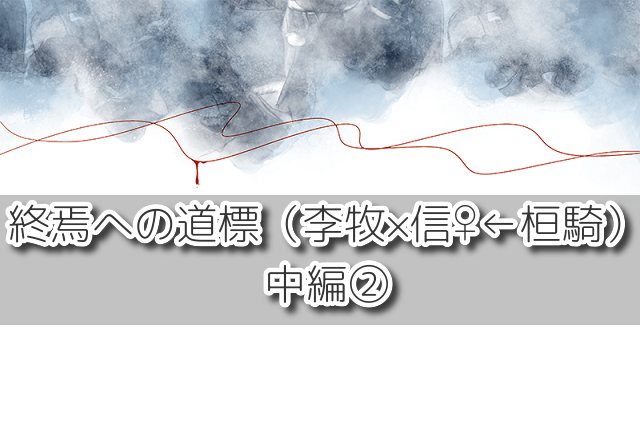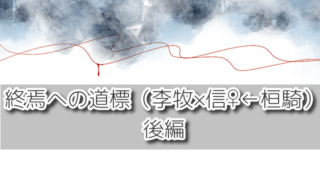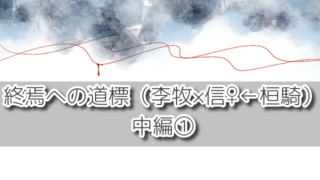- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 李牧×信/桓騎×信/年齢操作あり/ヤンデレ/執着攻め/合従軍/バッドエンド/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は「平行線の終焉」の牧信IFルートです。
懺悔
激痛で焼き切れそうになる意識を繋ぎ止めたのは、幾度も死地を駆け抜けた強靭な精神力のおかげだったのかもしれない。
しかし、今となってはもう、武器を振るうことも出来ない弱い女が、ただ痛みに耐えているだけだった。
「信、気をしっかり持ちなさい」
止血のために切断面に布を被せ、強く圧迫しているのは、右手首を落とした李牧自身だった。
「ひぐ、ッぅ…ふ、ぅく…」
床に落ちている手と、止血をされている腕を交互に見て、右手が身体から切り離されたことを頭が理解するまで、しばらく時間が掛かった。
呼吸がしやすいように、咥えさせられていた布を外されると、がちがちと歯が打ち鳴った。
止血のために断面部を強く押さえられているものの、布はたちまち血で真っ赤に染まっていく。
右手を失うことくらい致命傷ではないと頭では理解しているものの、心臓が脈打つ度に血が溢れて、布だけでなく、床まで真っ赤に染まっている。
床を汚しているおびただしい血の量を見て、それが全て自分の血だと思うと、このまま死んでしまうのではないかという気持ちになった。
しかし、まだ死ぬわけにはいかない。信は歯を食い縛りながら、李牧を睨むように見据えた。
「こ、これ、で…桓騎は、見逃して、くれるんだな…?」
歯を打ち鳴らしながら何とか紡いだ信の言葉を聞いた李牧は、不思議そうな表情を浮かべて小首を傾げた。
「…何の話ですか?」
返された言葉に、信の中で一瞬だけ時間が止まった。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
呆然としている信を見据えながら、
「もう二度とあなたには武器を握ってもらいたくないとは言いましたが、桓騎に手を出さないと誓った覚えはありませんよ」
圧迫止血をする手を休ませることなく、李牧は残酷な言葉を吐き捨てた。
目の奥が燃えるように熱くなり、信はその一瞬、右手を切断された痛みを忘れるほど、怒りに頭が支配された。
「李牧、てめえッ」
残っている左手を振り上げる。
武器を持つことも考えられず、ただ拳を作っただけの攻撃に、李牧は驚くこともしなかった。
まるで信の反撃を予想していたと言わんばかりに、軽々と左手首を掴まれる。
これが決して埋められぬ力の差であると、認めざるを得なかった。
しかし、頭に血が上り切った信は、諦めを知らない。
両手が使えないならと李牧の腕に噛みつこうとした途端、耳を塞ぎたくなるような、嫌な音が響き渡った。
「あああッ」
左手の親指が不自然な方向を向いていることに気付くのと、新たな激痛に信が悲鳴を上げたのはほぼ同時だった。
「あ…ぁ…」
血を流し過ぎたせいだろうか、信の意識は白く霞んでいく。
着物が血で汚れることも厭わず、目線を合わせるように信の前で膝をついた李牧は、彼女の青白くなっていく顔を見つめる。頬に手を伸ばすと、しっとりと汗をかいているものの、まるで氷のように冷たくなっていた。
もう抵抗する気力も体力も底をついたのだろう、李牧に触れられても、信はその手を振り払うことも顔を背けることもしなかった。
「…自らの意志で敵地に乗り込んで来たことは称賛します。しかし、考えが甘かった。あなたの敗因は、卑怯者である私を信じたことでしょうね」
少しずつ瞳から光を失っていく信が、その言葉に反応するかのように唇を戦慄かせた。今の彼女が懺悔と後悔に支配されているのは、言うまでもない。
「か、桓、騎…」
頬を伝う涙は、血の気を失った青白い肌と違って温かった。
その涙を指で拭ってやりながら、李牧は小さく溜息を吐く。
「…あの夜は、桓騎に抱かれながら私の名を呼んでいたというのに、…今となっては、俺ではなく、あの男の名を呼ぶのだな」
悲しげな瞳をしていたが、その声は、刃と同じくらいに冷ややかだった。
右手の止血に集中しなくてはと思っていたのだが、最後まで信が抵抗を続けたせいで、速やかな処置が出来なかった。余計な出血をさせてしまったのはそのせいだろう。
青白い顔で床に倒れ込んでいる信は、か細い呼吸を繰り返していた。
僅かに目は開いているものの、その瞳に光はなく虚ろで、体も脱力している。もうほとんど意識を手放していると言っても良いだろう。
ちょうどその時、あらかじめ呼んでおいた医師が来訪した。
未だ出血している右腕の状態を見て、このまま止血を続けるより、切断面を焼いた方が早いだろうと言われる。
部屋の隅に設置していた青銅製の火鉢には、一本の剣が刺さっている。念のためにと用意していたものだったが、やはり使うことになったかと李牧は落胆を隠し切れなかった。
柄を掴んで剣を引き抜く。火鉢の中で熱を帯びていた刃がぬらぬらと熱を帯びて赤く光っていた。
医師が信の右腕を持ち上げて、未だに血を流し続ける断面を李牧へ向けた。
迷うことなく李牧は真っ赤な刃を断面に押し当てる。意識を失っていても体が激痛を感じているのか、信の体が大きく跳ね上がった。
皮膚が焼ける音がして、鼻につく匂いが煙と共に部屋に充満する。待機していた兵たちはその匂いに顔をしかめていたが、李牧だけはうっすらと笑みを浮かべていたのだった。
一瞬で焼け爛れた腕の断面に軟膏を塗布し、医師が丁寧に包帯を巻いていく。
左手の親指も骨の位置を正しく戻してから、きつく包帯で固定する。これでしばらく両手は使えないだろう。もっとも、右手は二度と使えないのだが。
「………」
李牧は床に落ちていた信の右手を拾い上げた。
切り離されたその手は少しずつ冷たくなっていて、すでに拘縮が始まっており、文字通り血の気が失われている。幾度も武器を振るって肥厚した将の手だった。
悲しみを堪えるために、拳を握って血が流れるほど爪を食い込ませた痕が残っている。他の誰でもない信の手だ。
腕を切り落とすのに借りた剣は、信が秦王嬴政から賜った剣であることを李牧は知っていた。彼女自身の血に塗れた刃をあえて拭うことはせず、李牧は兵に声をかける。
「これを秦国に、必ず送り届けて下さい」
礼儀正しく一礼した兵が李牧の手から、切り落とされた信の右手と血塗れの剣を受け取る。
信は多くの兵や民から慕われている秦将だ。秦王嬴政だけでなく、他の将とも交流があるし、配下たちからは厚い信頼を得ている。今頃、彼女の不在を不審がる者たちが現れているに違いない。
そんな時に趙からの贈り物が秦に届けば、混乱は必須。しかし、彼女が趙でその命を散らせたと誰もが信じ込むはずである。
そして合従軍から秦王と秦国を守り抜いた英雄として、信の存在は長く語り継がれることだろう。
なぜ彼女が戦でもないのに、趙国でその命を散らすことになったのか。それを深く追求し、答えに辿り着く者がいるとすれば、それは李牧の懸念材料である桓騎だけだろう。
(…きっと、あの男だけは信じないでしょうが)
自分の処刑を記した木簡を彼が読んだかは分からないが、信が必死に桓騎を守ろうとしていたあの姿を見れば、彼が救援に来ることを想定していたのだろう。
あの男の聡明な頭脳と知将としての才、そして信に向けている気持ちは李牧もよく知っている。
信が敵国へ、しかも秦を滅ぼさんとした趙の宰相の救援へ向かったと裏付ける証拠になり得るあの木簡を、桓騎は誰の目にもつかぬ場所で処分するはずだと睨んでいた。
命を懸けて秦国と秦王を守り抜いた彼女が趙と密通していたという疑いが掛けられれば、英雄から一転、裏切り者として中華全土にその汚名が広まることになる。
桓騎としては、信の名がそのように汚されることは断じて許さないはずだ。
もっとも、李牧にとっては信の訃報さえ広まれば、彼女が英雄扱いされようが、裏切り者扱いされようが、どちらでも良かった。
…そして、もしも桓騎が信を救出しに来るのならば、それは桓騎自身も命を捨てる覚悟を決めた時だろう。
彼が信と共倒れをするような、短慮な策を考える男ではないことを李牧も分かっていた。自らの命を犠牲にしてでも、何としても信を救い出そうとするに違いない。
そして李牧も、その機を逃すことなく、桓騎の首を取るつもりだった。
趙国の宰相である自分の屋敷に敵国の将がいるとなれば、下手に密通を勘繰る者もいるだろうし、飛信軍に恨みを抱く者たちが報復のために信の身柄を奪いに来るかもしれない。信の身に危険が及ぶことだけは避けたかった。
それに、どのみち秦国に贈り物が届いたのならば、生死は問わず、信の所在は趙にあると広まるだろう。彼女の死を信じない者たちから、信を奪われることだけは何としても避けたかった。
だが、もしも信を逃がすことになったとしても、桓騎の首を取った後で、もう一度取り戻せば良いだけだ。
彼女が自分のために身一つで趙へ駆けつけてくれたのは、長い間共に過ごしていた単なる情に過ぎない。それは桓騎への愛よりも下回る感情なのだと思うと、それだけで腸が煮えくり返りそうになる。
だが、もう二度と他の男の手垢に汚されることはない。
李牧は信を手に入れる未来のために、一度は彼女を手放したのだから。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
初めての嘘
命に別状はないとはいえ、右腕の出血がそれなりに多かったせいか、回復まで時間を要するだろうと医師は話していた。
今、彼女の身柄は李牧の屋敷にあり、信頼出来る従者たちにその世話を任せている。
その日、執務を終えて屋敷に戻るなり、従者から信がようやく目を覚ましたという報告を受けた李牧は、足早に彼女がいる部屋へと向かった。彼女が趙に来てから、三日目のことだった。
部屋に入ると、信は寝台で身を起こしていた。
李牧が部屋に入って来たことにも気づかず、ぼうっとした様子で格子窓の向こうにある月夜を眺めていた。
三日も眠っていたのだから、自分の身に何が起きたのか、彼女自身も混乱しているのかもしれない。
「信」
名を呼ぶと、信はゆっくりとこちらを振り返った。
「…李牧…?」
彼女の双眸に光は戻っていたが、李牧を見るなり、顔に僅かな緊張が浮かぶ。
趙国に信を誘い込んだだけでなく、その右腕を落としたのだから、怯えるのも無理はない。憎悪を向けられるのは当然だと思った。
しかし、信の瞳は戸惑うばかりで、こちらに罵声を浴びせることもしない。
人質という立場として利用している訳でもないので、信自身もどうして生かされているのか、きっと分からずに戸惑っているのだろう。
何と声を掛けようか、李牧が思考を巡らせていると、
「お前…今まで、ずっと、どこで何してたんだよッ!?」
まるで自分のことを案ずるような言葉を掛けられ、これにはさすがの李牧も動揺を隠し切れなかった。
何を言っているのだと聞き返そうとした途端、信の瞳にみるみるうちに涙が溜まっていく。
それが決して演技などではなく、本気で自分との再会に安堵しているのだと分かると、李牧は沸き上がる違和感に思わず眉根を寄せるのだった。
「あの雨の日、お前が急に居なくなって…俺、…」
嗚咽で濁ってしまった言葉に、李牧はまさかと目を見開く。
たった今、信の口から出たあの雨の日というのが、自分が彼女のもとを去ったあの日であると、すぐに結びついた。
李牧が内心動揺していることに気づかず、信は思い出したように言葉を続ける。
「あ、そ、そうだ!父さ、王騎将軍はっ?馬陽で趙軍の策に嵌められたんだ。俺、父さんを助けようと思って…それで…」
信の養父である王騎が没した馬陽の戦の話を持ち出され、李牧のこめかみは締め付けられるように痛んだ。しかし、それを表情に出すことはしない。
訴えから察するに、恐らく信は、馬陽の戦いから先の記憶が無くなっているようだ。
(まさか、そんなことがあり得るのか)
予想外の出来事に、李牧は言葉を失ったまま、信のことを見つめていた。
人は耐え切れぬ心痛に襲われると、防衛のため、無意識のうちに記憶を排除することがあるのだという。
医学に関してはそこまで知識のない李牧だが、その話は人づてに聞いたことがあった。
ただし、実例を見たことは一度もない。よって、記憶が元に戻る方法は、聡明な李牧であっても分からない話だった。
「…李牧?」
いつまでも黙り込んでいる李牧に、信が不思議そうに問いかける。
はっと我に返った李牧は、寝台に腰掛けている彼女のもとに近づくと、強くその体を抱き締めた。
信は抵抗する素振りを見せず、むしろ再会した自分との抱擁を喜ぶように、身体を預けて来た。
両腕を背中に回して自分の体を抱き寄せる信が堪らなく愛おしくて、李牧は喜悦に奥歯を噛み締めた。
信を滅びの運命にある国から救い出すために、李牧は彼女の元を去ったのだが、その間に彼女は心変わりをしてしまい、秦趙同盟で再会した時には既に自分との決別の意志を固めていた。
しかし、今の信は、何よりも誰よりも、恋人である自分を優先していた当時の彼女だ。
もう二度と会えないと思っていた彼女が戻って来てくれたのだ。それが他でもない自分のためであると、李牧は疑わなかった。
(もう二度と手放すものか)
心に固く誓いながら、李牧は信の体を強く抱き締める。
「…王騎は、生きている」
初めて、彼女に嘘を吐いた。
信を完全に我が物にするために、卑怯者に成り下がったことを、李牧は決して後悔することはなかった。
養父が生きていると聞かされた信は安堵の笑みを浮かべた。
「…良かった…」
自分の言葉を微塵も疑うことなく聞き入れるその姿が懐かしくて、李牧もつい笑みを深めてしまう。
この幸せを守っていくためなら、嘘を吐いてでも、卑怯者になろう。
それは信と自分の未来のために必要な好意であると、李牧は自分に言い聞かせた。
彼女を滅びの運命にある国から救い出すために、養父を奪い、合従軍で秦を責め立てた李牧には、もう痛む良心などなかった。
「お前は殿を務めているうちに倒れたんだ。覚えているか?」
信が自分に違和感を抱かぬよう、無意識のうちに、口調が昔のものに戻っていた。
そして当然のように事実と嘘を並べる。嘘を吐くことを、彼女を騙すことに対し、罪悪感など微塵も感じなかった。
全ては自分たちの幸福のためなのだから。
「……、……」
何があったのか思い出そうとしているのか、信が眉根を寄せる。しかし、そう簡単に記憶は戻らないようで、小さく首を横に振った。
馬陽は総大将の王騎の撤退により、秦の敗北で終わった。
撤退の途中で王騎は力尽き、その最期の瞬間に信は立ち会ったと聞いていた。実際にあの戦で殿を務めたのは別の将だが、李牧は都合よくそれを彼女に置き換えたのだった。
「…俺が殿を務めたってことは、…秦は、負けたんだな」
あの戦で秦が敗北したのは事実だ。李牧は沈黙で返事する。
殿は敵軍の侵攻阻止の役割を担う。後方に配置されることが主であり、いつも前線で敵を薙ぎ払っていた飛信軍が担当することは滅多にない役割だった。
自分が殿を務めたということから、信は敗北を察したのだろう。
しかし、彼女の言葉を聞く限り、王騎の死を覚えていない。どうやら、馬陽の戦の最中から記憶が途切れているらしい。
「…?」
未だ李牧の背中に回したままでいる右手に違和感を覚えたのだろう、信は小首を傾げながら、自分の右手に視線を向ける。
手首から先が失われ、包帯に包まれている右腕を見て、信がひゅ、と笛を吹き間違えたような声を上げた。
その視線の先を追い掛けた李牧は、信が自分に腕を落とされたことも覚えていないのだと確信した。
「あ…ぁ…」
信の顔がみるみるうちに青ざめていく。
腕を失うということは、武器を振るえないことに直結する。それはすなわち将としての命運が尽きたという残酷な宣告でもあった。
将以外の生きる道を知らぬ信にしてみれば、それは死刑宣告とも等しいことだろう。青ざめた顔が絶望に染まっていく。
咄嗟に李牧は、彼女を抱き締める腕に力を込めた。
「…お前が殿を務めたことで、王騎は死を免れた。お前のおかげで、王騎だけではなく、兵たちの犠牲も最小限に抑えられたんだ」
痛まし気な表情を浮かべ、彼女の心を傷つけぬように選び抜いた言葉を告げた。
「っ…、ぅ…」
李牧の胸に顔を埋めている信が、小さく嗚咽を零し始める。
「最後まで敵軍に抗ったことは、将として誇るべきことだ。お前を責める者は誰もいない」
その言葉は本心だった。
信が将として戦場に出ることで、どれだけ秦国に貢献しただろう。
蕞から合従軍が撤退することになったのは、信が命を懸けて秦王を守り抜き、そして圧倒的な兵力差にも怯むことなく士気を高め、最後まで戦い抜いたからだ。彼女の存在が秦の命運までも左右したと言っても過言ではない。
山の民からの救援が来なければ、蕞を落とせたのは言うまでもないのだが、仲間を信じていた秦軍の勝利であったことは覆せない事実だ。
「………」
泣き崩れる彼女を抱き締めてやりながら、李牧は昔のことを思い出す。
いつも悲しみを堪える彼女をこうして抱き締めながら、落ち着くまで泣かせていたものだ。そうしないと、彼女は拳を作り、血が流れるまで爪を食い込ませる。恐らく下僕時代からの癖だったのだろう。肥厚した皮膚がそれを物語っていて、李牧が信と出会った時にはその癖は習慣化されていた。
自分が彼女のもとを離れてから、その悪い癖は再発してしまったようだが、右手を失った今ではただの過去でしかない。
「…信?」
「……、……」
声を上げて泣き続けていた信だが、しばらくすると疲れてしまったのか、李牧の胸に凭れ掛かったまま、瞼を下ろし掛けている。
その頭を優しく撫でてやっているうちに、静かな寝息が聞こえ始めた。
寝台に横たえてやり、風邪を引かぬよう肩までしっかり寝具を掛けると、李牧は部屋を出ようと立ち上がった。
馬陽から先の記憶が失われているのは分かったが、もしかしたら一時的に記憶が混在しているだけかもしれない。
傷が癒えたところで、もう彼女が武器を振るうことは叶わない。左手も親指を折っているので、扉を開けることにさえ時間を要するだろう。とはいえ、今の信は休息が必要だ。
三日も眠り続けていたとはいえ、右腕を失ったせいでかなり出血もあったし、体が本調子に戻るまではしばらく時間がかかるに違いない。
従者たちには彼女を外に出さないようにと、常時見張りを頼んでいる。
両手が不自由でも、両脚に枷をしている訳ではないので、万が一のことも考えられたからだ。
二度と武器を持たせぬように右手を落とした時、逃げ出さぬようにと足を落とさなかったのは、やはり情があるのかもしれない。
がむしゃらに彼女を傷つけたい訳ではなかった。
信がここに来たのは自分を救出するためであり、それはまだ彼女の心に自分という存在が強く刻み込まれている証拠なのだから。
幸いにも、今の彼女には桓騎と相思相愛であった記憶はない。
過去に桓騎の素性を調査したが、どうやら彼には身寄りがなく、咸陽で行き倒れているところを信が保護したのだという。
今の信にとって、きっと桓騎はただの子どもでしかないだろう。このまま記憶が戻らなければ、彼女の心は自分が支配出来たままでいられる。
…問題なのは、今の信が、李牧を趙の宰相だと知らぬことだ。
王騎を討ち取った軍略を企てたのも李牧であり、養父の仇同然であると知れば、きっと信は大いに混乱するはずだ。
彼女の心の平穏を保つためには、そして記憶を取り戻すようなきっかけを遠ざけるためには、王騎の死も、自分の趙宰相である立場も告げぬ方が良いだろう。
次に目を覚まして、信の記憶がもとに戻っていたのなら、ただの杞憂で済む話だが、そう上手く事が運べるとも思っていなかった。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
懐古
「…?」
寝台から離れようとした時、腰元に何かが触れたので反射的に振り返った。
信は手首から先のない右腕を、懸命に自分の方に伸ばし、小刻みに動かしていた。きっと手が残っていれば着物を掴んでいたに違いない。
「信?」
まだ起きているのかと声を掛けると、閉ざされていた瞼が僅かに持ち上がり、泣き濡れている瞳と目が合った。
「…行くな、行か、ないで、くれ」
その言葉には聞き覚えがあった。
彼女のもとを去ったあの雨の日、信は泣きながらそう言って自分を引き留めようとした。
もう離れることはないというのに、目を離した隙にどこかへ行ってしまうのではないかという不安に打ち震える信を見て、李牧は胸が締め付けられるように痛んだ。
「ああ、もうどこにも行かない」
寝台の傍に膝をつき、眠っている彼女の体を抱き締める。
将としての未来も潰えてしまい、再び自分を失えば、今度こそ心が壊れてしまうと、信は無意識のうちに恐れているのだろう。
もう自分にしか縋るものがない信の心境を考えると、李牧は卑怯だと分かりながらも、ようやく彼女を手に入れることが出来たのだと思えた。
「李牧…」
弱々しく背中に腕を回して来て、安堵を顔に滲ませる信が堪らなく愛おしくて、浅ましいほどに情欲が膨れ上がる。
抑えなくてはと思うのだが、すでに李牧の手は彼女の両肩に伸びていた。
「…すまない、信。今すぐお前が欲しい」
情欲に染まった瞳を向けると、信は少し戸惑ったように視線を泳がせて、それから小さく頷いた。恥ずかしがりながらも、承諾してくれたことに懐かしさを覚える。
彼女の身体を組み敷くと、二人分の重みに寝台がぎしりと音を立てた。
「う…」
顔を寄せ合うと、信は緊張したように目を閉じた。
ゆっくりと唇を合わせる。秦趙同盟の後に唇を交わしたことを思い出し、李牧はうっとりと目を細めた。
あの時は別れを惜しむ口づけだったが、今はその反対で、再会の喜びを分かち合う口づけだ。
「ん…ふ、ぅ…」
舌を差し込むと、仄かに薬湯の苦味を感じた。
信が眠り続けている間も、気休め程度にしかならないだろうが、痛みを和らげる薬湯を飲ませるよう医師に指示していた。
「う…ぁ…」
舌を絡ませて口づけを深めようとすると、信の体が強張って顔を背けてしまう。
「信?」
口づけを嫌がるような素振りに、李牧はまさか記憶を思い出したのではないかと考えた。
「あ…えっと…」
狼狽える姿を見れば、記憶を取り戻した様子はない。
口づけを拒絶というよりは、恥ずかしさのあまり、どうしたらいいか分からないという反応だった。
「ひ、久しぶりだから、…その、う、上手く、できない、かも…」
信が顔を真っ赤にしたまま目を泳がせる。
緊張で身体を強張らせながら、上手く自分の相手が務まるか分からないと打ち明ける信の初々しい態度に、思わず頬を緩めてしまった。
きっと秦国では桓騎とも体を重ねたのだろうが、今の信には自分以外の男に抱かれた記憶がない。
それでいいと思った。自分以外の男に、その体を抱かれた記憶など、信には必要ない。彼女の破瓜を破ったのも、男に抱かれる喜びを教えたのも、この自分なのだから。
「傷に響くかもしれない。無理はするな」
欲しいと言ったのは自分の方だったのに、李牧は信を気遣う言葉を掛けた。
切り落とした右手は止血のために断面を焼き、今もまだ手当てを続けている。
左手の親指も骨は正しい位置に戻していたが、まだ完全に腫れは引き切っておらず、包帯できつく固定されたままだ。傷の処置は今も続けており、薬湯を飲ませているとはいえ、痛むこともあるだろう。
しかし、信は小さく首を横に振ると、まるで甘えるように李牧の首に両腕を回す。
「いいからっ…」
切羽詰まった声で催促されると、彼女も同じ想いで、自分を欲してくれているのだと分かり、李牧の心臓が激しく脈打った。
「んんっ…」
唇を重ねていたのはほとんど無意識だった。
二度と手放すものかと、李牧は独占欲に掻き立てられるままに、体を動かしていた。
「う…ぅん、ぁ…」
夢中になって舌を絡ませながら、李牧は信の着物を脱がせに掛かっていた。
同じように信も李牧の帯に手を伸ばしているが、右手が使えないせいで、残された左手もたどたどしい動きだった。親指にはまだきつく包帯が巻かれているので、残された四本の指しか使えないのである。
この手では、扉や窓を開けることは容易に出来ないだろう。
…もっとも、信が記憶を取り戻した時や、左手の親指が完治した時にはどうなるかは分からないが。
「はあ…ぁ、…」
まだ口づけしかしていないというのに、信の瞳が恍惚の色を滲ませている。
彼女の破瓜を破ったのも、男に抱かれる悦びをその身に刻み込んだのも全て自分だ。他の男に抱かれたとしても、信の体は自分に触れられる悦びを忘れてなどいなかった。
信の着物を脱がせると、最後に見た時よりも傷の増えた肌が現れる。
致命傷になり得た深い傷からそうでないものまで、自が信のもとを去った後も、彼女は何度も死地へ赴いていた。
この部屋に連れて来た時、胸元に残っていた赤い痕はもう消えかけていた。
それが戦で受けた傷痕ではなく、情事の時につけられたものであると、すぐに分かった。自分もこのような痕を残した記憶があったからだ。
きっと信がここに来るのを引き留めようとした桓騎の仕業だろう。彼女が眠っている間に、初めてその痕を見た時は嫉妬の感情が膨れ上がり、そのまま信の首を締めて、本当に自分のものにしてしまおうかと思ったほどだ。
しかし時間が経てばこの痕がいずれ消えてしまうように、きっと信の記憶からも自分以外の存在は全て消えてしまうに違いない。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
「ひゃ、ぅ…」
胸の柔らかさを手の平で味わっていると、信が甘い声を上げた。
最後にその体を抱いた時よりも幾分か成長していたらしく、豊満さを感じる。先端の芽を指で弾くと、信の体がぴくりと震えた。こちらは相変わらず鋭敏のようだ。
「ぁ…は、ぅ…」
二本の指で胸の芽を挟んだり、軽く摘まんだりしているうちに、信がもどかしげに膝を擦り合わせていた。
硬くそそり立ち、摘まみやすくなった芽をさらに可愛がってやりながら、身を屈め、李牧は信の耳元に熱い吐息を吹き掛ける。舌を差し込むと信の肌がぶわりと鳥肌を立てたのが分かった。
「あ、ぁぅッ…」
擦り合わせている膝を開かせ、脚の間に手を差し込むと、そこは熱と湿り気を帯びていた。
「やあっ…」
少女じみた反応に、変わっていないなと思わず笑みを深めてしまう。
自分を欲しがるくせに、恥じらいを切り離せないでいるのは、記憶の中の彼女のままで、目の前の信はその生き写しだった。
「う…、っ…」
両腕を動かし、男根を愛撫しようとしているようだが、両手が自由に使えないことで、信がもどかしげな表情を浮かべる。
「は…ぁ…」
それでも何とかして男根に触れようと、信は一度身を起こして、李牧の脚の間に頬を摺り寄せて来た。
まるで犬が飼い主に自分の身体を擦り付けるような甘える仕草に、李牧は思わず笑んでしまう。
もちろん愛しい女を奴隷や飼い犬のように扱うつもりは毛頭ないのだが、積極的に甘えて来る信の姿が純粋に嬉しかった。
「ん、んぅ」
自由に使えない両手では着物を脱がせられないと分かった信は、諦めたように着物越しに男根を愛撫することに決めたらしい。
「は、ふ…」
上下の唇で男根を甘く挟み込まれる。着物越しであっても、熱くて湿った吐息を感じ、李牧は思わず息を乱してしまう。褒めるように、脚の間に顔を埋めている信の頭を撫でた。
信の恍惚とした表情を見れば、彼女も同じ想いでいることが分かる。日焼けで傷んだ髪を指で梳きながら、李牧の胸は幸福感でいっぱいになっていた。
救済と幸福
着物越しの愛撫でも男根が屹立してしまったのは、相手が信だからだろう。
どれだけ技量の優れた妓女であったとしても、信でなければ、この身が欲情することはない。それは李牧が信のことを愛している証であった。
彼女のもとを去ってから、李牧は信のことを一日たりとも忘れたことはなかった。
初めから李牧は秦国のことを見限っており、信を滅びの運命から救い出すために、今の地位を築き上げたのだ。一度は彼女を手放すことになったが、その先にある未来のためにもやむを得ないことだった。
秦趙同盟で再会を果たしたとき、どれだけ説得を試みても、信が李牧を選ぶことはなかった。
信は決して自分の信念を曲げない心根の強い女だ。だからこそ、彼女が祖国を見捨てることは出来ないことは分かっていたし、共に滅びの道を選ぶことも分かっていた。
そんな運命から救い出さなくてはならない。過去に王騎を討ち取ったのも、秦国を滅ぼそうとしているのも、すべては信の救済のためだった。
二度と信の笑顔を見られなくなったとしても、それは彼女を滅びの運命から救い出す代償だ。
すでに自分が趙についたことと、王騎を討ち取った軍略によって、信頼は失っているし、今さら彼女から嫌われることを恐れるはずがない。
だから、一時的とはいえ、信が記憶を失ってしまったことに、再び自分を愛していたあの頃の彼女に戻ってくれたことに、李牧はただ幸福を感じていた。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
両脚を割り広げ、今度は李牧が彼女の脚の間に顔を埋めた。
驚きと羞恥で閉じそうになる脚をしっかりと押さえ込み、慎ましい淫華に唇を寄せる。
蜜が滲んでいるせいで、縦筋は艶めかしい光沢を帯びていた。縦筋をなぞるように尖らせた舌先を這わせると、信の体が大きく震えた。
「んんっ、ふ、くっ…はあっ…」
李牧の舌が卑猥な水音を立てながら花弁を捲り上げる度に、信の腰がびくびくと震える。
いつもなら敷布を強く握り締めるのだが、不自由な両手では物を掴むこともままならない。呼吸を切迫させながら、信は敷布の上で両腕を泳がせていた。
「あ、はぁ…」
唾液と蜜で濡れそぼった淫華は、男を誘うように珊瑚色をさらに艶やかに見せている。
固く閉じていた花弁がふやけて左右に開く頃には、信の瞳はとろんしており、もっと欲しいと言わんばかりに李牧に熱い眼差しを向けていた。
「ぁ、うっ…んんっ…!」
もっと善がらせてやろうと舌を差し込むと、信が力なく首を振って身を捩った。中の肉壁は奥の方までよく濡れていた。
一度口を離し、淫華の中に指を押し込んだ。
上壁のざらついた箇所を指の腹で擦る。目当てのものをすぐに見つけ、李牧は腹の内側を指で突き上げた。
「あ、やっ、ぁあっ」
隠れた性感帯を刺激され、信が目を剥いた。信が善がり狂う箇所は全て覚えていた。
自分の手技で善がり狂う信を見ると、彼女の全てを支配出来たような心地になった。
「っ、あ、待っ、ぇ…!」
指を動かしながら、李牧が再び脚の間に顔を寄せると、信が涙を流しながら制止を求めて来る。
花芯を舌で舐ると、彼女の声が甲高くなった。
外側と内側の急所を同時に責め立てられ、信が泣きながら善がる。両手が敷布を掴めないせいで、快楽から意識を逸らす術がなく、どうしようもなくなっているらしい。
久しぶりに身を重ねたのもあるが、感度が高いのはそのせいだろう。
「あっ、ぁ、はあッ、ああぁッ」
やがて、身体が大きく痙攣をしたかと思うと、信の体は力が抜けたように寝台の上に沈み込んだ。
二度目の初夜
寝台の上で荒い呼吸を繰り返す信は、長い睫毛を小刻みに震わせていた。
「信」
汗ばんだ頬を優しく撫でてやると、気持ち良さそうに目を細める。
もっと撫でて欲しいと言わんばかりに、手の平に頬を擦り付ける姿が愛らしくて、李牧は思わず唇を重ねていた。
「ん…」
今度は信の方から舌を絡めて来たので、どうやら絶頂を迎えたことで大いに緊張が解れたことが分かる。
李牧の襟合わせを開こうと、信が不自由な両手をたどたどしく動かす。
口づけを深めながら、李牧は自ら着物の帯を解いて着物を脱ぎ捨てた。
着物を脱いで素肌を寄せ合っても、皮膚で肌を隔てられていることがもどかしい。早く一つになりたいと焦る気持ちを押さえ込みながら、李牧は真っ直ぐに信を見据えた。
「信…本当に良いのか?」
正常位の体勢で結合に備えると、信は何度も頷いて、両手を李牧の背中に回して来る。
初めて彼女の破瓜を破った時も、こうやって何度も確認をした。その身を自分に委ねてくれることの了承の意味もあったし、本当に自分で良いのかという確認でもあった。
「…挿れ、て…くれ…」
泣き笑いのような顔で求められ、李牧は胸の奥から燃え盛るような感覚を覚えた。自分だけを求めているその態度が堪らなく愛おしくて、二度と彼女を手放したくないと思った。
男根の先端を淫華に宛がうと、信が切なげに眉根を寄せた。
胸に赤い痣が残っていたことから、桓騎とは頻繁に身体を重ねていたのかもしれないが、今の彼女にはその記憶はない。
男に身を委ねるのは随分久しぶりのことだと思っているに違いないし、先ほども彼女自身がそう言っていた。
だから、李牧は初夜の時のように、無理をさせず、ゆっくりと腰を前に送り出したのだった。
「は、っぁ、ああっ…!」
太い異物が中を掻き分けていくにつれて、信の背中が弓なりに仰け反った。
無意識のうちに逃れようとする信の体を両腕で強く抱き押さえ、花弁を巻き込むように、李牧は時間をかけて男根を押し込んでいく。
「っ…!」
彼女と身を繋げるのは随分と久しぶりのことだったので、尖端の一番太い部分が入ると、李牧はそこで腰を止めた。
初めて信の破瓜を破ったあの日も、かなり時間を掛けたことを思い出す。
自分と彼女の体格差は大きく、破瓜を破るにはただでさえ激しい痛みを伴うというのに、自分の男根を全て受け入れるのは苦痛でしかない。
破瓜を破るまでにも、李牧はかなりの時間をかけ、この行為は決して痛いだけではないのだとその体に教え込んだのである。懐かしいあの日々が瞼の裏に浮かび上がった。
「信…大丈夫か?」
「う、うぅっ…」
切なげに眉根を寄せながら、しかし信は何度も頷いた。
苦痛に呑まれていないと分かったが、少しでも痛がる様子があればすぐに止めようと、李牧は彼女の顔から視線を外さずに腰を引いてく。
「や、やあっ…」
浅瀬をゆっくり穿つつもりで腰を引いたのだが、男根が抜かれてしまうと誤解したのか、信は嫌がるように首を横に振った。
「ぜ、全部…挿れ、て…」
李牧の肩に腕を回し、強請るようにそんなことを言われると、つい応えたくなってしまう。
「だめだ」
しかし、李牧は首を横に振った。目を覚ましたばかりの体に負担はかけられない。
「力を抜いていろ」
言ってから、初夜の時も同じ指示をしたことを思い出す。
きっと今、自分たちは、二度目の初夜を過ごしているのだと思った。もう一度、彼女と身体と心を結ぶ幸福が訪れているというのに、負担を掛けることはしたくない。
しかし、信は涙を浮かべながら、駄々を捏ねる幼子のように首を横に振った。
「ふ、うぅっ…ん…」
両腕を李牧の背中に回しながら、信はその細腰を淫らに揺らして、男根を深く飲み込もうと淫華を押し付けて来た。
その顔は恍惚としており、苦悶の色は少しも見られない。心から自分を欲してくれているのだと思うと、めちゃくちゃに犯してしまいたくなる。
「どこでそんな強請り方を覚えた?俺はそんなものを教えた覚えはないぞ」
「うう、んぅっ」
叱りつけるように、李牧は呼吸を奪う勢いで、何度もその唇と舌を貪った。
「ふ、はッ…はあッ、あ…」
激しい口づけを終えて、呼吸を整えている信の顔中に何度も唇を落としながら、李牧はさらに腰を前に送り出した。
「っ、んんんッ!」
欲しがっていた信の望みを叶えると、彼女は苦しそうな吐息を洩らしたものの、うっとりと目を細めて李牧のことを見据えていた。
隙間なく密着した下腹部を見下ろし、李牧は自分の男根を全て飲み込んだ信の薄い腹を撫でる。
ゆっくりと指に力を込めて、外側から腹を圧迫すると、連動するように淫華が男根をさらに締め付けた。
「んんっ…!ぁ、そこ、押した、ら…」
内側を男根で犯され、外側からも刺激をされて、信はしたたかに身を捩る。
咄嗟に李牧は彼女の左手を掴み、男根を受け入れている腹に触れさせた。
「こんなに深くまで俺のが入っている。分かるか?」
自分の腹を犯している李牧の男根を感じたらしく、信が薄目を開けながらちいさく頷いた。
「ぁ、…李牧、の、…奥、まで、入って、る…」
身体だけでなく、意識でも一つになったことを実感させると、信の淫華が再び強く男根に吸い付いて来た。
男の子種を求めているその動きに、李牧は思わず生唾を飲み込む。
共に過ごしていた日々では、幾度も信とその身を重ねていたが、中で射精したことは一度もなかった。
当時の信はまだ将軍の座に就いておらず、養父の背中を追い掛けて将軍になろうと日々武功を重ねていた。将軍昇格への夢を、自分の浅ましい欲望で阻む真似はしたくなかった。
今思えば、彼女を手っ取り早く戦から遠ざけるためには、早々に孕ませてしまえば良かったのだ。
もちろんその卑怯な方法を考えなかった訳ではないが、当時の李牧には信を裏切る度胸がなかったのである。
出来ることなら傷つけたくなかったが、彼女を滅びの運命から救うためには、そんな生易しい気持ちではいられなかった。
しかし、今は違う。右手を失った信を妻にすることは容易いことだ。
秦国の女将軍と趙の宰相の婚姻となれば、周りからの反対されることは目に見えているが、李牧にとってそれは些細なことであった。
誰にも自分と信の邪魔はさせない。李牧が趙国についたのは信を滅びの運命から救うためであって、利用している他ならない。
もしも自分と信の婚姻を許さず、彼女を奪おうとする者が現れるのならば、力で捻じ伏せるまでだ。
| 【話題沸騰中!】今なら無料で遊べる人気アプリ | ||
 |
ステート・オブ・サバイバル_WindowsPC版 | |
 |
PROJECT XENO(プロジェクト ゼノ) | |
 |
ムーンライズ・領主の帰還 | |
 |
宝石姫 |
|
顔を寄せ合って熱い吐息を掛け合い、李牧は愛しい女との結合の実感を噛み締めていた。
無理はさせないと誓ったというのに、胸の内側に膨らんでいく独占欲と情欲が腰を動かし始める。
「あ…り、李牧…」
敏感になっている淫華の肉壁を硬い男根が擦り上げる度に、信が切ない吐息を洩らした。
手首から先を失った右手と、親指が折れた左手で顔を挟まれる。
唇が触れ合う寸前まで顔を引き寄せられて、潤んだ瞳に見据えられると、それだけで李牧は絶頂を迎えてしまいそうだった。
「もう…どこにも、行くな…」
縋るような哀願の言葉を掛けられて、李牧の胸は苦しいほどに締め付けられる。
腹の底から込み上げて来る衝動に突き動かされるようにして、李牧は信の身体を強く抱き締める。
「ふあッ…!?」
奥を突くと男根の切先に柔らかい肉壁があたり、それが信の子宮であることはすぐに分かった。
男根を咥えている淫華も、開通するまでにはかなり時間を掛けたものだが、そのさらに奥にあるこんな狭い場所で赤子が育まれ、そして産み落とされるのだと思うと、生命の神秘というものを感じた。
「信っ…!」
「んぁっ、ああっ」
力強く突き上げる度、信の瞳から止めどなく涙が伝っていく。
その涙さえ自分の物だと言わんばかりに、李牧は唇を押し付けて啜り取った。
「り、李牧っ、んぅうっ、ぁ、はあッ」
信が切迫した呼吸の合間に甲高い声で喘ぐ。
ひっきりなしに口から零れる声は喜悦に染まっており、少しも苦痛の色がないことが分かると、李牧は腕の中に収まっている信の体が浮き上がってしまうくらい激しい連打を送った。
顎が砕けるくらい奥歯を噛み締め、首筋に幾つもの線を浮かび上がらせながら、ひたすら信の体を貪る。
会えなかった時間を埋めるように、自分のものである証を刻み付けるように、李牧は夢中で腰を突き動かした。
「あぁっ、ぁッ、もっ、もう…ッ!」
信の体が大きく痙攣したかと思うと、これ以上ないほど淫華が男根を締め付け、李牧の腕の中で身体を仰け反らせていた。
信が絶頂に達した瞬間、李牧自身も目の眩むような快楽と恍惚に包まれて、意識が真っ白に塗り潰されてしまう。
「ッ…!」
息を止めて、彼女の身体を抱き締めながら、最奥で射精する。
幾度も彼女と身体を重ねたことはあったが、中で射精するのはこれが初めてだった。
信が将としての務めに全うするため、李牧の子を孕まぬように、その腹に子種を植え付けないでいたのは、二人の中で暗黙の了解としていたのである。
「あッ、ぇ、な、中…!」
中で射精されていることに気づいたのだろう、戸惑ったように信が眉根を寄せている。
「っ…、くっ…」
全ての精を出し終えるまで、李牧は彼女の体を抱き締めたまま、決して放さなかった。
愛しい女の苗床に、自分という子種を植え付けている感覚は、これ以上ないほど優越感で胸が満たされた。
絶頂の余韻に浸りながら荒い息を吐いていると、信の身体が腕の中でくたりと脱力する。
どうやら気をやったようで、腕の中で規則的な寝息を立てていた。しかし、その表情に苦悶の色は少しもない。
息が整ってからも、李牧は彼女の中から男根を引き抜こうとしなかった。
こうして信と身を繋げたのは随分と久しぶりのことだったが、まだ彼女の体は自分を覚えていたし、心から自分を求めてくれた。
その事実を知って、李牧はますます信のことが愛おしくて堪らなくなる。
(もう二度と手放すものか)
李牧は眠っている信に、静かに口づけた。