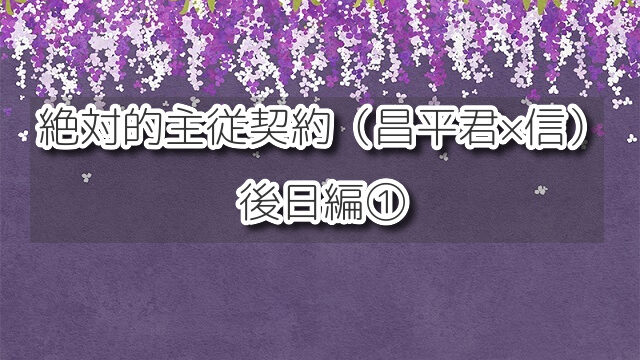- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 桓騎×信/毒耐性/シリアス/IF話/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は「毒酒で乾杯を」の番外編です。
前編はこちら
作戦開始
十日ぶりに帰還した屋敷は、一見何の変わりもないように見えた。
信は辺りを見渡して、罗鸿の姿がそこにないことを確認する。
「あれ?今日は来てねえのか…?」
いつもなら、贈り物が積まれている牛車が何台も並んでいるのだが、今日はそれも見当たらない。
罗鸿が咸陽で名を広めているのは、異国の品だとか他では手に入らない希少価値が高いものだとか、そういった品々を扱っているからだという。
その価値を知る物ならば驚愕してしまいそうだが、信にしてみればぎらぎらと光る目が痛いものばかりで、使い方も分からないし、何より置き場所に困る。
もちろんそんなものは要らないと毎度押し返すのだが、入手するまでの苦労や、二度と手に入らない希少なものだと商品の価値について長々と語り始めるので、これがまた面倒だった。
桓騎なら遠慮なくその貢ぎ物を受け取り、配下たちに分け与えたり、さっさと質に出してしまうか、元値の倍で他者に売りつけそうだと考え、信は小さく笑ってしまう。
「なんだ?」
いきなり笑った信に、桓騎が気味の悪そうな視線を向けて来る。何でもねえよと返した。
「…罗鸿のやつ、今日は来ねえのかも。俺がしばらく留守にしてたからか?」
今日は心強い味方がいるせいか、それともまだ罗鸿が現れていないせいか、信は随分と自分の心に余裕があるように感じた。
すぐに主を出迎えた従者に馬を預け、留守中に変わったことはなかったかを尋ねる。
「それが…」
どうやら信が不在の間も、罗鸿は頻繁にやって来たらしい。
信が屋敷に戻って来る日や行先についてを執拗に尋ねられたが、従者たちが一切答えなかったせいか、ここ数日は姿を現わしていないという。
自分の行方を調べるために、罗鸿が副官たちのもとへ行っていないか心配だったが、飛信軍の鍛錬を邪魔するようなことはなかった。
以前から罗鸿には迷惑していることを仲間たちに愚痴を零しており、副官たちや昔からの仲間たちも、その話を聞いて自分のことのように怒ってくれた。忠義に厚い自慢の将と兵たちである。
そんな大切な仲間たちに何か迷惑が掛かることがあれば、信もさすがにこれ以上の横暴は許さないと考えていたのだが、その心配は無用だったらしい。
罗鸿の目的は信との婚姻で、きっと飛信軍の副官たちに迷惑を掛ければ、すぐに斬り捨てられることを彼も分かっているのだろう。
だというのに、どうしてさっさと諦めてくれないのか。信には罗鸿の考えが少しも分からなかった。
「せっかく来てもらったのに、悪いな」
桓騎を客室に案内しながら、信は申し訳なさそうに眉根を下げた。
罗鸿が待ち構えていたのなら、桓騎も何かしら行動に出るつもりだったに違いない。
今までの罗鸿の行動から、きっと今日も待ち構えているとばかり思っていたのだが、今日は違った。
彼も商人としての仕事があるため、そう長い時間は構ってられないのかもしれない。そのまま商売に徹していてくれれば良いのだが、信が帰還したとなれば、きっとまた来るに違いない。
桓騎が屋敷に滞在してくれている間に来てくれることを願いながら、信は従者が淹れてくれた茶を啜る。
…罗鸿に会ったら、桓騎は何をするつもりなのだろうか。
向かいの席にどっかりと腰を下ろしている桓騎は、相変わらず余裕そうな表情を浮かべている。
目が合うと、彼はにやりと口角を持ち上げた。悪巧みを思いついた時のいつもの笑い方だった。
「門番として、雷土でも貸してやろうか?」
「いや、それは遠慮しとく…」
屋敷の門番をしている兵たちも、飛信軍で大いに訓練をこなしている者たちなのだが、罗鸿はそんな彼らに凄まれても引くことはなかった。
しかし、元野盗であり、桓騎の側近である雷土を立たせておけば、その辺の輩は怯えて近づくことはなくなるだろうと桓騎は笑った。
雷土も素直に引き受けるとは思えないが、お頭と慕っている桓騎からの指示で、なおかつ報酬を握らせておけば、本当に門番を引き受けてくれるかもしれない。
しかし、そんなことをすれば罗鸿だけでなく、屋敷の従者たちまで怯えてしまうだろう。
門番として雷土を採用する提案をしながらも、きっと桓騎はもう罗鸿への対抗策を考えているに違いないと信は思っていた。
彼は考えなしに動く男でない。桓騎自身は動かずとも、彼の頭の中には、いつだって勝利への道筋が描かれていることを信は知っていた。
いつだって余裕の表情を崩さない桓騎であるが、過去に何度か余裕のない表情を見せてくれたことがある。
それは情事の最中で、絶頂が目前に迫っている時の切なげに眉根を寄せている顔だ。きっとそれを知っている者は限られているだろう。
むしろそれ以外で、桓騎が余裕を崩した表情は見たことがないかもしれない。
一度だけ見たことがある珍しい表情といえば、過去に王翦の屋敷に赴き、三人で酒を飲んだ時のことだ。
あの酒の席で注がれたのが毒酒で、信は毒酒の副作用――媚薬を盛られたような状態――を起こしてしまい、王翦が前にいるというのにも関わらず、副作用を落ち着かせる名目で桓騎に淫らな悪戯をされてしまった。
…結局のところ、あれは信へ近づくなと王翦へ釘を刺すために、最初から最後まで桓騎が仕組んだ策であったのだが。
子供じみた独占欲もそうだが、王翦の前であのような辱めを受けたことに信は激怒した。
そして、その制裁として試みた策により、信は初めて桓騎を唆すことに成功したのである。
あの時に見た桓騎の愕然とした表情は、きっと信しか知らない秘密だろう。
「信」
「ん?なんだよ」
名前を呼ばれたかと思うと、桓騎に手招かれて信は立ち上がった。
「わっ…!?」
近づくと腰に手を回されて抱き寄せられて、椅子に腰かけている桓騎の膝の上に座る体勢になる。
密着したことで、信の脳裏に昨夜のことが浮かび上がった。
今日は早朝から屋敷に戻る日だったので、嫌だと言ったのに、桓騎の厭らしい手付きのせいで情欲に火が点いてしまい、結局いつものように身体を重ねてしまったのである。
酒も飲んでいなかったのに、あんな風に甘い声を上げて桓騎を求めた自分の浅ましい姿を思い出し、信は顔を真っ赤にした。
「お、おいッ…昨日も…!」
昨夜も散々体を重ねたというのに、まさかまだ足りないというのか。
今日は流される訳にはいかないと、信が桓騎の悪さをしようとしている手を掴む。
「昨日も?なんだ?」
わざと言葉の続きを促す桓騎に、わざと羞恥心を煽っているとしか思えず、信は悔しそうに奥歯を噛み締める。
その反応を見て、桓騎の口角がますます持ち上がった。
「…続きは?ほら、言えよ」
耳元に唇を寄せて低い声で囁かれる。
たったそれだけのことなのに、信の体が下腹部に甘い疼きが走り、全身が桓騎を求めているのだと分かった。幾度も男の味を覚えさせられ、桓騎の甘い言葉や手付きに一々反応するようになってしまったのである。
厄介な体になってしまったとは思いながらも、それに危機感を抱いていないあたり、彼に心を差し出してしまったことを認めざるを得ない。
「あ…」
耳元に熱い吐息を掛けられて、身体の芯から力が抜けてしまいそうになる。体が崩れ落ちそうになるのを何とか堪え、信は桓騎の胸に凭れ掛かった。
まるで甘えるような態度に桓騎の口角はつり上がる一方だ。
桓騎の膝の上に乗せられながら、彼の脚の間にあるそれが僅かに硬くなっていることが分かると、信は羞恥によって顔が上げられなくなる。
桓騎の骨ばった手が、いよいよ信の着物の帯に伸びた時だった。
「信将軍」
「うわあああッ!?」「うぐッ」
屋敷のことを任せている従者に扉を叩かれ、信は思い切り桓騎のことを突き飛ばしていた。
派手な音を立てて椅子ごと後ろに転げ落ちた桓騎は、思い切り背中を床に打ち付け、くぐもった声を上げる。
首切り桓騎と恐れられているはず彼のそんな無様な悲鳴を聞いたことがあるのは間違いなく信だけだろう。
「信将軍っ?」
「ななな何でもない!どうしたッ?」
扉越しに物音を聞きつけた従者が、何事だと焦って声を掛けて来たが、信は乱れた着物を慌てて整えながら部屋を出る。
「…ったく」
痛む背中を気遣いながら、桓騎はゆっくりと身を起こした。何事もなかったかのように取り繕った信が、咳払いを一つしてから扉を開ける。
取り繕ったとはいえ、未だに顔を真っ赤にした信が肩で息をしている信を見て、従者が不思議そうに小首を傾げていた。しかし、思い出したようにすぐに報告を始める。
「あの商人の男です。信将軍のご帰還をどこから聞きつけたのか、またやって来ました。いつものように屋敷の外で待っています」
「罗鸿か…」
従者の男が困ったように眉根を寄せる。
「まだご帰還していないと伝えましょうか?」
信は頭を掻きながら首を横に振った。
「いや、何を言ってもあの男なら待つだろ。今日は桓騎将軍と出迎える」
すっかり不機嫌になっている恋人の姿をちらりと横目で振り返り、信は従者に罗鸿を招き入れるように伝えた。
「おい、さっさと行くぞ」
「ちっ…」
信が先に部屋を出ていくと、未だ背中を痛そうにしながらも、桓騎は大人しく彼女の後を追い掛けた。
商人罗鸿
「信将軍!」
屋敷を出ると、数台の牛車が目に留まった。先頭の牛車のすぐ傍に立っていた男が、真の姿を見るなり駆け寄って来る。彼が罗鸿だろう。
年齢は桓騎よりも少し上に見えた。信とはそれなりに歳の差があるようだ。
身を包んでいる上質な着物や、丁寧に整えてある髪と髭、それから恰幅の良さを見れば、それなりに裕福な暮らしをしていると分かる。
咸陽では有名な商人と言っていたから、身なりから裕福さを感じさせるのも頷けた。
「お久しぶりでございます。お会い出来るのを楽しみにしておりました」
人の良さそうな笑みを浮かべ、罗鸿は深々と頭を下げる。
商売人としていつも笑顔を繕っているのだろう、笑い皺が目立つ顔だった。どこか胡散臭さが抜けないのは、笑顔さえも商売の武器として利用しているからなのかもしれない。
「私用でしばらく留守にしてた」
屋敷を空けていた事情を簡潔に伝えた信が横目で視線を送って来る。どうやらこの男が罗鸿だと教えているのだろう。
「…で?今日は何の用だ。言っとくが、貢ぎ物や土産は受け取らねえからな」
腕を組みながら、信が罗鸿の後ろにある幾つもの牛車に視線を向ける。
荷台には布で覆われているが、毎度持って来る贈り物の数々が詰まれているのだろう。
罗鸿はまだ何も話していないというのに、うんざりしながら断る信を見れば、本当に迷惑をしていることが分かる。
「そうおっしゃらず!他でもない信将軍のために、此度も珍しい異国の品を集めて参りました」
罗鸿と言えば、信にそのような態度を取られても、人の良さそうな笑みを微塵も崩すことはない。それはまるで余裕の表れのようにも見えた。
商人というものは交渉術に長けていないと利益を得ることが出来ない職だ。武や知略を用いて戦う将と違い、商人は自分の口が何よりの武器となる。
ある意味においては、相手の出方を探る知将に近い才を持っていると言っても良い。確かに信とは相性が悪そうだ。
信の隣に立つ桓騎と目が合うと、罗鸿は不思議そうに目を丸めた。
ずっと信の隣にいたというのに、桓騎の存在に今気づいたということは、よほど信と再会出来たことが嬉しかったのだろう。
それから罗鸿は思い出したように、はっとした表情になる。
「桓騎将軍ではございませんか!お噂はかねがね伺っております。まさかお目にかかれるとは、光栄にございます」
先ほどと同じように深々と頭を下げて自己紹介を始める罗鸿だったが、商人としての顔が輝いたのを桓騎は見逃さなかった。良い金づるに出会えたとでも思われたのかもしれない。
罗鸿が狙っているのは、信を中心とした商売相手の繋がりだ。
桓騎と違って、信は秦将や高官たちと仲が良い。人の心に土足で上がり込んで来るような彼女の性格を好む者は多く、名家の嫡男たちとも仲が良かった。
きっと罗鸿は信と婚姻を結ぶことで、商人としての地位を強固なものに確立し、秦王嬴政だけでなく、秦国の中でも上に立つ者たちを商売相手にするつもりでいるのだろう。
しかし、好いている女をまるで道具のように利用されるのは、決して気分が良いものではない。
「………」
腕を組んで桓騎が静かに罗鸿を見据える。
外道だと罵られるほど残虐な行いをすることで有名な桓騎に沈黙の視線を向けられると、大抵の者はそれだけで怯えて逃げ出すことが多いのだが、彼は違った。
自分の着物の懐に手を差し込むと、
「桓騎将軍、どうぞこちらを」
罗鸿は薄ら笑いを浮かべながら、取り出したそれを桓騎に差し出した。
渡されたそれは小瓶だった。中に薄い桃色の液体が入っている。香料の類だろうか。
「………」
すぐには受け取らず、これが何なのか目で問うと、罗鸿は信に背中を向けてから着物の袖で口元を隠し、声を潜めて話し始めた。
「…夜の宴に相応しいかと。飲み物に混ぜても味は変わりませんし、数滴だけでもすぐに効果が現れますよ」
その言葉から、これが媚薬の類であると桓騎はすぐに合点がいった。
すぐ傍にいる信に聞こえぬように話す辺り、桓騎と信の男女の関係には気づいていないようだ。
もしも罗鸿が自分たちの関係を知っていたのなら、このような無礼極まりない待ち伏せや貢ぎ物の押し付けなどはしなかっただろう。
自分たちの関係は大々的に知られている訳ではない。むしろ知っているのはお互いの従者たちと、親しい者くらいだろう。秦王嬴政とその妻である后も含まれている。
「桓騎将軍。こちらですが、とても希少な商品でございまして…」
桓騎が黙って話を聞いていると、罗鸿は次にその商品の製造工程について語り始めた。
この媚薬は一部の地域でしか育たないという貴重な植物から作ったものだという。
花蕾や果実を乾燥させてから、さらに樹脂や根茎と長時間煮込み、何度もろ過を繰り返す過程を経て、採取出来るのはこの小瓶に入っている僅かな量だけらしい。
工程はともかく、とにかく希少価値の高いものであることは分かった。
随分と鼻息を荒くしながら罗鸿が話し始めたものだから、隣で信が何の話をしているのだと気味悪そうに顔を歪めている。
(気に入らねえな)
こんな男に信を奪われようとしている状況の悪さを改めて理解し、桓騎は小さな溜息を吐いた。表情に出さないまま、嫌悪感を抱く。
先ほど、罗鸿はこの媚薬を着物の袖から取り出していた。
牛車の荷に積んでいなかったのは、価値の高いそれが移動中に破損しないようにという気遣いだったのかもしれないが、懐に忍ばせていたことから、常備していたと言っても良い。
もしも、自分がこの場に居なかったら、信は知らずにその媚薬を飲まされていたかもしれない。
飲み物に混ぜても味が変わらないと言ったのは罗鸿本人だ。信がそのような仕掛けに気づけるはずはないし、飲ませるのは容易なことだろう。
もしかしたら信から罗鸿のことを打ち明けられる前に、そんな危機的状況に陥ることがあったかもしれなかったのだ。
どれだけの効力を持つ媚薬かは不明だが、日頃から自分に抱かれ慣れている信のことだから淫らな獣に豹変してしまうに違いなかった。
それを口実に、罗鸿は信から肉体関係を迫られただとか、新たな噂を流すつもりだったのかもしれない。
もし信が媚薬を飲まされたとして、毒の副作用が現れた時と同様に男を求めるようになったら、罗鸿の策通りに事が進んでしまう。
冷静な判断が出来ず、本能のままに快楽に溺れるあの姿を桓騎は良く知っていたし、絶対に他者に知られてはならないと思っていた。
副作用のことを考慮して、自分以外の前で毒酒を飲むなと口酸っぱく伝えていたのはそのためである。
信のあのような淫らな姿を前にして、正気でいられる男はきっといないだろう。
自分でさえ冷静でいられる自信はないし、趙の宰相だってそうだった。そこらの男が我慢出来るとは思えない。
婚姻の口実を作るためにあれこれ手を回している罗鸿も骨抜きになり、自分の地位の確立のためだけでなく、異性として信のことを手に入れようとするに違いなかった。
「どうぞ、お気に入りの女子にでもお使いくださいませ」
「………」
怒りを煽るように追い打ちを掛けられて、桓騎のこめかみに熱くて鋭いものが走った。
自分の知らない場所で信がこの男から卑猥な言葉を掛けられることも、肌を隅々まで見られ、ましてや触れられることなんて、絶対に許す訳にはいかないと思った。
趙の宰相に抱かれたと知った時は腸が煮えくり返りそうになったし、裏で手を回し、呂不韋と趙の宰相の暗殺まで計画していたのは桓騎だけの秘密である。
いつまでも桓騎が受け取らずに沈黙を貫いていると、痺れを切らしたのか、罗鸿が強引に小瓶を握らせて来た。
「どうぞ遠慮なさらずお受け取り下さい。これはお近づきの証です」
遠慮などしていないというのに、有無を言わさずに押し付けて来るこの強引さに、信も困り果てているのだろう。
話を聞くだけで理解していたつもりだが、これは確かに面倒な男だと思った。
この汚らわしい手が、指一本でも信の体に触れる前に、腕ごと落としてやろうかと考える。
「桓騎?」
名前を呼ばれて、反射的に振り返る。隣で信が心配そうに桓騎を見つめていた。
いつまでも黙り込んでいる桓騎の口元が僅かに引き攣っている異変には気づいたようだが、渡されたこの小瓶の正体が媚薬の類だということには気づいていないようだった
反撃開始
日に日に信への独占欲が深まっていることは自覚していたし、信もそれには気付いているようだったが、普段の自分を知っている彼女に、感情を剥き出しにする無様な姿は見せたくなかった。
静かに息を吐いて、僅かに波立った心を落ち着かせてから、桓騎は罗鸿の方に向き直る。
「…もっと他に珍しい品はあるか?」
桓騎は小瓶を手の中で弄びながら問いかけると、罗鸿の瞳が輝いた。仕入れた品々に桓騎が興味を示したのだと思ったのだろう。
「ええ、ええ!もちろん用意してございますとも!桓騎将軍がお望みならば、何だって取り寄せましょうぞ!」
またもや鼻息を荒くしながら、罗鸿が何度も頷く。
「なら、日を改めて用意して来い。気に入ったものがあったら良い値で買ってやるよ」
「おお…!ありがとうございます!」
信と同じく大将軍の地位に就いている桓騎となれば、戦での褒美や普段からの給金など、その辺の者とは比べ物にならないほど得ている。
思わぬ商売の機会が飛び込んで来たことに、罗鸿は満面の笑みを浮かべて頭を下げた。
「何かお好みはございますか?桓騎将軍のお気に召す品を揃えて参ります」
胸の前で両手の手の平を擦り付けながら、罗鸿が問う。顎を撫でつけた桓騎は少し考えるふりをした。
「…なら、良い嫁入り道具を揃えておけ」
「は…?嫁入り道具…ですか?」
「そうだ」
意外だったのだろう、罗鸿が目を丸めている。隣にいる信も何の話だと小首を傾げていた。
一般的に嫁入り道具とは、女性が婚儀で着用する嫁衣や、嫁ぎ先で使用する家財道具のことを指す。家具や調度品、着物や装飾品など、それらは花嫁の実家の地位や財力を示すものでもあった。
本来なら女性の実家が用意すべきものということもあって、罗鸿は桓騎が何のために嫁入り道具を欲しているのか、理解出来ずにいるようだった。
それでも結婚を連想させる物であることから、桓騎自身か、彼の身内の祝い事が関わっているのだろうと良いように解釈したらしい。
「ええ、ええ、もちろん一級品をご用意させていただきます!」
気前の良い返事に、得意げに口角を持ち上げた桓騎は信の肩に腕を回し、その体を強引に抱き寄せた。
もう罗鸿には興味を失ったように、信だけを視界に入れ、桓騎は優しい眼差しを向ける。
「俺のところに輿入れするのに必要だろ?なあ、信?」
その言葉に驚愕したのは罗鸿だけでなく、声を掛けられた信自身もだった。
何を言い出すんだと信が口を開きかけた途端、桓騎は肩に回していた手で彼女の二の腕を思い切り摘まむ。
「ぅんッ!?」
突如走った痛みに、信が身体を跳び上がらせながら不器用な返事をした。
思わず笑いを噛み堪えていると、
「え、ええと?お、お二人は、これから、ご結婚される…ということで、ございましょうか?」
驚愕の表情のまま、罗鸿が尋ねて来た。
「ああ、そうだ。こいつの育て親はもういないからな。嫁入り道具は自分で用意しなきゃならねえだろ?」
信の育て親である王騎と摎が馬陽の戦いで没しているのは、秦国で広く知れ渡っている事実だ。
しかし、桓騎と信の男女の関係を知らなかった罗鸿は、二人の結婚話など微塵も予想していなかったのだろう、あからさまに狼狽え始める。
桓騎が他者を手の平で弄ぶのが堪らなく面白いと感じるのは、この動揺っぷりを目の当たりにした瞬間だった。
「………」
信が何か言いたげに視線を送って来たが、桓騎はいつでも二の腕を摘まめるように肌の上に指を這わせる。
どうやらそれで桓騎の意図を察したらしく、信は大人しく口を噤んで縮こまっていた。
罗鸿の目には、信がまるで桓騎に甘えるかのように、その身を委ねているように見えたらしく、苦笑が引き攣り笑いになっている。
お前の入る余地はないのだと言わんばかりに、見せつけるように桓騎は信の体を抱き締めたままでいた。
「そ、それはそれは…!おめでたいですな…!いやはや、日頃から噂話には耳を傾けているものの、そのような吉報は初耳でした…」
何とか冷静さを取り繕うとしている罗鸿の姿が滑稽で、桓騎はさらなる動揺を煽るように言葉を紡ぐ。
「秦王を驚かせてやろうと思ってずっと内密にしていた。…あいつの面白え顔を拝むために、このことはくれぐれも外部に洩らすなよ」
もっともらしい理由で信がこれまで縁談を断っていた理由を代弁し、釘を刺すようにドスの効いた声で低く囁くと、罗鸿は青ざめながらも頷いた。
信といえば、この国で絶対的権力を持つ親友をあいつ呼ばわりした桓騎に呆れた視線を向けている。
「で、では、あの、一級品をご用意させていただき、また日を改めて、お伺いいたします…」
「ああ、頼んだぜ」
先ほどまでの商人としての勢いが鎮火されたようになり、罗鸿は縮こまって頭を下げた。
いくら罗鸿が信の夫の座を狙っていたとしても、桓騎には敵わない。それは商人という立場が将軍よりも下だという自覚がある証拠だった。
信がずっと縁談を断り続けていた理由をようやく理解した罗鸿は、狼狽えることしか出来ずにいるらしい。先ほどまでは威勢よく商売をしていたくせに、あたふたと言葉を選んでいる姿に、桓騎は笑いを噛み堪えるのが大変だった。
ふと、放置されたままの牛車に気が付いた。
積んである荷は布で覆われているため、何が詰まれているのかは分からない。しかし、信が興味を抱かないものということは、恐らく金や銀で作ったような高級な物なのだろう。
どうせこれらは全て信への貢ぎ物で、信本人は不要だと言うのだから、自分が代わりにもらってやろうと考えた。配下たちへの手土産にちょうどいい。
この高級な品々を、全て信へのご機嫌取りのために押し付けるということは、それを仕入れるにあたって相当な金を貯め込んでいることも分かる。
良い金づるを見つけたと考えたのは罗鸿だけでなく、桓騎もであった。
「今日の貢ぎ物はもらっておいてやるよ。こいつの夫になる俺の物でもあるだろ?」
「そ、そうですね…」
信との婚姻どころか、彼女のご機嫌取りのために用意した貢ぎ物までもが桓騎に奪われることとなり、罗鸿はその顔に苦笑が隠せずにいた。
しかし、桓騎が何か文句があるのかと言わんばかりに鋭い一瞥をくれてやると、彼は逃げ出すようにその場を後にしたのだった。
穏便解決?
罗鸿の姿が見えなくなった後、信は桓騎の腕の中から抜け出した。
険しい表情を浮かべているのを見て、てっきり笑顔で感謝されるとばかり思っていた桓騎は小さく小首を傾げる。
呆れたように信が肩を竦めた。
「お前…いくら何でも、あんなこと言って騙すなんて…」
「騙す?」
心外だと桓騎は肩を竦めた。
「悪い虫を追い払ってやったのに、礼もなしか?」
口を尖らせて不機嫌を顔に出すと、信は少し考えてから、罗鸿が置いていった牛車を指さした。
「じゃあ、あれ全部やるから、これで貸し借りはナシな?」
「………」
ひくりと口元が引き攣る。
それなりに価値があると見て、罗鸿から上手い具合に奪い取った品々だが、まさかそれを今回の礼として宛がわれるとは思わなかった。
「ま、あの様子ならもう来ないだろうし、本当に助かったぜ。ありがとな」
花が咲いたような笑顔を向けられる。罗鸿と違って胡散臭さは微塵も感じられず、本当に安堵しているといった表情だった。
どうやらこれで清算した気になっているらしいが、礼を言われても桓騎の胸は釈然としない。
何故なら、この件はまだ終わりではないからだ。
「…あいつ、まだ諦めてねえぞ」
「えっ?」
罗鸿に渡された小瓶を手で弄びつつ、桓騎が独り言ちると、信が驚いたように聞き返す。
「な、なんで…?」
あれだけしつこく縁談を迫って来た男がこのまま素直に引き下がると本当に思っているのかと、桓騎は唇に苦笑を浮かべた。
「少しは頭を使えよ。…動き出すのは、向こうの準備が整ってからだろうがな」
まるで罗鸿の行動を先読みしているかのような言葉に、笑顔を取り戻したはずの信の表情が曇る。
「わっ?」
切なげに皺が寄せられた彼女の眉間を指で弾き、桓騎はにやりと笑う。
「心配すんな。全部上手くいく」
その言葉を聞いた信の頬が自然と緩んだ。
罗鸿からの誘い
その後も桓騎は信の屋敷に滞在していた。
予想では十日ほど経ってから罗鸿が再び現れると睨んでいたのだが、彼が一級品の嫁入り道具を手配したと屋敷に書簡を寄越したのは、五日が経ってからのことだった。
早急に動き出したところから、桓騎と信の関係を知って、よほど余裕がなくしていることが分かる。
実際に罗鸿と会って分かったことだが、彼が私欲のために信を利用しようとしていたのは間違いないだろう。彼の目は信を異性として好いているものではなく、高い地位を得るために踏み台にしか見ていない。
そしてそれは、桓騎が罗鸿を排除するのに十分過ぎる理由であった。
(さァて…どう出るか)
書簡を読み終えた後、桓騎は頬杖をついて、気だるげに目を伏せる。
罗鸿から送られて来た書簡には、桓騎が依頼した一級品の嫁入り道具を用意したと記されていた。
嫁入り道具の受け渡しに当たっては、ある条件が記されていた。
桓騎が信との婚姻を内密にしていることを伝えたからだろう、罗鸿は他の民たちからの目を気にしてか、夜になってから受け渡したいと申し出たのである。
二人が婚姻を未だ公には出来ない事情から、罗鸿の屋敷でささやかながら祝いの席を設けたいことや、嫁入り道具だけでなく、祝いの品も贈りたいという言葉が綴られていた。
このことから予想出来るのは二点。
一つは罗鸿が今後も良い商売相手として、自分たちと繋がりを持っておきたいと考えていることである。
そしてもう一つは、罗鸿が信との婚姻を諦め切れていなかった場合の話だ。桓騎はきっと後者に違いないと睨んでいた。
「…なあ、本当に行くのか?」
不安げに瞳を揺らしながら、同じく書簡を読んだ信が問いかけて来た。罗鸿の誘いに乗ってやろうと言ったのは桓騎の方である。
「せっかくの誘いだからな」
余裕たっぷりの笑みを見て、信は不安そうに眉根を寄せる。
桓騎が信頼している配下にさえ策を共有しない男であることは知っていた。それは桓騎の中で勝利への道筋が浮かんでいるからだと、理解していたのだが、それでも信は不安の色を隠せない。
桓騎が浮かべている勝利への道筋を疑っている訳ではなく、いつもの極悪非道な首切り桓騎が何をしようとしているのかという不安であった。
捕虜や女子供には一切手出しをしないことを信条としている信は、桓騎がこれまで行って来た血も涙もない命の奪い方を良いものだとは思えなかった。
たとえそれが、桓騎の信条であったとしてもだ。
「………」
切なげに眉根を寄せた信に、桓騎は薄ら笑いを浮かべるばかりで何も語ろうとしない。
桓騎が自分にさえ策を告げようとしないのは、全く異なる信条を貫く信から口を出されるのが面倒だと思っているからだろうか。
「信」
いつまでも顔から不安の色を消せずにいる彼女に、桓騎は優しい声色で名前を呼んだ。
「安心しろ。お前が不安がるようなことはしない」
「本当か?」
間髪入れずに信が聞き返すと、
「……あいつの出方次第だがな」
意味深な沈黙の後に桓騎がそう言ったので、信はひと悶着起こることを予想して、深い溜息を吐いた。