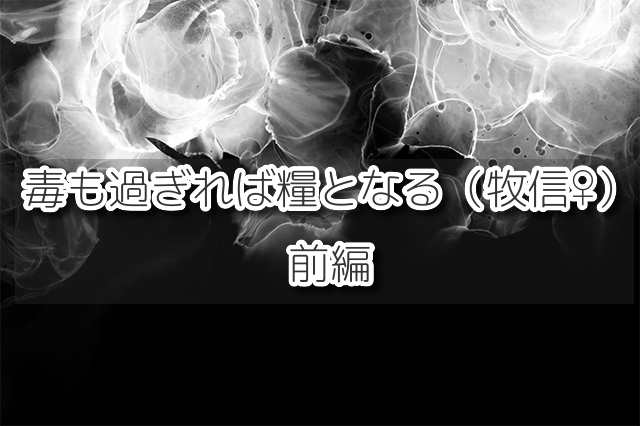- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 桓騎×信/毒耐性/シリアス/IF話/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は「毒酒で乾杯を」の番外編です。
もてなし
後日、他の民たちの目を避けるためにという名目で、二人は罗鸿の指示通りに、夜になってから彼の屋敷に訪れた。
罗鸿は二人が護衛も連れずにやって来たことに驚いていたものの、すぐにあの胡散臭い笑顔で出迎えてくれた。
大きな門を潜ると、すぐに広大な庭院が現れた。石橋が掛かっている池の中央には四阿 がある。
池の水には淀みや苔一つないことから、頻繁に手入れが施されているようだ。金色の鱗を持つ立派な鯉が幾匹も泳いでいる。
これほどまでに大きな屋敷を築き上げることや、その手入れを任せるのに人を雇う財力はそこらの商人では得られない。
屋敷の外装もそうだが、この広大な庭院を見れば、罗鸿が商人として大いに成功していることを物語っていた。
「どうぞこちらへ」
罗鸿が石橋を渡り、池の中央にある四阿へと案内される。すでに四阿には二人の侍女が待機していた。
設置されている椅子に腰を下ろす。机には酒瓶と杯、それから両手に抱えられるくらいの大きさの桐箱が用意されていた。
二人が椅子に腰かけたのを見届けてから、罗鸿が二人に深々と頭を下げた。
「ささやかですが、私からお祝いをさせていただきます。まずはご依頼いただいた品の一つをご覧ください」
用意されていた桐箱の蓋を開けると、そこには赤い嫁衣が収納されていた。
絹糸で繕ったその嫁衣は光沢があり、美しい花の刺繍が施されている。着物の価値が分からぬ者でも高級品であると見ただけで理解出来る代物だ。
「一級品の嫁衣をご用意いたしました。婚儀の際にはぜひこちらをお召しください」
「へえ…」
吐息を零しながら信も美しい嫁衣に見惚れている。手に入れたいというよりは、芸術品でも鑑賞しているような顔だった。
金目のものに一切の興味を示さないはずの信がそんな反応を見せるのは珍しいことで、こればかりは罗鸿に依頼しておいて良かったかもしれないと考える。
「信将軍。せっかくですからご試着をしてみてはいかがでしょう」
信の反応に気を良くした罗鸿が両手の手の平を擦り付けながら、胡散臭い笑みを浮かべる。
「え?でも…」
桓騎との婚姻は、罗鸿を諦めさせるための偽装工作だ。かなりの値打ちものであるこの嫁衣を実際に着る機会がないことを、信は心のどこかで申し訳なく思っているのだろう。
「良いじゃねえか。試しに着てみろ。修整も必要になるかもしれねえだろ」
それらしい言葉を使って試着を勧める桓騎に、信は少し戸惑いながらも頷いた。
待機していた侍女の一人が嫁衣の入った桐箱を箱抱え、もう一人が信を連れて行く。着付けのために母屋の一室へ案内するらしい。
罗鸿が試着を勧めたのは、きっと信をこの場から遠ざけるためだろう。
恐らく信はこれが罗鸿の策だと気づいていないに違いないが、桓騎はそれを見抜いており、あえてその策に乗ってやろうと、信に試着をするよう命じたのだ。
「信」
三人が四阿を出て、石橋を踏み込んだところで、桓騎は信の背中に声を掛けた。
「面紗 はつけるな。それは婚儀の時で良い」
「あ、ああ、分かった」
魔除けの意味が込められており、花嫁の顔を覆うための紗を外すのは、婚儀の時に夫となる男の役目である。
単なる試着だとしても、面紗をつけるのは正式な婚儀の場であるべきだ。
規律に縛られることを何よりも嫌っているこの自分が、婚儀の習わしに従おうとしている矛盾に桓騎は苦笑した。
もちろん婚儀を挙げるのは作り話なのだが、彼女が嫁衣を身に纏う姿は是非とも見ておきたい。
(…さァて)
侍女たちに案内され、回廊を通っていく信の姿が見えなくなると、桓騎はいつものように、両足を机へどんと乗せた。
招かれている立場だとしても無礼極まりない態度であることは十分に自覚していたが、罗鸿の感情を煽る目的もあった。
冷静さを取り繕ってはいるものの、余裕を失くした罗鸿が行動に出るならそろそろだろう。
彼自身が行動に移すのはこれからで、しかし、もうすでに水面下では事が進んでいることを、桓騎は書簡を受け取る前から予見していたのである。
「桓騎将軍。信将軍がお戻りになるまで、こちらの美酒をご堪能ください。ささやかですが祝杯でございます」
胡散臭い笑みを深めながら、罗鸿が用意してあった酒瓶を手に取った。
祝い酒として杯に注がれていくそれを見て、桓騎は僅かに目を細める。
「…酌をするやつが、野郎なのは気に入らねえな」
桓騎は注がれた酒をすぐに飲むことはせず、退屈そうに背もたれに身体を預ける。
「どうぞご勘弁を」
そんな理由で酒を飲まれないとは思っていなかったようで、罗鸿が困ったように頭を下げた。
先ほどの侍女たちは信の着付けを行っているようで、戻って来る気配はない。かといって他の侍女が来ることはなく、この場にいるのは桓騎と罗鸿だけだった。
「私はしがない商人で、そう多くは侍女の手配も出来ませんので…」
もっともらしい理由で罗鸿が答える。しかし、桓騎は注がれた酒を飲むことはしなかった。
「随分と謙遜するじゃねぇか?信にはあれだけ自信満々で迫ってた野郎が、どういう風の吹き回しだ?」
遠慮なく棘のある言葉を投げかけると、罗鸿の笑顔が引き攣ったのが分かった。
何を思ったのか、彼はその場に躊躇いなく膝をつく。
「まさか桓騎将軍と信将軍が婚姻を結ばれるとは存じ上げず…どうかご容赦を…」
恐れをなしたというよりは、単に桓騎の機嫌を損ねないようにしているのだろう。少しも誠意のこもっていない謝罪に、桓騎は肩を竦める。
目的を叶えるためなら、容易く膝をついて頭を下げることも厭わない自尊心の低さにはむしろ感心してしまう。
男の膝には大いなる価値があるというのに、商人というものは相手の機嫌を伺わなくてはならない面倒な商売だ。
「隠してたからな。信が縁談を断り続けてたのもこれで納得しただろ」
「返す言葉もございません」
詫びを入れるその顔は、やはり申し訳なさを繕っただけの表情であった。
それから桓騎はこれまで信に貢いで来た贈り物は何なのか、どこで仕入れた品なのかを罗鸿に問うた。
別に興味がある訳ではなく、罗鸿の出方を見るための時間稼ぎである。
他愛のない話を続けていると、どうやら痺れを切らしたのか、罗鸿がわざとらしく咳払いをする。
「桓騎将軍、まだ信将軍はお戻りになりません。先に美酒を堪能してはいかがでしょうか?」
先ほど注いだまま放置していた酒を飲ませようとすることから、やはり酒に何かしらの細工をしているのだと桓騎はすぐに見抜いた。
他の家臣や侍女たちが来ない二人きりの状況で酒を勧めるだなんて、どうぞ疑ってくださいと言っているようなものである。
細工の正体はきっと眠り薬か毒の単純な二択だろう。しかし、早急に桓騎の処理を考えている今の罗鸿が選ぶなら、当然後者になる。
さっさと桓騎を消してしまいたいという焦りが全面的に表れていることに、罗鸿本人は気づいていないようだ。
「…お前も飲めよ。一級品の嫁入り道具を用意してくれた礼だ」
台の上に置かれていた酒瓶を手に取ると、恐らくは信が飲むために用意されていた杯に酒を注いでやる。
「………」
酒を注ぎながら、桓騎は罗鸿の表情に変化がないか横目で確認する。
もしもここで酒を勧められたことに動揺するならば、この酒瓶の中身が毒酒であると見て間違いないだろう。
「いえ、この酒はお二人の祝いのために取り寄せた貴重な代物です。私が頂くには値しません」
表情に動揺は見られなかったが、桓騎の誘いを上手い具合に回避したことから、中味が毒酒であることを確信する。
胡散臭い笑顔で罗鸿は仮面をした気になっているのだろうが、その瞳からはひしひしと殺意が沸き上がっていた。はっきりと殺意を感じるようになったのは、信がこの場からいなくなってからだ。
幼い頃から過酷な環境で育ち、今でも将として戦場に出れば死と隣り合わせである桓騎の前では、殺意は隠しても意味がない。
そして奇策を用いて相手を攻め立てる桓騎には、ずる賢い策略など、たとえここが戦場でなくとも無意味なのである。
きっと罗鸿からしてみれば、桓騎さえいなければ、あともう一押しで信を手に入れることが出来たと歯痒い想いをしていることだろう。
だが、そもそも人の女を盗ろうとした方が悪いのだ。
最後は自分が勝利を噛み締めて高らかに笑っている姿を想像しながら、桓騎は罗鸿の策に乗ってやろうと、自分に注がれた酒杯に手を伸ばした。
もてなし その二
「罗鸿様」
ちょうどその時、先ほど信を母屋へ連れて行った侍女の一人が現れた。嫁衣の着付けが終わったのか、侍女が罗鸿に何かを耳打ちする。
桓騎が違和感に覚えたのはその時だった。
侍女の鼻から顎まで厚手の布で覆われており、顔の半分が隠されていたのである。
仕入れた嫁衣は桓騎の注文通り、一級品の代物なのだから、着付けの際、侍女の化粧や香油がつかないように配慮したのかもしれない。
未だ桓騎が酒を飲まずにいることには気がかりのようだが、侍女の話を聞いた罗鸿は桓騎の方に向き直り、あの胡散臭い笑顔を浮かべた。
「信将軍の御支度が整ったようです。それでは、さっそくこの場にお連れしなさい」
「え…よろしいのですか?」
侍女が聞き返すと、罗鸿はきっと彼女を睨みつけた。
その視線に怯えた侍女は足早に四阿を後にする。支度を終えた信を連れて来るらしい。
良い金づるである桓騎と信の前では、いつだって笑みを絶やさずにいたのに、侍女に見せた鋭い目つきに、桓騎はそちらが罗鸿の本性かと考えた。
そんな表情を呆気なく披露してしまうくらい、もう彼には余裕が残されていないのだろう。
「いやはや、信将軍の花嫁姿が拝めるとは、なんたる幸福でしょう」
罗鸿の鼻息は僅かに荒かった。
信の嫁衣姿を心待ちにしていたのか、それともこれから邪魔者を消して自分の策略通りにいくことを想像し、出世の喜びを噛み締めているのか。
…どちらにせよ、それは今しか味わえない幸福だと桓騎は心の中でほくそ笑んだ。
「お連れしました」
二人の侍女に連れられて、赤い嫁衣に身を包んだ信が回廊から現れる。
「ほう」
その姿を見て、自然と口角が上がってしまう。
桓騎に言われた通りに面紗はしていなかったが、顔には化粧が施されている。
信の顔に刻まれている小さな傷痕が隠れているのは白粉を使ったからだろう。唇には紅が引かれており、上品さが際立っている。
いつもは後ろで一括りに結んでいるだけの髪も丁寧に結われていた。美しく着飾った信の姿に、桓騎はつい感嘆の溜息を零す。
いつも背中に携えている秦王から授かった剣は預けて来たらしい。確かに嫁衣を着て、剣を背負う女など聞いたことがない。
頭のてっぺんから足の先まで着飾った彼女は滅多に見られないので、こうして目に焼けつけるようにしている。今の信の姿を生き写しておく道具がないことが悔やまれる。
絵で描く程度ではだめだ。筆と紙に乗せたところで信の美しさが再現出来るはずがない。
罗鸿ならば今の信の姿を、まるで時を止めたかのように、生き写すことが出来る類の珍しい品を持っているのではないだろうかと考えた。
「…?」
ふと、二度目の違和感を覚える。
ここに来てから信はまだ一滴だって酒を飲んでいないはずなのに、まるで酔ったかのように足元がふらついているのである。
それに加え、とても眠そうな瞳をしており、瞼が落ちかけている。侍女たちの支えがなければすぐにでも倒れ込んでしまいそうだった。
「信?」
「……、……」
声を掛けても、信から返事や反応はない。すでに意識の半分を手放しているようだった。
布で鼻と口元を覆っている二人の侍女に支えられながら何とか四阿へと戻って来た信だが、椅子に座るや否や、化粧や着物の乱れも気にせず、机に突っ伏してしまう。
「おい、信」
「……、……」
不自然なほど、すぐに寝息を立て始めた信に声を掛けるが、深い眠りについてしまったのか返事はない。
本当に眠っているのかと彼女に顔を近づけたその時、茉莉花 の香りが鼻についた。嫁衣に焚いてあった香だろうか。
茉莉花自体に鎮静作用があり、気分を落ち着かせる効果があるのだという知識は桓騎も知っていた。
以前、信が屋敷に来た時に、些細なことで言い争いになってしまい、その時に摩論が茉莉花の茶を淹れてくれたのである。
二人が屋敷で喧嘩をすると自分たちが胃を痛めるのだと、さり気なく嫌味を言われながら、茉莉花の効能についても話してくれたのだ。
(眠らされたか)
あれだけ不安定な足取りであったにも関わらず、連れて来た侍女たちは心配するような素振りも見せず、早々に席を外していった。
つまりは信があのような状態になるのを初めから知っていたに違いない。
摩論が茶を淹れてくれた時に嗅いだものと、着物に焚かれている香では僅かに匂いが違った。恐らくは茉莉花以外に催眠作用のある薬も一緒に焚かれていたのだろう。あるいは、着付けを行う部屋の香炉に薬を仕組んでいたのかもしれない。
そして信の着付けを行った侍女たちが鼻と口元を布で覆っていたのは、着付けの際にその強力な香の影響を受けないようにしていたに違いない。
顔の半分を隠す理由を信に問われれば、貴重な嫁衣に化粧がつかぬようにと答えただろうし、その返答で信も納得して着付けを任せただろう。
それら全てを罗鸿が指示を出したのだと思うと、彼はなかなかの策士であることが分かる。よほど信との婚姻を諦められずにいるらしい。
桓騎の推察
桓騎のその読みは当たっていた。
罗鸿の狙いは信であり、彼女を傷つけることは絶対に出来ない。それはここに来る前から断言出来た。
婚姻を結ぶにあたっては、信自身にも良い結婚相手という印象を抱かせておかないと、彼女と親しい者たちから反対されるのは目に見えているし、そうなれば付き合いの短い罗鸿よりも仲間たちの言葉を信用するはずだ。
そして、桓騎という邪魔者を消そうとしていることを信に勘付かれれば、間違いなく彼女に阻止されるどころか、瞬時に信頼を失うこととなる。
そうなれば罗鸿がいかに上手い言葉で弁解しようとも、信頼を失ったことで結婚への可能性も絶たれてしまう。むしろ桓騎の殺害を企てた罪で処罰を受けることになり兼ねない。
(そういうことか)
桓騎の中で、罗鸿が考えたであろう筋書きが浮かび上がった。
罗鸿が描く成功への道筋は、信に気づかれぬように桓騎を始末することである。
酒と嫁衣に仕掛けをしていたことを考えると、恐らくは信に席を外させて香で眠らせ、その間に桓騎の毒殺を試みるつもりだったに違いない。
毒酒で倒れた桓騎を人目のつかぬよう遺体の処理を行い、信は嫁衣を着せられたことで強引に婚姻の儀を執り行うつもりだったのだろう。
香のせいで抵抗の出来ない信を無理やり手籠めにするつもりだったのか、彼女に後ろ盾がないことから、婚儀の手順を大いに無視して婚姻を結ぶつもりだったのかは定かではないが、どちらにせよ卑劣なやり方だ。
秦の大将軍である桓騎を手に掛けたとなれば、罗鸿の死罪は確実となる。その罪から逃れるために、事故にでも見せかけて処理をするつもりだったのだろう。
罗鸿の筋書き通りにいかなかったことといえば、桓騎が酒を飲まずに時間稼ぎをしていたことだろう。
もしも罗鸿の筋書き通りに事が進んでいたのなら、桓騎が信とこの場で合流することはなかった。
支度を終えたことを報告しに来た侍女が、この場に信を連れて来て良いのかと罗鸿に聞き返していたことから、それは間違いないだろう。
報復開始
「やや、眠られてしまいましたね。随分とお疲れのご様子でしたから、致し方ありませんな」
静かに寝息を立てている信を見て、罗鸿が心配そうに独りごちる。眠り香を用意したのは他でもない彼自身のくせに、白々しい演技だ。
屋敷を訪れた時、信は疲労など微塵も感じさせなかったというのに、相変わらず罗鸿の言葉には演技じみたものを感じる。
罗鸿の冷静ぶりから、桓騎が警戒していることは初めから分かっていたようにも思える。もしかしたら、桓騎が酒を飲まなかった時の策も用意していたのかもしれない。
「風邪を引かれては大変です」
罗鸿が着ている羽織を脱いだのを見て、桓騎は僅かに頬を引き攣らせた。
机に突っ伏して眠っている信の身体が冷えぬように、嫁衣の上から自分の羽織を掛けようとする罗鸿に、反吐が出そうになる。すでに信の夫になったつもりなのだろうか。
「おい」
自分でも驚くような低い声で言い放つと、罗鸿は驚いたように身を竦ませた。
「腕が惜しければそいつに触るな」
今日は腰元に剣は携えていなかったが、いつでも腕を切り落としてやるという桓騎の態度に、罗鸿はみるみるうちに顔を青ざめさせていく。
「………」
何事もなかったかのように罗鸿は羽織に袖を通し、桓騎の威圧感に対抗すべく、まずは咳払いを一つした。
桓騎と彼の軍の残虐性については秦国でも有名だったので、罗鸿も聞いたことがあったに違いない。
躊躇なく子供も老人も例外なく殺す野盗の恐ろしさを前に、逃げ出さないのは度胸がある証拠か、それとも命知らずのどちらかだろう。
(ん?)
瞬きをした途端、罗鸿の顔つきと雰囲気が別人のように変わる。いよいよ本性を出して来たかと桓騎は心の中でほくそ笑んだ。
もしもここで完全に信から手を退くのなら見逃してやっても良かったのだが、交渉を始めようとする彼の態度から、信との婚姻をまだ諦めていないのだと察した。
救いようのないやつだと不敵な笑みを浮かべ、桓騎は相変わらずの余裕を見せつける。
「で?そいつに聞かれちゃ不味い話があるんだろ」
御託を並べられるのは面倒だと、桓騎の方から本題に切り込んだ。
しかし、小癪にも罗鸿の方はとぼけるつもりでいるのか、小首を傾げている。
「はて、何のことでしょう?仰る意味が分かり兼ねます」
仕方ないと肩を竦めた桓騎は、今日のために仕入れておいたとっておきの情報を告げることにした。
もう信も眠っていることだし、今はお互いに本性を曝け出す絶好の機会だ。腹の内がより黒いのはどちらか証明してやろう。
「…贈賄なんざ、手慣れてるじゃねえか。さすが闇商人だなァ?」
贈賄という言葉に反応したのか、もしくは闇商人か、はたまたどちらもか。罗鸿の顔があからさまに引き攣ったのを桓騎は見逃さなかった。
「か、桓騎将軍、どうかそのような悪い御冗談はおやめください」
口元を袖で隠しながら女のように笑うのは、商人として動揺を見抜かれまいと顔を隠そうとしているだろうか。
だが、嘘や隠し事の類は、相手に勘付かれては何も意味がない。
相手が信のように嘘や隠し事が一切出来ない真っ直ぐな性格であったらなら、まだ許容出来たかもしれないが、残念ながら罗鸿に関してはそうはいかない。
元野盗として、人の所有物を盗むことには手練れている桓騎だったが、自分の所有物を狙おうとしている輩には、一切の容赦なく制裁を与えるほど無慈悲で独占欲が凄まじいのである。執着と言ってもいい。
自分以外の誰かに、所有物を横取りされることは絶対に許せなかった。
「随分と物騒な商売してるんだってな?金になるんなら人間を売ることも厭わねえらしいじゃねえか」
罗鸿がぐっと歯を食い縛ったのが分かり、桓騎はさらに挑発するようにせせら笑った。
情報というものは金でやり取りできるものである。極秘事項であればあるほど金額も上乗せになるのだが、それだけの価値があると言ってもいい。
信に貸しを作ると言った日から、桓騎はさっそく動き出していた。
表向きには出回らない情報も、そちらの方面に知人の多い桓騎ならば、入手することは容易なのである。
もちろん彼らには随分と良くしてもらっているため、謝礼を払う必要もなく、情報を頂けたというワケだ。
…信に勘付かれたら色々と面倒になりそうなので、彼女には今後もその交友関係については内密にする予定である。
「知ってるだろうが、俺の気はそう長くない」
低い声を放った。
見逃してやる条件もまだ提示していないというのに、どうやら罗鸿はまだ挽回する機会あると哀れにも信じているようで、その顔に胡散臭い笑みを貼り付けていた。
「将軍。積もる話は、ぜひともこちらの美酒を味わってからにしましょう」
酒が注がれている杯を差し出しながら、罗鸿が微笑んだ。どうやらまだ毒殺を諦めていなかったらしい。
本来なら早々に桓騎を毒殺し、その死体の処理を行う気でいたのだろう。
桓騎を含め、桓騎軍を憎んでいる者は大勢いる。それを理由に死体の処理はどうとでもなると考えていたに違いない。
もしもそんなことになれば、気性の荒い仲間たちがどのように罗鸿へ報復をするのかも楽しみだが、生憎まだ死んでやるつもりはなかった。
「そんなに美味い酒なのか」
「ええ、ええ!それはとっても!酒蔵から仕入れるのにも、あまりにも人気で買い手が多く、苦労した代物でして」
理由付けて酒を飲ませようとする罗鸿に、もう一芝居打ってやるかと、桓騎は注がれた酒を迷うことなく口に運んだ。
「………」
喉を伝う強い痺れに、やはり毒酒の類だと察する。
何度か飲んだことのある味だ。つい最近も飲んだ蛇毒の酒である。毒酒の中でもそう珍しいものではないが、毒に耐性のない者が飲めば即死する代物であることには変わりない。
胃が燃えるように熱くなり、常人なら卒倒してしまいそうな強さの酒だった。
この手の毒は神経に作用するもので、体の痺れを引き起こす。
手足の麻痺から始まり、神経と筋肉の両方に麻痺が起こることで、呼吸器官にも影響するし、そうなれば死に直結する。
もちろん常人ならば抵抗も出来ずに絶命してしまうだろう。しかし、桓騎に限ってはそうでなかった。
「…ほう。確かに美味い酒だな?何処の酒蔵で仕入れた物だ?」
あっと言う間に杯を空にした桓騎が、感想を言いながら酒瓶を手に取って自らお代わりを注いだことに、罗鸿の顔があからさまに引きつっている。
狼狽える視線の先を追い掛けると、台の上にある杯と酒瓶がある。自分に飲ませる酒を間違えたのではないかと考えているのかもしれない。
きっと彼の中では、毒酒を飲んで倒れた桓騎の死体の処理を早々に行うつもりでいたのだろう。
「え、ええと、北方…いえ、蕞の方で贔屓にしている酒蔵、でしたかな?ははは、どうも物覚えが悪くて、申し訳ございません…」
予定を崩されたどころか、毒が効かぬ人間などいるのかと、罗鸿の思考は混乱の渦に陥ってしまったらしい。
「へえ」
二杯目の毒酒も軽々と飲み干した桓騎に、罗鸿の顔色はどんどん悪くなっていく。
「…信も寝ちまった。酌をしてくれる奴が居ねえのが残念だな」
残念そうに言うと、
「あ、ぜ、ぜひとも私が…」
罗鸿が三杯目の毒酒を杯に注いでくれた。その手は僅かに震えており、動揺を隠し切れていない。
なぜ死なないのかとその顔に深々と書かれているのがまた滑稽だった。
種明かしをするつもりはないのだが、その反応はなかなかに楽しませてくれる。
「こんなに美味い酒を俺が独り占めしちまうのは勿体ねえな。叩き起こして信にも飲ませてやるか」
その提案を聞いた罗鸿が驚いて声を裏返した。
「いえ!随分と御休みになっているご様子ですから…!また後日、信将軍には同じものをお贈り致します」
桓騎は得意気に口角を吊り上げたまま罗鸿を見やった。
「なら、お前が付き合えよ」
遠慮する必要はないと、桓騎は近くにあった杯を罗鸿に突き出した。先ほど自分が注いでやったものだ。
この自分が酒を注いでやるのは、信を含めて数える程度の人数しかいないのだが、罗鸿をその数に加えるつもりはない。
もうじき、この男とは永遠の別れになるのだから、加える必要などないのだ。
笑えるくらいに顔を青ざめた罗鸿が杯を受け取らずにいるので、桓騎はわざとらしく小首を傾げた。
「俺からの杯は受け取れねえか」
「あ、い、いえ、あの、貴重な酒ですから、どうぞ桓騎将軍がご賞味いただければと…!」
苦し紛れの言い訳も、そろそろ浮かばなくなって来た頃だろう。罗鸿が企てた計画は、桓騎の毒耐性によって全て狂わされたらしい。
毒酒を注いだ杯を一向に受け取ろうとしないので、桓騎は仕方なく自分で飲むことにした。
酔いが回り始めたことを自覚し、桓騎は頬杖をついて、罗鸿を見つめる。
そろそろ種明かしをしても良い頃合いだろうか。
「…で?家臣たちが誰一人助けに来ないのは、何でだろうなァ?」
愉悦を浮かべた目を細めながら罗鸿に簡単な問題を提示すると、彼は血の気の引いた唇を戦慄かせる。
「ま、まさか…」
すぐに正解を教えてやるのはつまらない。桓騎は口角をつり上げながら言葉を紡いだ。
「桓騎軍の噂は知ってるか?」
「………」
黙り込んでいるのはその噂を知っているからか、そうでないからか、桓騎にとってはどちらでも良かった。
「留守中に忍び込むのも得意だが、俺たちは夜に動く方がもっと得意なんだよ」
元野盗である自分たちは夜目がよく利くのだと教えてやると、面白いくらいに罗鸿の体が震え始めた。
自分の手の平で転がしている相手が、思い通りに動く姿を見下ろすのは優越感を抱くものだ。
桓騎は歯を剥き出して笑い声を上げた。
回想
秦の大将軍である桓騎を手に掛けることは、死罪に値するものだ。
その重罪の代償を背負いながらも、しかし罗鸿は信との婚姻を諦められずにいた。
彼女を手中に収めておけば、彼女の周りの者たちを商売相手にすることが出来る。中でも秦王嬴政との繋がりは喉から手が出るほど欲しい。
信は下僕出身でありながらも、武の才を見抜かれたことで名家である王家の養子となり、そこから他の名家や高官たちとの繋がりを広く持っている。
そんな彼女を妻に娶れば、たちまち商売も広がり、天下の豪商と称えられる日も近くなるだろう。
信との婚姻を狙っている男は数え切れないほどいることは分かっていたし、彼らを出し抜いて、ここまで婚姻の話を手繰り寄せたのは自分の他にいなかった。
だが、確実に自分が信と婚姻するためには、まず桓騎と信の婚姻を何としても阻止しなくてはならない。
桓騎を毒殺したとしても、彼の亡骸が見つかれば捜査が始まる。
あの男が自ら毒を仰ぐはずがない。自死ではなく、何者かの仕業だと必ず勘付く者が現れるだろう。
もちろん検死が入れば、確実に毒を盛ったことを見抜かれ、犯人探しが始まるに違いない。屋敷に招いた自分に疑いの目が向けられるのは当然のことだった。そうなれば信と婚姻するどころではない。
信が桓騎と共にこの屋敷に招かれたことを証言できる以上、二人を屋敷に招いた罗鸿は確実に桓騎を毒殺した罪に問われる。
だからこそ、信の意識がない間に桓騎を毒殺し、その亡骸を隠蔽する必要があった。
桓騎軍は桓騎を含めて元野盗の集まりだ。彼が他の将と違って、秦王に忠誠を誓わずにいる素行の態度は民にまで知れ渡っていたし、急に失踪したとしても何らおかしなことではない。
中華全土に知れ渡っている桓騎軍の残虐性から、彼に恨みを持っている者も多くいる。報復をされたと考えるのがきっと自然だろう。
それを利用して、罗鸿は桓騎を水面下で処理するつもりだった。
金になるならどんな代物でも扱う闇商人である自分だが、力で敵うことはない。
ならば、商人らしく頭を使った策を用いるべきだろう。桓騎が酒好きだという話は聞いたので、それを利用するまでだと考えた。
闇商人の繋がりから、暗殺道具である毒酒を製造している酒蔵を捜し出し、そこで罗鸿は蛇毒で作った毒酒を見つけたのである。
売ってくれた男は気前が良く、毒酒の効果を見せるために、野ネズミにその毒酒を注いだ。
野鼠がすぐに絶命したことから、それが本物の毒酒であると信用した罗鸿は、すぐに購入したのである。なかなかに良い値であったが、桓騎を処分するためには致し方ない出費だった。
騙されたのではないかと疑ったが、野ネズミが絶命したあの姿を見れば、毒酒は本物であると認めざるを得ない。
毒酒を売ってくれた男の話によれば、人間なら一杯飲めば確実に死に至るだろうとのことだった。
では、どうして桓騎はその毒酒を飲んで生きていられるのか。
自分が注ぐ酒を間違ったのではないかとも思えたが、さすがに直接飲んで確かめるのは代償が大き過ぎる。
本来ならば、信が嫁衣の着付けを行うために席を外している間に、桓騎を毒殺する予定だった。
信のために用意した嫁衣には、催眠作用のある香を焚きつけている。これで彼女を眠らせているうちに、桓騎の亡骸を隠蔽しておけば策は成る。
信が朝に目を覚ましたのなら、桓騎は急用で先に帰宅したとでも言えば良かった。彼女を言い包めることは容易いものだ。
そして嫁衣を着ている彼女を民たちに見せつければ、確実に罗鸿と婚姻を結ぶのだと誤解し、また噂が広まるだろう。そこまで念入りに情報操作が行われれば、もう桓騎は助けに来ないし、信も自分と婚姻をするしかない。
桓騎の亡骸を隠蔽するだけでなく、家臣たちとは口裏を合わせ、もしも桓騎の行方を追う調査が入ったとしても、屋敷を出て行く姿を見たと証言させるつもりでいた。
だから、何としてでもここで桓騎を仕留めておく必要があった。
…だというのに、桓騎は三杯目になる毒酒を飲んでも、少しも苦しむ様子を見せない。
罗鸿は、目の前で歯を剥き出して笑っている男を、呆然と見つめることしか出来なかった。