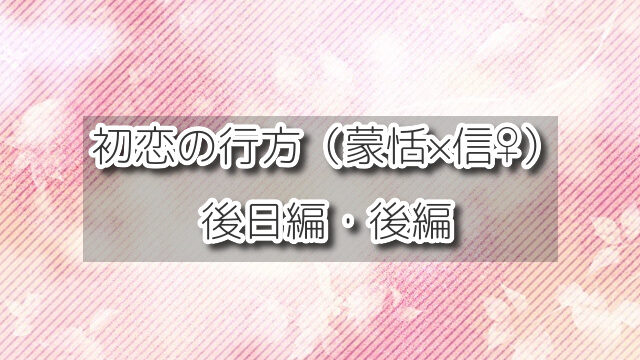- ※信の設定が特殊です。
- 女体化・王騎と摎の娘・めちゃ強・将軍ポジション(飛信軍)になってます。
- 一人称や口調は変わらずですが、年齢とかその辺は都合の良いように合わせてます。
- 桓騎×信/王翦×信/毒耐性/シリアス/IF話/All rights reserved.
苦手な方は閲覧をお控え下さい。
このお話は毒酒で乾杯をの番外編です。
毒の副作用
肩で息をする信を見て、王翦が仮面の下で僅かに顔をしかめた。
耐性を持っているにも関わらず、苦しがる信の姿に何が起きているのか分からないのだろう。
毒を摂取し過ぎると、媚薬を飲まされたかのように性欲と感度が高まるのは信も知っていたが、それを知らない王翦からしてみれば、苦しんでいる姿にしか映らないだろう。
「ッ…」
息を切らしながら、信は自分にしっかりしろと喝を入れる。時間さえ経てば落ち着くのだが、まだ当分先だろう。
あの場では毒を盛った庖宰 の男を庇うために飲まざるを得なかった。
もしも桓騎と王翦が鰭酒だと気づかなければ、信は飲んだふりをしてやり過ごしていただろう。そして本来、毒を盛られるべき相手が桓騎だったことは気づかなかったに違いない。
庖宰の男を庇ったことに後悔していないのだが、何としてでも毒の副作用で理性を失うことだけは避けなくては。
今の状況をどう切り抜けるか、信は靄が掛かり始めた思考で必死に考える。
とにかく、まずはこの場から離れなくてはと思い、一人になれる場所を探すために、信は立ち上がろうとした。
「っあ…!」
後ろからぐいと腕を引かれて、信は椅子に腰掛けている桓騎の膝の上に座り込んでしまった。
振り返ると、桓騎は悪い笑みを浮かべており、思わず背筋が凍り付く。何かを企んでいる時の顔だった。
毒の副作用で苦しんでいる時に桓騎がしてくれることといえば、一つしかない。
初めて鴆酒の毒が回って倒れた時も、嬴政の命を狙った刺客から毒の刃を受けた時も、彼は足腰が立たなくなるまで自分を抱いて、その副作用を落ち着かせた。
あの時は幸いにも嬴政がすぐに部屋を出て行ってくれたのだが、もしも親友の前で桓騎とまぐわっていたとしたら、二度と嬴政の前に顔を出せなかっただろう。
「ば、ばかッ、放せッ…!」
しかし、今は王翦が目の前にいるにも関わらず、桓騎が自分を抱こうとしているのだと察した信は必死に彼の腕を振り解こうとする。
どうやら桓騎の方も信が自分の企みに気づいたのだと分かったようで、ますます笑みを深めていた。首筋の赤い痣を隠していた襟巻きを解かれてしまう。
「桓騎ッ?」
戸惑っている信の体を両腕で抱き押えながら、
「悪いがこいつは俺のだ。潔く諦めろ」
まるで宣戦布告のように、桓騎は王翦へ言葉を投げかけた。
腕の中で顔を真っ赤にしている信へ視線を向け、それから勝ち誇ったような笑みを向ける。
驚いている信が腕の中から逃げ出すより前に、桓騎は堂々と彼女の着物の襟合わせに手を潜らせ、反対の手で帯を解いた。
普段よりも緩く巻かれているさらしの中に忍ばせた手で柔らかい胸を揉みしだく。
「お、お前、何してッ」
意図して弄ったのだとしか思えない手付きに、信は桓騎が本気であることを察した。
身体を重ねるようになってから、彼の手によって優しく育てられて来た二つの膨らみはすっかり感度が高まってしまい、特に先端の芽は敏感になっていた。
桓騎以外の誰かの目があるとしても、感度の上がったそこを刺激されれば、全身い甘い痺れが走るのだ。
当然それは桓騎も分かっている。王翦がいる前だというのに、わざとやったとしか思えない。
敏感な胸の芽を指で弾かれると、思わず声が上がりそうになる。
「触んなっ…!」
慌てて桓騎の手首を掴むが、決してやめることはなかった。
「擦れるだけで感じるようになっちまったもんな?」
普段は着物の下でさらしを巻いているらしいが、さらしがなければ着物に擦れてくすぐったいだと、恥じらいながら話していたことを桓騎は思い出した。
耳に熱い吐息を吹き掛けながら、からかうように囁けば、顔を真っ赤にした信が悔しそうな顔で睨んで来る。
「誰のせい、で…!」
「ん?もしかして俺か?」
「あっ…」
親指と人差し指を使って胸の芽を強く挟むと、信の身体が小さく跳ねた。
「立派に育てちまって悪かったな。十分俺好みだ」
少しも悪いと思っていない口ぶりで、桓騎は胸の芽を指の腹で擦り付けた。
「ふ、ぅうっ…」
鰭酒の毒は強力であり、酔いが回るのは早い。
それを一気飲みしたのだから、いつもの副作用が出るのも、そして副作用の強さも普段の比ではなかった。
身体が火照り、普段よりも感度が上昇している。桓騎もそれを分かった上で、胸の芽を重点的に攻めているのだろう。
「~~~ッ…!」
羞恥で顔を真っ赤に染めながら、信は桓騎の指先から与えられる快楽に歯を食い縛った。
しかし、桓騎が指を動かす度に全身に甘い痺れが全身を貫き、腰が砕けそうになる。
「ふッ、うんん…」
淫らな声を堪えようとして、歯を食い縛っているというのに、鼻奥で悶える情けない声が上がってしまう。
その反応を楽しむかのように、桓騎が喉奥でくくっと笑った。
「おい、王翦が見てる前でなんて声上げてる」
「っうぅ…」
そんなことは分かっている。信は強く瞼を閉じたまま、背後からは桓騎の、そして前から王翦の視線をしっかりと感じていた。
羞恥のあまり、目を開くことも叶わない。毒のせいで頭がぐらぐらとして、理性を繋ぎ止めておくのがやっとだった。
仮面で顔を隠している王翦は、浅ましい声を上げる自分をどんな目で見ているのだろう。想像するだけで恥ずかしくて死んでしまいそうだった。
いっそ、意識までも毒に飲み込まれてしまえばと思ったが、強靭な理性がそれを許さない。
王一族の当主の前で、痴態を晒すのだけは絶対に嫌だった。
「やめ、ろ、って…!頼む、から…」
力が抜けそうになりながらも、信は抵抗を試みた。
何とか桓騎の手を胸から引き離そうとするのだが、耳に舌を差し込まれると力が抜けてしまう。
「ふ、ぅッ…」
背筋に戦慄が走る。未だ触れられてもいない下腹部がずくずくと疼いて、信は口の端から呑み込めない涎を流した。
淫らな姿を見せる信に苦笑を深めながら、桓騎は右手で胸を弄り、左手で彼女の下腹部に触れる。
足の間に、はしたない染みが広がっているのは分かっていたのだが、まだ触れずにいるのは楽しみを後に残しておくためだった。
「う、っん、ぅく…」
臍の下の、下生えよりも少し上の辺りを着物越しに指で押してやると、信の体がびくりと震える。
毒の耐性を得るのと引き換えに生殖機能を失った其処が、男の子種を求めて疼いているのだ。
「っ、…ぃ、やだ、って…!」
膝を擦り合わせながら、信が小さく首を横に振っている。
まさかまだ抵抗する気力が残っているのかと内心驚きながら、桓騎はその理性を完膚なきまでに砕いてやりたいと思った。
ここが二人きりの褥の中だったのならば、信は淫らに声を上げて、早く欲しいと訴えていただろう。それをしないのは王翦がこの場にいるからだ。
そんな分かり切ったことを考えながらも、桓騎は行為をやめるつもりはなかった。王翦へ信に手出しをさせぬよう、釘を刺しておく必要があった。
しかし、腕の中で淫らな声を上げて身を捩る信を見れば、王翦のことなどどうでもよくなって、情欲に身を任せてしまいたくなる。
(堪んねえな)
とことん泣かせたくなる加虐心が駆り立てられるのは、信の魅力なのかもしれない。
もちろんここまで淫らに育てたのは他の誰でもない自分であり、そのことに桓騎は優越感さえ覚えていた。
毒の副作用 その二
まだ胸と下腹にしか触れていないというのに、信は嫌悪と陶酔を織り交ぜた複雑な表情を浮かべていた。
「っん、うぅ…」
下袴の中に手を差し込み、確かめるように桓騎は足の間に指を這わせた。ぬるぬると粘り気のある蜜が指に纏わりつき、思わず口角がつり上がってしまう。
はしたない染みが出来ていた時から気づいていたが、嫌がる口とは正反対に、淫華は蜜を溢れさせ、早く触れてほしいと誘っているのだ。
「こんなにしてりゃあ、辛いだろうなあ」
「やッ…」
腰を軽く浮かせた隙に下袴を脱がす。膝辺りまで中途半端に脱がせたせいで、かえって身動きが取れなくなってしまったらしい。
羞恥によって、全身の血液が顔に全て集まってしまったのではないかと思うほど、信は真っ赤にしている。
信の眼前で淫華の蜜を纏った二本の指を広げてみせると、いやらしく糸を引いていた。
彼女を辱めるような言葉を投げかけておきながら、桓騎の視線は王翦へと向けられている。
目の前で桓騎が信に淫らなちょっかいを掛けているというのに、彼は少しも動揺することなく、黙って酒を口に運んでいる。視線は少しも合わなかった。
興味がないのか、それとも戯れに付き合ってやっているのかは定かではなかったが、確実に見聞きはしているだろう。そしていつまでも席を外そうとしないところを見る限り、留まる意志があるのは確かだ。
動揺を誘う訳ではないのだが、この女は自分のものであることを桓騎は目の前の男に知らしめたかった。
元より、王翦に釘を刺すつもりで今日の誘いに乗ってやり、信を連れて来たのだ。目的は果たさねばなるまい。
膝の辺りで引っ掛かっている下袴を脱がそうとする桓騎の手を、信は必死になって押さえ込んでいた。
毒が回っていないとしても、普段から力量差があるというのに、まだ諦めていないようだ。残っている僅かな理性を打ち砕かねばならない。
背後から耳に舌を差し込むと、信が身体を強張らせた。
「ひッ、ぃ…」
ただでさえ敏感な其処が滑った舌の感触に支配され、信が鳥肌を立てたのが分かった。
力が抜けた一瞬の隙をついて、下袴を奪い取ると肩越しに涙目で睨みつけられる。その潤んだ瞳に見据えられれば、それだけで情欲を煽られるものなのだと信はいつまでも学習しない。
「こんな、の、いや、だ…!」
羞恥心などさっさと手放してしまえばいいのに、辱めを受けている気分でいるのか、いよいよ信が啜り泣き始めた。
それまで強気に腕を掴んでいたというのに、くしゃくしゃに顔を歪めて、幼子のように声を上げる信を見ると、桓騎の中の残虐心が駆られてしまう。
頬を伝う涙を見ると、同時に罪悪感も浮かび上がって来た。
(悪いな)
心の中で謝罪しながらも、桓騎は手を止めることはしない。
こんなことをすれば信に嫌われるのは百も承知だったが、それを上回る独占欲に支配されていることも桓騎には自覚があった。
身じろぐ信の身体を二本の腕で強く抱き締めてやり、桓騎は項に唇を寄せる。
「ふ、あ…ッ」
僅かな刺激であっても、信は火傷をしたかのように身体を反応させた。足の間からは相変わらず蜜が溢れ出ている。
堰を切ったように涙を流している信を見て、先に折れたのは桓騎の方だった。
「信」
脇下に手を忍ばせて、彼女の身体を反転させる。向かい合うように膝上に座らせると、信の視界から王翦は消える。
「ぁ、う…」
身体の向きを変えただけで、この場から王翦が居なくなったワケではないのだが、極限状態まで追い詰められていた信は僅かに安堵したようだった。
縋るものを探しているのか、首元にぎゅうとしがみ付いて来る彼女に、つい頬が緩んでしまう。
「ッ…ぅ…?」
狼狽えながらも、信の視線が下げられたことを桓騎は見逃さなかった。着物越しに硬く勃起している男根を感じたのだろう。
蜜を流している其処を擦るように腰を動かせば、信が身体を震わせた。すぐにでも欲しいと蠢いている下の口を焦らすように、着物越しのむず痒い刺激を続けた。
いつもなら焦らすなと睨まれるところだが、背中に感じる王翦の視線が気になるのか、信は唇を強く噛み締めて身体を震わせている。
「う、んんッ…」
入り口を擦っているだけだというのに、身体が普段よりも敏感になっているせいで、もはや唾液を飲み込む余裕もないのか、信が肩に顔を埋めて来た。
こうなれば毒の副作用に支配されて堕ちるまであと僅かだろう。
にやりと意地悪に笑んだ桓騎が手を伸ばし、急所とも言える花芯に触れた。
「ぁううッ」
指が擦れただけだというのに、胸の芽を弄った時と同じで、信は甘い声を上げる。
「っ…ふぅ、…ん、く…」
腕に爪を立てて、なおも堪えようとする信を見下すと、我慢比べをしているような心地になった。桓騎は鰭酒を一滴も飲んでもいないのだから、勝敗の予想などする必要はないのだが。
しつこいくらいに花芯を指の腹で擦りつけていくと、信の身体が小刻みに震え始める。
「あッ…!」
二本の指できつく花芯を摘まんでやると、腕の中で信の身体が大きく仰け反った。
「信」
その体を強く抱き締めながら、耳元に唇を寄せて、低い声で名前を囁く。
彼女の白い内腿が痙攣し、着物越しに触れている入り口がぎゅうときつく口を閉じたのが分かった。
「う…っ…」
身体を硬直させた後、抜け殻になってしまったかのように信の身体がくにゃりと脱力する。
肩口に顔を埋めたまま動かなくなった信を見下ろし、桓騎は何度か瞬きを繰り返した。
(…マジかよ)
お楽しみはこれからのはずだった。
しかし、桓騎の燃え滾った情欲など知るかと言わんばかりに、信は意識の糸を手放してしまったらしい。
「……、……」
「………」
まさか信の不戦勝で終わるとは、流石の桓騎も予想しておらず、室内には信の寝息と王翦が酒を飲んでいる音だけが響き渡った。
桓騎の策
信に口づけをしなかったことで、幸いにも鰭酒を一滴も口にしなかった桓騎だが、ここまで大きく膨らんだ情欲の捌け口を失くしてしまい、お預けを喰らった気分になった。
(こうなりゃ、仕方ねえな)
羞恥と快楽に狭間で意識を失ってしまった信を見つめながら、桓騎が穏やかに笑む。
無理強いをするのは昔から好きだが、信に限ってはそうではない。眠っている間にその体を抱くのは容易いことだったが、桓騎はそうしなかった。
「………」
二人のまぐわいを見せつけられた王翦は、静かに酒杯を口に運んでいるばかりで微塵も表情を変えていない。
王翦が信を気に入っていることは知っていたので、自分も混ぜろと立ち上がるのだとばかり思っていたが、意外にもそれはなかった。
いつも何を考えているか分からない男であっても、あれだけ信の淫らな姿を見せられれば、少しは反応を示すと思っていた。信のあの姿にも反応を示さないとは、本当に男なのだろうか。
「…貴様の趣味は、とことん理解出来ぬ」
呆れたような口調に、桓騎がにやりと笑った。
「他人に理解されるような趣味も愛し方も知らねえだけだ」
「だから毒だと知りつつ飲ませたのか?犯人を引き摺り出す目的だけでなく、私の前で王騎の娘を抱くために」
まるで意図的に毒を飲ませたとでも言いたげな王翦の口調に、桓騎はさらに口角をつり上げた。
何を言っているのだと、桓騎はとぼけようとしたが、
「杯をすり替えた理由が他にあると思えんな」
王翦に言葉に遮られてしまった。まさか見ていたのかと桓騎は舌打つ。
この部屋にもてなされ、鰭酒を注がれていたのは、初めから桓騎だった。
毒耐性を持っているのは信だけでなく、桓騎もであり、黙って飲み干しても良かったのだが、彼はわざと信の杯とすり替えたのである。
―――…あいつら…
―――どうした?
―――いや、何でもない。
二人の気を逸らすために、わざと大きな独り言を洩らしたのだが、どうやら王翦には杯をすり替えた瞬間を見抜かれてしまったようだ。
しかし、桓騎が考えなしに動く男でないことを王翦は知っている。二人はそれだけ長い付き合いだった。
彼の意図を探るために、王翦は桓騎が杯をすり替えたことを、あえて指摘しなかった。
騒動になるのを避けるためか、信は注がれた酒が鰭酒であることを隠そうとしていたというのに、反対に桓騎といえば、王翦の話を聞いて毒殺されるのは自分だったのだと推測まで打ち明けていた。
(…解せんな)
その理由が王翦には分からなかったのだ。
初めから鰭酒だと気づいていたのなら、なぜ杯をすり替えてまで信に飲ませる必要があったのか。
毒見役として飲ませたのかもしれないが、ならばなぜ信に黙って杯をすり替えたのか、その理由だけが分からない。
未だに信を抱き締めて放さずにいる桓騎から、こちらを挑発する笑みが消えないのを見て、王翦は小さく肩を竦める。
(…なるほど)
きっと、これは牽制だ。
信は意識を失う最後までずっと抵抗をしていた。鰭酒を飲んだことで抵抗出来ない状態でなければ、きっと桓騎のことを殴りつけてでもやめさせただろう。
彼女が抵抗出来ないように鰭酒を飲ませ、まるで王翦に見せつけるように声を上げさせながら抱き、この女は自分のものだと王翦に牽制したのだ。
注がれた酒が毒だと気づいた瞬間から、僅かな間で桓騎がここまでの策を立てたことに王翦はいっそ感心してしまった。
(実に厄介な男だ)
同時にとんでもない独占欲を胸に秘めている男だとも思った。
桓騎がいる限り、飛信軍を率いる有能な将を副官にすることは愚か、不用意に近づけば彼の恨みを買うことになる。
今は腕の中で寝息を立てている信を見て、厄介な男に好かれたものだと同情してしまう。
しかし、今まで見たことのないほど穏やかな表情を浮かべている桓騎を見れば、彼自身は信が傍にいるだけで幸福なのだろう。
…逆に言えば、今の桓騎にとって信の存在は、これ以上ないほどの弱点ということにもなる。
彼女を利用することで、今見せている穏やかな顔がどのように歪むのか、焦燥感に駆られた人間らしい桓騎の一面も垣間見えるに違いない。それに興味がないといえば嘘になる。
「…せいぜい呆れられぬように気をつけろ」
「あぁ?」
忠告も兼ねてそう言うと、桓騎の瞳に一瞬怒りの色が宿った。しかし、王翦は顔色一つ変えない。
女の機嫌というものがどれだけ変わりやすいのか、桓騎は知っているのだろうか。
きっと目を覚ました信から、今日のことを散々責め立てられるのは明白だろうに、それでも彼は王翦の目の前で彼女を抱いたのだ。未遂ではあったが。
奇策を用いて、いつも戦況を思い通りに動かしているというのに、信に対しては随分と不器用な男だ。
彼女の怒りを簡単に包み込んでしまうほどの余裕を持ち合わせているようだが、それがいつまで続くものか見物である。
そして、信がいつまでも桓騎の言いなりになっているとも思えない。
彼女の心が揺らいでいるところに甘い言葉でも掛ければ、すぐにこの身へ凭れ掛かって来るだろう。
(…毒の味か)
王翦は酒で喉を潤しながら、毒酒というものはどのような味がするのかと考える。それを口実に、改めて信を酒の席に誘おうか。もちろん桓騎は呼ばず、二人きりで。
王一族当主からの誘いとなれば、信は断ることは出来ないだろう。
「…こいつに手ェ出してみろ。お前であっても容赦しねえぞ」
王翦の考えを読んだのか、桓騎が声を低めて言う。
殺気しか込めていない瞳に睨まれると、王翦は苦笑を浮かべるしか出来なかった。
「…かん、き…?」
物騒な会話で目を覚ましたのか、腕の中で信が身じろいだ。
着ていた羽織りをその身に掛けてやりながら、桓騎は穏やかな笑みを向けたまま彼女の頬を撫でる。
そして、王翦に再び見せつけるようにして唇を落とした。
「ん、ぅ…」
寝ぼけ眼でいる信も、桓騎から与えられる優しい口づけに応えるように薄く口を開けている。
意識を失っていたせいか、王翦がいることをすっかり忘れているようだ。
口ではああ言っていたが、どうやら信は心からこの男に夢中になっているらしい。そしてそれは桓騎も同じである。
鰭酒はたった数滴であっても死に至らしめる強力な毒だ。信の口内に残っている分であっても、殺せるほどの効力を持っている。
口付けても苦しむ様子がないことから、恐らく桓騎にも毒の耐性があるのだと、王翦はその時点で見抜いたのだった。
彼らは互いに毒として、骨の髄まで蝕んでいるのだろう。
その毒が、どれほど甘美なものなのか、知将と称えられる王翦でさえも、それを知る術だけは持たなかった。
後日編・桓騎の策~全貌~
翌朝、客室の寝台で目を覚ました信は、昨夜のことを思い出し、当然ながら憤怒した。
羞恥と怒りで顔を真っ赤にしながら、自分を抱き締めたまま眠っている桓騎をそのままに、愛馬の駿と共に帰ってしまったらしい。
信が屋敷を出てしばらくしてから目を覚ました桓騎は、腕の中に信がいないことに気付き、珍しく慌てた様子だった。
いつも信よりも先に目を覚ましていたので、慢心してしまったらしい。
桓騎という知将が一人の女に取り乱す姿を見るのは初めてだったので、王翦は昨夜の詫びだと受け取ることにしたのだった。
来客が帰宅したことで、屋敷はいつもの穏やかさを取り戻していた。
「…昨夜の庖宰 はどうした」
王翦が家臣たちに声を掛けると、彼らは戸惑ったように目を合わせる。
恐らくは逃げるようにして暇をもらったのだろう。
まだ彼がいるのなら、客人へ毒を盛ったことにどんな理由があるのかを尋ねようと思っていた。恐らくは私怨だろうと王翦は考えていた。
桓騎軍の素行の悪さは当然ながら王翦も知っている。彼らが手に入れた領地の民たちを虐殺することだって珍しくなかった。
もしかしたら、庖宰 の男は、その生き残りかもしれない。
王翦のもとに仕えながら、桓騎を暗殺する機会を伺っていたのだろうか。
しかし、毒を盛ったと気付かれて処刑される代償も承知の上だとしたら、なぜ桓騎のもとに仕えなかったのかが些か疑問である。
自分に恨みを持っている者を桓騎がいちいち覚えているはずがない。
顔を知られていないのなら、桓騎軍に入って本人に近づくのも一つの手だったはずだ。王翦の屋敷に仕えるなんて、桓騎との接点が無さ過ぎる。
…もしかしたら、あの庖宰の男に、桓騎に毒を盛るよう指示した真犯人がいるのかもしれない。
昨夜、庖宰の男に尋問しても、毒を盛ったことはおろか、理由を語ろうとしなかった。
言えない理由は処罰を恐れているのだとばかり考えていたが、真実を口外することによって、別の問題があったのかもしれない。
桓騎に毒を盛るよう指示した者がいる線が合っているのなら、庖宰の男は家族を人質にでも取られたのだろうか。
「あの、それが…」
家臣たちが気まずそうに口を開く。
続けて聞かされた言葉に、桓騎の策はまだ全貌が明らかになっていなかったのだと、王翦はようやく悟ったのだった。
「………」
蓋を開けてみれば、さまざまな厄介事が絡んでいることに気付いた。
冷静に考えれば、昨夜の時点で分かったかもしれないが、酒と面白い見世物のせいで王翦の思考は普段よりも鈍っていたのである。
王翦の屋敷を飛び出した桓騎は、自分の屋敷ではなく、信が住まう屋敷へと馬を走らせていた。
たかが女一人のために馬を走らせる余裕のない今の自分に、桓騎は苦笑を深めてしまう。それだけ信の存在に心を搔き乱されていることを自覚せざるを得なかった。
信の屋敷に到着すると、門番を務めている兵が険しい表情を浮かべた。
その表情だけで、信が自分を屋敷に入れるなと指示したことが分かる。しかし、桓騎は構わなかった。
もう侵入経路は頭に入っている。堂々と正門を通って入る必要はないのだが、最短距離はこの正門を通る道順だ。
馬から降りるのと同時に、腰元に携えていた護身用の剣を引き抜き、兵が身構えるよりも先にこめかみを打つ。
倒れ込んだ兵の胸がちゃんと上下に動いているのを確認してから、桓騎はさっさと正門を通った。
幸いにも内側から閂はされていなかったようで、あっさりと門が開いた。飛び越えることはしなくて済んだようだが、桓騎は違和感を覚えて、つい足を止めた。
(…妙だな)
信が激怒して屋敷に引き籠ることはこれまでも何度かあった。
その時は正門の入口に多くの兵たちが並び、頑丈に警備され、決して外側から開けられぬよう内側には必ずと言っていいほど閂を嵌められていた。正門以外の侵入経路を桓騎が把握していたのはそのためである。
桓騎の姿を見た時の兵の表情から察するに、恐らく信は「桓騎が来ても絶対に通すな」と命じたに違いない。しかし、何故か今日は警備の数が少な過ぎる。
閂が嵌められていなかったことにも、何か意図があるような気がしてならない。
「………」
桓騎は口元に手をやって思考を巡らせるものの、止めていた足を動かして信の私室へと向かった。
元下僕である信には家臣はおらず、屋敷を出入りする者は限られている。それでも屋敷を巡回している兵が数名いるのだが、やはり今日は普段よりも人数が少ない気がしてならない。
妙な静けさに、やはり違和感を覚えながらも、桓騎は身を隠しながら信の私室へと辿り着いたのだった。
扉を開けた途端、串刺しにされては堪らないので、扉越しに中の様子を伺う。剣を身構えているような気配は感じられなかった。
物音を立てぬように扉を開き、中を覗き込むと、奥の寝台に大きな膨らみがあった。
恐らく、王翦の前であのような痴態をさらしたことを悔いて、布団に潜っているのだろう。
「…信」
名前を呼んで寝台に近づく。恐らく聞こえているだろうが、信は布団に潜ったまま微塵も動かず、顔を出そうともしない。
「おい、とっとと機嫌直せ」
信は自分の女だと王翦に知らしめるためには、ああするしかなかったのだ。彼女に手を出すなと釘を刺したので、きっと副官の誘いもこれでしなくなるだろう。
今回、王翦との酒の席に信を同席させた目的は果たされたのだが、その代償として信の機嫌を大いに損ねてしまった。
自分と身を繋げることは嫌いではないくせに、他人に見られる羞恥心は抜けないことも桓騎は知っていた。
だからこそ、王翦の従者を利用して、鰭酒を飲ませたというのに、信はなかなか理性を手放さなかった。
王翦に釘を刺すのを目的としているのに、彼に毒を飲ませるわけにはいかなかった。
自分の女を奪うものを消すという意味では飲ませても良かったのだが、王翦の命が亡くなれば面倒な騒動になる。
だからこそ、間違えて配膳だけはせぬよう、印のつけた酒瓶――鰭酒――を自分の杯に注がせ、その後は信が黙って鰭酒を飲み干してくれれば良かったのだが、あの様子では全てを飲み干すことはなかっただろう。
なるべく生臭さがつかないように、毒魚の鰭をよく炙って酒に浸け込んでおいたのだが、やはり今回の鰭酒も信の口には合わなかったらしい。
毒酒の事前準備は出来たとして、酒の席で信に鰭酒を飲ませるためには、王翦の従者を利用するしかなかったのだ。
あの庖宰 の技量には前々から目をつけていたこともあり、今回の騒動に利用するのをきっかけに、自分の従者に引き抜いたのである。
十分な金を握らせただけでなく、王翦のもとを辞めざるを得ない状況を作ってやった。
今頃は暇をとって王翦の屋敷から抜け出し、桓騎の屋敷でさっそく料理の下準備でもしているだろう。
…そろそろ王翦は策の全貌に気づいただろうか。
彼はともかく、信の方は一生この策に気付くことはないだろう。あの庖宰の男が何らかの私怨で、恋人を毒殺しようとしたと思い込んでいるに違いない。
―――酒が苦手なんだよな?美味そうだから俺にくれよ。
あの時、信は毒の副作用が起きるのも構わずに、自らの意志で鰭酒を全て飲み干した。
庖宰の男に処罰が下されぬように、毒を盛った証拠を隠滅させたのだ。…もちろんそれは桓騎の読み通りである。
誰かのために、いつだって必死になる彼女の純粋さが、時折憎らしいほどに愛おしく思うことがあった。
後日編・信の策~失敗~
布団越しに彼女の身体を撫でながら、桓騎は重い口を開いた。
「…悪かった。機嫌直せ」
今回の件は、独占欲の強さゆえに企てたことだった。十分に自覚はあったし、それで信がどのような想いをするのかも分からなかったわけではない。
だが、信に嫌われたとしても、桓騎は彼女を手放すつもりなど微塵もなかった。
しかし、そのせいで信の笑顔が見れなくなるのが嫌だと叫んでいる自分がいるのも事実だ。
信のことを考えるだけで、他の男に奪われぬようにと考えるだけで、余裕がなくなり、心が搔き乱されてしまう。
「信」
返事もないことから、もう自分と口も利きたくないのだろうかと桓騎の胸が針で突かれたように痛む。
無視を続ける態度から、ちゃんと顔を見て謝罪をしろと言われているような気がして、桓騎は布団を掴んで引き剥がした。
「………は?」
布団を捲った中にあった物を見て、間抜けな声が上がってしまう。
てっきり、布団の中に信がいるとばかり思っていたのだが、そこに信の姿はなく、代わりにたくさんの布が積み重なっているだけだったのだ。
まさかと目を見開いた桓騎は、顔から血の気が引いていく感覚を初めて知った。
開いた木簡がそこに置いてあり、
―――俺がいつまでも引き籠ってると思ったら大間違いだからな。バカ桓騎。
感情のままに書き殴ったのだろう、見るに堪えない信の字がそこにあった。
「あの女ッ…!」
血の気が引いた感覚の後、一気に全身の血液が頭に戻って来る。
まさかこの自分がよりにもよって、信の策に嵌められることになるとは思いもしなかった。
正門の警備が普段よりも緩かったのも、閂がされていなかったことに違和感はあったが、全て信の策だったのだ。
王翦の屋敷を出た後、この屋敷に直行する桓騎の行動を信は事前に見抜いていたに違いない。
まんまと信の策に嵌められた桓騎は、ずっと誰も居ない寝台に向かって、謝罪を繰り返していたということになる。
もしもこんな姿を誰かに見られていたら、大笑いされていただろう。
(くそッ!)
ここまで心を搔き乱して来る女はきっと生涯、信だけだろう。桓騎は舌打ってすぐに部屋を飛び出した。
この屋敷にいないとすれば、今はどこにいるのだろうか。
頭も心も信のことでいっぱいになっている今の桓騎には、普段から知将として見せている冷静な面影など微塵もなかった。
荒々しく桓騎が部屋を飛び出していった物音が響いた後、室内に再び沈黙が戻って来た。
「………」
誰もいないことを確認してから、信はゆっくりと寝台の下から這い出て来る。
口元を手の平で押さえながら大笑いしそうになる自分を制し、しかし、目元には隠し切れない笑みが滲んでいた。
すぐに自分のもとに謝罪へ訪れたことから、桓騎の誠意は認めてやろうと思いながら、信はゆっくりと窓辺に近づいた。
誰が見ても慌てた様子で馬に跨った桓騎の姿が見えて、信は噛み締めた歯の隙間から笑い声が漏れてしまう。
きっとこれから自分を散々探し回り、結局見つけられず、くたくたに疲れ切った桓騎の姿を夕刻には拝めることだろう。
あの木簡の内容から、まさか最初から屋敷にいるとは思うまい。
しかも、寝台の下にずっと身を潜めていただなんて、さすがの桓騎でさえも予想出来なかったようだ。
知将と名高い桓騎を策に嵌めてやったのだと思うと、もしかしたら自分にも知略型の将の才があるのではないかと自負と優越感に浸ってしまう。
軍略はからきしである信だが、桓騎と共に過ごして来たことで、良い刺激を受けたのかもしれない。
相手の裏をかくというのがこんなにも気分が良いものだと知った信は、不敵な笑みを浮かべていた。
今日は桓騎のことを気にせずにゆっくりと寛ごうと欠伸をした途端、
「…ッ!?」
外にある厩舎から、愛馬の遠吠えかと思うほど大きな嘶きが響き渡った。
まるで桓騎を呼び止めているかのような嘶きに、信がまずいと青ざめる。すぐに窓を開けて身を乗り出し、厩舎にいる駿を睨みつけた。
「駿、静かにしろって!桓騎にバレるだろッ!」
慌てて愛馬に声を掛けたのだが、先に身を潜めるべきだった。
「あ…」
顔を上げた先で、こちらを振り返った桓騎と目が合ってしまった。
恐ろしいほど憤怒した表情に切り替わった桓騎がこちらに戻って来るのを見て、信は此度の策が失敗に終わったことを察した。
―――ああ、言っとくが、お前の愛馬も俺の味方だからな。
先日、桓騎が話していた言葉を思い出し、信は顔を引きつらせる。まさか最後の最後で愛馬に裏をかかれるとは予想外だった。
しかし、今まで見たことがない恋人の新たな一面を知れて嬉しいと思ってしまう。
きっと自分は救いようのないほど、骨の髄までこの男を愛しているのだと、認めざるを得なかった。
終
おまけ後日編「桓騎の策~失敗~」(2000文字程度)はぷらいべったーにて公開中です。
終
①毒酒で乾杯を(桓騎×信)
②毒杯を交わそう(李牧×信)
④恋は毒ほど効かぬ(桓騎×信←モブ商人)
⑤毒も過ぎれば情となる(桓騎×信)
⑥毒も過ぎれば糧となる(李牧×信)